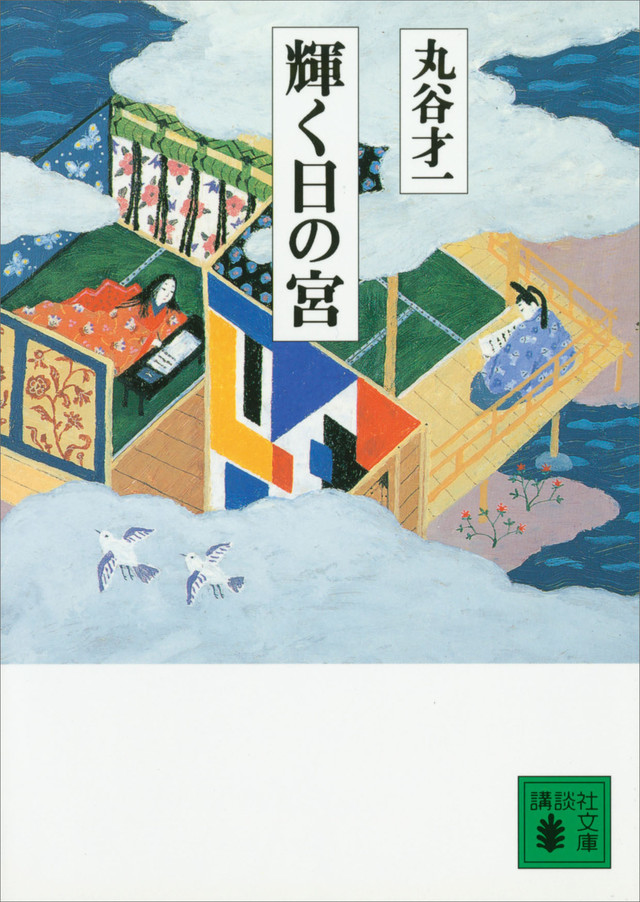江國香織『去年の雪』の123の話、断片(断章、スケッチ)は短いもので半ページ、長くとも数ページからなり、ひとひらひとひらはさらさらと舞い散る淡雪か細雪のようであり、湿って結び合うぼたん雪のようでもあり、あるいは知らぬ間に溶けて消えるかと思えば、黒く汚れていつまでも残り続ける。
テーマが連続することは稀だが、登場人物たち(100人以上もの名前、ときには猫、犬)や細部や余分な記憶が緩く連動し、時間と場所の時空(平安時代、江戸時代、1970年頃、現代(2020年頃か))を超えて侵犯し、通奏低音で響きあい、境界は溶融し、物語はシャッフルされて震え、反復と微妙なズレの仕掛けがあって、幻想を生じる。
オムニバス、過去の思い出、数珠つなぎ連想、しりとり、つながっているようでつながっていないのか、他愛なき「三千世界」の老若男女の群像たち(死者までも)一人一人の人生は、「あみだくじ」にたった一本の横棒が追加されたように、「万華鏡」がほんの少し回転したように、それぞれの視点が相対、相反、逆転して多面的なプリズムと化す。ときに不穏のモザイク、ときにセックスへの耽溺、新たな生に悦び、世界はがらりと変わってしまうが、しかし本質のライト・モチーフは波のように寄せてはかえし変容することなく、孤独、寂寥、無常観、生々流転、完結することも閉じることもなく、永劫回帰のように……
<スケッチ・サイクル・群像>
丸谷才一『文学のレッスン』(聞き手・湯川豊)から。
《丸谷 短篇小説とは何かという定義となると、一筋縄ではいかない難しさがあるから、それは脇に置くとして、短篇小説の短さにもおのずから限度があって、極端にうんと短くなってしまうと、それはアネクドート(逸話)になる。短篇小説じゃなくなる。アントニー・バージェスというイギリスの作家・批評家が『エンサイクロペディア・ブリタニカ』の「小説」の項目でそういってるんです。バージェスの説は、たとえばワシントンが桜の木を伐(き)って、それを正直に父親にいった。父親がその正直さをほめて伐ったことを許したという話、あれはアネクドートであって短篇小説ではない、ということですね。(中略)
アネクドートは短篇小説ではないとしますね。そのアネクドートと接して、ここから短篇小説になるというのは、スケッチという言葉がぴったりかも知れない。川端康成の「掌の小説」は駄作もあるけれど、おおむねいいものが多いんです。今の作家では江國香織さんの書くものは、短篇小説というよりもむしろスケッチに近いものがあって、あれ、うまいですね。》
《丸谷 もう一つ、連作短歌とか連作俳句というのがあるでしょう。俳句の場合だと水原秋桜子(しゅうおうし)とか山口誓子(せいし)とかが、どこか旅に出て、長崎なら長崎の句を連作としてつくって一緒に発表するというものですね。あの連作に似ているのが、小説のサイクルという方法です。サイクルというのは、この場合、一団とか一群という意味なんです。
具体的にいうと、ジョイスの『ダブリン市民』。ダブリンの人びとのことばかりを短編連作のように書いて、一冊の短篇集にしている。あれはサイクルです。》
「待ちに待った江國香織さんの最新作は、今こういうときこそ読みたい小説だ! 『去年の雪』」(本が好き。)で、江國はこう語っている。
《「これまで私の興味はいつも個人に向かっていました。ですが、今回はいろんな人がさまざまに生きている世の中の話を書きたいと思ったんです。いろんな個人がいる世の中に初めて興味を持ったといいますか(笑)。この世からいなくなった人も、今生きている人と同じ時空間に生きていることを描きたいと考えました。私たちが生きている土地は限られていますが、同じ一つの場所にいろいろな生命体が発生しては消えていくことを、細かく説明せずに、いくつもの物語を重ねていくことで小説にできたらいい、と」》
それに江國は、「作家の読書道」というインタビューで、「童話屋さんでアルバイトをしていた頃(筆者註:短大を卒業したころ)って、もうご自身でも小説を書き始めていたのでは」と訊かれて、「そうですね、「お話つなぎ」とか、自分で遊びで書いているものの延長だったんですけれど。」と答えている。
<『去年の雪』読解(1話~30話)>
1話:「事故はあっというまに起き、制御不能で、どこを打ちどこが切れどこが折れたのか、皮膚がどうなり眼球がどうなりどの内臓が破裂したのか、頭ではもちろん身体感覚としてもわからなかった。(中略)死ぬという言葉を進行形で使ったのははじめてのことだったが、それを感慨深く思う余裕もなく、謙人(けんと)は息をひきとった。」 江國の小説は軽やかな印象とは裏腹に、ときに重く暗い「死」と「過去(時間)」を背負いもする。
2話:三保子が電話で、圭子ちゃんのお友達の御主人の息子さんの事故死を知る会話。「公にやっていることじゃありませんのでね、ご縁のあったかただけ、亡くなったかたのお名前をもう一度おしえてくださる? ウダガワ、ユウタさん? どんな字を書くの?」
3話:「夏レンコンは白い。」 ピーラーで皮をむきながら、律子はその野菜の肌に見とれる。夫の死後、律子の義理の母(2話の三保子?)が無料でやっている「供養」と「あちらとの交信」(亡くなった義父は死者たちの様子を事細かに教えてくれるという)について、台所に坐ってゲームに夢中の夫と会話している。この後、「白」の逸話は脈絡なく反復される。
4話:藤田みずきが大谷春香と海に来たのは写真を撮ることが目的だった。みずきは波打ち際で、「ざばん、ぷちぷち、ざばん、ぷちぷち、ざばん」という波の音とともに、「だけれどもさ、ヨーコさんだって悪気があって言うわけじゃないだろ」と、ふいに、はっきりと聞えた(おじさんっぽい声だった(3話の亡くなった義父?))が声の主らしい人は見あたらない。「六時すぎには恵比寿につくね」春香が言う。「竹田たちでも呼び出して飲む?」
5話:プラットフォームと電車のあいだの隙間をまたぐとき、小沼茉莉子はいつもすこし緊張する。電車に乗った初老の茉莉子は行儀よく坐っている目の前の男子小学生に思いをはせる。重ねたのは、すでに成人している息子の凛ではなく、五十歳そこそこの若さで祖母になった女子大からの親友香坂真紀子の孫勇也だった。小学生が降りた席に腰を下ろすと、尻に「キャラメルの空き箱」の感触を知る。「老い」もの。
6話:いやな事件(筆者註:黒い霧事件)があった翌年、稲生(いなお)が監督に就任した年(筆者註:1970年)のこと。両親がリコンをしたため先月東京に引越してきたばかりの、西鉄の野球帽を被り、習字の道具を持った小学三年生の末松織枝は、「クリームキャラメルの空き箱」をバスの座面と背もたれのあいだに押し込む。5話と違って、男子小学生ではなく女子小学生、電車ではなくバスであり、連続ではあるが微妙なズレがある。「子供」ものは、その繊細な感覚、どちらかというと孤独さをモチーフとした断片が、思い出したように繰り返され、積層してゆく。
7話:(4話で)大谷春香にラインで呼び出された竹田礼生(れお)は、気乗り薄の高橋雅人を説きつけて恵比寿に駆けつける。ロータリーに櫓(やぐら)が組まれ、ピンク色の提灯がたくさん、滲(にじ)むように灯(とも)っていた。高橋は店の確保でその場を離れる。大谷春香と藤田みずきは海に行ったのだという。二人が夏の終りを満喫する写真が、すでにインスタにあげられていた。
8話:恵比寿のバス停で高橋は、バスから降りてきた、真冬みたいな服装をして、古くさい野球帽を被って習字道具を持った女の子(6話)からユーテンジ(祐天寺)に行く道を聞かれる。歩くと遠いよ、電車で二駅分だから、と教えてやると「ゲバゲバ」(筆者註:1969年から71年まで日本テレビ系で放送されたヴァラエティー番組『巨泉・前武ゲバゲバ90分!』に由来)と返ってきた。バスに乗った方がいいよ、と言うのに歩いて去って行った。
9話:野村健太と裕子は渋谷のラブホテルでセックスに耽る。セックスに耽溺する男女の断片はこのあともいくつか嵌め込まれるが、どこか孤独な淋しさ、無為、無常観が漂っている。「セックス」もの。
10話:田中野花(のか)はアイスカフェラテを吸いながら、“ごめん。きょうはやっぱり無理だわ”という隆昭(たかあき)(空腹なときの方が気持ちがいいからと、会えばまずホテルに行き、食事はそのあとだ)からのラインを受ける。と、店の奥にいて帰り際に野花を見つけたという高校時代の級友「宮(みや)たん」に声をかけられる。野花は月に一度は会っている四人組に“誰に会ったと思う?”とラインを送る。
11話:平安時代を舞台としたシリーズ(『更科日記』を現代語訳した経験が生きているのだろう、比較的長い数ページからなる)で、荻原(おぎわら)正嗣(まさつぐ)、茴香(ういきょう)、規那(きな)(正嗣の弟)、柳(やなぎ)(茴香の妹)が登場してくる。正嗣は茴香と逢瀬を重ねている。「けんと」(1話の市岡謙人(けんと))という名の「もののけ」が現れる。
12話:連続して平安時代シリーズ。片方の羽の一部が緋色に染まったカラスが柳をじっと見ている。「御帳台(ベッド)」「簀子(ベランド)」「汗衫(ガウン)」といった時空の溶融表現。
13話:十五歳の土屋恭子が学校をさぼって公園のベンチでお弁当を食べながら、行き交う人々に見とれる。学校にいたら決して見られない種類の、昼間の人たち。「違う場所に行けば違う時間が流れている、ということを、学校にいると忘れそうになる。」 江國の小説は「見ること」の小説でもある。
14話:結婚祝いに妹から贈られた苗木だったが、玄関脇の狭い地面に植えたところよく根づいて、十一年間毎年春には白い可憐(かれん)な花を咲かせ、秋にはまっ赤な実をつけてくれた姫りんごの木が「死んでしまった」ので、幹の途中ですっぱり切られ、痛々しい切り株になっている。その悲しみに比べれば、夫の健太が数か月前から浮気をしていることなど、とるに足りないと野村萌音(もね)は思う。
15話:伊吹慎一と妻のありふれた家庭内会話。鳩時計がポッポオと十二回鳴く。他愛もない「老い」もの。
16話:夫も子供もなく、持っているものといえば、定年まで働いて貯めたお金と両親の残してくれた家と愛猫のトムだけの大垣香澄(かすみ)は、月に一度の割合で利用する男性コンパニオン(性的な接触は厳禁)と中華料理の食事をとっている。今回の男はたべ方が気持ちよく、マスカットのむき方まで美しかった。あの指に、今度は鮨かピザをつまませてみたいと香澄は思い、果汁に濡れた男の指先を見つめる。「老い」が忍び寄る。
17話:平安時代シリーズ。琵琶を弾く規那は「けんと」という名と答えた「もののけ」のことが頭を去らない。「あなたときたら、さっきから暗い顔で暗い曲ばかり」と母親に叱られ、“うぐいすと皇帝”を弾いてちょうだいと言われる。
18話:「雨音が聞こえ」島森りりかは、ピアノを弾く手を止める。ストリーボッグという作曲家による「すみれ」というピアノの音と雨の音との混ざり合う叙情に浸る。
19話:「雨?」 施術台から顔をあげた客に訊かれたマッサージ師の千葉考大(こうだい)は「みたいですね」とこたえる。考大は男性コンパニオンのアルバイトもしていて、婚約者の陽水(あきみ)は快く思っていない。最近年配の女性と中華料理をたらふくたべた(16話)。
20話:「雨が降っている。」 (白石)みどりは会社の営業車のなかで同僚の国見智志(さとし)とカーセックスに耽る。溺れる「セックス」もの。
21話:瓜生明彦(うりゅうあきひこ)の妻麻江は物置にトイレットペーパーを買い占めている(筆者註:過去、「トイレットペーパー買占騒動」はオイルショックによる1973年と、コロナ初期の2020年2月末の2度発生している。たしかに本作には1970年頃の話が出現するものの21話は1973年の設定ではなさそうであり、また本作発表は「小説野生時代」2017年11月号~2019年7月号なので執筆時にはコロナによるそれは未発生である)。玄関で、背の高い男が「コーポ・エリゼってなかったですか?」と長女恵(めぐみ)に尋ねてきて、「コーポ・エリゼ」ものがはじまる。
22話:千奈美と真奈美は小学生の双子だ。かみなりと雨粒の音の中で、「あなたときたら、さっきから暗い顔で暗い曲ばかり」という、パパにもママにも聞こえない声が二人には聞こえる(17話)。
23話:「ゆうべの雨はあがっていた。」 遠藤拓也は妻の小言と詰問に辟易している。切り株に片手を添えた隣家の妻がわざわざ玄関の外まででて夫を見送っていて、世の中には幸運な夫もいるのだ、と思う(14話)。
24話:小学二年生の佐々木絵美里は“夏休みのできごと”という題に、「おじいちゃんが死にました」と作文に書き、おじいちゃんの顔を思いだそうとする。「子供」もの。
25話:空港内のカフェレストランで、カメラマンの早坂みのりはカツカレーをたべている。こういう場所でカツカレーをたべるのは、もう十年も前につきあっていた男の習慣だった。
26話:遠藤由香は夫拓也が耳を貸さず無自覚なことにうんざりしているが、洗濯機からだしたばかりのバスタオルはあたたかく、夫のいない家のなかは静かで安らかで快適で、問題ないよと由香に囁く(23話との夫婦の心理の綾)。日常生活は長く重く暗いばかりでなく、さざ波はあっても安逸でもある。
27話:「コーポ・エリゼ」もの。バーのカウンターで、鍋島(なべしま)亘(わたる)を主体とした、亘の恋人でコーポ・エリゼの住人七海(ななみ)、バーテンダーの瞬(しゅん)、美容師琴子の会話。亘が「コーポ・エリゼ」を見失った話でいじられる。
28話:27話の続き。琴子が主人公で、マグに入ったモスコミュールを飲む。
29話:おばあちゃん子の香坂勇也はおばあちゃんの化粧、身支度をじっと見ずにいられない。両親は離婚しているのでお父さんは家にいないが、ときどき遊びに来る。「子供」もの。
30話:瓜生恵は「コーポ・エリゼ」がどこにあるか気になっている。恵の学校で三年生のときに転校してきて三年間おなじクラスの末松さん(6話)が学級会で掃除の仕方について提案するが多数決で却下された。でも恵は末松さんの言ったことを正しいと思った。家に帰ると母がピンクのトイレットペーパー(21話)が一袋盗まれたと騒いでいる。「子供」もの。
<エピファニー・不穏>
丸谷才一がジョイス『ダブリン市民』の「サイクル」「群像」について言及したが、新潮文庫の訳者安藤一郎は「エピファニー」を解説している。
《『ダブリン市民』は、十五編の短篇から成り、ことごとくダブリンとダブリン人を題材にして、幼年、思春期、成人もしくは老年の人間によって、愛欲・宗教・文化・社会にわたる「無気力」(麻痺(パラリシス))の状況を鋭敏に描いたものである。二十代の初期におけるジョイスは、詩のほかにスケッチ風の短い散文を書きはじめていて、これを彼自身が「エピファニー」と称していた――「エピファニー」というのは、宗教上の意味でキリストの降臨を言うのであるが、それから何か神聖な、もしくは超自然的存在の顕示あるいは出現をさすのである。ジョイスは、『スティーヴン・ヒアロウ』の中でつぎのように述べている。「エピファニーということで彼の意味するのは、ことばまたは身ぶりの俗悪においてでも、精神それ自身の記憶すべき様相においてでも、突然の精神的顕示のことである。彼は、そういうものそれ自身が時々(ときどき)の中でもっとも微妙でつかのまのものであることを見て、極度の注意深さでこれらのエピファニーを記録することは、文学者の役目であると信じていた」 つまり、感情の宗教的昂揚(こうよう)を、文学の創造におけるインスピレイションに変えているわけで、「美の最高の特質を見いだすのは、まさしくこのエピファニーにある」とも言う。文学を宗教におき換えているのが、ジョイスの思想の根本だったのである。》
また、リチャード・エルマンは『ジェイムズ・ジョイス伝』の中で「エピファニー」を次のように論じた。
《彼の言うエピファニーは、神の顕現、すなわちキリストが東方の三博士の前に姿を現わしたことを意味するものではなかった。ただ、それは彼の頭にあったもののメタファーとして有用であった。エピファニーとは、突然の「ものの本質の顕現」、「きわめて卑俗なものの魂がわれわれに輝いて見える」瞬間のことであった。彼の考えでは、芸術家はこのような顕現の瞬間の感知を委ねられているのであり、芸術家はそれを神でなく人間の中に、それも何気なくさりげない、時には不快でさえあるような瞬間に求めねばならなかった。「突然の精神的顕現」は「卑俗な言葉やしぐさ」か「精神それ自体の記憶すべき相」の中にあるかもしれない。時にはエピファニーは「聖体拝領的(ユーカリスティック)」であるかもしれない。この言葉もジョイスがおこがましくもキリスト教から借りて、世俗的な意味を与えたものであった。このような瞬間は充溢もしくは情熱の瞬間である。エピファニーは、時には不快な体験の匂いを正確に伝えるという意味でも重要であった。ジョイスの特徴的な主張でもあったが、精神は両方のレベルにおいて顕われ出るのである。これらのエピファニーは文体的にも多様である。あるものは見慣れない言語を用いたメッセージのように読める。そのようなエピファニーの秀逸さは、独特の大胆さと、意味を即座に明白にしてしまうような技法はすべて妥協の余地なく拒否している点にある。しかし中には意図的に暗号性を解除され、抒情に傾いているものもある。(中略)平凡な言葉と、人と場所の不思議な夢のような不確かさを巧みに対照させ、その結果、全体の効果は奇妙で、ほとんど不気味と言える。このようなスケッチの面白みがジョイスやこれを見せられた少数の者の心に刻みつけられた。(中略)
短篇「姉妹」の方法は完全に非妥協的である。叙情的エピファニーがジョイスを『芸術家の肖像』に導いたとすれば、飾らない抑制されたエピファニーが『ダブリンの人びと』の最初の物語へ彼を導いた。物語の中では一度もそうは言っていないが、彼は司祭の麻痺をアイルランドが病んでいる「狂った社会の全体的麻痺」の徴候にした。アイルランド人は違うことには目を向けず、一つ事にしがみついて、衰えてゆく。ジョイスは司祭の性格を、それぞれ異なる証言者――子供時代の不安な記憶を甦らせる語り手、疑り深い一家の知人、伯父、最後に、司祭と一緒に暮らしていた姉妹――の証言によって作り上げてゆく。それぞれの証言は読者に、司祭の落伍や、彼の破滅感、感じやすい子供に何気ないそれとない仕方で堕落を移し植えようとしている司祭の態度を暗示している。しかしこの不健康さは示唆にとどまっており、それは何もかも承知の二人の姉妹の不死身な様や、言葉の誤用と敏感さの混合する彼らの様子と対照をなしている。単語は平明だが、文章は精妙な律動性を持ち、言葉の抑制を捉えるジョイスの能力が現れている。》
デイヴィッド・ロッジは『小説の技巧』の「エピファニー」の項目で、ジョン・アップダイク『走れウサギ』の一節を引いて説明する(ここでは『走れウサギ』での具体的解説は割愛)。《カトリック背教者ジェイムズ・ジョイスにとって、作家という天職は司祭職の俗世版のようなものだったから、エピファニーという言葉にしてもジョイスは、ありふれた出来事や思いが、作家が技巧を駆使することによって時を越えた美を帯びるに至る過程を言い表わすのに用いた。「ごくありふれたものの魂が、我々の目に光り輝いて見えるとき」と彼の小説上の分身スティーヴン・ディーダラスも言っている。現在この語はもっと広く、見る者にとって外的世界が一種超越的な意味をたたえているような場面一般について使われる。物語やエピソードにクライマックスや結末をもたらすという、伝統的な物語では何か決定的な行為や事件が果たしていた役割を、現代小説ではエピファニーが引きうけることも多い。この点でも先駆者はジョイスである。『ダブリン市民』の短篇の多くは、一見アンチクライマックス(敗北、挫折、あるいは何かささやかな出来事)で終わっているように見えるが、言語によってそのアンチクライマックスが、主人公あるいは読者にとって――またはその両方にとって――真実の瞬間に変容するのである。(中略)エピファニーにおいて、小説は抒情詩の言語的緊密さに限りなく近づく(現代の抒情詩の大半は実のところエピファニー以外の何物でもない)。》
やはり十代のころ詩を書いていた江國香織も、『去年の雪』ではアンチクライマックスであっても、「ごくありふれたものの魂」の「エピファニー」がそこかしこで「我々の目に光り輝いて見え」て「真実の瞬間に変容する」。
ところで、江國香織の小説を語るとき、「不穏」という表現がよくでてくる。江國自身も他の作家を書評するときに「不穏」という言葉をよく用いる。
たとえば、『がらくた』のキャッチコピー(新潮社)は、《私は彼のすべてを望んだ、その存在も、不在による空虚さも――。45歳の翻訳家・柊子と15歳の美しい少女・美海。そして、大胆で不穏な夫。彼は天性の魅力で女性を誘惑する。妻以外のガールフレンドたちや、無防備で大人びた美海の心を。柊子はそのすべてを受け容れる、彼を所有するために。知性と官能が絡み合い、恋愛の隙間からこぼれ出す愉悦ともどかしさを描く傑作長編小説。》
『思いわずらうことなく愉しく生きよ』のキャッチコピー(光文社)は、《犬山家の三姉妹、長女の麻子は結婚七年目。DVをめぐり複雑な夫婦関係にある。次女・治子は、仕事にも恋にも意志を貫く外資系企業のキャリア。余計な幻想を抱かない三女の育子は、友情と肉体が他者との接点。三人三様問題を抱えているものの、ともに育った家での時間と記憶は、彼女たちをのびやかにする。不穏な現実の底に湧きでるすこやかさの泉。》
たとえば、柳美里『自殺の国』の書評では、《随分恐い表紙(とタイトル)なので、恐がりの私としては、最初、読むのがためらわれた。けれど読んでみてわかった。これはとても可憐な本だ。顔の見えない他人と(ときに陰湿な)やりとりをする「ネット」、そこで「自殺」を計画したり、一緒に死ぬ仲間を募ったり、実行したりする人々、という道具立てはたしかに不穏で毒々しいが、背景に惑わされずにまっすぐ読めば、そこにはごくありふれた、一人の、少女がいる。》
井上荒野『雉猫心中』の書評では、《ホラーといえば、小副川さんという人物がでてくる。「ハンサムな老人だ。若者が着るようなカーキ色のフリースのパーカに、スラックスという恰好(かっこう)だったが、着物を着せたら、歌舞伎役者のように見えるだろう」と描写される町内会長で、言葉つきも人当りもやわらかい。凡庸な作家なら好々爺(こうこうや)、不穏な不倫劇における一服の清涼剤、的な役をわりふりそうな人物だけれど、この人のこわさは尋常じゃなく、私はずっと、この人がもうでてこないことを祈りながら読んだ(でもでてくる)。》
江國『ちょうちんそで』の出版社対談で江國は、《平穏なものをちょっとつついたら不穏なものが出てくる。それも、どっと出てくるのではなくて、どこにもかしこにもそういうものがあって、そのうえで凪いでいるように見える。それってふつうのことなんじゃないかなと思います。》と語っている。
江國は「江國香織さんの最新作『去年(こぞ)の雪』。不思議な読後感を残す物語はこうして生まれた」(「家庭画報.com」2020.4.7)で、
《――万引き癖のある姉と、そんな姉と縁を切れという隠れアイドルおたくの夫。ふたりのことを考えながら、どちらが怖いだろうと自問する妹(妻)の言葉も残りました。
江國 世の中ってそういう不穏さがありますよね。たとえば電車には、痴漢はしなくても大きな胸やお尻に触ってみたいと思っている人はいるかもしれないし、誰かの顔に拳をめり込ませたいと思っている人もいるかもしれない。電車のなかだけでもそうだから、世の中全体となればどうだろう、と。》
『去年の雪』のほとんどは、あからさまに濃くない話でも、隠微な「不穏」の匂いがする。
実際、江國は「待ちに待った江國香織さんの最新作は、今こういうときこそ読みたい小説だ! 『去年の雪』」(「本がすき。」)のインタビューで、《「実は私……電車の中で他人の顔面を拳で殴りたいと考えたことがあるんです。もちろん、行動には移しませんが(笑)、私がそう思っていることを、その電車に乗っている人は誰も知りません。そして、そう思っている人は私以外にもいるかもしれないのです。作中、何人かの人に“今、何を考えているのか”と言わせているのですが、どれだけ親しくても、その人が何を考えているのか他人にはわかりません。これって怖いことですが、面白いことでもあると思うのです。本書に限らず、私はいつも“正解はない”ということを書きたいと思っています。正解はないのにみんなあれこれ考えて何とか生きています。そういう全体を“いいなあ”と思えるような小説を書けたらいいなと思いました」》と答えていて、72話で小説仕立てにしてしまった。
ジョイス『ダブリン市民』のライト・モチーフが「麻痺」であるならば、江國『去年の雪』のそれは「不穏」ではないだろうか。
<『去年の雪』読解(31話~60話)>
31話:伊吹夫婦(15話)は近所を散歩し、妻(弥生)は竹林の葉ずれにまじってたくさんの「声」を聞く。静かで、平穏な、抑制された「老い」もの。
32話:平安時代シリーズ。柳は“あたり”と読める平べったい棒や奇妙なものを幾つも「羽が緋色のカラス」がいた場所に落ちているのを集めている。「直衣(マジュアル服)」「枹(ジャケット)」。
33話:国見幸穂(さちほ)は産科主任の看護師で、毎日何人もの赤ん坊の出産に立ち会っている。夜勤あけに弟の聖の店でセロリのポタージュを食べながら、娘可奈の留学の話をしている。家のなかは任せっきりの夫(20話の智志)と幸穂は、おなじ家のなかにいても半ば互いを避けるように暮らしている。かつてヨーロッパを放浪した経験のある叔父(おじ)である聖を、可奈は理解者のように考えて、いろいろ相談しているらしい。どの赤ん坊もいずれ育って、可奈みたいに手に負えなくなるのだ。
34話:ベビーベッドのなかの、先月生れたばかりの娘葉月に赤池麻由美は話しかける。時間を止めて、永遠にこの夏のなかに閉じ込もっていたい、と思う。記憶、過去の物語が江國には多いが、それだからこそ現在もまた「時間」の意識下にある。
35話:34話に続いて赤ん坊と母親にまつわる逸話。育児経験もない年上の女田辺京子は、地下鉄に降りる銀座の階段で片腕に赤ん坊を抱き、反対の手に紙袋を持った若い女のバギーを持ってあげる。リュックサックのサイドポケットから、のみかけの水の入ったペットボトルがつきだしていて、どういうわけか、そのペットボトルに女の疲労や不安が凝縮されているように感じ、怯んだが、先輩然とした微笑みをつい浮かべる。「エピファニー」の瞬間。
36話:「死者」もの。気味の悪さがある。歩きだそうとして、自分に肉体がないことに泰三は気づく。泰三自身には見えない自分の肉体が、相手には見えているらしい。男が命からがらの体で自宅と思(おぼ)しきあばら家にたどりつき、戸をぴしゃりと閉めたとき、どういうわけか泰三は、戸の内側にいるのだった。
37話:妻が会食で遅くなるので、大石洋介は五歳と三歳の息子たちを託児所で迎え、自分で料理を作ろうとスーパーまでの道のり、何を作るか会話している。「鮨(すし)? 鮨はちょっと無理だなあ」「じゃあ、お豆!」「じゃあねえ、おたま!」「オクラ!」「おしり!」 子供と会話をするのは猫と会話をするより難しいのだ。店の前に停めてある何台もの自転車に、「夕方の日ざしが反射してまぶしかった。」 子供たちのとりとめなくつながる会話は『去年の雪』の断片・モザイクの表象のようでもある。
38話:白石みどり(20話)の不倫相手であり、幸穂(33話)の夫である国見智志の内的独白。「不穏さ」が漂っている。智志にはわからなかった。一体なぜこんなことになったのかも、自分のような男の、どこをみどりがいいと思ってくれているのかも。「夕方の光がアルミの灰皿に反射してまぶしい。」
39話:「四人組」の、高校卒業以来もう七年も続いている月に一度集まる食事会。田中野花、木元千絵、大和(やまと)留美、白石みどり(20話)はゲストの宮たん(10話)とおおいに盛り上がる。風俗描写。
40話:奥のテーブルで騒々しく食事をしている若い娘たち(39話の「四人組」らしい)を横目に、村田梓はおよそ四十年前におなじ学校に通った、仁美(ひとみ)、園子と食事をしている。梓が、シェフでありオーナーでもある菅原聖(33話の幸穂の弟)の料理と人柄に、夫婦揃って惚れ込んでいるからで、結婚の早かった仁美に長女果林が幾つになったかを尋ねる。聖がどんなに感じのいい男性であるか、婚期を逃したのは外国暮らしがながかったせいに違いなく、果林ちゃんならこういうお店のマダムも務まると思うのよ、と。
41話:江戸時代シリーズで、平安時代シリーズと同じような位置づけ。上絵師庄造と三人の娘(長女加代、次女茂(しげ)、三女綾)が登場する。カエルの幽霊の話題。茂と綾は湯屋に行く。
42話:41話の続き。湯屋から出た茂と綾はうぐいす形の飴を選ぶ。「若月」だ。糸みたいに細い金色の月が、空の低い位置にでている。
43話:「ほそーい三日月、見て。」と、七海は亘にラインした(27話の二人)。終電だったのですでに真夜中をすぎていたが、家の前(であるはずの場所)まで来たとき、七海は自分の目を疑った。野原なのだ。七海は動くことができなかった。一分か二分、野原はそこに存在し、七海の目の前でふいに消えた。七海の住むアパートを含む見慣れた住宅群が、あたりまえのように出現していた(亘が「コーポ・エリゼ」を見失った話と通底する)。
44話:「たとえ百人分の乳房が目の前にならんでも、自分には妻のそれがわかるだろうと、岩合(いわごう)和久は思う。」 和久は妻の仁美(40話)の乳房を下から支えるように持って、その重みと感触を味わうことはやめられない。
45話:「白」の逸話。「梨の肌は白い。」 朝の台所で新町詩織はそう思う。りんごの肌も白桃の肌も白いけれど、梨の肌の白さとみずみずしさには遠く及ばないと。姉の佳織が万引で三度目の逮捕となって、夫とのあいだでの子供たちへの二つ目の秘密となった。一つ目は夫が年若いアイドルグループの女の子たちを熱愛しているという事実だった。自分にとってどちらがよりおそろしいのか、詩織にはわからなかった。
46話:十六歳の今野まどかは隣のクラスの矢沢翔に誘われて、学校さぼりデートを敢行し、本八幡まで来るが、醒めてしまう。
47話:退職した古田明良(あきら)はマンツーマンの英語教室に通い、白人英語教師と会話をするが、教条的な教師と噛み合わず、悲喜劇の様相を醸す。「老い」と孤独。
48話:城戸崎(きどさき)陽水はいくどもカラスに待ち伏せされ、襲われた。結婚が決まって、陽水にべたべたしなくなってきた考大(こうだい)とはいえ、赤いスプレーペンキを噴射してカラスを撃退してくれたのは彼だった。考大と暮らしているマンションの前に着くと、どこかの家で「ひき肉料理をつくっているらしい匂い」が漂っている。ここではじめて、平安時代シリーズに登場する羽が緋色のカラスと結びつく。過去が現在を侵犯するばかりでなく、現在が過去を、未来が現在を侵犯するのだ。江國香織における「時空の侵犯」、「境界の溶融」。
49話:豊は湯船で息子とタオルまんじゅうで遊ぶ。遠い昔、豊も父親にタオルまんじゅうをつくってもらったが、その父親は豊が高校生のときに病気で死んだので、自分に孫がいることを知らない。豊は高校生のころ、自分で自分に外国名をつけていた。ダン・ブレイディ(別名ラリー・フィッシャー)だった。台所で妻の焼いている「ハンバーグの匂い」(48話)が、風呂場のなかにまで漂ってくる。
50話:四十二歳で独身、恋人もなく趣味もなかった乗鞍文世(のりくらふみよ)はカルチャースクールのゴスペル教室で、“イエス、神様は私を愛している!”とキリスト教徒でもないのに三回くり返して歌う。そこはかとない孤独の諸相(47話)。
51話:「たとえ百人分の男性器がならんでいても、自分にはこの人のそれがわかるだろうと、北村いずみは思った。」は40話に相対する、ミュージシャン小出道郎のそれだ。「セックス」もの。
52話:江戸時代シリーズ。御端下(おはした)の勢喜の趣味は読書で『犬枕』『世界民族図鑑』を読んでいる。親友の加代とお喋りをするのを楽しみにしている。
53話:TV局の出張で北海道にいる雄大(ゆうだい)を行広(ゆきひろ)は追って来ている。雄大はあっというまに抱く抱かれるの関係に発展してしまった年下の行広の顔を眺めた。行広はフロントガラスごしのキタキツネに夢中だ。さりげないゲイ、境界の溶融。
54話:「並木道、ガレージの隅に犬小屋のある家、バス停、小児科医院の色褪(いろあ)せた看板――。何の変哲もない風景なのに、そこには何か、昇の心に訴えかけるものがあった。ずっと昔、子供のころに自分はこの場所に立ったことがある、という気がした。が、そんなはずはないのだ。この街に来たのは生まれてはじめてなのだから。」 十月の北海道だった。里美(さとみ)へ求婚と両親への挨拶。空間の「記憶」。
55話:先崎(せんざき)明日香(あすか)は子供のころからよく忘れ物をした。今度は腕時計だった。フェイスが黒でベルトがアーミーグリーンの腕時計は、去年離婚した元夫の菊地くんに恋人同士だったころもらったものだった。過去の遺物として捨て去るべきか、短かった結婚生活の記念として大切にしておくべきか判断の難しいところだ。物の「記憶」。
56話:成瀬瑠璃は妹の玻璃(はり)に「デジャブ」と言った(22話に続いて双子)。「場所はまさにここ、代官山のキッドブルーの前で、玻璃のうしろを宅配便のお兄さんが台車を押して通ったことも、そばにトラックが停めてあることも、空気が秋の午前中のそれで、まぶしく晴れていることも、なにもかも記憶どおりだ。」
「デジャブってね、過去の記憶じゃなくて未来の記憶らしいよ」 紺色の、いかにも手触りのよさそうなセーターを触ってみながら玻璃が言った(都会のシチュエーション、風俗、仕草の描写が、長く重い物語世界など無縁と想わせてしまう、江國の軽妙でお洒落な世界でもある)。「未来のいつかにいまを思いだすだろうって、脳が先取りしてなつかしく感じさせるんだって大沢さんが言ってた」と玻璃はバイト先の画材屋の店長大沢さんに恋心を抱いている。未来の「記憶」。
57話:平安時代シリーズ。柳が拾った物の数々を規那に見せる。宝物(コレクション)は、なかに蘇芳(すおう)色の液体の入った小さな容器(あけると蓋の先が筆になっているので絵師の道具かとも思ったのだが、液体をこぼしてみてもほとんど色はつかず、かわりにぞっとする匂いが立つ)(マニキュア?)や、“あたり”と焼き印を押された木製の棒(棒アイスクリーム?)、硬いとも柔らかいとも言いかねる、さわるとひんやりする白い四角い物体(ある種の覆がつけられており、それにはトンボの図が描かれている)(消しゴム?)、黒い円盤状の物体に、海松(みる)色の帯がついている、円盤状の物体は、何か硬い、透明なもので覆われていて、なかに針が三本閉じ込められている、針のうちの一本はつねに動いており、残りの二本も、ゆっくりだがときどき動く(腕時計(55話)?)。規那「法具だろうか」、柳「唐(から)のものということ?」 いつもそばに羽に緋色の痣があるカラスがいた。規那「見せてもらったお礼に、私も秘密を一つ教えようか」「もののけに加持祈祷(きとう)は効かない」 現代の物たちが、48話の羽が緋色のカラスによって平安時代に運ばれている。現在・未来が過去を侵犯する。
58話:世のなかはこわいものだらけだ。十一年前に夫が病死し、子供は授からず、両親もすでに他界していた人間不信の奥野広子は、玄関先の郵便受けまででて夕刊を取りだした。妙に古くさい服装の少年が三人と、そばに背広姿の男性がいて「さっき牛乳箱のことでお詫(わ)びにうかがった子供たちのことなんですけど」と聞こえたものの、玄関に飛び込んで鍵をかけ、インターフォンが三度鳴るのも黙殺した。
59話:(58話の続きらしく)テレビを観せてもらい、りんごも食べさせてもらったと息子たちに説明された佐伯敦夫は、「それは何とも申し訳ない」と、インターフォンにこたえてでてきた、いかにも人のよさそうな赤ん坊を背負った丸顔の女性に言った。敦夫の息子と、息子の友達など五人の子供がどやどやとでてくる。子供が壊した牛乳箱は古くなっていたので牛乳屋に新しいものをもらう、こういうのは慣れっこ、大丈夫です、と言う。「さっきのかたはお母さまですか?」と訊くと女性はきょとんとした顔になる。新聞はまだとりこんでいなかった。さっき見たのは何だったのだろう。会員制クラブのオーナーをしている敦夫は息子たちと別れ、私鉄と国鉄(!)を乗り継いで有楽町で降りた。接待役の女の子たちは美人揃いで、「こういうのは慣れっこ」と言った先ほどの女性とは種族が異なる。赤信号で煙草をくわえた敦夫は、交差点のまんなかで少年のような風貌の女性(ジーンズに運動靴、フードつきのトレーナー、子供のようなリュックサックをしょっていた)とすれ違いざまにぶつかり、「ロジョーキンエンクですよ」と睨みつけられる。敦夫は「は?」と訊き返したがこたえはない。敦夫は1970年ごろの人間に違いなく、58話の奥野広子が幻覚なのか、敦夫がそうなのか。
60話:江戸時代シリーズ。綾が路地にしゃがんでいると吹きたまが空中を漂った。子供の声が聞こえた。「ちーちゃん、降りなよ」「まーちゃんも乗って。お客さんになって」 幼そうな女の子のものだ。綾はじりじりして「ねえ!」と叫んだ。「どこにいるの?」 沈黙が返る。「まただね」と、二つの声が揃った。
<断片・モザイク>
「断片」について、ベンヤミン『ドイツ悲劇の根源』から。
《気まぐれな断片に分かたれていながら、モザイクにはいつまでも尊厳が失われることなく保たれるように、哲学的考察もまた飛躍を恐れはいない。モザイクも哲学的考察も、個別的なもの、そして互いに異なるものが寄り集まって成り来たるのである。超越的な力――聖像のそれであれ、真理のそれであれ――というものを、このことほど強力に教えてくれるものはほかにない。思考細片が基本構造を尺度として直接に測られる度合いが少なければ少ないほど、思考細片の価値はそれだけ決定的なものとなり、そして、モザイクの輝きがガラス溶魂の質に左右されるのと同じように、叙述の輝きは思考細片の価値にかかっている。断片のこまかな細工が造形的な全体また知的な全体という尺度に対してもつ関係に見てとれるのは、真理内実は事象内実の個々の細部のすみずみにまで沈潜していく場合にのみ捉えうる、ということである。》
「江國香織さんの最新作『去年(こぞ)の雪』。不思議な読後感を残す物語はこうして生まれた」(「家庭画報.com」2020.4.7)から。
江國は「留められないものを留めるような、断片でできた小説を書きたいと思っていたんです」と話す。
《――たくさんの人が立ち現れては消え、ときに時空を超えてつながってゆく。『去年の雪』はたとえ難い小説でした。書き始める時点では、どんな話にしようと考えていたのでしょうか。
江國 小説を書くときは、大体いくつかのヒントが重なっているんです。そのひとつが、巻頭で引用しているフランソワ・ヴィヨンの詩、「だけど、去年の雪はどこに行ったんだ?」で、学生時代に初めて読んで以来、いつかこういう小説を書いてみたいと思っていました。
それと、連載が始まる前にソール・ライターという写真家の展覧会を見たのですが、その写真が素晴らしかったんです。残された写真はすごくビビッドだけれど、被写体になった人たちは多分もうこの世にいないということが頭に残っていて。この2つがイメージソースになっています。
あと、これもこの作品に限る話じゃないですけど、小説を書くときはいつも読む人に、初めての手触りと感じてもらえるような、既読感のない小説を書きたいという気持ちがあります。
――世の中を映す、人間図鑑のようでもあって。
江國 人が何を考え、どう暮らしているか。人の気持ちや生活の細部などは、たとえ親しい人のことでもなかなか見えないものですが、小説のなかでなら見ることができます。人は自分自身のことでさえ、考えたこと、やったことの大半を忘れてしまいます。取るに足りないことだから忘れるのだけれど、今日という一日はたしかにあって、人はたしかにいたわけで。
今、生きている人はもれなく死んでしまうけれど、でも、とりあえず今日はみんな生きているように、留められないものを留めるような小説にしたいという思いがありました。
――最初からこれほどたくさんの人が登場すると思いながら、書いていたのでしょうか。
江國 断片でできた小説を書きたいと思っていたので、それは最初から考えていましたね。空からたくさんたくさん降っては消えてゆく雪片のイメージと、たくさんの人がそれぞれに生きている情景が重なればいいな、と。
――老若男女国籍を問わず、小説ではいろいろな人が主人公として描かれますが、作者はどんな立ち位置にいるのでしょうか。
江國 私の場合、一人称で書いているときでも、主人公に自分を重ねるとか、物語に入っているということはなくて、物語を書いているときは観察している感じです。子どものときの感覚というのでしょうか。子どもって、まだ世界にちゃんと参加できていない、おミソみたいなものなので、世の中を見ているしかなかった、そのときの感覚に近いのかなと思います。》
ソール・ライターの展覧会を見て、被写体になった人たちはもうこの世にいない、との感慨に、ロラン・バルト『明るい部屋』の母の写真における《それは(・・・)=かつて(・・・)=あった(・・・)》を思わせる。
ちなみにフランソワ・ヴィヨン『去年の雪』の鈴木信太郎による訳は、
《疇昔(ちゅうせき)の美姫の賦
語れ いま何処(いづこ) いかなる国に在りや、
羅馬の遊女 美しきフロラ、
アルキビアダ、また タイス
同じ血の通ひたるその従姉妹(うから)、
河の面(おも) 池の辺(ほとり)に
呼ばへば応(こた)ふる 木魂(こだま)エコオ、
その美(は)しさ 人の世の常にはあらず。
さはれさはれ 去年(こぞ)の雪 いまは何処(いづこ)。
いま何処(いづこ)、才(ざえ)抜羣(ばつぐん)のエロイース、
この人ゆゑに宮(きゅう)せられて エバイヤアルは
聖(サン)ドニの僧房 深く籠(こも)りたり、
かかる苦悩も 維(これ) 恋愛の因果也。
同じく、いま何処にありや、ビュリダンを
嚢に封じ セエヌ河に
投ぜよと 命じたまひし 女王。
さはれさはれ 去年(こぞ)の雪 いまは何処。
人魚(シレエヌ)の声 玲瓏(れいろう)と歌ひたる
百合のごと 真白き太后(たいこう)ブランシュ、
大いなる御足(みあし)のベルト姫、また ビエトリス、アリス、
メエヌの州を領(りゃう)じたるアランビュルジス、
ルウアンに英吉利(イギリス)びとが火焙(ひあぶり)の刑に処したる
ロオレエヌの健(たけ)き乙女のジャンヌ。
この君たちは いま何処(いづこ)、聖母マリアよ。
さはれさはれ 去年(こぞ)の雪 いまは何処。
わが君よ、この美しき姫たちの
いまは何処(いづこ)に
在(いま)すやと 言問(ことと)ふなかれ、
曲なしや ただ徒(いたづ)らに畳句(ルフラン)を繰返すのみ、
さはれさはれ 去年(こぞ)の雪 いまは何処。》
<『去年の雪』読解(61話~90話)>
61話:「コーポ・エリゼ」ものの拡がり。菅原聖(40話)、風間行広(53話)の会話。かつて聖の店で行広はバイトをしていた。「晴美ちゃんは元気?」と尋ねられ、聖は元気とこたえた。聖には多彩(で、しばしば同時多発的)な女性遍歴があるが、最新の一人が晴美で、「フツー」を信奉していて、「それフツーじゃん?」「フツーがいちばん」などと口にする。「俺には若すぎるのかもな、あの子は」と聖はとりあえず無難と思われる言葉を吐く。
62話:声が聞こえたとき、真奈美(22話)は家のガレージでしゃぼん玉を吹いていた。姉の千奈美はパパの車のキーを持ちだして、運転席に坐っていた。最初に聞えたのは「ねえ!」だった。次いで「どこにいるの?」 その声が現実のものではないことがわかった。「まただね」 真奈美が言うと、千奈美もそう言っていた。60話と相互に共鳴している。
63話:「死者」もの。佐々木泰三(36話)は、外国らしい寂れた浜辺に出現している。濡れた砂を踏むことも、波とたわむれることもできない。かつて、自分は死んだことがある、そして、その前には生きていたこともあるのだ、そう考えると愉快だった。鳴いているカモメを友達のように思った。
64話:「死者」もの。謙人(1話)はバイクの事故で、死んだのだった。自分のいる現実を観察し、耳を澄ませ、匂いをかぐ。ひどく粗末な造りの家で、土間に犬が三匹寝ていて獣臭い。七人のうち、四人は子供だとわかる。数の足りない布団から、汚れた手足がはみだしている。カラカラと、何かが回る、乾いた、どこかなつかしい音が家の外でしきりにしている。女の子が薄く目覚めて謙人の方を見つめたが、微笑み、また目をつぶった。「謙人は安堵(あんど)する。この部屋の平穏の一部でありたかった。謙人にとって奇妙なのはこの場所ではなく、自分が憶えている気のする遠い物事の方なのだから。」
65話:斉木静香(さいきしずか)は売れた本を棚に補充しながら、ミュージシャンの小出道郎(51話)との結婚について考えている。道郎に複数のガールフレンドがいることは秘密でも何でもない。が、自分が別格であることも承知していた、二十年のつきあいなのだ。気がつけば一人の男性しか知らないまま三十七歳になっているのだった。道郎の返事は「結婚ねえ」だった。「困ったもんだ」と声にだして言ってみる(そうすると、ほんとうは自分はたいして困っていないんじゃないかという気もする)。雨の日の店内には書物が湿気を吸収する、「ひそやかな匂い」が漂っている。
66話:石鍋(いしなべ)蓮(れん)は一限目が休講になってしまい、近所に住む祖父母の家に行くことにした。祖母が「すずめ」のことで役所に苦情を述べているのに、対処してもらえないらしい。居間全体に、祖母の入れる「コーヒーの香り」が漂い始めている。
67話:妹は泣きじゃくったが、恩地正彦(おんちまさひこ)は泣かなかった。母親の親友の東(あずま)さんと、その娘の秋子さんも泣いているのに、正彦にはそのすべてが、自分には手の届かない場所で展開されていることのように思える。もう限界でしょう、と医者に言われてから三日、母親はもちこたえた。「母親のふくらはぎを、正彦はいきなり思いだした。ずっと昔、正彦がまだ子供だったころ、脚がだるいからふくらはぎを踏んでほしいとよく頼まれたものだ。布団の上にうつぶせに寝た母親の、生白くつめた、やわらかかったふくらはぎ――。あのころの母親はまだ三十代だったはずで、いまの正彦より妹よりはるかに若い。「患者が死ぬと、お医者さまってほんとうに腕時計を見て時間を確認するのね」 医者と看護師が出て行くと、涙声で妹が言い、東さんも秋子さんも泣きながら笑った。泣くことも笑うこともできない正彦はただ窓辺に立ち、天気がよくてよかった、と、それだけを何度でも思った。」 抑制された断片ながらも、ジョイス『ダブリン市民』の「死せる人々(The Dead)」における叙情的エピファニーを連想させる。
68話:小学生の大隈修太(おおくましゅうた)は退屈している。ゲームにも玩具にも飽きてしまった。マンションの前の道をゆっくり歩いた。落ちていた空き缶を蹴りあげると、泡立ったコーラが地面にこぼれた。
69話:平安時代シリーズ。露玉(茴香と柳の母)という美しい名で呼ばれていたこともあったのに、近頃ではみんな、お母さま、と呼ぶ。あんなにやってきた男たちも、いまでは夫を含めて誰も閨房にやってこない。ガシャンと音が聞こえて、露玉が近づくと、目に痛いほど鮮やかな緋色の、筒状の物体だった。そばに濁った水がこぼれており、しゅわしゅわと音を立てて泡立つその水を目にした途端、泥の混ざった海水だ、と露玉は直感した(68話で蹴られた缶コーラ)。
70話:「豆腐は白い。」 白すぎると土鍋の中身を凝視しながら板橋歩(あゆむ)は思った。「ピアノやめていい?」と小学四年の次女がふいに言って、「だめ」という妻のひとことでその話は終るが、「だめ」であっさりひきさがる次女の思考回路がわからなかった。
71話:ベッドで行為を終え、髪を指ですかれながら、友人の結婚式で出会った、新郎の従妹(いとこ)であり妻帯者であり、自分より八つ年上の薮内章吾に「何を考えているの?」と訊かれたとき、桐葉が考えていたのは、昼間見たねずみの死骸だった。
72話:もちろん実行するつもりはないが、中島裕介はここのところ、誰かの顔に拳(こぶし)をめり込ませたいとばかり考えている。ただ殴ってみたいだけなのだ。犯罪なので実行はしないが、どんな感じがするものなのか、想像すると胸が躍る。「不穏」さ。
73話:かわいかったのに。ある日郵便受けにチラシが入って、「すずめ」がとまれなくなるような細工を電線に施します、と役所からの告知だった。すずめの大群について近所から苦情がでたためだと書いてあった。石鍋寿子(ひさこ)(66話の石鍋蓮の祖母)はすぐに電話をかけたが、工事は決定してしまったそうで、たくさんいたすずめたちは、一羽もいなくなった。
74話:八十になった知花(ともか)は、姪の香澄(16話)が選んでくれた男性コンパニオンの千葉(16話、19話、48話)の車で映画館に向かう。スクリーンで観るのは数十年ぶりだった。フードコートのようなロビーは広すぎるし、のっぺりしている。映画館特有のひそやかさがないし、これから観る別世界を予感させる、陰翳(いんえい)というものがまったくない。ここで映画を観ることはできそうもないわ、もちろん料金は一日分お支払いしますから、とつけ足して、千葉を安心させた。74話、75話と「老い」の悲哀が滲み出ているが、後半に向って「老い」「死者」「無常観」の断片が増える。
75話:香澄(16話)と暮らしている黒猫トムの擬人的な内面描写。トムは自分がおそろしく年をとったことに気づいている。一瞬と一日と一年の区別が歴然(・・)と曖昧(・・)になり、記憶と現状認識の区別もまた歴然(・・)と曖昧(・・)になり、ほとんどの時間をまどろんで過ごしている。家のなかをふいに風がわたり、部屋も、屋根も壁も床も消えてなくなり、床だったところは水が流れている。彼らがトムに気づくことはない。だからトムも、彼らには構わない。じきにみんな消えてしまうのだ、流れる水も、人も石も木々も。「無常観」。
76話:二十一歳の小渕優菜は四季のうちで秋がいちばん好きなのに、年々短くなっている気がしている。気候変化ばかりでなく、地震、台風、テロも津波も飢饉も核兵器も。この世はこわいことや心配なことだらけだ。夕方の空は刻々と暗くなっていく。バスが来ず、心細いときにいつもそうするように、スマホをとりだして、グループラインから一つを選ぶ。理生(りお)から、百華(ももか)から、雅美から、次々と言葉とスタンプが増えていく。が、世界じゅうのスマホが突然反乱を起こして停止してしまったら一体どうなるのだろう。優菜のスマホは生きもののように、手のなかで震え続けている。
77話:鶴田里美は飛行機を降りて到着口までの長い通路を歩きながら、弟の要が住宅リフォーム会社で請求料金の水増しや過剰工事はあたりまえと話したことにぞっとし、富山で十三回忌法要を済ませたばかりの、要をとりわけ可愛がった祖母が知ったなら悲しむよ、あたしが通報したら逮捕されちゃうよ、と訴える。が、要は大袈裟だな、逮捕なんてされないって、とめんどうくさそうに言い、「カツカレー、こっちに戻ったら食おうって飛行機に乗る前から決めてたんだ。向うじゃほら、魚ばっかだったから」とにやにやしながらつけ足して、一人で店に入って行った。25話のカツカレーと関係ありそうでなさそうである。
78話:また、いる。夜中に目をさましたちさは、寝ている家族の向う側に立つ、ぼんやりした人影を見た。土間には三匹の犬たち(ベエジ、シビチ、カッキャン)が寝ているが吠え立てないから幽霊ではないらしい。薄目をあけ、寝たふりをしたままちさは人影に向って胸の内で祈る。仏さまと思(おぼ)しき人影は、あいかわらずぼんやりと立っている。たくさんのかざぐるま(母親が内職で作って、家の外側で糊を乾かしている)が回るかすかな音がしている。64話で死者謙人が現れた家で、薄く目覚めて謙人の方を見つめた女の子の側からの視点。カラカラと、何かが回る、乾いた、どこかなつかしい外からの音は、かざぐるまだった。
79話:江戸時代シリーズ。綾は勢喜に、三十も四十もの吹きたまが空に昇ってゆくのを見た(60話)と教える。
80話:香坂真紀は、女子大時代の友人である小沼茉莉子(5話)に電話をする。一人娘の杏子が離婚して、孫の勇也(29話)を連れて帰ってきて以来、生活の静かさと平穏は消えて、ハンパない。「茉莉子?」という真紀の言葉に返事はなく、混戦している。雑音と他人の会話の断片(「……ホウグだろうか……カラのもの……柳……お礼に……効かない」)(57話の平安時代の会話)だけだったので、切ってかけ直すと無事につながる。時空の溶融。
81話:玉井(たまい)紫苑(しおん)は久しぶりに電話をかけてきた弟に、毎日愛犬ケイクの散歩に行くと、不思議なほど見事に会ってしまう八十がらみの老女が自転車に乗ってものすごいスピードで疾走してくるのが怖いと訴える。弟の反応は夫や息子と同様に紫苑が過剰反応しているという含みが感じられて憤懣やる方ないのに、弟は由香と離婚したと報告する。由香の希望で離婚はしたけど、当面いっしょに住む、とも。
82話:大場信吾はメキシコから帰国の空港で、熊本の両親に電話して無事に帰国したことを知らせた。長年の習慣となっている。マンションに帰っても、結婚も子供もいない。五十六歳になったいま、自分の人生を受け容(い)れている。九回の見合い経験があり、デートは何度もあるが、二度目の誘いに応じてもらえたためしはない。しかし一年の半分は南米への海外出張で、そこにはガールフレンドがたくさんいる。帰りついたマンションの部屋が拒絶しているような気がした。自分がこの部屋で異国を(というか、リンダやルイーサやマルガリータを)恋しく思うことはあっても、異国の地でこの部屋を恋しく思うことはないという事実を、この部屋は知っているのかもしれない。さまざまな人生。
83話:野沢晴美(40話)はバーテンダーの瞬に「聖さんは元気?」と尋ねられ「二週間会ってない」と正直にこたえる。鍋島亘と恋人の七海が反応する。「コーポ・エリゼ」もの(27話、28話、33話、40話、61話)の相手側からみた展開。晴美の恋人である菅原聖はやさしいが、家族にも友達にも紹介してくれない。喧嘩して聖の経営するビストロを飛び出した日に、有楽町の交差点で、くわえ煙草のスーツ姿で帽子までかぶっていた変なおじさんにぶつかって(59話)、「失敬」と言われた。何時代だよと思った。これまでいつだってシンプルイズベストで生きてきて、上手(うま)くいっていたのに、聖との関係においては、何一つシンプルにいかないのだ。雨は安定した降りぶりで空気をふるわせ、道路を濡らしている。
84話:寺村有為子(ういこ)の「無為」。パジャマ姿のままベッドに寝ころがって海外ドラマのDVDを観る。今月になって四度目か五度目だ。入社一年目なのに。連続ドラマのいいところは、観ているあいだ何も考えずにいられるところだ。次々に事件が起り、陰謀がうずまき、愛が燃えあがったり冷え切ったりし……有為子のかわりに人生を生きてくれる。だから有為子は何もせず、ただ観ていればいいのだ。
85話:牧野洋美(ひろみ)は空港の免税店で働いている。人は時と共に変るのだから、ヤドカリが引越しをするように、洋美も仕事を変えてきた。ゆうべひさしぶりに会った、今年六十六歳になったはずの父親(大手のレコード会社に勤めて羽振りがよかったのが、何らかの不祥事(そのときには両親はすでに離婚していて洋美は理由を知らされなかった)で離職を余儀なくされて以来、どんな仕事をしているか謎だった)にまたも無心された。母親に相談すべきかと思ってもみたが、母は自分の人生から、かつての夫をとっくに抹消していた。退社時間まで接客に追われた。みんな移動している。まるで回遊魚とか渡り鳥とかみたいで、生れ育った土地での日常生活だけでも、十分に疲れるというのに。25話、77話、82話とおなじく「空港」が舞台だが、どれも『ダブリン市民』の「麻痺」症状に似た倦怠感がある。
86話:いま市岡謙人(1話、64話)がいるのは馬小屋だった。小屋の隅の、ほとんど天上あたりにいるようだった。輪廻における「中有」のような浮遊感。馬が五頭。体臭がきついが、生命と体温のある好ましさを感じる。ここがどこか考えることを、謙人はもうやめている。どこであれ、いまの謙人にはここが世界のすべてなのだ。「死者」もの。
87話:「死者」ものが連続する。ほんとうに死んだのか、原田真弓は納得がいかない。涙まじりの父親の悲痛な言葉(「もういい。もう頑張らなくていいから」)も憶えているが、それでも納得がいかない。だってここは、どう見ても遊園地だ。ポップコーンの匂いをしみじみ吸いながら考える。痛みはもう感じていない、それは自分が死んだ証拠かもしれなかった。真弓は父親の背中で眠ってしまったらしい幼い子供のほっぺたに見惚(みと)れる。肉体を持たないいまの真弓には、それに触れることはできないが、吸い込まれそうになるほど近づいて、その白さ、息遣い、質感にびっくりする。子供から離れる。青い空だ。自分には何の義務も予定もしがらみもない。ちょっと茫然とする、そらおそろしいような自由だった。
88話:「死者」もの。井波真澄は花を見ている。さるすべりの花で、夏だとわかり、夏らしい空と日ざし。温度と湿度を感じてもいる。自分が浮遊している気持ちはしないが、地面に立っている気もしない。薄い花びらがふるえていて、淡い匂いも感知できる。死んだ記憶はないし、死ぬ前に生きていた記憶もない。自分が井波真澄という認識はないが、目の前の花がさるすべりという認識だけがあった。それで十分なのだった。浮遊感、ふるえ、匂い。
89話:五頭の白馬の絵を前にバイトの成瀬玻璃(56話)は、恋心を抱く店長の大沢淳一郎と話をしている。注文品を取りに来ない古川さんに電話すると、例によって、奥さんらしき人が出て、古川は留守にしているが、電話があったことは申し伝えておきますと請け合ってくれるが、いつまでも取りに来ないのだった。
90話:大学まで佐賀の実家住いだったが、就職を機に上京して一年半の北條和樹は、三軒茶屋のドラッグストアにきょうも吸い寄せられて、入浴剤コーナーに向かう。日によって香りのちがうものを試したいので、小袋で買う。“やわらかで透き通るようなコットンミルクの香り”、“やさしくフルーティーなイチジクミルクの香り”など四種類がお気に入りだった。何かと物入りなので、帰ってカップ麺を啜ることに決める。実家を離れたのは失敗だったかもしれないと和樹は本気で考え始めている。とはいえ、昭和メンタルの父親に、尻尾をまいて逃げ帰ってきたとは思われたくなく、入浴剤を入れた風呂につかることだけがたのしみなのだった。人々の、余分なものから成り立っている他愛もない日常だが、寂しげながらも幸福感がある。
<物語・時間>
江國香織は「須賀敦子の魅力」という対談で、湯川豊相手に須賀の魅力を語っているが、これらは多分に江國の自己分析、内省であろう。
《湯川 さっきちょっと対談に入る前に事前にお話していたら、物語というものを常に感じさせる、あらゆる書かれたものから物語的なものというものを感じ取る、そういう性質に共通点みたいなものがあって、だから懐かしさも感じられるんだというふうなお話をちらっとなさっていますけれども、も物語的体質というか、そういうものは作家である江國さんご自身の中にも非常に濃厚にあるというものでしょうか。
江國 そうですね。ただそれは、小説家だからではなく、もともと性質というか体質なんだと思います。私は、小説を書いていなくても、物語しか信じられないところがあって、書いたり読んだりしていないときでも、現実を物語のように感じてしまうんです。須賀さんにもそのような匂いを感じます。》
《江國 ちょっと抽象的なんですけど、概念的に、物語の生息する場所というのがあると思うんですよね。それは、ありとあらゆる物語がそこにある、そこに行かれるか行かれないかのことだと思うんです。
逆に言うと、でも、そこから逃れられないというのもあって、須賀さんは回想的なものを多く書かれて、実在の名前や土地や、ノンフィクション的な要素のあるものを書かれていますけれども、いくら事実に即して書こうとしても物語になってしまうという言い方もきっとできて、物語を書くまいと、もし思われても、物語になってしまう。それは魅力であると同時に、ある種の枷(かせ)でもあるのではないか。
きっと、書かれるだけじゃなくて、そのことはよく自分でも考えるんですけれど、普通に会話をしていても、言葉にした途端に、きのう何を食べたとか、お元気ですかとか、お久しぶりですという言葉すらも、言葉にしてしまった途端に物語性を帯びる、そういう人であったようなきがします。》
《江國 たとえばですが、須賀さんの『塩一トンの読書』という本があり、それは、いろんな本について須賀さんがお書きになったエッセイをまとめたものですけれども、その中にジャン・グルニエという作家の『エジプトだより』という本の諸評があります。そこで、須賀さんはその本の中で紹介されているアラブの詩人の言葉を引用されています。
「君より前に生きた人びとの骨からなるこの大地の上をそっと通り過ぎよ。君は不用意にも何の上を歩いているのか知っているのか」
こういう文章を須賀さんが引用していらして、確かに、そこがイタリアであれ、日本であれ、エジプトであれ、君なり私なりが歩く場所は、それ以前のものすごい数の人の骨の上だし、歴史の上だし、それ以前のすべての後ろにある。その認識が須賀さんにはとても強く、しかも自然にあったような気がするんです。》
《湯川 江國さんのこの短い文章(筆者註:須賀敦子『霧のむこうに住みたい』解説》を読んで、思ったことでもあります。江國さんはここで、「本質的には物語とはすべからく長く重く暗いものだということを、須賀さんのエッセイは思いださせてくれる」と書いていらっしゃるんですね。
江國 (前略)だからこそ、小さいことが、仲間がいるということとか、たとえば仲間とめぐり合えた、夫とでもいいんですけど、親友とでも、人と人が出会うということ、そして、ある街を歩くということ、その一瞬が永続はしないからすばらしいわけで、そういう永続しないものたち、既に書かれた時点でもういなくなってしまった人や変わってしまった街、今現在のものだとしても、明日には変わってしまうかもしれない、十年後には、まず間違いなく変わってしまっているであろうものたちへのまなざしというのが、ご本の中では、すごく徹底して、その側に立たれた方であるような気がします。》
《湯川 江國さんは二十一歳のときに『ある家族の会話』をお読みになって、非常におもしろく、心惹かれたという文章がここにあるんですが、『ある家族の会話』をどういうふうにお読みになったかというのをちょっと思いだしてください。
江國 (前略)まさにタイトルどおり、家族の話なんですけれどね。家族間でやりとりする言葉の小説なんですね。ある人はこういう口癖だとか、兄弟でも合い言葉じみたこととか、お母さんの言い間違えとか、そういうことがたくさん出てきて、もう、そういうものがただ楽しくて愉快で、何度も読みました。しかもそのとき、私は漠然と物を書きたいと思っていて、二十一のころですけれども、粗筋が大事ではない小説でもいいんだという、それこそクライマックスがあったり、起承転結がはっきりしていたり、教訓みたいな胸打つテーマみたいなものが、ないと言うと乱暴ですけど、わかりやすくなくてもいいんだというので励まされもしました。》
初期の短篇集『つめたいよるに』(1989年単行本刊行)の文庫本で川本三郎が解説した《やさしい。悲しい。といってその気持を深く書きこまない。最後のところで作者は、ふっと読者の前から姿を消していく。説明をしたり、説教をしたりしない。大仰に感動を盛り上げようともしない》は、須賀敦子から学んだ流儀・方法論であろう。そのうえ川本が論じた、《江國さんは、子どものころ早くに、好きなものはいずれ消えてしまうという悲しい事実を知ってしまったのだろう。江國さんの小説世界はそこから始まっている》、《きっと江國さんにとっては、死とは、その“ずっと昔の、私がまだ生まれてもいないころ”に帰っていくことなのだろう。生きているときには、はっきりと意識していなかった故郷に帰っていくことなのだろう。江國さんのなかでは、いまと昔がどこかでつながっている》は、約30年後に書かれた『去年の雪』の「物語・時間」に通底している。
<『去年の雪』読解(91話~123話)>
91話:さやかは、飲むと自分がどんなにいい夫かをまくし立てる磯田さんの斜め前に坐ったことを後悔している。「オレはヨメさんの自由を認めているから」、「ヨメさんを家内とか言う男はゴミだね」、「とにかくね、自由にさせとくのが円満の秘訣(ひけつ)だよ」 電話がかかってきたふりをしておもてにでる。飲み会が嫌いではないが、疲れるとも思う。ということは、たぶん、生きることは疲れることなのだろう。
92話:平安時代シリーズ。茴香は奇妙な夢を見た。あばら家のようなところにいるのだが、そばにいる男は祝言をあげたばかりの正嗣ではなかった。すこし前まで正嗣以外にも通ってくる男が何人かいたが、夢のなかの男はその誰とも似ていなかった。屏風の一つに五頭の白い馬(89話?)が描かれていた。朝食を食べていると、妹の柳が入ってくる。昔から、飾り糸と見れば三つ編みにして、乳母に叱られていた柳が、几帳についた飾り糸を意味なく三つ編みにしてしまう。ほどいても糸にうねりが残ってしまい、なかなかまっすぐ流れるようには戻らないのだ。
93話:時岡明日美(ときおかあすみ)の掃除はきりがない。夫を会社に、娘を小学校に送りだして、寝室、リビング、廊下、階段、トイレ、風呂場などの掃除に取りかかり、八つある室内ドアの内側と外側を拭き、窓枠に雑巾をかけるころには午後一時を過ぎていた。ようやく済ませ、ソファの上にたたまれた膝掛けを見て、フリンジがまたしてもすべて三つ編みにされていた(娘のしわざに違いなかった)(92話の柳のしわざ?)ことに腹が立った。モヘア糸はほどくのに手間がかかる上、周囲が毛羽だらけになるのだった。
94話:掛川文月(ふづき)は藤丸龍馬(ふじまるりょうま)にうしろから抱きしめられて冬の海を眺めている。十年前に文月が勤めていたアパレル会社とおなじビルに龍馬の会社も入っていて、雑談をする程度だったのが、今年の夏に偶然再会したのだった。すこし離れた場所で、中年の男性が飼い犬にフリスビーを投げてやっていた。フリスビーが、龍馬の足元近くに落ちて、レトリバー犬が突進してくる。「シンディ!」 龍馬は腰をおとして犬をねぎらう。「それは自業自得でしょ」 荒い犬の呼吸音と波の音に混ざって、小さくだがはっきりと聞こえた。「ヨーロッパ?」「絶対に認められない。言語道断だね」「いいわねえ、ヨーロッパ」「だけどもさ、ヨーコさんだって悪気があって言うわけじゃないだろ」(「ヨーコさん」は4話とおなじ声だが、どこから侵犯してくるのか? 「ヨーロッパ」はどこからか(33話の留学話が近いけれど)?) 文月はぞっとして鳥肌が立つ。
95話:米屋の奈良橋勝善(かつよし)は自転車で疾走してゆく老女(81話)(米屋で御用聞きにまわる勝善なのに老女の住いに心あたりがないと呟くと、妻は老人ホームじゃない、とこたえる)の毅然とした表情や姿勢のよさに、高校時代に憧れていた一学年上の女性、橋本先輩を思いだし、それなら六十八か九だが、老女はどう見ても七十を越えている。私たちも一度、老人ホームを見学に行ってみない、と妻は提案してくる。
96話:加々美(かがみ)双葉(ふたば)は退屈している。ママといっしょに買物に行かず、留守番を選んだので一人で留守番をしている。いま小学二年生で、友達がいないが、誰とでも話をするので先生が言うとおり「クラス全員が友達」なのかもしれない。家のなかをぐるぐる歩きながら、デタラメな歌を歌う。「げんかんはー、チェーンをかけたのであかないよー。ドロボーがきてもあかないよー。オオカミがきたってあかないよー。魔女がきたってあっかないよー。トラがきたってあっかないよー。」 「子供」もの。
97話:「死者」もの。今泉牧也(いまいずみまきや)は幼い頃ヴァイオリンの神童と騒がれたが、高校になると興味を失い、大学時代はゴルフに熱中し、結婚して息子二人に恵まれたが十一年で離婚した。父親が亡くなり、その多額の借金を返済し終えたところで再生不良性貧血という病いを知らされたときには、かなり進行していた。でも、それらは霧の向うの過去のことで、いまの牧也が知りたいのはここがどこかということだ。死んで以来さまざまな奇妙な場所に、自分の意志とは無関係に、出現している。湿ったような書物の匂いがして、棚にならんでいる。図書館かもしれない。牧也は読書家ではなく、図書館ともあまり縁がなかったが、今は書棚の間で安らかさに陶然としている。幼い頃にくり返し眺めた図鑑(恐竜図鑑、乗り物図鑑、昆虫図鑑)を思いだす。
98話:「死者」ものが続く。死んで随分たつので、森田あやめはもう、ここはどこだろうとは考えない。かわりに、ケモノくさい、と思って瞬時に活気づく。自分があやめであることも、子供を五人産んだことも、神田の大火を経験したことも、二度の戦争を生きのびたことも憶えていない。いまは視覚も聴覚もないので、自分が犬の毛のなかにいることを知る手がかりがない(犬は若い雌で、ケイク(81話)という名をつけられているが、あやめにそれを知る由はない)。憂いも曇りもなく、輝かしいばかりに幸福だった。
99話:「死者」もの。佐々木泰三(63話)は漂っている。「パパはあなたのことが心配なのよ」女性の声がした。「もうすこし時間をかけたら?」 声はほとんど泰三の耳元でささやかれる。「ママはどう思ってるの? 若月くんのこと、ママもつまらないと思ってるの?」とベンチの娘が言って、煙草の煙を吐いた女性が「思ってるわ」と言った。娘の恋人を認めるとか認めないとかの話だろうと理解はできたが興味は持てず、それよりも風呂あがりの肌の匂いに郷愁をかき立てられて、すぐそばにいる女性の顔が見たいのだった。彼女の肉体が自分を通りすぎるのを感じる。
100話:ラブホテルの壁をうろうろと這っている、ごく小さな蜘蛛に気づいて村上周太(しゅうた)は顔をしかめる。諸岡(もろおか)なつめ(確かそんな名前だ)は気づくふうもなく、ブラジャーをはずしているところだ。簡単すぎると周太は思う。暮に飲み会で知り合って、連絡先を交換して別れ、会いたいとメッセージをやりとりしたあとで、新年早々二人で会った。こうなることを、期待していたのではなく知っていた。大学生活も終りに近づいたいま、わかるのは女の子というものが浅はかな生きものだということだが、浅はか故に好まれるなんて最低だった。よく知りもしない男とこんなところに来やがって。怒りに任せて周太は突き、突いて、突く。罰するみたいに、あるいは、おなじ罪で罰せられていることに腹を立てて――。いっしょにシャワーを浴び(マスカラが溶け流れて黒くなったなつめの顔はまぬけだった)、でてくると、まだ蜘蛛がいた。「セックス」もの。
101話:朝、窓を開けた瞬間に、富樫(とがし)敏子(としこ)は、きょうも世界を享受できることが嬉しかった、ああ、私、まだ生きている。七十八という年齢は、まだそれほど死に瀕してはいないのかもしれないが、死から遠いわけもなく、自分はいまお迎えを待っているところなのだという自覚がある。楽しい朝食が済むと簡単に掃除をして、朝刊を丹念に読み、息子と娘から電話がきたら、おもしろい記事を話してやる。散歩、買物、昼風呂、映画専門チャンネル、恵まれた老後だと思う。両親も夫も多くの友人たちもいなくなってしまったいま、自分が生きているのは奇妙な気がする。すばらしい人たちだったのだ。ああ、私、まだ生きている、と小躍りしそうに嬉しくなるとき、恥かしさと申し訳なさに身がすくむ思いも、同時にする。「老い」ものだが、明るい。
102話:浮かせた左足を戻す床がないほどの満員電車で、二十七歳の堂島(どうじま)灯(あかり)は、若月くんに、どう説明すればいいのかわからない。毎年箱根で過す正月は最低だった。若月くんとの結婚を両親に反対されるとは想像もしていなかった。反対の理由は“つまらない”からで、父親は他にもひどいことをたくさん言った。いやな空気を変えようとして、母親が散歩に連れだしてくれた(99話)のだが、母親の意見も大同小異だった。嘘はつきたくないので、時間をかけなさいと母親(自分は二十一で結婚したのに)は言っていたから、結婚はもうすこし待つように言われた、とだけ若月くんに話すのがいいかもしれない。
103話:5年間同居していて、紙を一枚役所に提出するだけで簡単だった結婚の、初めての日曜日のお祝いということで、地下鉄の運転士である無口な浦部と、スーパーマーケットでステーキと海藻とオイルサーディンとりんごジュースを買ってマンションに戻った優雅(ゆうが)は、買った憶えのないピンク色のトイレットペーパー(古めかしく、外側のビニール袋が劣化している)(30話)を目にして戸惑う。
104話:江戸時代シリーズ。勢喜の家の向いの宿で長逗留している絵師に興味を持った加代は、奉公先から休暇をもらって帰っている加代と、妹の綾と茂のことで川辺の縁台に坐って話をしている。ぽちゃんと魚が跳ね、加代のすぐ耳元で、子供の歌う声が聞こえた。「げんかんはー、チェーンをかけたのであかないよー。ドロボーがきてもあかないよー」 まわりを見回したが、それらしい子供ぬ姿はない。「オオカミがきたってあかないよー。魔女がきたってあっかないよー。トラがきたってあっかないよー」(96話) 「いまの聞こえた?」と加代が訊くと勢喜は「魚が跳ねただけよ。加代ちゃんたらこわがりね」と可笑しそうに笑った。
105話:「白」の逸話。「餅は白い。」 気品というか、何か特別な風格がある、と早期退職をした五十八歳の梅原充生(みつお)は思い、「何かに似ているような気がするんだけどね」と呟くと突然、目の前の光景のすべて(台所の炊飯器、リビングのソファ……)が自分とは関係ないものに思え、昼食も摂らずに床に坐って工作(ドールハウス)に熱中している妻も、見知らぬ女(二十八年も)だと思った。大根おろしまみれの餅の残骸を流しに捨てた瞬間、それが冬の朝の障子の、やわらかく仄(ほの)あかるい白さと気づく。が、そのときにはもう餅は生ゴミ用のネットのなかにまぎれて見えなくなってしまった。
106話:「友達だと思っていたのに」と木村舞(まい)に言われ、大友(おおとも)だりあは泣きたくなった。「二千円でいいから」 舞にはもう十回近くお金を貸していたが、返ってきたことは一度もない。恵比寿と渋谷と明大前で三回乗り継ぎをして、安心な家に帰りたかった。そのためなら二千円払ってもいいと思った。お金を渡すと「ありがと」と言って、ぱっとだりあを抱擁し、「いい友達」と囁(ささや)いた。だりあはいま高校一年生で、卒業までまだ二年以上、あといくら舞にお金を貸すことになるのか、考えるのもおそろしかった。
107話:ベッドに寝たまま安積(あづみ)大介(だいすけ)は、カラスが至近距離まで匂いがかげそうなほど近づいてきたのを、あれも夢の一部、朦朧(もうろう)とした意識が見た幻想だったのかもしれないと思った。半年ほど前からやってくるようになったカラスは片側の羽に赤い汚れが付着していて(48話)、ふてぶてしかった。ゆうべ発熱し、朝いちばんの病院でもらった風邪薬が効いたのか、汗で湿ったパジャマを着替えると、だいぶ楽になっていた。電話が鳴って、“なみ”と表示された。つきあい始めたばかりの彼女からなのででてみると、彼女の声ではなく、キーンというすさまじく大きな耳鳴りのような金属音が止む気配がなく、いったん切ってかけ直すと、今度は本人が出て、電話などしていない、テレパシーかも、大介くんのことを考えてたから、と。しばらく喋って、寝る前にもう一度薬をのんでおこうと枕元を見ると、確かにそこに置いたはずの薬が忽然と消えていて、またしても、熱のせいで頭がどうかしたのではないかと心配になる。
108話:平安時代シリーズ。母親の乳母だったというお客があって、柳は笙を弾かなくてはならなかった。庭に出ると、旅の疲れをとるために寝(やす)んでいると思ったお客さまがいた。“せいせい”する場所、築山(つきやま)に案内すると枯れ草のなかに白いものが見えた。紙で上手に作られた袋で、まぶしいほどぴかぴかした銀色の、手が切れそうに新しく四角い物体が三つ(それぞれがたくさんの白い玉を内包している)入っていた。あのカラスが運んできたに違いない、ということは、たぶん唐のものだ。袋にはいかにも唐っぽい字文字――内服薬とか安積大介とか――がならんでいる(107話)。宝物(コレクション)に加えて、早く規那に見せたい。平安時代シリーズはここまでで、クライマックスもなく、漂うように……
109話:綿貫(わたぬき)誠司(せいじ)のスマートフォンには千枚近い写真が保存されている。撮ることも撮られることも好きでなかったのに、数年前に妻の病気が発覚し、すぐに連絡がつくように購入したのだが、妻は逝き、電話が残った。撮り始めると癖のようになった。撮りたいと思ったものを時空間ごと、確かに閉じ込められたと感じる。とどめ置けないものをとどめ置くこと。子供たちか、じきにできるかもしれない孫たちの誰かが発見し、鑑賞してくれる可能性もゼロではない、と思いたい。たとえば自転車で疾走する老女のうしろ姿(81話、95話)、電線に止まった夥(おびただ)しい数のすずめ(73話)、池に張った薄氷、風呂場のカビ、心に訴えかけてくるものは、存外そこらじゅうにある。「とどめ置けないものをとどめ置くこと」とは『去年の雪』のテーマでもあろう。「老い」ではあるが、「新たな生」でもある。
110話:隣の席の金丸美生(みお)が「言葉ってどこに行くんだろう」と、また変なことを話しかけてくる。木村舞(106話)は美生が苦手だ。舞は小学校に入学した日から舞と呼ばれていたのに、木村さんと呼んでくるのもしゃくにさわった。「だってほら、一度発生した運動は永遠に止まないっていう法則があるわけでしょう? そうしたら、一度発生した声はどこに行くんだろう。ずーっと空中を漂ってるのかな」「消えるよ」舞はこたえる。「美生はね、ずーっと前に弟に言われた『ばかじゃない?』っていう言葉がときどき聞こえるの。思いだすとかじゃなく、ほんとに聞えるんだよ」 この子は、だりあ(106話)ほどには弱くない。舞には本能的にわかる。弟に、そんなこと言うとしめるよって言ってやんなよ、と言うと、無邪気そうに笑って、「美生は誰かをしめたりできないもん、木村さんと違って」と言うのだった。美生の疑問は、『去年の雪』で飛び交う時空を超えて侵犯する「声(言葉)」にも言えることだ。
111話:いつもとおなじ夕方だった。楫取清(かんどりきよら)は一度帰宅してシャワーを浴び、楽な恰好で約束の店にでかけた。いつもとおなじ夜だった。交際五年目になる恋人の岩渕(いわぶち)真人(まこと)との関係は順調で、週に二日は、いつもの店(和洋中の三軒のどれか)で会って食事をする。 “たべるモード”に入ったのに、「別れてください」というのが真人の言葉で、冗談ではなく、笑っていなかった。「ごめんなさい」「他に好きな人ができました」とシンプルな説明を加える。清は箸をとったが、味はわからず、涙はでなかった。「わかった」清は言い、席を立ったとき、ひきとめてもらえるはずだと、どこかで期待していたが、真人は何も言わなかった。見慣れた景色のすべてがよそよそしく、もう何一ついつもとおなじではない。パスモをだそうとポケットに手を入れると、代々木(よよぎ)のピザ屋(真人と行くいつもの“洋”)で会計のときにくれるキャンディの包み紙が四枚出てきた。傷を抉(えぐ)るような気持ちで反対側のポケットもさぐると、先週真人と観た映画の半券や、去年真人と行った社会人アイスホッケーのチケットがでてきた。すべてポケットに戻す。それらをどうすればいいのか、見当もつかなかった。
112話:真織が五人の子持ちだと言うと、みんな驚く。フェイスブックの“友達リクエスト”の文言は短く、アロー、真織、私を憶えてる? スウェーデン人のパニーラからで、加齢による変化はあるもののなつかしい友人の顔だった。三歳の長女が寄ってきたので、卵に絵をかいてくれる?と提案する。真織は持てるエネルギーのすべてを子育てに傾注している。過去を、いまではまったく思いださない、というより、自分ではない誰かの過去のように感じる。パニーラをめぐる記憶はアリにつながる。美大生の真織は政府の助成金を得てフランスに留学したが、学業など放棄して、人生の探索と恋愛にのめり込み、留学生だったパニーラとよく遊んだ。八年間、アリ一筋で、永住するつもりだったが、アリに新しい(しかも男性の)恋人ができた(自分がゲイであることに「ようやく気づいた」と説明された)ときには絶望した。アリなしのフランスは耐え難く、逃げるように帰国して、結婚目的のマッチングサイトに登録した。三十歳だった。使い果たしたと思っていた愛情は、一人目の子供が生まれると、アリのときとは比較にならない烈しさで噴出し、十三年間で五人が産まれ、愛情とは別の観点から選んだ夫のことも、子供たちの父親だと思えば大切にできた。さまざまな顔の描かれた卵を手にとって見ながら、パニーラには返信すまいと決める。あの娘はもういないのだ。それに、子供を産み育てるより大切なことなんて、結局のところこの世には一つもないのだから、と。「新たな生」。
113話:四日前に妻が出て行った。三十二歳の渡辺耕介(こうすけ)は、離婚届が置いてあるリビングは避けている。このまま離婚してしまえばわずか三年で結婚は潰(つい)え、出会いから結婚までの七面倒くさいプロセスをくり返さなければならないので、妻に戻ってきてほしかった。枕元には週刊誌の山とカップ麺の空容器。週刊誌の「食べてはいけない加工食品の見分け方」「あなたの血管年齢は大丈夫か」という記事を読んで暗澹とした。カップ麺を食べたと知ったら妻は激怒しただろう。最近どこからか大量に飛んでくる「すずめ」(73話)が、やかましく鳴き立てている。
114話:江戸時代シリーズ。絵師の犬喜(いぬき)が描くような奇妙な絵を加代は見たことがなかった。怪しさと美しさと物語性で加代の心をざわつかせる。「またあの犬がいた」と、行為のあと、布団に横たわった姿勢で犬喜は言う。真昼間からこんなことをしていると知ったら、勢喜や妹たちは驚くだろう。煮売屋の裏の道に、誰かを待っているみたいに、じっと立っていて、他の犬とは違うものが、あの犬にはある気がする。灰色でおそろしく痩せている。加代の腹に唇をつけ、このくらい滑らかな肌をしているし、妙な野良着みたいなものまで着せられている、と加代を笑わせた。江戸時代シリーズもまた、起承転結も続きもなく……
115話:風呂場だ。電気のあかるさと閉塞感(へいそくかん)に市岡謙人は怯む。「俺だって会いたいけど」「五月の連休にはまた帰るし」と風呂場の外側で男の声が聞こえた。相手の声が聞こえないので、電話で話しているのだろう。男が入ってきて、バスタブに入浴剤をふり入れ、「きょうはイチジクミルク」(90話)と電話の相手に言った。生起を男は放っていた。キナ(17話)や、寝ていた子供たち(64話)や犬たち(78話、)や、馬たち(86話)とおなじように。「死者」もの。
116話:浪人が決定したきょう、海堂(かいどう)治(おさむ)が感じたのはまず解放感だった。四校七学部全部終ったのだ。ローストビーフやちらし寿司(ずし)や、合格祝いになるかもしれないという母親の期待を裏切り続けた。ここ一年自分に禁じていたあれこれ――ゲーム、漫画、街をぶらつく、などなど――を、いましばらくのあいだはしてもいいのだ。来年また落ちたらと不安がないわけではないが、一年や二年の回り道が何だという気もあり、早く食事を終えて自室で漫画雑誌の読破にとりかかりたいのだった。
117話:若い男が若い女を自宅アパートに監禁した上殺害したというニュースの続報を。糸井(いとい)武男(たけお)(43話の「コーポ・エリゼ」に住む糸井七海との関係は?)は見ることも読むこともできない。その若い男が自分の孫だからだ。喪失感。信じてきたもの、まっとうな人間であるという認識、誇りや信頼、心の平穏といった、あたりまえに所有していたはずのものがすべて消えてしまった。せめてもの救いは、妻がすでに他界していることだ、生前あれほどかわいがっていた孫が何をしでかしたか知らずに。武男は、あの少年(やさしい子供で、金魚を水槽に閉じ込めることさえ嫌がり、携帯電話の使い方を辛抱強く教えてくれた中学生だった)と拘留(こうりゅう)されている犯人とはべつの人間だ、というふりでもしないと正気を保てそうもない。世界はすっかり、そして永久に変容してしまった。
118話:谷田部理保(やたべりほ)と島原(しまばら)恭子(きょうこ)は小学校時代からの友達で、学習塾にもいっしょに通い、無事おなじ中学に入学した仲で、こんないい天気の日に学校にいるのはもったいない、と公園のベンチに座って、あるジャンルのなかでいちばん好きなものはどれか、について話している。「シブースト」「いちじくタルト」、「サーティワンならキャラメルリボン、ホブソンズならアップルパイ」「サクレレモン」。趣味や考えることが違っていて、驚かされる。「車? 車種とかわかんないな。興味もないし」と理保はこたえ、恭子は「私はハマーが好きなんだけど、もう製造されてないんだって。まあ、私が大人になって車を買うころには、もっといい車がでてるかもしれないけどね」と、まだ免許も取っていないのに、車を買うことが決っているかのような口ぶりに、理保は驚かされ、他に何と言っていいのかわからずに「でてるといいね」と言った。「子供」もの。
119話:「若い娘たちの気配だ、とそれ(・・)は思う。」 自分の名前もとっくに忘れてしまっているのに、若い娘たちというのがどういうものかは忘れていないのだ。老人が手にしている新聞を、それは新聞としては認識しない。ただ、紙。とだけわかる。それがいま感じているのは草だ。それは気持ちよくその静かな生気を味わう。「死者」もの。
120話:119話に続いて「死者」もの。「またべつのそれ(・・)もおなじ公園にいる。」 それが感じているのは硬さとつめたさで、青銅製の騎馬像に密着しているからだ。いまやそれにわかるのは、自分と自分以外のものの区別だけだ。ヘリコプターが存在しないころを生きて死んだそれはしかし、その振動を世界の鼓動の一部として、何の苦もなくあたりまえに受け容(い)れる。「死者」ものには詩情が伴う。
121話:スーパーマーケットで、近田ひかりは、犬のバンビをおもてにつないで待たせ、八人の友人を手料理でもてなすための買物を手早く済まそうとしていた。バンビはイタリアングレイドハンドの雌で、皮膚はベルベットみたいに滑らかな手ざわりで、セーターを着せられ、華奢(きゃしゃ)で優美な身体つきだ(114話)。「バンビ?」 声をかけたが空中の一点をじっと見つめ続ける。まるで、ひかりには見えない何か――あるいは誰か――が見えるみたいに。
122話:五歳になったばかりの尾形啓斗(けいと)は退屈している。母親に美容室に連れられているからで、うろうろ観察し、お姉さん的な人に対応されるが絶望し、母親の膝につっぷして嗚咽(おえつ)してしまう。「子供」もの。
123話:坪倉新那(にいな)は喘息の発作で学校を休んでいる。吸入器を当てると、いつものように治まり、もう百回くらい観た気のする“アナと雪の女王”のDVDを観せられたりしているうちに回復する。リビングのひきだしからパパが眼鏡を拭くときに使う小さな紙の束から、そっと一枚だけ破りとる。鼻に、ほっぺたに、おでこに、あごにあてるが紙には何の変化もない。パパがすれば、紙はたちまち濃く深く色を変え、透き通る(!)のに。パパは、その不思議を見せながら、新那も大人になればできるようになるよ(あぶらの問題だそうだ)と言ってくれる。“大人になる”のはいつなのだろう。待ちきれなかった。「子供」もの。
こうして江國香織『去年の雪』は、「さはれさはれ 去年(こぞ)の雪 いまは何処」のごとく……
(了)
*****引用または参考文献*****
*江國香織『去年の雪』(角川文庫)
*江國香織『つめたいよるに』(解説:川本三郎)(新潮文庫)
*江國香織『号泣する準備はできていた』(新潮文庫)
*江國香織『泳ぐのに、安全でも適切でもありません』(集英社文庫)
*江國香織『薔薇(ばら)の木 枇杷(びわ)の木 檸檬(れもん)の木』(集英社文庫)
*江國香織『ちょうちんそで』(新潮文庫)
*江國香織『がらくた』(新潮文庫)
*江國香織『思いわずらうことなく愉しく生きよ』(光文社文庫)
*江國香織『ひとりでカラカサさしてゆく』(新潮社)
*江國香織『物語のなかとそと 江國香織散文集』(朝日新聞出版)
*『新潮ムック 江國香織ヴァラエティ』(新潮社)
*丸谷才一『文学のレッスン』(聞き手:湯川豊)(新潮文庫)
*デイヴィッド・ロッジ『小説の技巧』柴田元幸・斎藤兆史訳(白水社)
*ジェイムズ・ジョイス『ダブリン市民』安藤一郎訳(新潮文庫)
*ジェイムズ・ジョイス『ダブリナーズ』柳瀬尚紀訳(新潮文庫)
*ジェイムズ・ジョイス『若い芸術家の肖像』丸谷才一訳(新潮文庫)
*ジェイムズ・ジョイス『『若い芸術家の肖像』の初稿断片 スティーヴン・ヒーロー』(付録:エピファニーズ)(永原和夫訳(松柏社)
*米本義孝『言葉の芸術家ジェイムズ・ジョイス 『ダブリンの人びと』研究』(南雲堂)
*金井嘉彦・吉川信編著『ジョイスの罠 『ダブリナーズ』に嵌る方法』』(言叢社)
*金井嘉彦・道木一弘編著『ジョイスの迷宮(ラビリンス) 『若き日の芸術家の肖像』に嵌る方法』(言叢社)
*ヴァルター・ベンヤミン『ドイツ悲劇の根源』浅井健二郎訳(ちくま学芸文庫)
*湯川豊篇『新しい須賀敦子』(湯川豊+江國香織対談「須賀敦子の魅力」所収)(集英社)
*須賀敦子『霧のむこうに住みたい』(解説:江國香織)(河出文庫)
*「作家の読書道 第206回:江國香織さん」(WEB本の雑誌): https://www.webdoku.jp/rensai/sakka/michi206_ekuni/index.html
*「江國香織さんの最新作『去年(こぞ)の雪』。不思議な読後感を残す物語はこうして生まれた」(「家庭画報.com」2020.4.7):https://www.kateigaho.com/article/detail/75373
*「待ちに待った江國香織さんの最新作は、今こういうときこそ読みたい小説だ! 『去年の雪』」(「本が好き。」):https://honsuki.jp/pickup/30514/index.html
*江國香織「柳美里『自殺の国』の書評」(All Reviews)
*江國香織「井上荒野『雉猫心中』の書評」(All Reviews)
*『竹取物語/伊勢物語/堤中納言物語/土左日記/更級日記 (池澤夏樹=個人編集 日本文学全集03)』(『更級日記』江國香織訳(河出書房新社)
*ナタリア・ギンズブルグ『ある家族の会話』須賀敦子訳(白水uブックス)
*リチャード・エルマン『ジェイムズ・ジョイス伝』宮田恭子訳(みすず書房)
*フランソワ・ヴィヨン『ヴィヨン全詩集』鈴木信太郎訳(岩波文庫)
*ロラン・バルト「明るい部屋」花輪光訳(みすず書房)
*藤井貞和『源氏物語入門』(「慿入の文学」所収)(講談社学術文庫)