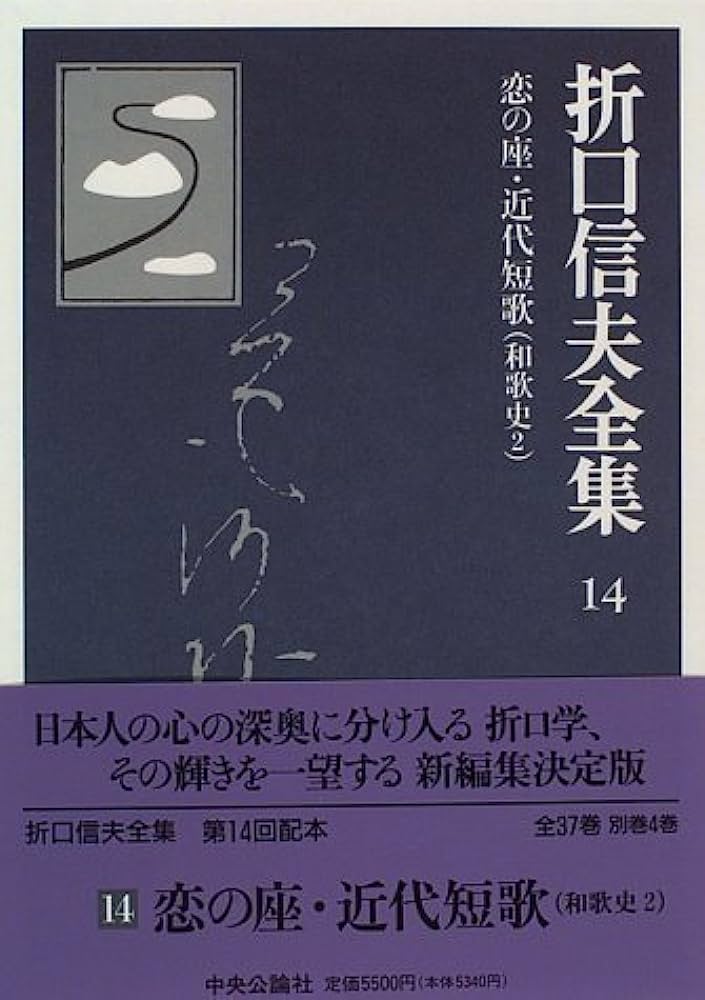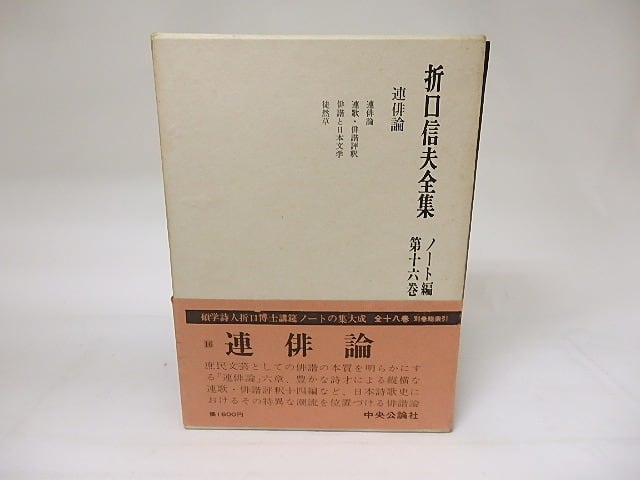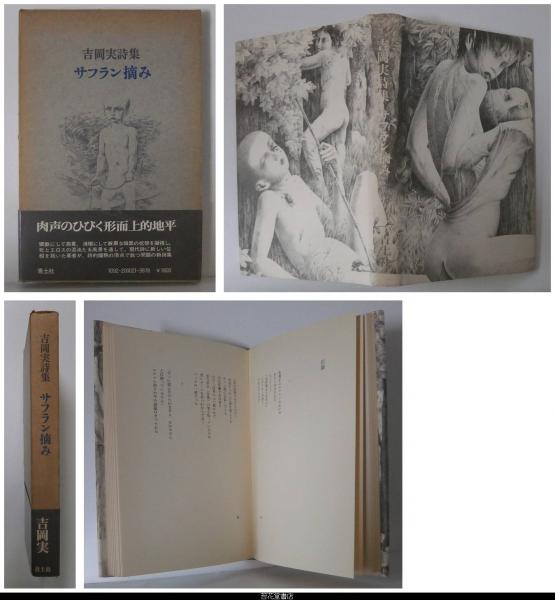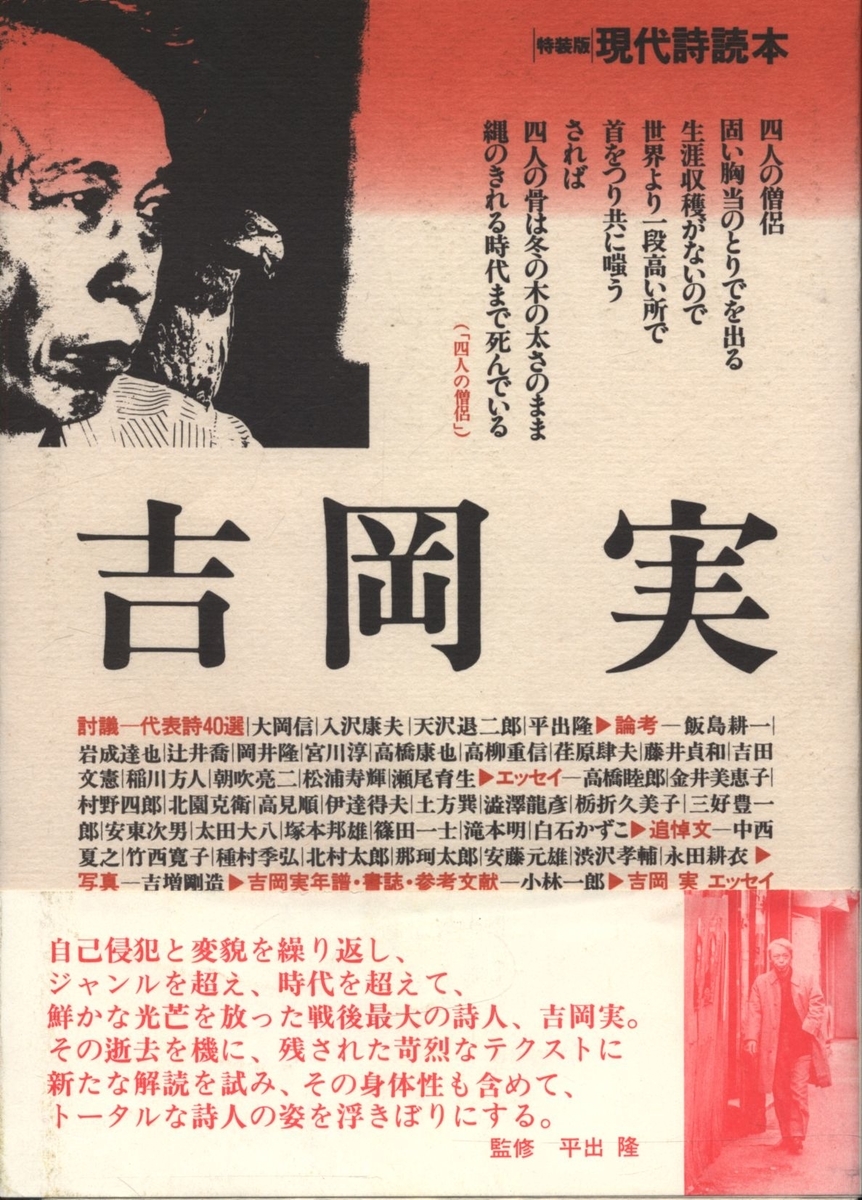「(同じく妻。)だわ。……雛の節句のあくる晩、春で、朧で、御縁日、同じ栄螺と蛤を放して、巡査の帳面に、名を並べて、女房と名告(なの)つて、一所に詣る西河岸の、お地蔵様が縁結び。……これで出来なきや、世界は暗夜(やみ)だわ。」
という稲葉家お考(こう)の台詞を、古くは花柳章太郎や初代水谷八重子、近年では坂東玉三郎の舞台で聞いたことがあれば、あるいは「まあ、長襦袢を見ないで芸者を口説く。……それぢや暗夜(やみよ)の礫(つぶて)だわ。」と言ってのけるお考淡島千景の映画を見たならば、リフレインされる「露地の細路……駒下駄で……」という唄声の通奏低音とともに忘れられないだろう。
泉鏡花の大正三年作の小説『日本橋』は、翌年には本郷座で、真山青果、喜多村緑郎らの脚本によって初演されたが、大正六年に鏡花は戯曲『日本橋』を発表し、以降、新派によってたびたび上演されている(客演として、六代目歌右衛門、玉三郎がお考を、二代目吉右衛門、十五代目仁左衛門(当時片岡孝夫)が葛木を演じてもいる)。もともとの小説が、会話を主体としての台詞とト書き構成であることから戯曲化しやすいうえに、戯曲化を前提に背景や場面を書き割り描写されていた。
谷崎潤一郎が、《鏡花氏の場合に於ては、その多くの作品は、最初から小説にすべきではなく映画にすべきではなかつたかと思はれるほど、それほど映画に適して居るやうに感じられる。》と書いたように、二度にわたって映画化(昭和四年溝口健二監督(フィルムは喪失)、昭和三十一年市川崑監督(淡島千景のお考、山本富士子の清葉、若尾文子のお千世))されてもいる。
加賀藩の能役者(葛野流大鼓方中田万三郎豊喜)の娘鈴(すず)を母とし、伯父(母の次兄)は宝生流シテ方松本家の養子松本金太郎だった鏡花は、「夢幻能」にも似た回想構造をとって小説を書いたのに対して、演劇と映画は観客のわかりやすさからか直線的な時系列構造とした。もともと鏡花小説が、会話を主体とした台詞とト書き構成であることもあいまって、小説からの戯曲、映画へのアダプテーションは、入り組んだ回想部分をそのまま聞き語りさせるかわりに、観客をあきさせないよう演技、実写したり、鏡花独特の飛躍した空白表現(葛木がお考に別れを告げる場面)をわかりやすさから補完、潤色してはいるものの、筋立ての差異は少ない(もっとも上演ごとに足したり引いたりの苦心の跡が見られる)。
ここでは小説からの引用を主にとりあげ、芸能、文芸の影響を中心に、その表象としての「紅と浅黄の段染麻の葉鹿の子の長襦袢」を考察してゆきたい。影響というよりもむしろ、積極的に先行する江戸芸能、文芸という伝統から作り上げたということだろう。いわば、T.S.エリオットの「伝統と個人の才能」による「古典と前衛」の世界、宇宙である。
小説は、章題「篠蟹(さゝがに)」「檜木笠(ひのききがさ)」「銀貨入」「手に手」「露地の細路」「柳に銀の舞扇」の(一)~(十七)ではじまり、「河童(かはたろ)御殿」「栄螺(さざえ)と蛤」「おなじく妻」「横槊賦詩(ほこをよこたへてしをふす)」「羆(ひぐま)の筒袖」「縁日がへり」「サの字千鳥」「梅(うめ)ヶ枝(え)の手水(てうず)鉢(ばち)」「口紅」「一重桜」「伐木丁々」「空蝉(うつせみ)」「彩(いろ)ある雲」「鴛鴦(をしどり)」「生理学教室」「美挙」「怨霊(をんりやう)比羅(びら)」「一口(ひとふり)か一挺か」「艸冠(くさかんむり)」「河岸(かし)の浦島」「頭を釘」「露霜(つゆじも)」の章題による二年前の回想(十八)~(六二)を経て、「彗星(はうきぼし)」「綺麗な花」「振向く処を」「あわせかがみ」「振袖」で(十七)に続く現在に回帰しての(六三)~(六七)となる、世阿弥による能の「序破急」構造をなす。
佐藤春夫が岩波文庫『日本橋』(一九五三年発行)に書き下ろした「解説」の、《この篇を一貫する主題は愛情である》、《怪異談、因縁ばなしや清葉の笛に対する熱情の名人気質の片鱗など、この篇にも鏡花世界の万華鏡の模様は全く影をひそめたのではなく》、《その常套手段たる人情本や草双紙の様式の襲用によりながら、また自然主義に対抗する観念小説でありながらどこまでも鏡花流に終始した別個の近代小説をもくろんでゐる》といった指摘を確かめよう。
<「篠蟹(さゝがに)」 (一)>
《盛(さかり)の牡丹の妙齢(としごろ)ながら、島田髷(しまだ)の縺れに影が映(さ)す……肩揚を除(と)つたばかりらしい、姿も大柄に見えるほど、荒い絣の、聊か身幅(みはゞ)も広いのに、黒繻子の襟の掛った縞御召の一枚着、友染の前垂(まへだれ)、同一(おんなじ)で青い帯。緋鹿子(ひがのこ)の背負上(しよひあげ)した、それしや(・・・・)と見えるが仇気(あどけ)ない娘風俗(ふう)、つい近所か、日傘も翳(さ)さず、可愛い素足に台所穿(ばき)を引掛(ひきか)けたのが、紅と浅黄で羽を彩る飴の鳥と、打切(ぶつきり)飴の紙袋を両の手に、お馴染なじみの親仁(おやじ)の店。有りはしないが暖簾(のれん)を潜りさうにして出た処を、捌いた褄も淀むまで、むら/\とその腕白共(わんぱくども)に寄つて集(たか)られたものである。》
《「大な声がどうしたんでえ。」
と、一人の兄哥(にい)さん、六代目の仮声(こわいろ)さ。》
お千世のビジュアルな登場。「六代目」とは六代目尾上菊五郎。
<(二)>
《(何。)とか云ふ鮨屋の露地口。鼬(いたち)のやうにちよろりと出た同一(おなじ)腕白。下心(したごころ)あつて、用意の為に引込んで居たらしい。芥溜(ごみため)を探したか、皿から浚つたか、笹(さゝ)ッ葉(ぱ)一束(ひとたば)、棒切の尖(さき)へ独楽なはで引括(ひつくゝ)つた間に合せの小道具を、さあ来い、と云ふ見(み)で構へて、駆寄ると、若い妓の島田の上へ突着けた、ばさ/\ばッさり。
が、黙つて、何にも言はないで、若い妓は俯向(うつむ)いて歩行(ある)き出す。
頸摺(うなじず)れに、突着け、突掛(つツか)かけ、
「やあ、おいらんの道中(だうちう)々々(/\)!」
「大高(おほたか)、旨いぞ。」と一人が囃す。
「おつと任せの、千崎弥五郎(せんざきやごらう)。」》
千崎弥五郎は歌舞伎『仮名手本忠臣蔵』である。
朝田祥二郎『注解 考説 泉鏡花 日本橋』によれば《傾城に傘をさしかける道中の振事は「積恋雪関扉」の墨染と関兵衛が花道で見せるのをはじめ、歌舞伎舞踊で廓風俗を描写するきまりの所作であって、(中略)本文ははっきり歌舞伎がかりをうたっている》という。
《「笹や、笹々笹や笹、笹を買はんせ煤竹(すゝだけ)を――」
大高うまい、と今呼ばれた、件(くだん)の(鼬みめよし)が、笹を故(わざ)と、島田の上で、ばさ/\と振りながら、足踏をして唱出(うたひだ)した。
声を揃えて、手拍子で、
「笹を買わんせ煤竹を――」
ここで三音諧(さんおんかい)張上げる。気障(きざ)な調子で、
「大高源吾は橋の上えゝ。」》
笹売りの大高源吾は浪花節『大高源吾』ならびに歌舞伎『松浦の太鼓』で、俳諧の師其角に両国橋で出会う。
物語の冒頭部(一)~(四)を、世相、人心の鏡である子供たちの講談口調めいた赤穂浪士づくしによって、忠義を称揚する封建道徳、国家主義、権威主義を戯画化している。
<「檜木笠(ひのききがさ)」 (三)>
《「嘘よ、お前さんぢやないのよ。その大高源吾とか云ふ、ずんぐりむつくりした人がね、笹を担いで浪花節で歩行(ある)いては、大事な土地が汚(けが)れるつて。……橋は台なし、堪らないつて、姉さんが云ふんだわ。」》
鏡花は浪花節の野卑な語り口を嫌った。「橋は台なし」とは、九代目市川團十郎が歌舞伎座で浪花節がかかったのを、舞台の板を削れと怒った話からという。
《「不断、然(さ)う云(い)やがるとよ、可(い)いか。手前(てまえ)ン許(とこ)の狂女(きちがい)がな、不断然(さ)う云やがる事を知つてるから、手前(てめえ)だつて尋常(たゞ)は通さないんだぜ。僕がな、形を窶してよ、八百屋の小児(こども)に生れてよ、間者(かんじや)に成つて知つてるんだ。行軍将棊でもな、間者は豪(えら)いぜ、伴内阿魔(ばんないあま)。」》
伴内は『仮名手本忠臣蔵』で高師直の配下鷺坂(さぎさか)伴内のことで、お考を師直、抱えのお千世を伴内に見立てた。
<(四)>
《「僕は赤鞘(あかざや)の安兵衛てんです。」》
安兵衛は、浪花節『義士銘々伝』の「高田馬場の仇討」の堀江安兵衛。
《「怜悧(りこう)だな。何、天晴(あつぱれ)御会釈。如何(いか)さま、御姓名を承りますに、此方(こなた)から先へ氏(うぢ)素姓(すじやう)を申上げぬと云ふ作法はありませなんだ。しかし御覧の通り、木(き)の端(はし)同然のものでありますので、別に名告(なの)りますほどの苗字とてもありませぬ。愚僧は泉岳寺の味噌摺坊主でござる。」》
泉岳寺は赤穂義士の墓所。
<「銀貨入」 (五)>
《その両方の間(あはひ)の、もの蔭に小隠れて、意気人品(ひとがら)な黒縮緬、三ツ紋の羽織を撫肩に、縞大島の二枚小袖、襲(かさ)ねて着てもすらりとした、痩やせぎすで脊(せい)の高い。油気の無い洗髪(あらひがみ)。簪の突込み加減も、じれッたいを知つた風。一目にそれしやとは見えながら、衣紋つき端正(しやん)として、薄い胸に品(ひん)のある、二十七八の婀娜(あだ)なのが、玉のやうな頸(うなじ)を伸して、瞳を優しく横顔で、熟(ぢつ)と飴屋の方を凝視(みつ)めたのがある。
「あら、清(きよ)葉(は)姉さん。」
と可懐(なつか)しそうに呼掛けて、若い妓はバッタリ留つた。
「お千世(ちせ)さん。」
と柳の眉の、面(おもて)正しく、見迎えて一寸立直る。片手も細(ほつそ)り、色傘を重さうに支(つ)いて、片手に白(しろ)塩瀬(しおぜ)に翁(おきな)格子(がうし)、薄紫の裏の着いた、銀貨入を持つていた。
若い妓はお千世と言う、それは稲葉家(いなばや)の抱妓(かゝへ)である。》
清葉は日本橋芸者の粋な蒲柳体型、たたずまいで、小間物にまで行き届いた風俗描写で登場する。
<(六)>
《序(ついで)にもう一つ通名(とほりな)があつて、それは横笛である。曰く、清(きよ)葉(は)、曰く令夫人で可(い)いものを、誰(た)が詮索に及んだか、その住居(すまひ)なる檜物(ひもの)町(ちやう)に、磨込んだ格子戸に、門札(かどふだ)打つた本姓(ほんせい)が(滝口。)はお誂(あつらへ)で。むかし読本(よみほん)のいわゆる(名詮自称(みやうせんじしよう)。)に似た。此の人、日本橋に褄を取つて、表看板の諸芸一通(ひととほり)恥かしからず心得た中にも、下方(したかた)に妙を得て、就中(なかんづく)、笛は名誉の名取(なとり)であるから。》
『平家物語』の滝口入道と横笛の恋物語を思い合わせた。
物語の最後に清葉がお考に笛を手向けることの伏線で、小説では《清葉が盃を挙げて唄ふ、あれ聞け横笛を。――露地の細路駒下駄で――》、戯曲でお考は《「清葉さん、笛はお持ちか。こゝで手向けておくれ、迦陵頻伽(かりょうびんが)の迎ひのやうに」》と頼む。
<「手に手」 (八)>
《飴屋が名代の涎掛を新しく見ながら、清葉は若い妓と一所に、お染(そめ)久松(ひさまつ)が一寸戸迷(とまど)ひをしたという姿で、火の番の羽目を出て、も一度仲通へ。何方(どつち)の家へも帰らないで、――西河岸の方へ連立つたのである。》
「お染(そめ)久松(ひさまつ)」は、歌舞伎、浄瑠璃の『新版歌祭文』や浄瑠璃『染模様妹背門松』からで、お染が着る「段染麻の葉鹿子」はこの後重要な記号となる長襦袢の柄であって、重要な予兆、伏線。鏡花は読み返すと気づくのだが、伏線を張りめぐらしている。
<(十)>
《……お千世のためには、内の様子も見て置きたい、と菊家へ連れようとした気を替えて、清葉はお孝を見舞ひに行くのに、鮨というのも狂乱の美人、附属(つき)ものの笹の気が悪い。野暮な見立ても、萎(しを)る人の、美しい露にもなれかしと、こゝに水菓子を選んだのである。》
鮨につきものの笹が、能で狂い乱れる人物が手に掲げて象徴する「狂い笹」(子を失った母親がシテの『百万』や『隅田川』、男性への恋慕のために狂女となった遊女がシテの『班女』など)を連想させた。
<「露地の細路」 (十二)>
《露地の細路……駒下駄で……》
久保田万太郎の随筆「水上滝太郎君と泉鏡花先生」に、《先生のおすきなもの(中略)唄は上方唄の「愚痴」――「露地の細みち駒下駄で」》とあり、鏡花の愛唱歌だったという。
「愚痴」の全歌詞は、「愚痴ぢやなけれど、コレマア聞かあしやんせ、たまに逢ふ夜の楽しみは、逢うてうれしさ、エ、なんの烏が意地悪な、おまえの袖とわしが袖、合せて歌の四つの袖、路地の細路駒下駄の、胸おどろかす明けの鐘」
後半部の「おまえの袖とわしが袖、合わせて歌の四つの袖、路地の細路駒下駄の、胸おどろかす明けの鐘」は、歌舞伎『恋飛脚大和往来』の梅川忠兵衛封印切の場(井筒屋)から道行、情死にいたる下座音楽として使われて有名となった。死を連想させもして、不吉といえば不吉である。
「露地の細路」章における若菜家お若の不幸な怪談、物(もの)の怪(け)、怪異性は『源氏物語』(光源氏と同じ鏡花の「亡母追慕」)の「夕顔」に似たところがある。
<「柳に銀の舞扇」 (十五)>
《はらりと音して、寝ながら投げた扇が逸(そ)れたか、欄干を颯と掠めて、蒔絵の波がしら立つ如く、浅(あさ)翠(みどり)の葉に掛つて、月かと思ふ影が揺ぐと、清葉の雪のやうな頬を照らす。……と思はず、受けたは袱紗の手。我知らず色傘を地に落して、その袖をはつと掛けて、斜めに丁(ちやう)と胸に当てた。
清葉は前刻(さつき)から見詰めた扇子(あふぎ)で、お孝の魂が二階から抜けて落ちたやうに、気を取られて、驚いて、抱取(だきと)る思ひが為(し)たのである。
潜つて流れた扇子の余波(なごり)か、風も無いのにさら/\と靡く、青柳(あをやぎ)の糸の縺(もつ)れに誘はれた風情して、二階にすらりと女の姿。
お孝は寝床を出た扱帯(しごきおび)。寛(ゆる)い衣紋を辷すべるやう、一枚(いちまい)小袖(こそで)の黒繻子の、黒いに目立つ襟白粉、薄いが顔にも化粧した……何の心ゆかしやら――よう似合ふのに、朋輩が見たくても、松の内でないと見られなかつた――潰(つぶし)島田(しまだ)の艶は失せぬが、鬢のほつれは是非も無い。
生際(はえぎは)曇る、柳の葉越、色は抜けるほど白いのが、浅黄に銀の刺繍(ぬひとり)で、此(これ)が伊達の、渦巻と見せた白い蛇の半襟で、幽(かすか)に宿す影が蒼い。》
二階建ての書割は、水平の舞台に垂直の視線を導入してドラマチックであり、歌舞伎『楼門五三桐』や『金閣寺』で見られて、天と地の階層を連想させるが、映画では活かされたものの、舞台では長らく上演されていない。
《我知らず色傘を地に落して、その袖をはつと掛けて、斜めに丁(ちやう)と胸に当てた。》の優美な所作。
「白い蛇の半襟」に浄瑠璃、歌舞伎『日高川入相花王』の清姫、能『道成寺』や歌舞伎『京鹿子娘道成寺』の蛇体のアレゴリーともなっている。
<(十六)>
《唯(と)……思つたほどは窶れも見えぬ。
病気の為めに失心して、娑婆も、苦労も忘れたか、不断年より長(ふ)けた女が、却つて実際より三つ四つも少ないくらゐ、つひに見ぬ、薄化粧で、……分けて取乱した心から、何か気紛れに手近にあつたを着散したらう、……座敷で、お千世が何時(いつも)着る、紅と浅黄と段染(だんそめ)の麻の葉鹿(か)の子(こ)の長襦袢を、寝衣(ねまき)の下に褄浅く、ぞろりと着たのは、――予(か)ねて人が風説(うはさ)して、気象を較べて不思議だ、と言つた、清葉が優しい若衆立(わかしゆだち)で、お孝が凜々しい娘形(むすめがた)、――宛然(さながら)の其の娘風の艶(えん)に媚かしいものであつた。
お孝は弛んだ伊達巻の、ぞろりと投遣りの裳(もすそ)を曳きながら、……踊で鍛えた褄は乱れず、白脛(しろはぎ)のありとも見えぬ、蹴出(けだし)捌きで、すつと来て、二階の縁の正面に立つたと思うと、斜めに其処の柱に凭(もた)れて、雲を見るか、と廂合(ひあはひ)を恍惚(うつとり)と仰いだ瞳を、蜘蛛に驚いて柳に流して、葉越しに瞰下(みおろ)し、そこに舞扇を袖に受けて、見上げた清葉と面(おもて)を合せた。
「あゝ、お考さん。」
と声を掛ける。》
ここで、「紅と浅黄と段染(だんそめ)の麻の葉鹿(か)の子(こ)の長襦袢」が表象記号的に登場する。
「弛んだ伊達巻の、ぞろりと投遣りの裳(もすそ)を曳きながら、……踊で鍛えた褄は乱れず、白脛(しろはぎ)のありとも見えぬ、蹴出(けだし)捌きで、すつと来て、二階の縁の正面に立つたと思うと、斜めに其処の柱に凭(もた)れて、雲を見るか、と廂合(ひあはひ)を恍惚(うつとり)と仰いだ瞳を、蜘蛛に驚いて柳に流して、葉越しに瞰下(みおろ)し」までの鏡花の艶な花柳世界への確かな眼と描写力、そして舞台、映像を喚起する演出技量。
<(十七)>
《向うへ対手(あいて)に廻しては、三味線の長刀(なぎなた)、扇子(あふぎ)の小太刀、立向う敵手(あひて)の無い、芳(よし)町(ちやう)育ちの、一歩を譲るまい、後(おくれ)を取るまい、稲葉家のお孝が、清葉ばかりを当(たう)の敵(かたき)に、引くまい、退(の)くまい、と気を揉んで、負けじとするだけ、豫(かね)て此方(こなた)が弱身なのであった。
張(はり)も、意地も、全盛も、芸も固(もと)より敢て譲らぬ。否、較べては、清葉が取立てて勝身は無い。分けて彼方(むかう)は身一つで、雛妓(おしやく)一人抱えておらぬ。
此方(こなた)は、盛りは四天王、金(きん)札(さつ)打つた独武者、羅生門(らしやうもん)よし、土蜘蛛よし、猅々、狼も以(も)つて来(き)なで、萌黄、緋縅、卯の花縅、小桜を黄に返したる年増(としま)交(まじ)りに、十有余人の郎党を、象牙の撥に従へながら、寄すれば色ある浪に砕けて、名所の松は月下に独り、従容として名を得る口惜(くや)しさ。
弱虫の意気地なしが、徳とやらを以て人を懐(なづ)ける。雪の中を草鞋穿いて、蓑着て揖譲(おじぎ)するなんざ、惚気(のろけ)て鍋焼を奢るより、資本(もとで)のかゝらぬ演劇(しばゐ)だもの。
「字(あざな)は玄徳(げんとく)め。」
と、所好(すき)な貸本の講談を読みながら、梁山泊(りやうざんぱく)の扈三娘(こさんじやう)、お孝が清葉を詈(のゝし)る、と洩聞いて、
「其の気だから、あの妓こは、(そんけん)さ。」
と内証で洒落た待合の女房(おかみ)がある由。》
講談本、洒落本の「三国志」および能『土蜘蛛』の諧謔、パロディで、お考の気性を表現している。
《「私、……私よ、お孝さん。」
と二度目に呼んで声を掛けるや、
「葛木(かつらぎ)さん。」
と、冴えた声。お孝が一声応ずるとともに、崩れた褄は小間(こま)を落ちた、片膝立てた段(だん)鹿(か)の子(こ)の、浅黄、紅(くれなゐ)、露(あら)はなのは、取乱したより、蓮葉とより、薬玉(くすだま)の総(ふさ)切れ/゛\に、美しい玉の緒の縺れた可哀(あはれ)を白々地(あからさま)。萎なえたやうに頬杖して、片手を白く投掛けながら、
「葛木さん。」
二度まで、同じ人の名を、此処には居ない人の名を、胸を貫いて呼んだと思うと、支えた腕(かひな)が溶けるやうに、島田髷(しまだ)を頂(の)せて、がつくりと落ちて欄干(てすり)に突伏(つツぷ)したが、たちまち反(そ)り返るやうに、衝(つツ)と立つや、蹌踉(よろ)々々(/\)として障子に当つて、乱れた袖を雪なす肱で、緊乎(しつかり)と胸にしめつゝ、屹(き)と瞰下(みお)ろす目に凄味が見えた。》
《崩れた褄は小間(こま)を落ちた、片膝立てた段(だん)鹿(か)の子(こ)の、浅黄、紅(くれなゐ)、露(あら)はなのは》から《支えた腕(かひな)が溶けるやうに、島田髷(しまだ)を頂(の)せて、がつくりと落ちて欄干(てすり)に突伏(つツぷ)したが、たちまち反(そ)り返るやうに、衝(つツ)と立つや、蹌踉(よろ)々々(/\)として障子に当つて、乱れた袖を雪なす肱で、緊乎(しつかり)と胸にしめつゝ、屹(き)と瞰下(みお)ろす目に凄味が見えた。》の「段染麻の葉鹿の子」の静と動との物狂いめいた所作の凄艶。
<「栄螺(さゞえ)と蛤」 (二十二)>
《「旦那。」
と暗がりに媚かしく婀娜(あだ)な声。ほんのりと一重桜、カランと吾妻下駄を、赤電車の過ぎた線路に遠慮なく響かすと、はつと留楠木(とめき)の薫(かをり)して、朧を透(すか)した霞の姿、夜目にも褄を咲せたのは、稲葉家のお孝であった。》
<「おなじく妻」 (二十三)>
《「もし、一寸(ちよいと)。」
右側の欄干際に引添った二人の傍(わき)へ、すらりと寄つたが、お端折(はしおり)の褄を取りたそうに、左を投げた袖ぐるみ、手をふら/\と微酔(ほろよひ)で。
「旦那、其方のお検べはまだ済みませんか。」
と斜めに警官を見て、莞爾(につこ)り笑ふ……皓歯(しらは)も見えて、毛筋の通つた、潰島田は艶麗(あでや)である。
警官は二つばかり、無意味に続けざまに咳(しはぶき)した。
「お前は何かい、あゝ。」
「はあ、お次に控えておりました、賤(しづ)の女(め)でござんすわいな。」とふら/\する。》
見染めの場。歌舞伎でいえば『与話情浮名横櫛』お富と与三郎の木更津浜潮干狩の場、『生写朝顔話』深雪と阿曾次郎の宇治蛍狩の場、『新薄雪物語』薄雪姫と園部左衛門の清水寺花見の場など。
<(二十五)>
《唯(と)顧みて、其処で、ト被直(かぶりなほ)して、杖(ステツキ)をついた処、お孝は二つばかり、カラ/\と吾妻下駄を踏鳴らした。
「唯別れるの。……不意気(ぶいき)だねえ、――一石橋の朧夜に、」
四辺(あたり)を見つゝ袖を合せた、――雲を漏れたる洗髪。
「女と二人逢いながら、すた/\(かねやす。)の向うまで、江戸を離れる男ッてのがお前さん江戸にありますか。人目に然うは見えないでも、花のような微酔で、こゝに一本(ひともと)咲いたのは、稲葉家のお孝ですよ。清葉さんとは違ひますわ。」》
七五調の黙阿弥劇めいた名乗り。最後に、清葉への対抗意識。
<(二十六)>
《「(同じく妻。)だわ。……雛の節句のあくる晩、春で、朧で、御縁日、同じ栄螺と蛤を放して、巡査の帳面に、名を並べて、女房と名告(なの)つて、一所に詣る西河岸の、お地蔵様が縁結び。……これで出来なきや、日本は暗夜(やみ)だわ。」》
初出の小説では「日本は」だが、三年後の戯曲では、なぜか「世界は」となった。なぜか、と言えば、映画でこの黙阿弥口調の台詞は淡島千景によって語られることなく、「春で 朧(おぼろ)で ご縁日」とだけ大きく字幕で出た。
<「横槊賦詩(ほこをよこたへてしをふす)」 (二十八)>
《「千世(ちい)ちやん、清葉さんの長襦袢を見たかい。」
「えゝ、可(い)いわねえ。」
「色が白くて、髪が黒い処へ、細(ほつそ)りしてるから、よく似合ふねえ。年紀(とし)よりは派手なんだけれど、娘らしく色気が有つて、まことに可い。葛木さん、一寸(ちよいと)、彼処(あすこ)へ惚れたんぢやないこと。」
「馬鹿な。」
「でも可いでせう。」
「長襦袢なんか、……些(ちつ)とも知らない。」
「まあ、長襦袢を見ないで芸者を口説く。……それぢや暗夜(やみよ)の礫(つぶて)だわ。だから不可(いけな)いんぢやありませんか。今度(こんど)、私が着て見せたいけれど、座敷で踊るんでないと一寸着憎い。……口惜いから、この妓(こ)に拵(こしら)へて着せませうよ。」
やがてお千世が着るやうに成つたのを、後にお孝が気が狂つてから、ふと下に着て舞扇を弄んだ、稲葉家の二階の欄干(てすり)に青柳の糸とともに乱れた、縺(もつ)るゝ玉の緒の可哀(あはれ)を曳く、燃え立つ緋(ひ)と、冷い浅黄と、段染の麻の葉鹿の子は、此の時見立てたのである事を、一寸ここで云つて置きたい。》
因縁の「燃え立つ緋(ひ)と、冷い浅黄と、段染の麻の葉鹿の子」の清葉、お千世、お考の三人にわたる来歴の一端が《一寸ここで云つて置きたい》との唐突な作者の顔出しによって語られる。「燃え立つ緋(ひ)と、冷い浅黄」の色彩と触感に鏡花が終生囚われた「火」と「水」のイマージュが宿る。
<「羆(ひぐま)の筒袖」 (二十九)>
《背後(うしろ)をのさ/\と跟(つ)けて来て、阿爺どの。――呼声は朱鞘の大刀(だんびら)、黒羽二重、五分月代(ごぶさかづき)に似ているが、すでにのさ/\である程なれば、然うした凄味な仲蔵(なかざう)ではない。
按ずるに日本橋の上へは、困つた浪花節の大高源吾が臆面もなく顕れるのであるが、未だ幸に西河岸へ定九郎(さだくらう)の出た唄を聞かぬ。……尤も此のあたり、場所は大日本座の檜舞台であるけれども、河岸は花道ではないのであるから。》
歌舞伎『仮名手本忠臣蔵』五段目、山崎街道の場の中村仲蔵による斧定九郎。このあたり鏡花独特の諧謔性、滑稽味がある。
《むかし権三は油壺。鰊蔵(にしんぐら)から出たよな男に、爺さんは、きよとんとする。》
近松浄瑠璃『鑓の権三重帷子』の浜の宮馬場の段の「鑓の権三は伊達者の、どうでも権三は好い男。油壷から出すやうな、しんとろとろりと見とれる男。」
<「梅(うめ)ヶ枝(え)の手水(てうず)鉢(ばち)」 (三十五)>
《「ですから、今度つから、楠の正成で、梅ヶ枝をお呼びなさいよ、……其の手水鉢へ、私なら三百円入れてやりたい、と此方(こつち)でも思ふばかりだから、先方(さき)さまでも、お孝がこんな家へ来るもんか、とは言はないわね。……貴方お盃を下さいな、……チョッ口惜いねえ、清葉さんは。……」》
浄瑠璃『ひらかな盛衰記』の神崎揚屋の段、傾城梅が枝は「君傾城になりさがつても一度客に帯とかず」とあるように、梶原源太に操を立てて客のためには帯を解いたことがない女で、愛する源太を一の谷の合戦に送り出すためにの三百両を工面しようと、小夜の中山の「無間の鐘」を撞くと現世では巨万の富を得ることができるが来世は地獄に堕ちるという伝説になぞらえて、「この世は蛭にせめられ未来永々無間堕獄の業を受くともだんないだんない大事ない」と柄杓で手水鉢を叩くや、お金が二階から降ってくる奇跡が起きる。
<(三十六)>
《「何した、お爺さんは遅いぢやないか。」
「あら、姉さん、来るもんですか。」
「私は来るつもりで待つて居たのに――其処の襖を開けて御覧よ、居るかも知れない。」
「まあ、」と可愛く、目をぱち/\。
「可(い)いから一寸(ちよいと)御覧。」
と言ふ、香の煙に巻かれたやうに、跪いて細目に開けると、翠帳紅閨(すゐちやうこうけい)に、枕が三つ。床の柱に桜の初花。》
為永春水作の人情本『「春色梅児誉美(しゆんしよくうめごよみ)』に、「翠帳紅閨の中に新枕せしその初は偕老同穴(かいらうどうけつ)のかたらひをなし後世(ごせ)かけて契おくしたしみのあはれにもなつかしく」とある。
『春色梅児誉美』は深川芸者の恋の鞘当てが眼目で、鎌倉恋ヶ窪の遊女屋「唐琴屋」の養子丹次郎は、養家を追われて深川でわび住まいをしていた。唐琴屋の内芸者米八は窮状を見て、貢ぐために深川の羽織芸者となる。丹次郎の許嫁のお長もまた、丹次郎に貢ぐため女浄瑠璃竹長吉となる。一方、丹次郎は深川芸者仇吉とも恋仲になり、女たちの恋の鞘当てが始まる。お考と清葉に鞘当てを見ている。
<「一重桜」 (四十)>
《「寒く成つた、掻巻(かいまき)をおくれ。」
とお孝は曲げた腕(かひな)を柔く畳に落して、手をかへた小袖の縞を、指に掛けつゝ男の膝。
「姉さん、私、帯を解いてよ。」
「生意気お言ひでないよ、当(あて)も無しに。可(い)いから持つといで。」
「うまい装(なり)をして、」
と膚(はだ)の摺れる、幽かな衣(きぬ)の捌きが聞えて、
「御免なさいまし。」と抱いて出た掻巻の、それも緋と浅黄の派手な段鹿子であつたのを、萌黄と金茶の翁格子(おきながうし)の伊達巻で、ぐいと縊(くび)つた、白い乳房を夢のやうに覗かせながら、ト跪ひざまずいてお孝の胸へ。
襟足白く、起上るようにして、ずるりと咽喉(のど)まで引掛けながら、
「貴方、同じ柄で頼母(たのも)しいでせう、清葉さんの長襦袢と。」
学士は黙つて額を圧へる。
「姉さん、枕よ……」
「不作法だわ、二人で居る処へ唯(たつ)た一ツ。」
「知らない、姉さんは。」
「持つてお帰り。」
「はい。」
と立って、脛(はぎ)をする/\と次の室(ま)へ。襖を閉めようとして一寸立姿で覗く。羽二重の紅(くれなゐ)なるに、緋で渦巻を絞ったお千世のその長襦袢の絞が濃いので、乳の下、鳩尾(みづおち)、窪みに陰の映(さ)すあたり、鮮紅(からくれなゐ)に血汐が染むやうに見えた――俎に出刃を控へて、潰島田の人形を取つて据ゑた其の話しの折の所為(せゐ)であらう。
凄さも凄いが、艶(えん)である。その緋の絞の胸に抱く蔽(おほひ)の白紙(しらかみ)、小枕の濃い浅黄。隅田川のさゞ波に、桜の花の散敷く俤。
非(あら)ず、この時、両国の雪。
葛木は話したのである。
「姉の優しい眉が凜(りん)となつて、顔の色が蝋のやうに、人形と並んで蒼みを帯びた。余りの事に、気が違つたんぢやないかと思つた。
顔の色が分つたら祖母(おばあ)さんは姉を外へ出さなかつたろうと思ふね。――兄弟が揃つた処、お祖母さんも、此の方がお気に入るに違いない、父上(おとうさん)、母上(おつかさん)の供養の為に、活(いき)ものだから大川へ放して来ようよ……
で、出たつ切、十二時過ぎまで帰らなかつた。》
お千世が抱いて出た《掻巻の、それも緋と浅黄の派手な段鹿子であつた》うえに、「貴方、同じ柄で頼母(たのも)しいでせう、清葉さんの長襦袢と。」とお考に嫌味を言われる始末。
《乳の下、鳩尾(みづおち)、窪みに陰の映(さ)すあたり、鮮紅(からくれなゐ)に血汐が染むやうに見えた》はお千世が襲われる悲劇の予兆か。
「凄さも凄いが、艶(えん)である。」以降の緋、白、浅黄の色彩美も凄いが、さゞ波、桜の花の散敷くイメージから「両国の雪」の、舞踊『鷺娘』の降りしきる魔的な雪の白へと意識の流れが溢れ出て、読者への時間、時制、現在、過去への言及もなく、葛木の姉の回想へという急激な場面転換、転調は、読みにくい、わかりにくい、といえばその通りだが、しかし佐藤春夫「解説」の、《鏡花の文章は感情も感覚も理念でさへ時にはごつちやまぜになつた不思議に印象的なさうして飛躍する厄介な文章だから慣れないうちは、読みにくいかも知れないが、この稀代の名文家の文章は見なれさへすれば見かけの難解なのには似ずわかりのいいもので、それもそのはず、工夫に工夫を凝らして、そつもごまかしもないから、文字のままを素直に辿つて行きさへすれば面白さは自らその名かにあり少々は不可解(といふのは時々思ひ切つて飛躍しているからで)でも、おしまひまでゆけば何もかもはつきりわかるやうに親切に書かれてゐるのだから、たとひ途中でつまづくとも安心して読み進めさへすればよいのである。》に納得する。
<「空蝉(うつせみ)」 (四十三)>
《「もし/\、貴女様、もし……」
此処に葛木に物語られつゝある清葉は、町を隔て、屋根を隔てて、彼処(かしこ)に唯一人、水に臨んで欄干に凭(もた)れて彳(たゝず)む。……男の夢の流ではない、一石橋の上なのである。が、姿も水もその夢よりは幻影(まぼろし)である。》
「此処に葛木に物語られつゝある清葉」とは、丁度その時、葛木がお考に清葉との別れを物語っていたからで、この並行的な時間・空間処理は前衛的小説技法ともいえる。
こうして清葉もまた、お考に続いて一石橋にたたずむ。そもそも鏡花は、『義血侠血』の「滝の白糸」を郷里金沢の浅野川の天神橋に登場させたように、瀬田の唐橋、宇治橋、一条戻橋、など怪異の出現する、異界との境界、通路としての「橋」というアレゴリーに憑かれていた。
お考の清葉への嫉妬を考察するには、鏡花と親交のあった柳田国男の「橋姫」が参考になる。
柳田は「橋姫」を《橋姫と云ふのは、大昔我々の祖先が街道の橋の袂に、祀つて居た美しい女神のことである。地方によつては其信仰が夙く衰へて、其跡に色々の昔話が発生した。是を拾ひ集めて比較して行くと、些しづゝ古代人の心持を知ることができるやうである。》とはじめて、山梨の猿橋の橋姫伝説に謡曲の「葵の上」や「野宮」が出てくること、さらに美しい女が鬼女に変貌することは重要であるとし、橋姫と謡曲の関係を次のように指摘した。
《つまり「葵の上」は女の嫉妬を描いた一曲であつて、紫式部の物語の中で最も嫉妬深い婦人、六条の御息所と云ふ人と賀茂の祭の日に衝突して、其恨の為に取殺されたのが葵の上である。「野宮」と云ふのも所謂源氏物の謡の一つで、右の六条の御息所の霊をシテとする後日譚を趣向したものであるから、結局は女と女との争ひを主題にした謡曲を、この橋の女神がこのまれなかつたのである。「三輪」を謡へば再び道が明るくなると云ふ仔細はまだ分らぬが,古代史で有名な三輪の神様が人間の娘と夫婦の語ひをなされ、苧環の糸を引いて神の験の杉木の上に御姿を示されたと云ふ話を作つたもので、其末の方には「又常闇の雲晴れて云々」或は「其関の戸の夜も明け云々」などゝ云ふ文句がある。併し何れにしても橋姫の信仰なるものは、謡曲などの出来た時代よりもずつと古くからあるは勿論、源氏の時代よりも更に又前からあつたことは、現に其物語の中に橋姫と云ふ一巻のあるのを見てもわかるので、此には只どうして後世に、そんな謡を憎む好むと云ふ話が語らるゝに至つたかを、考へて見ればよいのである。》と論じた。
<「鴛鴦(をしどり)」 (四十七)>
《「姉さんで可愛がられるのに不足なら、妹にまけて可愛がられて上げませう。従姉妹(いとこ)に成つてなかよくしませう。許嫁(いひなづけ)でも、夫婦でも、情婦(いろ)でも、私、まけるわ、サの字だから。鬼にでも、魔にでも、蛇体にでも、何にでも成つて見せてよ、芸人ですもの。」
と裳(もすそ)を揺(ゆ)つて拗ねたやうに云ひながら、ふと、床の間の桜を見た時、酔つた肩はぐたりとしながら、キリゝと腰帯が、端正(しやん)と緊まる。
「何の、姉妹(きやうだい)に成るくらゐ、皮肉な踊よりやさしい筈だ。」
掻巻(かいまき)の裾を渚の如く、電燈に爪足(つまあし)白く、流れて通つて、花活(はないけ)のその桜の一枝、舞の構へに手に取ると、ひらりと直つて、袖にうけつゝ、一呼吸(ひといき)籠めた心の響、花ゆら/\と胸へ取る。姉の記念(かたみ)に豈(やは)劣るべき花柳(はなやぎ)の名取(なとり)の上手が、思のさす手を開きしぞや。
其の枝ながら、袖を敷いた、花の霞を裳に包んで、夢の色濃き萌黄の水に、鴛鴦(をし)の翼に肩を浮かせて、向うむきに潰島田。玉の緒揺(ゆら)ぐ手柄の色。
「葛木さん。」
「…………」
「人形が寂しい事よ。」》
「蛇体」に歌舞伎『京鹿子娘道明寺』などの清姫伝説をみる。
《花活(はないけ)のその桜の一枝、舞の構へに手に取ると、ひらりと直つて、袖にうけつゝ、一呼吸(ひといき)籠めた心の響、花ゆら/\と胸へ取る。姉の記念(かたみ)に豈(やは)劣るべき》とあるように、「一重桜」(三十九)で葛木が聞かせた《一重桜の枝を持つて、袖で抱くようにした京人形、私たち妹も、物心覚えてから、姉に肖(に)ている、姉さんだ/\と云ひ/\した》姉の記念(かたみ)の肖(に)た人形に扮して、「人形が寂しい事よ。」と女から情交を求める濡場であるが、人形は、姉・清葉、次いでお考へと変身、同化するわけだから、近親相姦的な倒錯ともいえる。
花柳小説、艶本としての荷風『腕くらべ』を思わせさえする技巧、手練手管である。
<「美学」 (五十二)>
《嘗て、その岐阜県の僻土(へきど)、辺鄙に居た頃ぢやつたね。三国峠を越す時です。只今、狼に食はれたと云ふ女の検察をしたがね、……薄暮(うすぐれ)です。日帰りに山家(やまが)から麓の里へ通う機織(はたおり)の女工が七人づれ、可(え)えですか。……峠を最(も)う一息で越さうと云ふ時、下駄の端緒が切れて、一足後(おく)た女が一人キヤツと云ふ。先へ立つた連の六人が、ひよいと見ると、手にも足にも十四五疋の、狼で蔽被(おほひかぶ)さつた。――身体はまるで蜂の巣です哩(わ)。
私(わし)は反対の方から上りかゝつたんでね。峠から駆下りて来た郵便脚夫が一人、(旦那、女が狼に食はれて居ります。)と云ひ棄てて、すた/\行きをる。――あとで、其の顔を覚えとつたで、(なぜ通りかゝって助けんかい。)……叱った処で、在郷軍人でもなし仕方が無い。然う云ふ事も現在見た。
又、山の中に、山猫と云ふのが居る、形は嘗て見せん。見たものは無いと云ふです。唯深更に及んで其の啼声ぢやね、此を聞くと百獣悉く声を潜むる。鳥が塒(ねぐら)で騒ぐ。昔の猅々ぢやと云ふ。非常に淫猥な獣(けもの)ぢやさうでね、下宿した百姓の娘などは、その声を聞くと震へるです哩(わい)、――現在私(わし)も、其は知つとる。
炭焼の奴が、女を焼いて食つた事件もある。》
鏡花の権力嫌いのカリカチュア(しかし微笑ましく造形化されている)たる笠原巡査の話す奇譚は柳田国男『遠野物語』の民話が源である。鏡花は明治四十三年の『遠野の紀聞』という文に「近ごろ近ごろ、おもしろき書を読みたり。柳田国男氏の著、遠野物語なり。再読三読、なお飽くことを知らず。」と残している。
<「艸冠(くさかんむり)」 (五十八)>
《お孝は遁げたでないですが。……あの階子(はしご)は取外しが出来るだでね、お孝が自分でドンと突いて、向うの壁へ階子をば突(つツ)ぱずしたもんですだ。(短刀をお抜き、さあ、お殺し、殺しやうに註文がある。切つちや不可(いけな)い、十の字を二つ両方へ艸冠(くさかんむり)とやらに曰(いわく)をかいて。)とお前(ま)ん、……葛木と云ふ字に、突いて殺せ。(名まで辛抱は出来まいが、一字や二字は堪(こら)へて見せよう。さあ早く。)と洞爺湖(どうやこ)の雪よか真白な肌を脱いで、背筋のつる/\と朝日で溶けて、露の滴(た)りさうな生々(なま/\)としたやつを、水浅黄ちらめかいて、柔(やは)りと背向(うしろむ)きに突着けたですだで。
豊艶(ふつくら)と覗いた乳首(ちゝくび)が白い蛇の首に見えて、むら/\と鱗も透(す)く、あの指の、あの白金(プラチナ)が、そのまゝ活きて出たらしいで、俺は此の手足も、胴も、じな/\と巻緊められると、五臓六腑が蒸上(むれあが)つて、肝(きも)まで溶融(とろ)けて、蕩々(とろ/\)に膏切(あぶらぎ)つた身体な、――気の消えさうな薫の佳(い)い、湿つた暖い霞に、虚空遥に揺上(ゆりあ)げられて、天の果に、蛇の目玉の黒金剛石(くろダイヤ)のやうな真黒な星が見えた、と思ふと、自然(ひとりで)に、のさんと、二階から茶の間へ素直(まつすぐ)、棒立ちに落ちたで、はあ。」
と五十嵐伝吾は腹を揺(ゆす)つて、肩を揉んで、溜息(ためいき)して言う。》
お考を付け回す赤熊こと五十嵐伝吾が一石橋で葛木に直訴した情痴話の果てのお考は、あたかも『道成寺物』の「白い蛇」のようだ。
<「露霜(つゆじも)」 (六十二)>
《はッと声に出して、思わず歎息(ためいき)をすると、浸(にじ)む涙を、両の腕。……面(おもて)を犇(ひし)と蔽うていた。
俥(くるま)の上で――もう夜半(よなか)二時過。
この辻車が、西河岸へヌッと出たと思うと、
「あゝ。」
葛木は慌しく声を掛けた。
「一寸待て、車夫(くるまや)。」
「へい/\。」
「忘れものをして来た、帰つてくれないか。」
「唯今、乗(め)した処へ。」
「あゝ。」
夜延仕(よなし)でも、達者な車夫(しやふ)で、一もん字に其の引返す時は、葛木は伏せた面(おもて)を挙げて、肩を聳(そびや)かす如く痩せた腕を組みながら、切(しきり)に飛ぶ星を仰いだ。が、夜露に、痛いほど濡れたかして、顔の色が真蒼であった。
「可し、此処で――此処で――此処で――」
と焦(あせ)つて、圧へて云ひ/\、早や飛下りさうにしつゝも駆戻(かけもど)る発奮(はずみ)にづか/\と引摺られるように町の角を曲つて、漸(やつ)と下立(おりた)つた処は、最(も)う火の番を過ぎて、お竹蔵(たけぐら)の前であつた。
直(す)ぐに稲葉家の露地を、ものに襲はれた体(てい)に、慌しく、その癖、靴を浮かして、跫音(あしおと)を密(ひそ)めて、した/\と入ると、門(かど)へ行つた身を飜(かへ)して、柳を透かしながら、声を忍んで、二階を呼んだ。
「お孝さん、……」
寂然(ひつそり)としていたが、重ねて呼ぶのに気を兼ねる間も無く、雨戸が一枚、すつと開(あ)いて、下から映(さ)す蒼(あお)い瓦斯を、逆に細流(せゝらぎ)を浴びた如く濡萎(ぬれしを)れた姿で、水際(みづぎは)を立てて、其処へお孝が、露の垂(た)りさうに艶麗(あでやか)に顕れた。
が、其れは浴びるばかりの涙なのである。
唯(と)、見る時、葛木も面(かほ)にはら/\と柳の雫が、押へあへず散乱るゝ。
今宵(こよひ)は三度目である。宵に来て、例(いつも)のごとく河岸まで送られて十二時過に帰つた時は、夢にも恁(か)うとは知らなかつた。――一石橋で赤熊に逢つて、浮世を思捨てるばかり、覚悟して取つて返した時は、もう世間もここも寐静まつて居た上に、お孝は疲れた、そして酔つても居た。……途中送る折も、送る女が、送らるゝ男の肩に、なよ/\と顔を持たせて、
「邪慳だね、帰るなんて。」
ぐつすり寐込んだに相違ない。えゝ、決心は鈍らうとも、まゝよ、此の次に、と一度引返さうとして、たゞ、口ずさみのひとりでに、思はず、
「お孝……」
と呼ぶと、
「あい。」と声の下で返事して、階子(はしご)を下りるのがトン/\と引摺るばかり。日本の真中に、一人、此の女が、と葛木は胸が切(せま)つたのであつたが。
暖い閨(ねや)も、石の如く、砥(と)の如く、冷たく堅く代るまで、身を冷して涙で別れて……三たび取つて返したのが此の時である。
お孝は、乱書(みだれがき)の仮名に靡く秋風の夜更けの柳にのみ、ものを言わせて、瞳も頬も玉を洗つたやうに、よろ/\と唯俯向(うつむ)いて見た。
「済まないがね、――人形を忘れたから。」
「はい。」
と清く潔い返事とともに、すつと入ると、向直つて出た。乳の下を裂いたか、とハッと思う、鮮血(なまち)を滴(したゝ)らすばかり胸に据ゑたは、宵に着て寝た、緋の長襦袢に、葛木が姉の記念(かたみ)の、あの人形を包んだのである。
ト片手ついたが、欄干(てすり)に、雪の輝く美しい白い蛇の絡(から)んだ俤。
「お怪我の無いやう……御機嫌やう。」
とはらりと落すと、袖で受けたが、さらりと音して、縮緬の緋のしぼ(・・)は、鱗が鳴るか、と地に辷つて、潰島田の人形は二片(ふたひら)三片(みひら)花を散ちらして、枝も折れず、柳の葉末に手に留(とま)んぬ。
「清葉さん、――然(さ)やうなら。」
カタリと一幅(ひとはゞ)、黒雲の鎖(とざ)したやうな雨戸が閉つて、……
――露地の細路、駒下駄で――
と心悲(うらかな)しい、が冴えた声。鈴を振る如く、白銀(しろがね)の、あの光、あけの明星か、星に響く。
葛木は五体が窘(すく)んだ。》
男女の別れの「愁嘆場」だが、葛木がお考に別れを告げる場面そのものは、ここでも、物理的な時間の流れよりも心理的、精神的な時間の流れを優先し、時には文章の流れによって時間が操られる印象主義的、プルースト的な文体による、鏡花独特の回想の順序のモザイク模様(三度目の訪問が先に記述されて、その際に二度目の訪問が回想されるので後からの記述となり、しかもどこからどこまでが二度目、三度目とはっきり書かれない)と、肝心かなめの別れの切り口上が省略されているため極めてわかりにくい(さすがに戯曲『日本橋』では「生理学教室(雛祭)」の場を補完、潤色させて具体的に観客にわからせた)。まるで書かないこと、空白にこそ真実、魂が宿る(そういう意味で川端康成は正統の後継者である)とばかりに。
《宵に来て、例(いつも)のごとく河岸まで送られて十二時過に帰つた時は、夢にも恁(か)うとは知らなかつた。》が一度目の訪問。 《一石橋で赤熊に逢つて、浮世を思捨てるばかり、覚悟して取つて返した時は、もう世間もここも寐静まつて居た上に、お孝は疲れた、そして酔つても居た。》が、赤熊の自然主義的な直訴で衝撃を受けての二度目の訪問。そこで、一度目の訪問の帰りの《……途中送る折も、送る女が、送らるゝ男の肩に、なよ/\と顔を持たせて、
「邪慳だね、帰るなんて。」》と想い出しつつ、
《ぐつすり寐込んだに相違ない。えゝ、決心は鈍らうとも、まゝよ、此の次に、と一度引返さうとして、たゞ、口ずさみのひとりでに、思はず、
「お孝……」
と呼ぶと、
「あい。」と声の下で返事して、階子(はしご)を下りるのがトン/\と引摺るばかり。日本の真中に、一人、此の女が、と葛木は胸が切(せま)つたのであつたが。
暖い閨(ねや)も、石の如く、砥(と)の如く、冷たく堅く代るまで、身を冷して涙で別れて》の、最後の行間で葛木はお考に非情な別れを告げたのだった。
そうして、三度目こそ、
《もう夜半(よなか)二時過。(中略)
「忘れものをして来た、帰つてくれないか。」
「唯今、乗(め)した処へ。」》
《直(す)ぐに稲葉家の露地を、ものに襲はれた体(てい)に、慌しく、その癖、靴を浮かして、跫音(あしおと)を密(ひそ)めて、した/\と入ると、門(かど)へ行つた身を飜(かへ)して、柳を透かしながら、声を忍んで、二階を呼んだ。
「お孝さん、……」》と他人行儀な「さん」づけの呼びかけで、
《寂然(ひつそり)としていたが、重ねて呼ぶのに気を兼ねる間も無く、雨戸が一枚、すつと開(あ)いて、下から映(さ)す蒼(あお)い瓦斯を、逆に細流(せゝらぎ)を浴びた如く濡萎(ぬれしを)れた姿で、水際(みづぎは)を立てて、其処へお孝が、露の垂(た)りさうに艶麗(あでやか)に顕れた。
が、其れは浴びるばかりの涙なのである。
唯(と)、見る時、葛木も面(かほ)にはら/\と柳の雫が、押へあへず散乱るゝ。》
そして《お孝は、乱書みだれがきの仮名に靡なびく秋風の夜更けの柳にのみ、ものを言わせて、瞳も頬も玉を洗ったように、よろよろとただ俯向うつむいて見た。
「済まないがね、――人形を忘れたから。」
「はい。」
と清く潔い返事とともに、すっと入ると、向直って出た。》とようやく時間は前に進んで行く。
《乳の下を裂いたか、とハッと思う、鮮血(なまち)を滴(したゝ)らすばかり胸に据ゑたは、宵に着て寝た、緋の長襦袢に、葛木が姉の記念(かたみ)の、あの人形を包んだのである。
ト片手ついたが、欄干(てすり)に、雪の輝く美しい白い蛇の絡(から)んだ俤。》の白い蛇体のイメージを、《袖で受けたが、さらりと音して、縮緬の緋のしぼ(・・)は、鱗が鳴るか、と地に辷つて、潰島田の人形は二片(ふたひら)三片(みひら)花を散ちらして、枝も折れず、柳の葉末に手に留(とま)んぬ。》という蛇の鱗にまで細密描写するとは、さすがに装飾的彫金の家職の出だった。
<「綺麗な花」 (六十四)>
《「まあ、綺麗に花が咲いた事。」
一町ひとまち、中を置いた稲葉家の二階の欄(てすり)に、お孝は、段鹿子の麻の葉の、膝もしどけなく頬杖して、宵暗(よひやみ)の顔ほの白う、柳涼しく、この火の手を視(なが)めていた。……》
お考は、反復するかのように、脱皮しても脱皮しても、「段鹿子の麻の葉」模様である。
<「振向く処を」 (六十五)>
《柳に片手を、柄下(つかさが)りに、抜刀(ぬきみ)を刃尖(はさき)上(あが)りに背に隠して、腰をづいと伸(の)して、木戸口から格子を透かすと、ちょうど梯子段(はしごだん)を錦絵の抜出したやうに下りて、今、長火鉢の処に背後(うしろ)向きに、すつと立つた、段染の麻の葉鹿の子の長襦袢ばかりの姿がある。
がらりと開けると、づか/\と入るが否や、
「畜生!」
振向く処を一刀(ひとかたな)、向うづきに、グサと突いたが脇腹で、アッとほとんど無意識に手で疵(きず)を抑へざまに、弱腰を横に落す処を、引なぐりに最(も)う一刀(ひとたち)、肩さきをかッと当てた、が、それは引かき疵に過ぎなかつた。刃物の鍛(きたへ)は生鉄(なまくら)で、刃は一度で、中じやくれに曲つたのである。
「姉さん、――」
虫が知らしたか、もう一度、
「お爺さん。」と呼ぶと斉しく、立つて逃げもあえず、真白な腕(かひな)をあはれ、嬰児(あかんぼ)のやうに虚空に投げて、身を悶えたのは、お千世ではないか。
赤熊は今日も附狙つて、清葉が下に着た段鹿子を目的(めあて)に刃(やいば)を当てた。
このお千世の着て居たのは、しかし其では無く、……清葉が自分のを持(もた)して寄越したのであることを、此処で言ひたい。
「一寸、お茶を頂きに。」
清葉の眉の上つたのを見て、茶の缶をたゝく叔母なるものは、香煎(にばな)でもてなすことも出来ないで、陰気な茶の間が白(しら)けたのであったが。――》
《清葉が自分のを持(もた)して寄越したのであることを、此処で言ひたい。》という、「段染の麻の葉鹿の子の長襦袢」の来歴を(二十八)同様に作者が顔を表して説明することで、「柳に銀の舞扇」(十七)末尾の、《清葉はきりゝと、扇子(あふぎ)を畳んで、持直して、「一寸、お茶を頂きに。」》の、清葉とお千世がお考を見舞いに来る場面へと、音声、聴覚に触発されて戻る円環構造(これもまたプルースト的である)。
着物を見間違えて殺してしまうのは、黙阿弥歌舞伎『曽我綉侠御所染(そがもようたてしのごしよぞめ)』で御所五郎蔵(ごしよのごろぞう)が傾城皐月の打掛を着ていた傾城逢州を誤って殺してしまう、などがある。
<「あはせかゞみ」 (六十六)>
《お千世が、その膝を抱くやうに附添つて、はだけて、乳(ち)のすくお孝の襟を、掻合せ、掻合せするのを見て、清葉は座にと着きあへず、扇子(あふぎ)で顔を隠して泣いた。
背後(うしろ)へ廻つて、肩を抱いて、
「お大事になさいよ、静にお寝(やす)みなさいまし、お孝さん、一寸(ちよいと)お千世さんを借りますよ。――お座敷にして。」
と顧みて、あとは阿婆(おばあ)に云つた。
「から、意気地も、だらしも有りませんやね、我まゝの罰だ、業(ごふ)だ。」
と時々刻んで呟つぶやいた阿婆が、お座敷と聞くと笑傾(ゑみかたむ)け、
「そらよ、お千世や、天から降つたやうな口が掛つた。さあ、着換へて、」
直ぐに連れて出ると心得た阿婆が、他(ほか)には無い、お孝の乱心(みだれごころ)にゆかしがつて着ていた、その段鹿子を脱がせようと、お千世が遮る手を払つて、いきなりお孝の帯に手を掛けて、かなぐり取らうと為(し)たのである。
「叔母さん、まあ、」
とお千世はおろ/\。……
「失礼をいたします。」と、何の事やらまた慇懃に、お孝が、清葉に手を支(つ)いたのは涙ならずや。
「これが可厭(いや)なら、よく稼いで、可(い)い旦那を取つてな、貴女方を、」
と、清葉を頤(あご)、
「見習つて幾枚でも拵(こしら)へろ、そこを退(ど)かぬかい。」と突退(つきの)ける。
「お待ちなさいまし。」
凜(りん)と留めて、
「切火(きりび)を打つて、座敷へ出ます、芸者の衣物(きもの)を着せるには作法があるんです。……お素人方(しろうとがた)には分りません、手が違うと怪我をします。貴方、お控えなさいまし。――千世(ちい)ちやん、今(箱さん。)を寄越すから、着換へないでいらつしやいよ。姉さんを気をつけて。お孝さん、」
何も知らず横を向いたお孝に、端正(ちやん)と手を支(つ)いて、
「さようなら。――二人で、一度あわせものをしませうね。」
と目を手巾(ハンケチ)で押えて帰つた。……
襦袢は故(わざ)と、膚馴れたけれど、同一(おなじ)其の段鹿子を、別に一組(ひとくみ)、縞物だつたが対(つゐ)に揃へて、其は小女(こをんな)が定紋の藤の葉の風呂敷で届けて来た。
箱屋が来て、薄べりに、紅裏香(べにうらにほ)ふ、衣紋を揃へて、長襦袢で立つた、お千世のうしろへ、と構へた時が、摺半鐘(すりばん)で。
「木の臭(にほひ)がしますぜ、近い。」
と云ふと、箱三(はこさん)の喜平(きへい)はひよいと一飛(ひととび)。阿婆(おばあ)も続いて駆出した。
お千世の斬られた時、衣物(きもの)はそこにそのまゝである。》
ようやく現在時制に追いつこうとする糊代のような一場の回想。内気そうだった清葉が、お考の身代わりのように凛とした日本橋芸者の姿を見せる。
火事の「摺半鐘(すりばん)」で、『伊達娘恋緋鹿子「櫓のお七」』や『三人吉三廓初買』のお嬢吉三が鳴らす鐘や、能『道成寺』、歌舞伎『京鹿子娘道成寺』に出現するシンボリックな鐘を想わずにはいられない。
<「振袖」 (六十七)>
《其の時、山鳥の翼を弓に番(つが)へて射るごとく、颯(さつ)と裳(もすそ)を曳(ひ)いて、お孝が矢のやうに二階を下りると思ふと、
「熊の蛆め、畜生。」と追縋つて衝(つ)と露地を出た。
が、矢玉と馳違(はせちが)ひ折かさなる、人混雑(ひとごみ)の町へ出る、と何しに来たか忘れたらしく、こゝに降かかる雨の如き火の粉の中。袖でうけつゝ、手で招きつゝ、
「花が散るよ、散るよ。」
と蹴出(けだ)しの浅黄を蹈くゞみ、その紅(くれなゐ)を捌きながら、ずる/\と着衣(きもの)を曳いて、
「おゝ、冷い、おゝ、冷い。……雪やこんこ、霰(あられ)やこんこ。……おゝ綺麗だ。花が散るよ、花が散るよ。」》
狂乱の道行。
《目の前へ、すつと来て立つたのはお孝である。
「刀をお貸し。」
黙つて袖口を、なぞへに出した手に、はつと、女神の命(めい)に従う状(さま)に、赤熊は黙つて其の刀を渡した。
「おゝ、嬉しい、剃刀一挺持たせなかつた。」
と、手遊物(おもちや)のように二つ三つ、睫を放して、ひら/\と振つた。
眦(まなじり)を返す、と乱るゝ黒髪。
「覚悟をおし。」と、澄まして一言(ひとこと)。
何か言ひさうにした口の、唯またニヤ/\と成つて、大(おほき)な涎の滴々(だら/\)と垂るゝ中へ、素直(まつすぐ)にづきんと刺した。が、歯にカッと辷つて、脣を決明果(あけび)の如く裂きながら、咽喉(のど)へはづれる、その真中、我と我が手に赤熊が両手に握つて、
「うゝゝ、うゝ!……抉(えぐ)れ、抉れ、抉れ。」
懐中(ふところ)をころがる小児(こども)より前に、小僧はべた/\と土間を這ふ。
「了(しま)つた。」
手を圧へたのは旅僧である。葛木は、人に揉まれて、脱け落ちた笠のかはりに、法衣(ころも)の片袖頭巾めいて面(おもて)を包んだ。
「お孝さん。」
「先生。」
と、忘れたように柄(つか)を離すと、刀は落ちて、赤熊は真仰向(まあふむ)けに、腹を露骨(あらは)に、のつと反(かへ)る。
お孝の彼を抉つた手は、こゝにただ天地一つ、白き蛇(くちなは)のごとく美しく、葛木の腕に絡(まつは)つて、潸々(さめ/゛\)と泣く。(中略)
お孝は法衣(ころも)の葛木に手を曳かれて、静々と火事場を通つた。裂けた袂も、宛然(さながら)振袖を着た如くであつた。
火の番の曲り角で、坊やに憧れて来た清葉に逢つた。
「あゝ、お地蔵様。」
夢かとばかり、旅僧の手から、坊やを抱取(だきと)つた清葉は、一度、継母(けいぼ)とともに立退(たちの)いて出直したので、凜々(りり)しく腰帯で端折(はしよ)つていた。》
「乱るゝ黒髪」は、前の《浅黄を蹈くゞみ、その紅(くれなゐ)を捌きながら》とあいまって、段染麻の葉鹿の子の衣裳で物狂う歌舞伎、浄瑠璃『妹背山女庭訓』金殿の段のお三輪、『心霊矢口渡』のお舟や、『伊達娘恋緋鹿子「櫓のお七」』で見られるそれであって、とりわけここでの《宛然(さながら)振袖を着た如くであつた》に「振袖火事」の照り返しがある。
また、《坊やを抱取(だきと)つた清葉》に「亡母追憶」「母子愛」が見てとれよう。
最後まで、「白き蛇(くちなは)のごとく美しく、葛木の腕に絡(まつは)つて」のお考の蛇のアレゴリーゆえに、『娘道成寺』の幕切れでもある。「橋」は勿論、「川」「水」「白」がそうであるように、「火事」「蛇」も鏡花の永遠のテーマである。
蛇となって物狂いせずにはいられない悲しい女たちの纏う「紅と浅黄の段染麻の葉鹿の子」こそ、佐藤春夫解説の《ヒューマニスト鏡花は愛の人であり常に弱者の味方である。女性がわが社会の弱者であるがために彼は亦フェミニストであつた。就中(なかんづく)妓女は弱者中の不遇な境涯の者であるといふ見解で、鏡花はその作品中で狭斜の地の婦女を好んで描き遇するには最も懇切であつた。狂女お考の意地や張、姉のために心ならぬ人に仕へる清葉にも道念や芸に対する心構など鏡花はその愛する妓女たちを描くに当つてはただ容姿の美と境遇の悲しさのみを以ては読者の同情を買はず、別にその各自にも可憐にも凛然たる志を与え、この愛情講義の物語にふさはしい彼女等の精神美を説いてゐるのも注目すべきである。》の象徴である。
これはまた、若桑みどりが「鏡花とプロテスタンティズム」で論じた、《鏡花の場合、まごころをたて通すのは女である。男は「世間」なり「体制」なり、「職分」なりの「外部」に対して心をゆりうごかす。しかし、男の本心は二つに割れている。そして結局のところ、身をほろぼすのは女と同じである。だが、そのプロセスがまるでちがう。そこのところの二重の心理の対位法が鏡花の作品のライト・モティーフになっている。
なぜ鏡花は、女に情をたて通させたのか。それは、女がもともと体制にくみこまれていず、権力のどのような段階にも入りこむことがない存在、全階級的にネイティヴなアウトローだからである。相対的に男は体制的であり、国家であり、権力であり、富である。鏡花の主人公は片手を「女」につかまれ片手を、出世とか権力とか富の形をした一方の「手」につかまれている。
「滝の白糸」となった「義血侠血」も、主人公の男は、「検事」という体制側の人間としてあらわれ、女は卑しい芸人であり、殺人犯という罪人としてあらわれる。》が、《ドストイエフスキーの娼婦ソーニャや、そして何よりも、アナトール・フランスの娼婦タイスのように、卑しく、この世でおとしめられ、傲慢から遠く、心にあわれみあり、苦しむものが、この世では滅びるが、あの世では、“救われる”のである。》は流転の女たち、お考や清葉のそれであろう。
若菜家お若の死の後に稲葉家お考が引っ越して来て物語が始まり、物語の末尾では、お考の死の後に火事にあった滝の家清葉が引っ越してくる。『日本橋』は「反復」の物語でもある。
《滝の家は、建つれば建てられた家を、故(わざ)と稲葉家のあとに引移つた。一家の美人十三人。
清葉が盃を挙げて唄ふ、あれ聞け横笛を。
――露地の細路駒下駄で――》
佐藤春夫「解説」の、《その異常な感覚に、その凛乎たち精神に、その純粋な詩的観念に、その印象的な描写に、その飛躍した文体に、幾多の近代文学――否超近代文学――的要素を具へながら、その取材とその表現の様式とのために、鏡花は今日の読者にはわかりにくく、親しまれなくなつてしまつてゐるのであらう。鏡花は正しくもう古い。理由はそれがあまり文学だからである。今日のためにこそ惜しめ、鏡花のために惜しむ要は更にない。
鏡花はもう古くなつてしまつた。さうして最も新らしい古典となつただけである。》から半世紀以上を経て、その予言性は加速度的にますます真実となっている。
(了)
*****引用または参考文献*****
*泉鏡花『日本橋』(「解説」佐藤春夫)(岩波文庫)
*『鏡花全集 巻二十六』(戯曲『日本橋』所収)(岩波書店)
*朝田祥二郎『注解 考説 泉鏡花 日本橋』(明治書院)
*佐伯順子『泉鏡花』(ちくま新書)
*川村二郎『白山の水 鏡花をめぐる』(講談社文芸文庫)
*渡辺直己『泉鏡花論 幻影の杼機』(河出書房新社)
*『柳田國男全集 7』(「一目小僧その他」に「橋姫」所収)(筑摩書房)
*『泉鏡花集成 8』(「遠野の奇聞」所収)(ちくま文庫)
*『谷崎潤一郎全集 22』(「映画雑感」所収)(中央公論社)
*『久保田万太郎全集 10』(「水上滝太郎君と泉鏡花先生」所収)(中央公論社)
*『国立劇場プログラム 昭和四十九年、第三回 十月新派公演「日本橋」』)(国立劇場事業部)
*市川崑監督、映画『日本橋』
*『日本古典文学大系 64』(為永春水『春色梅児誉美』所収)(岩波書店)
*『國文學解釈と教材の研究 特集 泉鏡花・魔界の精神史(1985年6月号第30巻7号)』(若桑みどり「鏡花とプロテスタンティズム」、宇波彰「泉鏡花の記号的世界」、郡司正勝「鏡花の劇空間」、延広真治「鏡花と江戸文芸――講談を中心に」等所収)(學燈社)
*谷沢永一、渡辺一考編『鏡花論集成』(立風書房)
*渡辺保『娘道成寺』(駸々堂)