
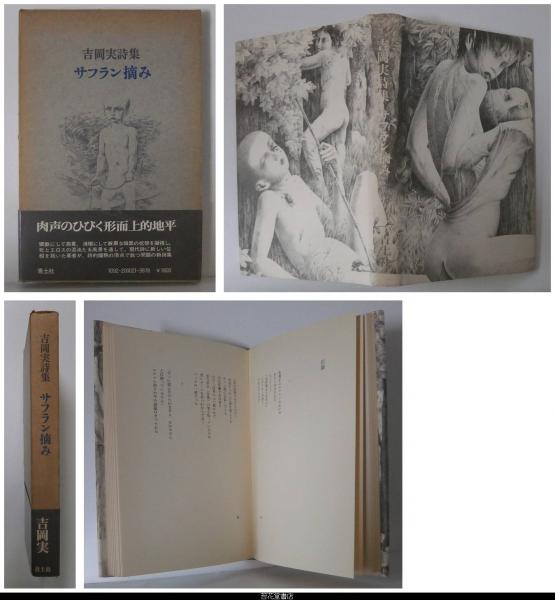

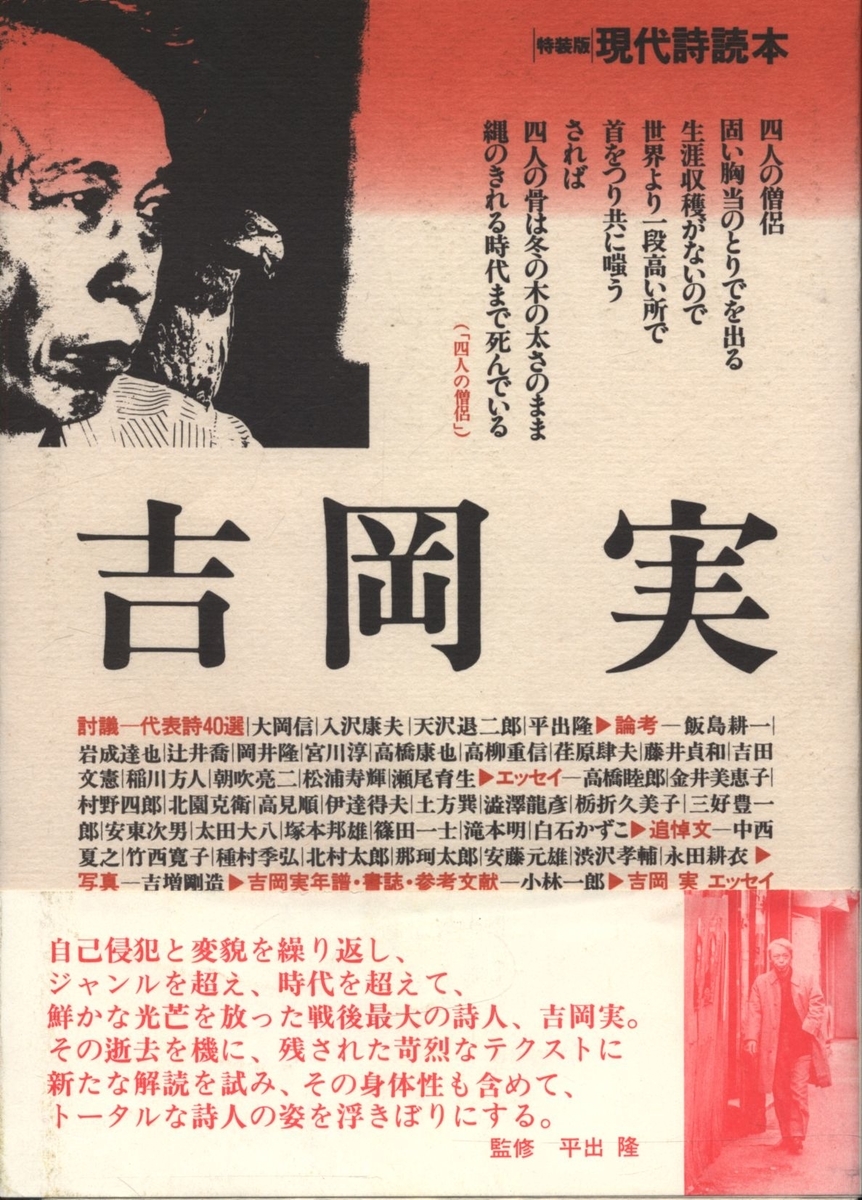
詩人吉岡実に、舞踏家土方巽についての『土方巽頌――<日記>と<引用>による』という書物がある。その「補足的で断章的な後書」によれば、
《「土方巽とは何者?」誰もがそう思っているにちがいない。この人物と二十年の交流があるものの、私には「一個の天才」を十全に捉えることは出来ないだろう。そこで私は自分の「日記」を中心に据え、土方巽の周辺の友人、知己の証言を藉り、そして舞踏家の箴言的な言葉を、適宜挿入する、構成を試みた。まさしく、「日記」と「証言」に依る「引用」の『土方巽頌』である。》
その方法にならい、吉岡実の詩、散文や討議・対談の発言を「引用」して、「吉岡実とは何者?」に少しでも迫ってみたい。吉岡は「補足的で断章的な後書」の最後にこう引用したではないか、《「私たちのように思考する者にとっては、あらゆる事物がひとりでに踊るのだ」》(ニーチェ)。
「吉岡実をめぐる対話 没後三十年を機に 朝吹享二+城戸朱里」(『みらいらん 2020 Summer第6号 特集吉岡実』に所収)の発言と、松浦寿輝「後ろ姿を見る――『サフラン摘み』の位置」(『特装版 現代詩読本 吉岡実』に所収)からの引用を軸に、「討議 大岡信・入沢康夫・天沢退二郎・平出隆「自己侵犯と変容を重ねた芸術家魂――『昏睡季節』から『ムーンドロップ』まで」や吉岡の散文などを絡めながら吉岡実の詩と踊りたい。
<「吉岡実をめぐる対話 没後三十年を機に 朝吹享二+城戸朱里」>
《城戸:いちばん重要なのは、吉岡実が、徹底したリアリストであったということだと思います。
吉岡さん自身が自らの詩を一行、一行、リアリズムと語ったことがありましたが、あれだけ異形(いぎょう)の詩が、吉岡さんにとってはリアルなものとして把握されていた。
それは、いったいなぜなのか。ここに吉岡実を理解するひとつのポイントがあると思います。
吉岡さんは社会人としては戦後、筑摩書房に勤め取締役までなったわけで、少なからぬ友人が語っているように、きわめて常識的な人でもありました。コーヒーが好きで、舞踏や美術を愛し、俳句や短歌を好んで読まれていましたが、同時にストリップとポルノ映画の愛好家でもあった。そして、そうしたものから詩想を汲み上げていったわけですが、その意味では、吉岡さんの詩はリアルな何かから始まって、吉岡実という触媒が介在することによって異形の詩の言葉が生成していくという印象がありますね。》
ストリップに関して補足すれば、
大岡信《吉岡実もストリップ劇場に行ってせんべいをぼりぼりかじったりしている連中のなかで出し物を見てると気持ちが安まるってことがあったでしょう。宮沢賢治はストリップには通わない。朔太郎は何やらこわごわと行ったんじゃないか。吉岡実は嬉々として行った(笑)。「岐阜のどことかはすごいよお」とかいう情報を彼から聞いて、なるほど筑摩書房の重役さんはいろんなところへ行っとるなあと思った(笑)。》(討議 大岡信・入沢康夫・天沢退二郎・平出隆「自己侵犯と変容を重ねた芸術家魂――『昏睡季節』から『ムーンドロップ』まで」)
その「リアル」(あるいは「半具象」)に関連して、吉岡実の数少ない散文のうち、「読書遍歴」「リルケ『ロダン』――私の一冊」と、自他ともに詩論を書かなかった吉岡にしては稀有な「わたしの作詩法?」から引用しておこう。
《昭和十六年八月から満州へ出征し、朝鮮済州島で終戦を迎えるまでの、四年六ヵ月、わたしは果してどんな本を読んだか、その多くを記憶していない。軍隊の悲惨な日々の中で、ひそかに日記と詩を書きながら、折にふれて、岩波文庫のリルケの『ロダン』を読んでいた。内務検査の時、わたしはいつも厩舎の寝藁の中へ、七、八冊の翻訳書を匿したものだ。ゲーテの『親和力』もその数少ない私物品の一つだった。リルケの『ロダン』の手仕事の精神が、戦後のわたしの詩作へ大きく影響しているといえる。》(「読書遍歴」)
《さて、リルケの『ロダン』であるが、巨匠ロダンへの詩人の純粋な魂が、いかに傾倒していったかの、告白の書である。しかし、私にとっては、ロダンの偉大さは、どうでもよかった。透明な空間へ鋳こまれたような、リルケの言葉――肉体の鎖、螺条、蔓。罪の甘露が痛苦の根からのぼって行く、重くみのった葡萄のように房なす形象――というような陰影深い詩的文体に、私は魅せられた。(中略)
『ロダン』一巻は、リルケがロダンの精神と彫刻を賛美しながら、自己の「試論」を展開しているように、私には思われた。だが真の啓示を受けたと、いえるのは次の章句である。
何物かが一つの生命となり得るか否かは、けっして偉大な理念によるのではなく、 ひとがそういう理念から一つの手仕事を、日常的な或るものを、ひとのところに最後までとどまる或るものを作るか否かにかかっているのです。
この言葉はおそらく、ロダンの言葉であると同時に、またリルケの理念といってもよいのだろう。私は一つの方向を指示された思いだった。それからは、詩を書くときはつとめて、職人が器物をつくるように、「霊感に頼ることなく」、手仕事を続けてきたのである。それらの詩篇が、詩集『静物』へと生成していったのであった。》(リルケ『ロダン』――私の一冊)
《或る人は、わたしの詩を絵画性がある、又は彫刻的であるという。それでわたしはよいと思う。もともとわたしは彫刻家への夢があったから、造形への願望はつよいのである。詩は感情の吐露、自然への同化に向って、水が低きにつくように、ながれてはならないのである。それは、見えるもの、手にふれられるもの、重量があり、空間を占めるもの、実在――を意図してきたからである。だから形態は単純に見えても、多肢な時間の回路を持つ内部構造が必然的に要求される。能動的に連繋させながら、予知できぬ断絶をくりかえす複雑さが表面張力をつくる。だからわたしたちはピカソの女の顔のように、あらゆるものを同時に見る複眼をもつことが必要だ。中心とはまさに一点だけれど、いくつかの支点をつくり複数の中心を移動させて、詩の増殖と回転を計るのだ。暗示・暗示、ぼやけた光源から美しい影が投射されて、小宇宙が拡がる。》(「わたしの作詩法?」)
《 苦力
支那の男は走る馬の下で眠る
瓜のかたちの小さな頭を
馬の陰茎にぴったり沿わせて
ときにはそれに吊りさがり
冬の刈られた槍ぶすまの高梁の地形を
排泄しながらのり越える
支那の男は輝く涎をたらし
縄の手足で肥えた馬の胴体を結び上げ
満月にねじあやめの咲きみだれた
丘陵を去ってゆく
より大きな命運を求めて
朝がくれば川をとび越える
馬の耳のあいだで
支那の男は巧みに餌食する
粟の熱い粥をゆっくり匙で口へはこびこむ
世人には信じられぬ芸当だ
利害や見世物の営みでなく
それは天性の魂がもっぱら行う密儀といえる
走る馬の後肢の檻からたえず
吹きだされる尾の束で
支那の男は人馬一体の汗をふく
はげしく見開かれた馬の眼の膜を通じ
赤目の小児・崩れた土の家・楊柳の緑で包まれた柩
黄色い砂の竜巻を一瞥し
支那の男は病患の歴史を憎む
馬は住みついて離れぬ主人のため走りつづけ
死にかかって跳躍を試みる
まさに飛翔する時
最後の放屁のこだま
浮かぶ馬の臀を裂く
支那の男は間髪を入れず
徒労と肉欲の衝動をまっちさせ
背の方から妻をめとり
種族の繁栄を成就した
零細な事物と偉大な予感を
万朶の雲が産む暁
支那の男はおのれを侮辱しつづける
禁制の首都・敵へ
陰惨な刑罰を加えに向う
(中略)
これは兵隊で四年間すごした満州の体験である。
「支那の男」とは、当時の満人である。満人というより、「支那の男」の方がスケールが大きいと思ったからである。彼らは裸馬を巧みに乗りこなしていた。馬は満馬といって、小形であるが、大変気質が激しく、乗りにくい。
わたしたち輜重兵は、馬運動と称して、毎日のように、馬にのって遠くの部落まで。高粱畑を越して行った。冬は刈られた高粱が、まさに鑓先を揃えて、どこまでも続く。万一にも落馬したら、腹にでも顔にでも突きささるだろう。そんな恐怖感があった。(中略)「排泄しながらのり越える」とは、兵隊とはいえ、わたしたちの中には、排泄の場所は習慣として、一定のところへするが、満州では、満人部落の周辺といわず、曠野に道に、排泄物がちらばっている。もちろん家畜のものもあるが、排泄物こそ彼らの力であるように思えた。極寒の兵舎の厠のぞっとする底で、火山の噴出物のような排泄物の氷った塊の山をつるはしで崩していた満人の見えない顔。(中略)或る別の部落へ行った。兵隊たちは馬を樹や垣根につなぐと、土造りの暗い家に入って、チャンチュウや卵を求めて飲む。或るものは、木のかげで博打をする。豚の奇妙な屠殺方法に感心する。わたしは、暗いオンドルのかげに黒衣の少女をみた。老いた父へ粥をつくっている。わたしに対して、礼をとるのでもなければ、憎悪の眼を向けるでもなく、ただ粟粥をつくる少女に、この世のものとは思われぬ美を感じた。その帰り豪雨にあい、曠野をわたしたちは馬賊のように疾走する。ときどき草の中の地に真紅の一むら吾亦紅が咲いていた。満人の少女と吾亦紅の花が、今日でも鮮やかにわたしの眼に見える。揚柳の下に、豪華な色彩の柩が放置されているのも、異様な光景だ。ふたをとって覗いて見たらと思ったが、遂に見たことはない。びらんした屍体か、白骨が収まっているのだろう。みどりに芽吹く外景と係りなく。やがて黄塵が吹きすさぶ時がくるのだ。
反抗的でも従順でもない彼ら満人たちにいつも、わたしたちはある種の恐れを抱いていたのではないだろうか。(中略)
彼らは今、誰に向って「陰惨な刑罰」を加えつつあるのか。
わたしの詩の中に、大変エロティックでかつグロテスクな双貌があるとしたら、人間への愛と不信をつねに感じているからである。》(「わたしの作詩法?」)
平出隆《「苦力」というのは特徴のある詩なんですけれども、一つは吉岡さん自身の身ごなしのようなものが見えてくるような作品ですね。いろんな方がエッセイで生身の吉岡さんの身ごなしについて語っているんですけれども、「支那の男」の身軽さ、舞踏性すらある身軽さ、そういうものが詩人自身の身体表現にもつながってゆくわけですね。このことは例えば土方巽さんとの交りなんかともかかわっていくように思えます。》(討議 大岡信・入沢康夫・天沢退二郎・平出隆「自己侵犯と変容を重ねた芸術家魂――『昏睡季節』から『ムーンドロップ』まで」)
大岡信《吉岡実と同世代の大学まで行ったような人たち、つまりエリートコースに否応なく乗ってしまって軍隊に学徒動員みたいな形で行った人たちと彼との違い、一兵卒で招集されて満州へ行って馬と格闘したという違いが、吉岡実の最晩年まで貫いているように思うんです。だけどそうであるから吉岡実は孤立していたかというとそうじゃなかった。そのことがこの人の場合、詩人の栄光としてあったと思います。》(討議 大岡信・入沢康夫・天沢退二郎・平出隆「自己侵犯と変容を重ねた芸術家魂――『昏睡季節』から『ムーンドロップ』まで」)
《朝吹:詩集『僧侶』において特筆すべきは肉体の特出性です。吉岡実の詩の物質性についてはすでに指摘しましたが、ここにあらわれる肉体のプレゼンスも凄い。
ここでとりわけ注目したいのは「管」です。「はげしい空腹と渇き/やみから抽き出された/一つの長い管を通りぬけ/坐りこんだ臓物」(仕事)とか「流通する熱と臭気をぬきながら 肛門につながる管をけんめいにたぐり出す 抑えきれぬゴムの状態で かさばりはじめ 部屋中を占めてのたうちまわる」(伝説)とか「もろい下の躰の管をすすむ血の粗い無責任な軍隊を見すごす」(固形)の出てくる「管」です。次の『紡錘形』の有名な「下痢」もそうですし、疫病で言えば、ペストではなく「コレラ」(『神秘的な時代の詩』)なんですね。人がただ単なる一本の筒であり管になってしまう。まさにアントナン・アルトー的というか、器官なき身体というか。これは強烈です。
この肉体の(あるいは肉体の空洞化の)プレザンスはしかし言葉のプレザンスそのものなわけです。エロスもそうですね。禁忌への侵犯、羞恥の暴露という要素も言葉の問題として考えています。例えば「死児」の「首のない馬の腸のとぐろまく夜の陣地/姦淫された少女のほそい股が見せる焼かれた屋根/朝の沼での兵士と死んだ魚の婚礼」ここは特にポルノグラフィックなエロスはないのですが、グロテスクな像をむすぶ言葉が重なって、そのイメージの動き、つまり言葉の動きのなかに怖ろしいエロスがあらわれてくる。見てはいけないものを見てしまうエロスがある。「水のもりあがり」でも「女と魚 くらい鏡の割れ目からもりあがってくる水」のような見てはいけないモノを暴露するエロスがあるのですね。》
大岡信《吉岡実の愛用した言葉の一つに「いかがわしい」という言い方があります。いかがわしい世界を書きたいという欲望があって、それは『僧侶』ではひじょうに明確にあるんですね。あれは昭和三十三年に出た詩集です。》(討議 大岡信・入沢康夫・天沢退二郎・平出隆「自己侵犯と変容を重ねた芸術家魂――『昏睡季節』から『ムーンドロップ』まで」)
《朝吹:『神秘的な時代の詩』は『静かな家』から始まり『サフラン摘み』に至る、それまでのグロテスクなまでの肉のプレザンスによるエロスとはまた異なるエロティシズムが充溢する三部作ともいえる詩集のひとつなのですが、(中略)『僧侶』『紡錘形』の形而下的な肉のあらわれから形而上的なエロスへ、と言っていいかもしれません。『静かな家』でいえば、「桃 あるいはヴィクトリー」に「わ ヴィクトリー/挽かれた肉の出るところ/金門のゴール?」「かがやかしく/大便臭い入江/わ ヴィクトリー/老人の口/それは技術的にも大きく/ゴムホースできれいに洗浄される」といったあいかわらず管化した筒としての肉が描かれますが、どこかきらきらかがやいているところがある。「わたしたち再びうまれるとしたら/さびしいヴィオレット色の甘皮からだ/それはいじるより見る方が美しい」(聖母頌)とあるように見るという、エロスの対象への距離が重要になってくる。それはエロスの後退ではなく、どこまでも到達できない対象への痙攣的な欲望を示しているのだと思います。「夕焼けの空のストロベリージュースを/きみの母の血でなければ/かれらの妹の植物化した直腸の液」(内的な恋唄)のように肉なんだけどどこか遠い。この距離感は批判ではありません。むしろ距離がつくられることでかがやかしいエロスが浮き上がってくる。『神秘的な時代の詩』の「少女こそぼくらの仮想の敵だよ!/夏草へながながとねて/ブルーの毛の股をつつましく見せる」(聖少女)、ここから『サフラン摘み』のアリス詩篇は直結していますね。「それにしてもわしは覗きたい 袋とペチコートの内側を/なまめかしい少女群の羽離れする 甘美な季節の終り/かくも深く彼女らの皮膚を穿ち 水と塩を吸い/夜は火と煙を吹き上げる 謎の言語少女よいずこ」(『アリス』狩り)覗き見、視姦の密かな悦び。しかし、一体何を見ているのか? 言語少女なのです。視姦されているのは言語なのだというのは重要ですね。》
《城戸:吉岡実においては「見る」ことが、詩の発端にあったということは重要ですよね。その意味では、吉岡さんにとって、舞踏や美術とストリップやポルノ映画も同じ次元にあるものだったのでしょう。》
天沢退二郎《『薬玉』や『ムーンドロップ』の言葉の在り様、行をズラして括弧でくくって仕切りとして上から見れば見えるということはどこからくるかというと、一つは映画だと思うんですね。吉岡実が好きだったものの一つは映画で、特にロマンポルノなんかはよく観ていましたよね。(中略)吉岡実の詩法が映画と関係があると気づいたんですね。例えば映画のカメラ・アイが玉ノ井の私娼窟で客と娼婦が寝ているところを上からスーと見ているわけですよ。》(討議 大岡信・入沢康夫・天沢退二郎・平出隆「自己侵犯と変容を重ねた芸術家魂――『昏睡季節』から『ムーンドロップ』まで」)
《朝吹:確かに「見る」のだけど、言語化することによって、新たに見直すということが起きるのですね。言葉によって新たに見るのです。そういう重層化した「窃視」の構造が明白に意識されるのが『サフラン摘み』なのでしょう。アリスの写真を見るという行為から始まるわけですが、作品化の過程で、言葉によって、見るということがもう一度見られることになる。言葉による「窃視」がもう一度起きる。その重層化が生々しく禍禍しくもあるのですね。》
《城戸:これは私の個人的な思いなのかも知れませんが、エロスとタナトスの壮麗な絵画のような吉岡実の詩を読んでいると、あのニーチェの名高い箴言、「深淵を覗くとき、深淵もまたあなたを覗いているのだ」を思い出すんです。まるで、自分が逆に見つめられ、詩的惨劇と喜劇のなかに巻き込まれてしまうような。これは吉岡実の詩が単純な平面的情緒のなかに完結するのではなく、複層とその逆転から成り立っているからかも知れません。》
《だが『サフラン摘み』に至って「見る」が回帰する。ここで詩人が、見えないものをたしかに見えていることをわれわれは疑うことができない。実際、詩篇《マダム・レインの子供》を読むたびにわれわれは「マダム・レインの子供」をたしかに見て(・・)、ほんの少し死にたくなるだろう。この驚くべき凝視の力とニヒリズムの輝きを浴びてそうならない者がいるとしたら、その読者は吉岡実の詩とはついに無縁の衆生なのである。
しかしそれならば、マダム・レインの不可視の子供は初期吉岡実の実存世界と同質の空間に棲んでいるのかと言えば必ずしもそうは言えないというところに、『サフラン摘み』の位置の両義性が露呈しているのだ。(中略)ここにあるのは、可視と不可視を分かつ境界線上の記号の戯れが、猛々しい軽さの闖入によってその基盤を揺るがされ、ほとんど自壊しかけながらなお実存的想像力によって充填され支持されて辛うじて機能している不安定な均衡状態である。》
ジャック・ラカン『精神分析の四基本概念』に、《サルトルは『存在と無』の中のもっとも見事な個所で、他人の実在という次元で、眼差しを機能させています。もし眼差しがなかったとしたら、他人というものは、サルトルの定義にしたがえば、客観的実在性という部分的にしか実現されえない条件にまさに依存することになってしまいます。サルトルの言う眼差しとは、私に不意打ちをくらわす眼差しです。つまり、私の世界のあらゆるパースペクティヴや力線を変えてしまい、私の世界を、私がそこにいる無の点を中心とした、他の諸々の生命体からの一種の放射状の網へと秩序づけるという意味で、私に不意打ちをくらわす眼差しです。無化する主体としての私と私を取り巻くものとの関係の場において、眼差しは、私をして――見ている私をして――私を対象として視ている人の目を暗点化させるにまで至る、という特権を持つことになります。私が眼差しのもとにあるかぎり、私はもはや私を視ている人の目を見ることはできないし、逆にもし私が目を見れば、そのときは眼差しは消えてしまう、とサルトルは書いています。
これは正しい現象学的分析でしょうか。そうではありません。私が眼差しのもとにあるとき、私が誰かの眼差しを求めるとき、私がそれを獲得するとき、私は決してそれを眼差しとしては見ていない、というのは真実ではありません。
眼差しは見られるのです。つまり、サルトルが記述した、私を不意打ちするあの眼差し、私を恥そのものにしてしまう――というのはサルトルが強調したのはこの恥という感情ですから――あの眼差し、それは見られるのです。私が出会う眼差しは、これがサルトルのテクストの中に読み取ることができるものですが、見られる眼差しのことではまったくなくて、私が〈他者〉の領野で想像した眼差しにすぎません。
彼のテクストに当たってごらんになればお解りになると思いますが、彼は視覚器官に関わるものとしての眼差しの出現のことを語っているのでは決してなくて、狩りの場合の突然の木の葉の音とか、廊下に不意に聞こえる足音とか――これはどういうときかというと、鍵穴からの覗きという行為において彼自身が露呈するときです――のことを言っているのです。覗いているときに眼差しが彼に不意打ちをくらわせ、彼を動揺させ、動転させ、彼を恥の感情にしてしまうのです。ここで言われている眼差しは、まさに他人そのものの現前です。しかし、眼差しにおいて何が重要かということを我われが把握するのは、そもそも主体と主体との関係において、すなわち私を視ている他人の実在という機能においてなのでしょうか。むしろ、そこで不意打ちをくらわされたと感じるのは、無化する主体、すなわち客観性の世界の相関者ではなくて、欲望の機能の中に根をはっている主体であるからこそ、ここに眼差しが介入してくるのではないでしょうか。
欲望がここでは覗視の領野において成り立っているからこそ、我われは欲望をごまかして隠すことができるのではないでしょうか。》
《『サフラン摘み』のこうした危うい過渡期的性格を体現しているものは、後ろ姿(・・・)のイメージであるように思われる。「見ること」の戯れ自体、ここではすでに他人には見えないものが詩人には見えるという特権的想像力の発現ではなく、見たくないものをあえて見ずにはいられないという脅えと受苦の体験へと位相をずらしており、それはそれで十分に徴候的であるが、さらにその当の「見る」べきものが、正面を見せずに後ろ向き(・・・・)で登場しているという点が注目に値するだろう。
裸のマダム・レインは美しい
でもとても見られない細部を持っている
夏ならいいのだが
雪のふる夜をマダム・レインは分娩していたんだ
うしろからうしろからそれは出てくる
これはクレタの王宮の華麗な壁面の中で四つんばいになってサフランを摘んでいるあの少年の、
岩の間には蒼い波がうずまき模様をくりかえす日々
だがわれわれにはうしろ姿しか見えない
というこの「うしろ姿」と同じ方向づけを持ったイメージであるように思われる。マダム・レインと同様に少年もまた後ろ向きになって何ものかを分泌しているのだが、彼の突き出された尻から落ちてくる「一茎のサフランの花の香液のしたたり」とは、それに続く「白い三角波」や「猿の首」――「波が来る 白い三角波/次に斬首された/美しい猿の首が飾られるであろう」――ともどもに、それを見たら「そのたびぼくらは死にたくなる」といった種類の光景に属しているものだろう。(中略)やはり『サフラン摘み』に収められている詩篇《自転車の上の猫》にも、「禁欲的に/薄明の街を歩いてゆく/うしろむきの少女」が登場している。
なるほど『僧侶』の時期の《感傷》にはすでに「桃をたべる少女はうしろむき」という戦慄的な一行が含まれているので、これが『サフラン摘み』で初めて出現したイメージであるとは必ずしも言いきれないのはたしかだが、《感傷》の場合は、語られざる一語としての「尻」を媒介にしての「隠喩」的でもあり「提喩」的でもある桃と少女との結合が必然的に要求する後ろ姿だったのであり、これはたいへん官能的ではあるが思いのほか自然(・・)なイメージでもあると言える。》
吉岡実には、「尻(臀)」への窃視症的偏執があって、丸い(《その球体の少女の腹部と/関節に関係をつけ/ねじるねじる》(「聖少女」)ハンス・ベルメールの人形や、《いままでに彼女の全作品を見ている。そしてその美しい裸に、美しい夢を紡いできた》というブリジット・バルドー(同じく尻フェチのゴダールはバルドーの尻を撮りたいがために映画『軽蔑』を撮影した)、卵、固体と液体、腸(管、筒)、便器、下痢、排泄、肛門などと照合する。
《ときに牝の尻の穴 柔媚な
紅の座を嗅ぎつけ 嫣然と眦をほそめてゆく
時――ああ果は 滂沱たる放尿の海》(「寓話」)
《中の一人が誤って
子供の臀に蕪を供える》(「僧侶」)
《めいめい死児の裸の臀を叩く》(「死児」)
《割れた少年の尻が夕暮れの岬で
突き出されるとき》(「サフラン摘み」)
《わしの知っとる
「もう一人のアリスは十八歳になっても 継母の伯母に尻を
鞭打たれ あるときはズックの袋に詰められて 天井に吊る
される 美しき受難のアリス・ミューレイ……」》(「『アリス』狩り」)
《朝吹:『ムーンドロップ』の表題作「ムーンドロップ」はナボコフの章句を借用したと註記されながら、もちろんナボコフもあるのだけど、「ロベルト夫人の下着の下の梨形の/(臀部)/その全体の重み/その(共犯性)」とむしろクロソウスキーへの言及がなされる。引用とか地の文とかの区別もどんどん無化されていて、むしろちりぢりになっている。》(「吉岡実をめぐる対話 没後三十年を機に 朝吹享二+城戸朱里」)
クロソウスキー『ロベルトは今夜』で「窃視」と「尻」は、
《それから彼は、ロベルトの高くもちあげられた動かない手をとらえ、手袋を脱がせて手首をにぎりしめ、背後から彼女の黒のスカートをまくりあげ、尻をあらわにして愛撫しはじめた。ロベルトは、あらわな手ににぎりしめた手袋が落ちるにまかせながら、自分の体にかがみこんでいるヴィクトールを押しのけようとした。彼がいまにも語りかけようとしたのに気づいたロベルトは、手袋をつけていない手のひらを彼の唇にあてた。いっぽうヴィクトールは、まるみのある彼女の尻をなでまわしていた。やがて彼女は、ヴィクトールの口にあてた手のひらをひっこめて、下にさげ、指をのばしてヴィクトールの一物をにぎり、払いのけようとこころみながらも、けっきょくは手放さずに上体をのけぞらせた。(中略)
それからヴィクトールは、やすやすとロベルトを向きかえさせた。いまやアントワーヌに、うら若い伯母の尻、目、膝のくぼみ、黒いコルセットをつけた長い脚などを見せる時であった。ヴィクトールは、背後から彼女の二つの手首をにぎり、彼女を一物の上にすえつけた。そして彼女は爪先だって、このどうにもあらがいがたい試練をうけいれることになった。アントワーヌはカーテンの後にかくれていた。あまり感動が激しくて、その情景を見つめていることができなかったのである。だがこのとき彼は、しわがれた叫び声を聞いて思わず飛びあがり、もう一度その情景をのぞきこまずにはいられなくなった。》
同じくクロソウスキーの『ディアーナの水浴』の罪深い「窃視」と「尻」打ち、
《アクタイオーンは牡鹿の頭で自分の顔をかくし、《女神めあてに仮面を被った》とはわれながら実に悪賢いと思いながら、泉に向って進み、洞窟の中にかくれようとする。彼は彼女が来るのを待つ。》
《彼は片手で銀の弓を彼女から奪い、もう片方の手で女神が箙に近づけていた方の手首を押えると、いまや彼女の耳を弓で打ちはじめ、彼女が打撃を避けようとして頭を下げる間に、テュニックは落ち、帯はほどけ、箙は地面に矢をばらまき、そしてついに彼は彼女の尻をまくり上げ、弓も砕けんばかりの一撃を喰わせるが、まるでそれは銀の弓が自分からディアーナの尻の上で踊っていると思わせかねない。そして事実、彼女の暗闇からは光あふれる三日月の角が姿を現わし、彼女はその光輝を長く影の深い手でいまだに隠している。だが尻打ちが激しくなればなるほど、三日月は大きく昇る。そして偶像の臀部に隙間が開くので、アクタイオーンは頭を下げてそこに突っ込む。いまや彼は自己の召命の終点にある。》
吉岡実が「わたしの作詩法?」で自解したように、クロソウスキーもまたリルケに(こちらは直接)学んだ、芸術家としての禁欲(拘束)的苦行と規範の人だった。あるインタヴュー(「エロス・ベルゼバブ株式会社」)で、
《一九二五年にリルケが最後にパリにいた時、毎晩のように家にやって来て、皆で雑誌に新しく出た文章や、モーリャックやジッドの小説などの読書会をしたものでした。その時私が第一に教えられたことは、極めて本質的なことで、それが私の人生を大きく支配する考えとなりました。それは、創造には苦行と絶対的謙下の精神が必要なのだ、ということです。芸術家はその作品の中に消え去らねばならない。無私無欲の創造を行う、修道僧のような不撓不屈の精神――ここに最大限の謙下の意味がある――そして瞑想の対象を生み出すという喜びより外の喜びは持たない。ただし、実際の創作の前にあらかじめ規範を定めておき、それを完全に遵守する。このリルケの教えから、私は絶対的受動性という考えを得たのだと思います。つまり、創造し制作しようという欲求に拘束を課して、表現のあらゆる様式に強制的な規範を設けるわけです。》
平出隆《吉岡さんの詩の変化というのは、こういうものは使っちゃいけないという自分なりのルールのようなものがその時点で確かなものとしてあって、それを自己侵犯していくものとして出てきますね。固有名詞の問題と言い、引用の問題といい。》(討議 大岡信・入沢康夫・天沢退二郎・平出隆「自己侵犯と変容を重ねた芸術家魂――『昏睡季節』から『ムーンドロップ』まで」)
入沢康夫《やはりエロティックなものグロテスクなものも本当はもっとあるわけですよ。でも全部それを出しているとは思いませんね。こういうものを文字にしてはいけないという気持ちが強く働いていたんでしょうね。》
大岡信《私生活においてもぼくらが知らないようなところで、ひじょうに禁欲的な生活をしていたように思うんですね。》
入沢康夫《そうですね。これを書いては自分の芸術家としての品格、作品の品格にかかわるということがあったみたいですね。》(討議 大岡信・入沢康夫・天沢退二郎・ 平出隆「自己侵犯と変容を重ねた芸術家魂――『昏睡季節』から『ムーンドロップ』まで」)
松浦は続ける、《ところで、「後ろ姿を見る」という主題に関しては、まだ語られることが残っている。というのも、「死にたくなる」のを避けようとするあまりか、われわれは未だマダム・レインの「とても見られない細部」を具体的に(・・・・)見てとるべく眼を凝らそうと努めてはいないからである。凝視の必要があるだろう。少年または女性の裸体を「うしろ」から見るというのはどういうことか。つまり、そこにはいったい何が「見える」のかを具体的に問わねばなるまい。(中略)「死の器」への言及に続く、「球形の集結でなりたち/成長する部分がそのまま全体といえばいえる/縦に血の線がつらなって/その末端が泛んでいるように見えるんだ/比喩として/或る魚には毛がはえていないが/或る人には毛がはえている」といった部分に、女陰のイメージを読み取らないことは難しい。本来は「生の器」としてあるべきなのに、「ムーヴマンのない」「体操のできない」「恐しい子供」しか産み落とせないがゆえに「死の器」と呼ばれている女性性器こそ、それを見るか見ないかがこの詩篇において終始問題にされている当のものなのである。マダム・レインの美しい裸体の持つ「とても見られない細部」とは性器にほかならず、そして「恐しい子供」というのも実は彼女の性器それ自体の外在化されたイメージにほかなるまい。(中略)吉岡実における女陰は、人目につかぬ深みに身を隠しつつ言葉の表層にその屈折した垂直的な照り映えをゆらめかすことでおのが存在を誇示している何かといったものではない。それは、言葉の表層にあからさまに現前しつつ、絶えずその水平面上でのイメージ連結の、無方向的な力の戯れを組織しつづけている負の陥没点なのだ。(中略)
迂回せよ
月の光に照らされて
あらわに見えて来る
〔膣状陥没点〕……
(《〔食母〕頌》『ムーンドロップ』所収)
露わに見えているがゆえに「迂回」を強いられる陥没点としての女陰は、或る意味では吉岡実の創造したあらゆる詩的イメージのうちで至高のものである。それは、単に特異な吉岡的エロティシズムの一構成要素というだけのものではない。それはまず、見ることと見ないこととをめぐるまなざしの遊戯の対象として特権的なものであり、そのかぎりにおいて、詩人の視線が世界と関わり(あるいは関わりを拒み)、その関係の(あるいは疎隔の)ありようを分節化するその仕方の雛形を示している極めつけのオブジェである。吉岡実の詩の官能性が窃視症的なエロティシズムに染め上げられていることは間違いあるまいが、「エロス」と「見ること」という二つの主題のどちらが彼にとって本質的であるかと言えば答えは明らかだろう。女体の官能性への関心がまずあってそれを見ることが次に問題となるのではなく、他の何にも先行して吉岡実はまず見る人(・・・)なのだ。というよりむしろ、覗く人(・・・)と言うべきかもしれぬ。そして、見る行為が、その内包する孤絶と距離の意識を尖鋭化させていった挙句に窃視者の脅えと快楽へと近づいてゆくとき、そこに覗き(・・)の対象として唯一至高なるものとしての女性の秘部の主題が大きくせりあがってくることになるのである。それは見えないもの、見たくてたまらないもの、選ばれた瞳の持つ幻視の力によってのみ見ることのできるもの、しかし見ることはできてもそれに触れたりそれを享受したりすることはできないものだ。そうした意味では、吉岡実の創造したすべてのイメージは女陰のヴァリエーションにすぎないとさえ言えるかもしれない。》
ジュリア・クリステヴァは、穢れ、おぞましさというアブジェクト(abject)について、『恐怖の権力 <アブジェクション>試論』で、《おぞましきもの(アブジェクション)に化するのは、清潔とか健康の欠如ではない。同一性、体系、秩序を攪乱し、境界や場所や規範を尊重しないもの、つまり、どっちつかず、両義的なもの、混ぜ合わせである。言い換えれば、良心にあふれた裏切者や嘘つきや犯罪者、人助けだと言い張る破廉恥な強姦者や殺人者……。およそどんな犯罪でも、法の脆さを目立たせるので、アブジェクトとなる。だが計画的な犯罪、狡猾な殺人、偽善に満ちた復讐はなおさら法の脆さを人前に晒すために、より一層アブジェクトである》、《おぞましきもの(アブジェクト)は倒錯〔頽廃〕と類縁関係をもっており、私が抱くおぞましさ(アブジェクション)の感情には超自我に根差している。アブジェクトは倒錯的〔頽廃的〕だ。なぜならそれは禁止や法則や掟に見切りをつけることも引き受けることもせずに、その向きを変え、道を誤らせ、堕落させるからである》、《恐怖症はしばしば窃視症へと脱線してゆく。窃視症は対象関係の構成にとって構造的に不可欠であり、対象がアブジェクトの方向へ揺れ動いてゆくたびに現われる。それが真の意味の倒錯となるのは、主体/客体の不安定さを象徴化する作業に失敗した場合に限られる。窃視症はアブジェクションのエクリチュールの同伴者である》と書いたが、吉岡実もまた同伴者に違いない。
吉岡実「私の好きなもの」(一九六八年)
《ラッキョウ、ブリジット・バルドー、湯とうふ、映画、黄色、せんべい、土方巽の舞踏、たらこ、書物、のり、唐十郎のテント芝居、詩仙洞、広隆寺のみろく、煙草、渋谷宮益坂はトップのコーヒー。ハンス・ベルメールの人形、西洋アンズ、多恵子、かずこたちの詩。銀座風月堂の椅子に腰かけて外を見ているとき。墨跡をみるのがたのしい。耕衣の書。京都から飛んでくる雲龍、墨染の里のあたりの夕まぐれ。イノダのカフェオーレや三條大橋の上からみる東山三十六峰銀なかし。シャクナゲ、たんぽぽ、ケン玉をしている夜。巣鴨のとげぬき地蔵の境内、せんこうの香。ちちははの墓・享保八年の消えかかった文字。ぱちんこの鉄の玉の感触。桐の花、妙義の山、鯉のあらい、二十才の春、桃の葉の泛いている湯。××澄子、スミレ、お金、新しい絵画・彫刻、わが家の猫たち、ほおずき市、おとりさまの熊手、みそおでん、お好み焼。神保町揚子江の上海焼きそば。本の街、ふぐ料理、ある人の指。つもる雪》
吉岡実年譜(吉岡陽子編)
《一九九〇年(平成二年)七十一歳
一月、国立劇場で正月公演の歌舞伎を観る。「文学界」一月号に詩「沙庭」を発表(最後の詩篇となる)。二月、会田綱雄死去。声帯麻痺のため声が嗄れ 嚥下力も落ち食欲が細る。二十八日、道玄坂百軒店の道頓堀劇場へ行く(長年親しんだストリップ・ショーの見納め)。三月、共済病院で内科の精密検査を受け結果は正常。折笠美秋死去。四月十五日、自宅で誕生日を祝う。りぶるどるしおるの一冊として『うまやはし日記』書肆山田より刊行。鈴木一民、大泉史世、宇野邦一が来宅。差入れの料理とワインで祝杯。近所に住む吉増剛造から復活祭のチョコレートの玉子と〝誕生日おめでとう〟のメッセージが届く。足腰弱り体重三七・五キロの痛々しい七十一歳。一週間で体重二キロ増えるが不調。足の甲が亀のように浮腫む。二十二日、雨の中渋谷駅前で見舞いの飯島耕一夫人と妻が会い入院を勧められる。二十三日、共済病院で検査の結果、翌日入院。腎不全のため週三回の人工透析を受ける。二四時間体制で中心静脈の栄養点滴。『うまやはし日記』弧木洞版限定一〇〇部、書肆山田より刊行。五月九日、結婚記念日。初めての輸血。大泉史世から贈られた銀のスプーンでゼリーひと口食べる。二十五日、白血球六〇〇から二〇〇に減少し個室に移され面会謝絶。三十日、妻の夜の付き添いが許される。重態。三十一日、午後九時四分、急性腎不全のため永眠。臨終には妻の他、居合わせた鈴木一民、妻の親友辻綾子、従妹太田朋子が立ち会った。六月一日、自宅で仮通夜。二日、巣鴨の医王山真性寺で本通夜。三日、葬儀。町屋火葬場で茶毘に付された。》
ちなみに国立劇場正月公演の演目は、「矢の根」(二代目尾上左近(現四代目尾上松緑)、七代目尾上菊五郎、五代目中村富十郎)、「水天宮利生深川(すいてんぐうめぐみのふかがわ)」(十二代目市川團十郎)、「雪振袖山姥(むつのはなふりそでやまんば)」(四代目中村雀右衛門、五代目中村富十郎)だった。
(了)
*****参考(吉岡実の詩)*****
「僧侶」
1
四人の僧侶
庭園をそぞろ歩き
ときに黒い布を巻きあげる
棒の形
憎しみもなしに
若い女を叩く
こうもりが叫ぶまで
一人は食事をつくる
一人は罪人を探しにゆく
一人は自潰
一人は女に殺される
2
四人の僧侶
めいめいの務めにはげむ
聖人形をおろし
磔に牝牛を掲げ
一人が一人の頭髪を剃り
死んだ一人が祈祷し
他の一人が棺をつくるとき
深夜の人里から押しよせる分娩の洪水
四人がいっせいに立ちあがる
不具の四つのアンブレラ
美しい壁と天井張り
そこに穴があらわれ
雨がふりだす
3
四人の僧侶
夕べの食卓につく
手のながい一人がフォークを配る
いぼのある一人の手が酒を注ぐ
他の二人は手を見せず
今日の猫と
未来の女にさわりながら
同時に両方のボデーを具えた
毛深い像を二人の手が造り上げる
肉は骨を緊めるもの
肉は血に晒されるもの
二人は飽食のため肥り
二人は創造のためやせほそり
4
四人の僧侶
朝の苦行に出かける
一人は森へ鳥の姿でかりうどを迎えにゆく
一人は川へ魚の姿で女中の股をのぞきにゆく
一人は街から馬の姿で殺戮の器具を積んでくる
一人は死んでいるので鐘をうつ
四人一緒にかつて哄笑しない
5
四人の僧侶
畑で種子を播く
中の一人が誤って
子供の臍に蕪を供える
驚愕した陶器の顔の母親の口が
赭い泥の太陽を沈めた
非常に高いブランコに乗り
三人が合唱している
死んだ一人は
巣のからすの深い咽喉の中で声を出す
6
四人の僧侶
井戸のまわりにかがむ
洗濯物は山羊の陰嚢
洗いきれぬ月経帯
三人がかりでしぼりだす
気球の大きさのシーツ
死んだ一人がかついで干しにゆく
雨のなかの塔の上に
7
四人の僧侶
一人は寺院の由来と四人の来歴を書く
一人は世界の花の女王達の生活を書く
一人は猿と斧と戦車の歴史を書く
一人は死んでいるので
他の者にかくれて
三人の記録をつぎつぎに焚く
8
四人の僧侶
一人は枯木の地に千人のかくし児を産んだ
一人は塩と月のない海に千人のかくし児を死なせた
一人は蛇とぶどうの絡まる秤の上で
死せる者千人の足生ける者千人の眼の衡量の等しいのに驚く
一人は死んでいてなお病気
石塀の向うで咳をする
9
四人の僧侶
固い胸当のとりでを出る
生涯収穫がないので
世界より一段高い所で
首をつり共に嗤う
されば
四人の骨は冬の木の太さのまま
縄のきれる時代まで死んでいる
「サフラン摘み」
クレタの或る王宮の壁に
「サフラン摘み」と
呼ばれる華麗な壁画があるそうだ
そこでは 少年が四つんばいになって
サフランを摘んでいる
岩の間には碧い波がうずまき模様をくりかえす日々
だがわれわれにはうしろ姿しか見えない
年の額に もしも太陽が差したら
星形の塩が浮かんでくる
割れた少年の尻が夕暮れの岬で
突き出されるとき
われわれは 一茎のサフランの花の香液のしたたりを認める
波が来る 白い三角波
次に斬首された
美しい猿の首が飾られるであろう
目をとじた少年の闇深く入りこんだ
石英のような顔の上に
春の果実と魚で構成された
アンチンボルドの肖像画のように
腐敗してゆく すべては
表面から
処女の肌もあらがいがたき夜の
エーゲ海の下の信仰と呪詛に
なめされた猿のトルソ
そよぐ死せる青い毛
ぬれた少年の肩が支えるものは
乳母の太股であるのか
猿のかくされた陰茎であるのか
大鏡のなかにそれはうつる
表意文字のように
夕焼けは遠い円柱から染めてくる
消える波
褐色の巻貝の内部をめぐりめぐり
『歌』はうまれる
サフランの花の淡い紫
招く者があるとしたら
少年は岩棚をかけおりて
数ある仮死のなかから溺死の姿を藉りる
われわれは今しばらく 語らず
語るべからず
泳ぐ猿の迷信を――
天蓋を波が越える日までは
「マダム・レインの子供」
マダム・レインの子供を
他人は見ない
恐しい子供の体操するところを
見たら
そのたびぼくらは死にたくなる
だからマダム・レインはいつも一人で
買物に来る
歯ブラシやネズミ捕りを
たまには卵やバンソウコウを手にとる
今日は朝から晴れているため
マダム・レインは子供に体操の練習をさせる
裸のマダム・レインは美しい
でもとても見られない細部を持っている
夏ならいいのだが
雪のふる夜をマダム・レインは分娩していたんだ
うしろからうしろからそれは出てくる
形而上的に表現すれば
「しばしば
肉体は死の器で
受け留められる!」
球形の集結でなりたち
成長する部分がそのまま全体といえばいえる
縦に血の線がつらなって
その末端が泛んでいるように見えるんだ
比喩として
或る魚には毛がはえていないが
或る人には毛がはえている
それは明瞭な生物の特性ゆえに
かつ死滅しやすい欠点がある
しかしマダム・レインの所有せんとする
むしろ創造しようと希っている被生命とは
ムーヴマンのない
子供と頭脳が理想美なのだ
花粉のなかを蜂のうずまく春たけなわ
縛られた一個の箱が
ぼくらの流している水の上を去って行く
マダム・レインはそれを見送る
その内情を他人は問わないでほしい
それは過ぎた「父親」かも知れないし
体操のできない未来の「子供」かも知れない
マダム・レインは秋が好きだから
紅葉をくぐりぬける
*****引用または参考文献*****
*『特装版 現代詩読本 吉岡実』(討議 大岡信・入沢康夫・天沢退二郎・平出隆「自己侵犯と変容を重ねた芸術家魂――『昏睡季節』から『ムーンドロップ』まで」、宮川淳「言語の光と闇」、高橋康也「吉岡実がアリス狩りに出発するとき」、松浦寿輝「後ろ姿を見る――『サフラン摘み』の位置」、守中高明「吉岡実における引用とパフォーマティブ」、飯島耕一「青海波(せいがいは)」、吉田文憲「覚めて見る、夢」、瀬尾育生「詩は死んだ、詩作せよ」、朝吹享二「エニグム・アノニム」、「代表詩40選」、他所収)(思潮社)
*『現代詩手帖 1995.2 特集 吉岡実再読』(「討議戦後詩 野村喜和夫・城戸朱里・守中高明「第一回 吉岡実」」、城戸朱里「「吉岡実」を現在として」、他所収)(思潮社)
*『現代詩手帖 1980.10 増頁特集 吉岡実』(鈴木志郎康「詩への接近」、高橋康也「吉岡実と劇的なるもの」、三浦雅士「葉の言葉」、「対談 吉岡実/金井美恵子」、三好豊一郎「半具象」、千石英世「胚種としての無」、四方田犬彦「内部の貝と外部の袋」、飯田善國「<謎(エニグマ)>に向かって」、他所収)(思潮社)
*野村喜和夫『詩のガイアをもとめて』(「吉岡実、その生涯と作品」)(思潮社)
*『現代詩文庫14 吉岡実詩集』(吉岡実「わたしの作詩法?」、飯島耕一「吉岡実の詩」、他所収)(思潮社)
*『みらいらん 2020 Summer第6号 特集吉岡実』(「吉岡実をめぐる対話 没後三十年を機に 朝吹享二+城戸朱里」、他所収)(洪水企画)
*吉岡実『「死児」という絵〔増補版〕』(「懐しの映画――幻の二人の女優」、「読書遍歴」、「うまやはし日記」、「リルケ『ロダン』――私の一冊」、「ロマン・ポルノ映画雑感」、「ポルノ小説雑感」、「想像力は死んだ 想像せよ」、「手と掌」、「官能的な造形作家たち」、他所収)(筑摩書房)
*吉岡実『土方巽頌――<日記>と<引用>による』(筑摩書房)
*『夜想22 特集クロソウスキー』(「ピエール・クロソウスキー「エロス・ベルゼバブ株式会社」杉原整訳」所収)(ペヨトル工房)
*ピエール・クロソウスキー『ロベルトは今夜』遠藤周作、若林眞訳(河出書房新社)
*ピエール・クロソウスキー『ディアーナの水浴』宮川淳、豊崎光一訳(美術出版社)
*ジュリア・クリステヴァ『恐怖の権力 <アブジェクション>試論』枝川昌雄訳(法政大学出版局)
*ジャック・ラカン『精神分析の四基本概念』ジャック=アラン・ミレール編、小出浩之・新宮一成・鈴木國文・小川豊昭訳(岩波書店)
*小林一郎「吉岡実の詩の世界――詩人・装丁家吉岡実の作品と人物の研究」(「<吉岡実を語る」「吉岡実年譜」「吉岡実書誌」「吉岡実参考文献目録」ほか)http://ikoba.d.dooo.jp/index.html