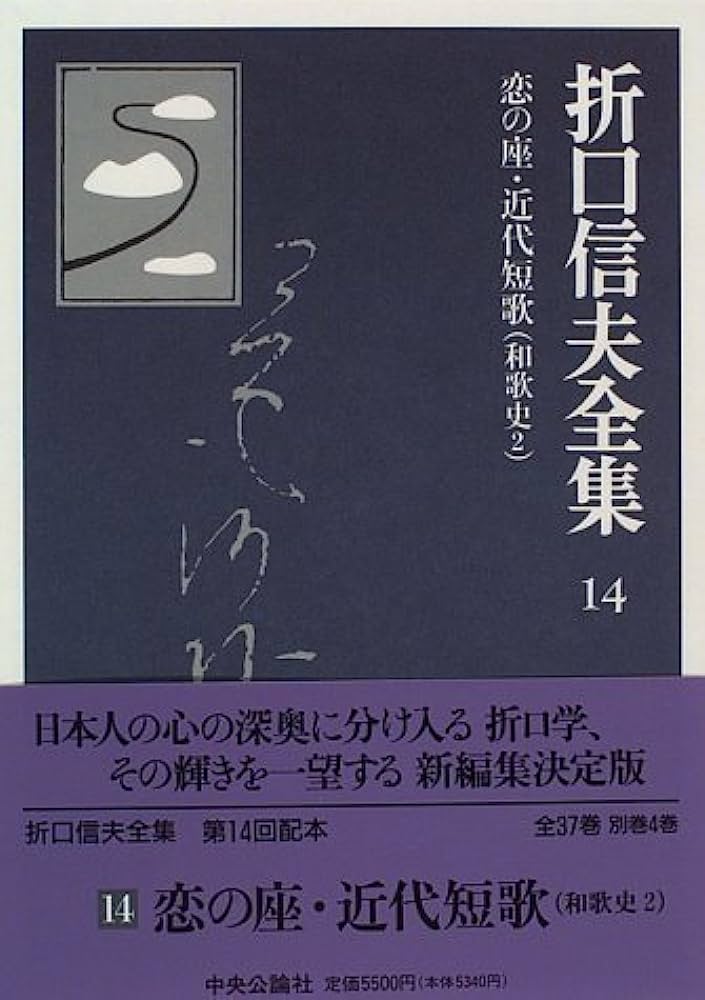
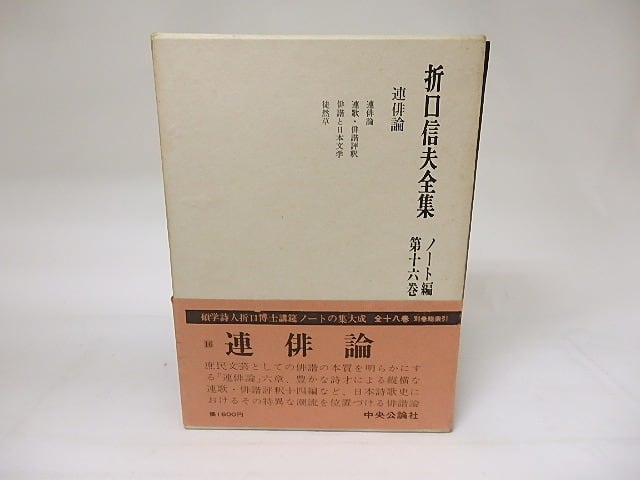


折口信夫は歌(和歌、短歌)について、『古代研究』、『国文学の発生』、『口訳万葉集』、『日本文学の発生 序説』などの「学術的」論考や同時代批評を残しており、約四十巻に及ぶ『折口信夫全集』は歌・文学(釈迢空名での歌集『海山のあひだ』、『倭をぐな』、小説『死者の書』など)の「国文学」と「民俗学」(『大嘗祭の本義』などの天皇学、『かぶき讃』などの芸能学)がほぼ半々となっていて、それらを称して「折口学」と呼ばれている。
歌についてはそれほどの質と量であるが、俳諧(俳句)については、前身としての連歌を含めても一巻をなすこと到底かなわず、歌の百分の一にも満たないのではないか。
二十数巻からなる『折口信夫全集(ノート編)』では、『連俳論』、『連歌・俳諧評釈』によってかろうじて一巻をなすが、あくまでもノートで終っているのだ。
それは文学としての歴史時間的な長さにもよるだろうが、たぶんに折口の吸いつくような「口うつし」の偏執的・粘着的体質が歌に向いていて、俳諧的ではなかったからではないか、という推定はひとまず置いておくとしよう。
あまり論じなかったからといって、折口の俳諧に対する理解、読解、解釈が足りないということを意味しはしない。芭蕉『恋の座』を読めば、芭蕉と越人(えつじん)をめぐって、俳諧とは、連歌とは、芭蕉文学とは、恋句とは、日本文学における恋愛とは何であるか、の核心そのものが論述されている。
折口信夫『恋の座』は、素直とは言いがたい、やや複雑な構成をとっている。
以下、折口の章立て名称に従って読んでゆく。
<恋風雅 恋欲情>
《 うらやまし。おもひ切時 猫の恋 越人
先師、伊賀より此句を書贈りて曰く、心に風雅有もの、一度口にいでずと云事な し。かれが風流、此にいたりて、本性を顕せりと也。此より前、越人、名四方に高く、人のもてはやすほ句多し。しかれども、此に至りて、初て本性を顕すとはの給ひけり。(去来抄)
越人の作物は、前から評判を得てゐたが、風雅の本質を吐露するに到らなかつた。ところが、この句にはじめて、彼の優れた素質が顕れて来た。》
ところが、「風雅有もの」が「俗情あるもの」となって流布した暁台本があって、文意は正反対になってしまっている。折口は、俳諧師という隠者伝来の優越感と、後来発生したらしい越人勘当説、一方で隠者の持って廻った重苦しい表現法による解釈も頭に入れて妥当性を検討したうえで、《師翁、越人の発見を賞賛して、「風雅を哀心に抱くもの、いづくんぞ廋(カク)(筆者註:=隠(かく))さむや。此句に到つて、其本心の良質を吐露することを得たものよ」と喜んだ報告らしく聞えて来る》として「俗情あるもの」を退けた。
さらに折口らしく、問いそのものを問う。
《それに今一つ、猫の恋の作為を、風雅として迎へるか、俗情として却けるかに纏綿して、二様の解釈が生じ、こんな文面の変化が起つたことも、一通り考へておかねばならぬ。
つまり、かう言ふ句づくり(・・・・)は、蕉風からしては、外道として悪まれたか、文学の本髄として待ち迎へられたかと言ふ所に、結句、問題が集つて来る訣なのだ。だから、よくもあしくも此句などは、芭蕉文学のある指標として、重大な意義のある作品だと言はれよう。「猫の恋……」を俗だとするのなら、てんで(・・・)問題にはならぬ。春季では既に相当重いものに見られてゐた規の語で、連歌以来の成句であり、約束である。此季題の渉る聯想を排除するやうな鑑賞は、俳心からすれば、寧大いに俗情あるもの、と言はれよう。なま温くて、色情的で、清潔なものを感じないからと言つて、之を俳諧的でないと言ふうけとり方をするなら、其は古俳諧は勿論、蕉風にも、風馬牛な俳論になつてしまふ。芭蕉は古俳諧の題材の内において、寧改竄修正することを極度に避けて、おし拡げられる限りおし拡げ、含みを持たせられるだけは含みを持たせ、成長させられる限り成長させて、俗悪・低劣を俗悪・低劣なるが為に、愈人生的に深いものゝ感じられる所まで、其を普遍化した。そこに蕉風の価値があり、俳諧の意義のある訣である。》
安東次男もまた『続 芭蕉七部集評釈』の中で軽く、「欲情あるもの」は誤伝、あるいは偏見が生んだ改鼠だろう、としている。ここに紹介すべき安東の指摘は、次の文章ぐらいであろう。
《そうした越人流の滑稽が、よく物の本情に届いたのは『猿蓑』入集の「うらやましおもひ切時猫の恋」であろう。同じく『猿蓑』に入ったかれの「ちるときの心やすさよ米嚢花(けしのはな)」と同想異曲の句でありながら、前者のなかに作者が見た断念の正体は後者のなかにはない。句は、恋猫が思切ったときの哀れさに恋の正体を見届けたというのであって、恋人をあきらめたときに恋猫をうらやましく思ったというのではない。初五文字の次に切字が働けば、「おもひ切時(が)猫の恋」としか読み様がないからである。》、《「猫の恋」の句は越人の秀作である。そうには違いないが、『猿蓑』あたりを境にしてかれが新風の「軽み」に随いてゆけなくなったことも事実で、荷兮・野水らと共に次第に芭蕉から離れていった。》
<俳諧における典拠>
《芭蕉の俳諧師としての知識は、即座に此が、藤原定家作と言ふ「うらやまし。世をも思はず のらねこの妻恋ひさそふ春の夕暮れ」――尤、果して其作物かどうかは疑はしい。其上、世間かまはず恋をする猫が羨しいとはとれない様な羨しが何を羨んでゐるのか、春の夕暮れが妻恋ひをさそふと見てよいのかと謂つた、辻褄のあはぬ所がある。伝来の怪しいものだが、連歌師・俳諧師の間には、さう言ふ伝説を持つて伝へられて居たことも考へられる。之を翦裁して俳諧化し、更に発句として独自の生命を生ぜしめ、更に歌を以て旁註たらしめ得た――芭蕉の発句と、古歌との間にも、屢此と同じ関係が見られる。其に、本歌も、短歌における関係と、発句における関係とでは、全然違つてゐる――点を、まづ芭蕉が大きく認めたに違ひない。さうして、此句の持つてゐる小説的な題材の選択と、抒情式な風情を愛して、此こそ、恋の句の行くべき道だと、直観する所が、あつたのであらう。実は、翁自身が求めて居たものに、接し得た気がした訣である。》
ところで折口は『連俳論』で、芭蕉の古典味について次のように講義している。
《芭蕉の連句のよさは、いろいろいえるが、恋の句が非常に洗練されていることである。おそらく、彼の恋の句を厳重に調べていったら、室町時代の名高い連歌の巻物のものに、起源があるにちがいない。芭蕉のえらかったのは、連歌をよく勉強し、名高い百韻や千句をよく読んでいることである。叙景の句のよくできているのも当然だが、恋の句を巧みに作っていることは、驚くばかりである。
芭蕉の恋の句のよさは、クラシックのよさである。クラシックなもので、現代生活をつつんでいるところにある。芭蕉の恋の句は、芭蕉ひとりの経験から出たのではない。古典によって刺激されたものが出てきてるとみるのが本当だ。たった一人の芭蕉のために、何十人もの人があるようなものだが、それだけよい種が、連歌にあったことが考えられる。高尚な遊戯として、連歌をもてあそんだ連歌師の一生など、無駄なようだが、芭蕉ひとりによって救われている。》
『恋の座』に戻る。折口信夫による句の読みの確かさ(歌の読みから来ているのは当然)、音感、語感、調べに対する鋭い感覚が読みとれる。
《だが、当時の俳諧者流の約束を超えて、此句の音覚を正直に言ふ段になると、古典的に感じることは、知的な錯覚で、正しいものだつたとは謂えぬ。「思ひきるとき(・・) 猫のこひ(・・)」の句の関聯に、著しいをどり(・・・)を感じる。二句とも、い列音で終結し、其が更に等しく名詞感の深いものである。殊に此発句の、強力な第一句のい列音の形容詞どめが、二三句に響いて跳ね返るやうな音覚の無内容な鋭さが、穏和であるべき此句の内容に、どれだけ、破綻を来してゐるか知れぬ程である。歌で言へばしらべが、破れてゐるのである。》
蕉風を切り開き、広める前衛者、蕉門を先導し、指導する心構え、ついてまわる昏迷、孤独について、折口は次のように推定する。
《ともかく、越人の句を採つた芭蕉は、句自身の価値よりも、之を理論的にとりあげ過ぎ、又自ら待ち望んでゐたものが現れた、といふ喜びに囚われ過ぎた点が、十分に見えてゐる。つまり、芭蕉の懐包してゐる理論の方向には一致しても、其の、円満に具体化せられたものではなかつたと言ふことになる。(中略)
自分から出たものが、育つて自分に還つて来たのに驚いたことも、芭蕉には度々あつたであらうし、又自分の欲したと思はれるものが、弟子の心から出て来たのに驚かされたこともあつたに相違ない。(中略)
芭蕉はこのやうに、弟子から与へられるものを、自由にとり入れた人だが、此後も転化飛躍して、門弟子からは遥かに離れた文学境――寧、文学ではない境――に踏み出した。かうなるともう、誰も追随して行けぬやうになつた。「この道や、行く人なしに 秋の暮」は言ふまでもなく、此実感を寓してゐるので、先行する者なきを言うたものではない。だが其かと謂つて、全然弟子の持つ新しい刺激に、方角の暗示を感じなかつたのではない。》
このあたりの記述、述懐には、自身における「折口学」の弟子たちとのことを連想しうるだろう。
<題材と理論と>
《どうも恋の文学だけは、別の物のやうに、芭蕉は腹をきめてかゝつて居たのではないかと言ふ気がする。が又、さうでもなかつたとしたら、翁の恋の句のみづ/\しさは、失はれてゐたに違ひない。さう言ふ作物から窺へる芭蕉の色気や、艶は、かうした理会の上に持ち続けられてゐたのかも知れぬ。ともかく彼が、今思ふよりも、遥かに艶(エン)なる境に、俳諧の「恋」の目安を置いて居たことは、信じてよいと思ふ。だから、越人の句を俗情と罵つたものと考へることは、芭蕉の恋の句を、俗情としてとり扱ふと、おなじことになるのである。蕉風以前の恋の句が、どんなものだつたかと言ふことを見れば、それはすぐに訣る。談林全盛時代又は、貞徳前後の恋の句及び其に相当するものゝ名高いものゝ多くが、単に恋の字を結んだと言ふやうなものでなければ、頗猥雑放恣なものであつた。論より証拠、翁早期の作物自身が、どんなに糜爛したものであつたか。其と此とを考へ合せると、よくここまで達したと言ふ気がする。品もあり、あはれもあつて、而も恋であるだけに、みづ/\しさも落されないと言ふのが、結局恋の句に対して、心構えを異にしてゐた彼の翁の腹の中であつたのではないか。》
ここで、『折口信夫全集(ノート編)』の『連俳論』、『俳諧「あら何ともな」の巻抄』などを参照すれば、「猥雑な恋」として「談林全盛時代又は、貞徳前後の恋の句及び其に相当するもの」の例としては「くびをのべたるあけぼのゝそら/きぬ/\゛におほ若衆のくちすひて」、「火によくあふれまへようしろよ/雪の暮女若衆のたつねきて」などいくらでもあげられ、「翁早期の糜爛した作物」としては、桃青を名乗っていた芭蕉初期の「寺参り思ひ初たる衆道とて(伊藤信徳)/みじかきこゝる錐で肩つく(桃青)」や「あゝ誰ぢや下女が枕の初尾花」などが該当するだろうか。
《さうしてこの「恋」に対する態度が、ある意味における絶頂に達して居り、他の句境も、勿論之と同列の水準を、まだ動かなかつたのが「猿蓑」であつた。芭蕉自身は其から更に転身して、謂ふ如き「炭俵」の軽みに達するのである。猿蓑の古典主義から、炭俵の自然主義への転化を諾(ウベナ)はぬ人々は多い。さうした心持ちも、よく訣る。古典主義は、文学鑑賞上の一つの普遍論であり、又相応に健康的な啓蒙主義でもある。自然主義は、正しい文学の方向ではあるが、ある人々にとつては、文学らしさを持たぬ文学を推挙することがある。》
<隠者資格の認定>
ここでは、『猿蓑』と「猫の恋」の句とを念頭に、越人と芭蕉との伝記的な足跡(芭蕉は『更科紀行』の旅路に越人を伴い、そのあとで江戸深川へ誘った)に触れている。また蕉門の高足の中で、越人はもっとも俳諧隠者らしく、隠者生活表現から言うと、其角のは新風であり都市風で、芭蕉・越人などは、旧式で、地方的な点を存した、と考察している。
<古典的創作>
この章は『猿蓑』の有名な恋の句の折口ならではの精妙な評釈である。これに続く二つの章、<連句の特異な表現法>と<日本恋愛文学の歴史>は、連句ならではの表現法、読みの解釈、制約の解説と、日本「恋愛」文学の歴史講義であって、どの文章も重要なので全文引用する。
《 きぬ/\゛や あまりかぼそく、あてやかに 芭蕉
かぜひきたまふ声の うつくし 越人
芭蕉一代でも有数な附け合ひである。私の師匠柳田柳叟(筆者註:柳叟(りゆうそう)は柳田國男の俳号)先生、常に口誦して吝(ヲシ)むが如き様を示される所の物である。越人之に先立つて「足駄はかせぬ雨のあけぼの」の前句を出してゐる。翁は侍女たちが女君の心を推察して、後朝の帰り、急ぎ立ちする男を去(イ)なすまいとする様に見立てゝ、――足駄を隠したり、とりあげたりするやうにとりなしたのである――之に、別れを悲しむ女君の様をとりあはせたのだが、さう言ふ風に見てゐるのは右の男の心である。離れ難い愛著――後髪ひかれると言ふより、もつとなごり惜しい心持ち――立ち去らうとして、そこに悩む姫の顔姿の繊細に、高貴な様、言説のよくする所でないあえかさ(・・・・)に囚われてゐる男の心である。平安末期から鎌倉初期へかけて、あれほど恋愛描写の叙事技巧に苦労した歌人たちも、こゝまでは行つて居ないし、又其人々の作物がある窮極に達すれば、間違ひなく、此とほりの表現をとつたことが信じられる。語が大体此範囲を離れてはならぬし――連句と、短歌との様式上の相違をどうして乗り越すかゞ、よほどの問題である――又時代を超越して、此情調を構成する詞は勿論、情景も、此まゝでなければならぬものである。つまり、時・処・形態の障壁を無視して突発させた表現である。越人の附け句は、稍時代の指定を自由にしてゐる。「かぜひき給ふ」ことが、其古典時代にも勿論あつたのであるが、語が世話に砕けて来てゐる為に、我々はやゝ時代感を自由にすることが出来る。前句の清純なのに比べて、柔靡性を含んだ通俗質を十分に持つて来てゐる。文学としては第一義的な点は、師翁の作に譲らねばならぬが、俳諧性は寧此方に逞しく見られる。謂はゞ、古典の口訳から来る笑ひたさと言ふべきものが出てゐるのである。も一つ、越人を褒めてよいなら、其口訳味の為に、前句の古典体な品位を破つて居ぬ点がえらいと思ふ。連句では、寧さいあつた方が、変化を喜ばれることが多いのだが、あまり美しい長句の情趣を破るに忍びず、変化はさせながら、急転させず、時代を稍さげて来たと言ふいたはり(・・・・)の十分見える所がよいのである。「風邪ひき給ふ」は、「風邪をひいていらつしやる所の」であることは言ふまでもない。起きてゐる女性(ニヨシヤウ)で見てもよいが、風邪をひいてるのだから、起きあがらずにゐるものと見るのがほんたうだらう。寝ながら物言ふ人の声が、風邪声(カザゴヱ)ながら、――又其風邪声であることの為に、いよ/\うつくしく聞えるのである。風邪の鼻声に美しさを感じたところに、近代感がある訣である。前句は、男の心持ちに這入つて行つてゐるのであるが、――そこに又、特殊なしなやかさがあるのだが、此は別れに悩む佳人の様子を第三者として述べてゐるのである。「きぬ/\゛や」は此附け合ひの鑑賞の上には、問題にせずともよいが、実はこゝは軽く見て行つてよいのである。
序に言はうなら、其附け句は、師翁「手もつかず、昼の御膳もすべり来ぬ」である。之も亦恋とうけ取つても、恋の連続、四五句に渉ることもあつた習慣から、勿論さし支へはないのである。だが段々、早くくりあげる傾向が著しくなつて、二句ぎりのも頻りに出て来るし、さうあつてはならぬことになつて居た、一句ぎりで棄てる恋の句すらも、許される風に向いて来た頃であつた。》
<連句の特異な表現法>
《前句の表現全体に、附け句がぴつたり張りついて行かねばならぬものではない。連句は屢、前句の一部分を力強く把握して、其部分だけに密接する方法をとる。近代の例をとれば、すぽつとらいとを、一部分だけに鮮明にあてる。其によつて、他の部分の描写能力が非常に減退する。即、附け句は、先行した句の一部の表現だけを鮮かに捉へて、其に意義を連接させる。さうすることによつて、残りの部分の表現力を薄れさせてしまふ。さう言ふ風に考へたと言ふより、さうした表現法が認められ、其が更に、次第に能力をおし拡げて来た為に、一句一文の中に、意義を持つ部分と、意義を喪失してしまふ部分が出来ても、毫も後味のわるい未解決な気持ちの残らぬと言ふ、連句特有の表現法が、次第に著しくなつて来たのである。前句自身が意義の一部を失ふのではなく、附け句の方向によつて、前句の意義が、一部的に集約せられて来る訣である。だから連句では、附け句が、表現の根幹をなすもので、前句は、其局限力を脱することが出来ぬのである。たとひ前行した句が、如何ほど優れた句でも、此様式上の制約からは、離れられないことになつて行つた。
お上から御膳がさがつて来た。朝もさうであつたが、昼の御膳部も、其まゝ箸を触れられた痕もなく、そのまゝ静かにずつとさがつて来た。御主はこゝのところ、風邪ごゝちがまだ癒えられぬのである。「かぜひきたまふ」と言ふ句を前句の中心表現と見て、外は顧みずに、「手もつかず……」と連接したのだ。此つけ合ひでは、まだしも其風邪ひいた御主の声のうつくしくはなやいで聞える様につけたと思うても、必ずしも誤りではない。又、さう解釈する自由もある訣だが、さう言ふ点に、解釈法の普遍性と言ふことを立てる必要がある。もつと解釈を自由にする必要があるのである。さうでなくては、連句などは、自由解読に任せられてゐるだけに、解釈の公理と言ふものを失ふ虞れがある。其で、強ひても、かうした詞章全面の連接と言ふ、一見健康さうな解釈法を顧みることの出来ぬ場合の多いこと――又其が、当然であることを明らかにして置く必要がある。
尚一つ、前の句のつけ味を説いたところにも述べたが、「きぬ/\゛や……」に対する「かぜひきたまふ……」は、後朝(キヌゞゝ)に関係なくつけてゐると見てよいのであつて、寧その方が正しいといふ考へが、こゝまで話が進むと起つて来るだらうと思ふ。後朝の別れに女は風邪をひいてゐる――さう見ることもないのである。唯漠と翳(カゲ)の如く、月暈(ツキガサ)のやうに、ぼつと視界の外に喰み出てゐると見ておけばよいのである。かう言ふ風に、内容を感受する修練が、連句鑑賞の上には、必ずいるのであつて、此用意がなくては、解釈があくどくて、堪へられなくなる場合が多いのである。風邪心地に寝てる女性の声にほひやかに、顔姿のあえかに、清い状態だけを言うたのだとした方が、一つ前の句――即、隔句(ウチコシ)――に対する前句の関係と、後句に絡む其句との交渉の形が、かはつて来るのがよいのである。かうした前句の意味が、おなじであつても、隔句――打越――と後句とが、全然別な立ち場から附けて居ればよい訣である。又、強ひて隔句と附け句との連接において、一つの語句の意義が、すつかり変つたものと扱つたち、同音異義に解したりせぬ方が、自然でよい。が、何としても変化の乏しい嫌ひがないでもない。其で、隔句と附け句とが、別々の面からつけて行くと言ふ態度を守つて行くにしても、中軸になる前句の意義の変転が望まれる様になる。そこで起つて来た方法がある。即、附け句は、前句の一部の意味を明るく照し出し、そこに連接して行くといふ行き方が、次第に望ましい形と思はれて来たのである。
越人の句は、翁の前句に対して、毫も遜色を示して居ない。其どころか、師翁の前句のよさを、おのれの句を以て、発揮させてゐる。其は、今も言つた風に、時代や地位や人柄を、少しにじらしてつけてゐる所にあるのだ、と言ふことを考へる必要がある。》
安東次男は『続 芭蕉七部集評釈』で、『猿蓑』の「雁がねもの巻」において、「足駄はかせぬ雨のあけぼの/きぬ/\゛やあまりかぼそくあてやかに/かぜひきたまふ声のうつくし/手もつかず昼の御膳もすべりきぬ/物いそくさき舟路なりけり」一連を、これまでの諸評に対して冷徹、辛辣に、しかし連衆の一人と化しているかのように評釈している。その中で『恋の座』にも言及している。
《これは折口信夫も「恋の座」なる文で言っていることであるが、連句というものは前句の表現全体にかかわらねばならぬというわけではなく、おのずからかかわり方の強弱はあってよい。》、《折口はこの句の付あじを前句の後朝に関係なく付いている、と言う。つまり後朝は風邪気味の女の視界の外に在って、「唯漠と翳(カゲ)の如く、月暈(ツキカサ)のやうに、ぼつと」はみ出ている、と言うのである。匂付ということをどこまで句の情景から引離して読むか、これはむつかしい問題であるし、また「雁がねもの巻」興行のころそれほど進んだ匂付の解釈があったか、ということも疑問になる。とりかわこの句は芭蕉の付ではなく、越人の付であるから、そこのところの判断は猶のことむつかしくなる。しかし、折口の解釈が許されぬわけでもない。》
安東はまた「手もつかず昼の御膳もすべりきぬ」を次のように評釈している。
《打越以下、対象が三句同一人物という点に気がかりの残るはこびだが、句の表はいずれも他からの観察あるいは噂であり、なよなよとした女人の姿は狂言廻しにすぎない。床臥も風邪のせいばかりとも言えぬのである。あとをたのんで帰ってゆく男と、のこされた侍女たちとの感情のやりとりの方が、話の本筋だろう。そこに気がつけば、この越人・芭蕉の付合からは、女主人を気遣う表情のほかに、男女の仲についてあれこれとささやき交し、男の品定めをする女どもの様子までも浮かんでくる。場所も別室に移し替えられている。はこびの障りはあるまい。『猿蓑』「夏の月の巻」の、
待人入(いれ)し小御門(こみかど)の鎰(かぎ) 去来
立かゝり屏風を倒す女子供 凡兆
の付合と、男が帰ると来るとの違はあるが、よく似た情景の句作りである。
芭蕉の「手もつかず」の句はすでに恋から離れているが、恋の余韻をまだのこしていて、これは何ともうまい。》
<日本恋愛文学の歴史>
《千載集時代から新古今集期へかけて、短歌における「恋歌(コヒカ)」は、其以前のものよりも確かに進んでゐる。つまり文学としての立ち場を発見したことである。個人経験としての愛欲を述懐し、恋情を愁訴する態度から離れて、如何に美しい恋愛の心境があるか、其をとり出し、表現しようとする、文学としての立ち場を発見したことであつた。だが其は、徹頭徹尾文学に終始してゐて、生活内容が欠けてゐた。時としては、あべこべに生活を文学化した人々の逸話が伝へられてゐる。やはり極めて古い中世にも、芸術を模型として、生活を表現しようとする者があつたのである。真実を中核とする恋愛生活においては、さう言ふ生活表現が、如何にも、ふまじめ(・・・・)なものに、今日からは見えるが、昔は必ずしもさうは思はなかつた。真に美しい感情生活に殉じたものとして、賞賛せられた伝説が多かつたのである。も一つ前の「恋歌」は、今言つた王朝末の歌の出る前提として、自分の恋を陳べるよりも、恋愛の心理解剖に傾いてゐた。此が、小町等の代表する恋歌であつた。かうした物の出て来る原因は訣つて居て、解説の興味も、十分に感じて頂けるとは思ふが、今は其に時を移すことが出来ぬ。たゞ中古においては、恋の呪歌とも言ふべきものが、恋愛詩の本流と見えてゐたのであつた。こひかと言ふ名義自体が、恋の成就を呪する歌の義であつた。かうした中間発生が、後世に脈を引いたに繋らず、恋歌の真の本流は、其以前にあつて、真に愛の哀情を訴へるものであつた。併し其も、後世からは、恋愛の正しい表現は、正に其より外にない様に見えたのだが、さうした表現自身が、やはり最古い時代の呪法で、思ふ人の魂を、おのれの内界に迎へとることによつて、遂げられる恋愛――結婚――を考へたのであつた。日本人の恋愛の表現法は、専ら此「魂(タマ)ごひ(○○)」――迎魂(コヒ)――以外になかつたのである。だから、此方法の線に沿うて、恋愛表現が発達して来たので、恋愛文学も、単にその呪詞呪章の変化したものに過ぎなかつた。王朝末では、本来叙情詩であるべき歌の上に、抒情詩以外に姿のあるべくもない恋愛が、叙事詩の形を持つて出て来たのである。千載・新古今の恋歌は決して抒情詩ではない。小説と言へば早わかりのする叙事詩である。「こんな恋がある」といふ報告を、出来るだけ美しい境遇に描きあげた画であつた。美であり、文学ではあつたが、生活ではなかつた。
まづ、これと似たものを、俳諧の上に持ち来(キタ)したのが、芭蕉である。だから、芭蕉作物の中、最文学であり、美であつたのは、恋の句であつた。其にも繋らず、他の芭蕉文学は、美の境涯にのみは留らなかつた。今一つ先の領域に既に踏みこんでゐた。蕪村は即、其一つ手前に留つた為に、あの唯美の文学とも謂はれるものを、連句及び発句の上に築き上げた。唯、芭蕉の更に優なる点は、其を抜け出ることの出来たところにある。さうは言ふものゝ芭蕉の偉大なことは、いつまでも其処には、踏み留まつてゐたのではなかつた。発見しては又、其を棄てゝ進んだのである。従来の猥雑な「恋」の文学を整頓し、醇化しようとして、方法に、中世の短歌を捉へたのである。此が一つの道であると共に、今一つ別の途があつた。おなじく、以前の「恋の句」の処理から出てゐる。猥雑は猥雑とし、卑陋淫靡を貫徹することによつて、終に普遍性を捉へ得たのであつた。其方法としては、軽みを態度としては、技巧を突破して自ら口を衝いて出る言語に期待することであつた。芭蕉晩年の恋の句は、其いづれかに属するのである。其中、価値の高いのは、文学らしさの少い、軽みの恋の句であつた。俗悪に見える題材が、却て痛切な生に即せしめて、その作物に、切実性と、飄逸味とを持たせる事になつたのである。併し其にしても、恋の句における芭蕉は、他の境涯をとりあげたものよりは、文学的であることを生命点としてゐることは、著しいことである。
文学的なものゝ大きな傾向は、古典的であり、擬古的であつたことである。――其から大いに自由を得て、地方的生活の古典味に到達することが出来てゐる。此は俳諧道における俗悪味のくり返しから卒業して到つた軽みではあるが、其整頓の力量は、文学上の古典玩味力が齎した所も多いのである。
多くの芭蕉党の人々は、俳諧の猥雑から出た芭蕉なることは、万々知り乍ら、尚且、恋の句の行蹟を見て駭(おどろ)かされることが多かつた。》
<隠者の芸術生活><掛け合ひ文学の持続><連句以前の恋>
前章までを受けたようであっても、論点を微妙にずらしたような、ここまで来て芭蕉以前に時代をさかのぼるような、しかしこれを言いたかったがための迂回でもあったような、折口独特の展開となる<隠者の芸術生活><掛け合ひ文学の持続><連句以前の恋>の章については、有名な『女房文学から隠者文学へ』や『連歌俳諧発生史』などに則して隠者・唱和に焦点を当てた文学史的・発生史的な、及び民族的・民俗学的なものに回帰して、芭蕉の恋の句から離れて行くので省略する。
最後に、折口信夫による後記を引用しておこう。
《恋の座ということ、俳諧用語としては、厳格には使はぬものである。たゞ時として、昔から世間の常識として、希まれ、月・花の座を言ふやうに言はれてゐる。此文の表題には、何となきことばの練れ(・・・・・・)を愛して、利用することにした。恋愛が、日本抒情文学の主座を占めて来る過程が、幾分でも書ければといふ望みを持つ小論なのである。其が、恋の座の字に、執(シフ)する所以であると言へば、その外に言ふことはない。》
(了)
*****引用または参考文献*****
*『折口信夫全集』(第十四巻に『恋の座』所収)(中央公論社)
*『折口信夫全集(ノート編)』(第十六巻に『連俳論』、『連歌・俳諧評釈』所収)』)(中央公論社)
*『安東次男著作集Ⅰ~Ⅲ』(青土社)