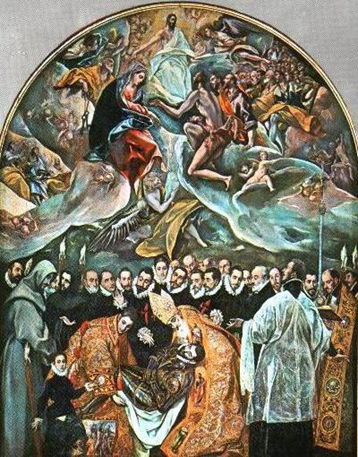須賀敦子は、生前五冊の本を出版している。
六十一歳で刊行した『ミラノ 霧の風景』(一九九〇年)からはじまって、『コルシア書店の仲間たち』(一九九二年)、『ヴェネツィアの宿』(一九九三年)、『トリエステの坂道』(一九九五年)、『ユルスナールの靴』(一九九五年)である。これらは、数年にわたって雑誌に書いた作品を一冊にまとめたものであったり、書きおろしであったり、十二か月の雑誌連載であったり、さまざまである。
他によく知られた『遠い朝の本たち』『時のかけらたち』『本に読まれて』『イタリアの詩人たち』『地図のない旅』『霧のむこうに住みたい』『塩一トンの読書』『こうちゃん』は、死後の一九九八年から二〇〇三年までに世に出たものだ。
須賀敦子は、イタリア文学の翻訳者としてさきに知られ、ナタリア・ギンズブルグ『ある家族の会話』『マンゾーニ家の人々』、アントニア・タブッキ『インド夜想曲』『遠い水平線』、イタロ・カルヴィーノ『なぜ古典を読むのか』、ウンベルト・サバ『ウンベルト・サバ詩集』などを一九八五年から翻訳出版している。しかしもっと評価されるべきなのは、ずっとはやくの一九六三年から、谷崎潤一郎『春琴抄』『蘆刈』、川端康成『山の音』、漱石、鴎外、一葉、鏡花などをイタリア語に翻訳出版することで日本文学を彼の地に知らしめたことだろう。さらに遡れば、一九五七年から一九六八年にかけて、限られたカトリック信者を読者とする『聖心(みこころ)の使徒』(日本祈祷の使徒会)という雑誌に、『シエナの聖女』、『アッシジでのこと』などのエッセイを書くことから、執筆活動は地味ながらスタートしていたといえる。
須賀の作品は、しばしば「小説風の自伝的エッセイ」などと、たんなる「エッセイ」ですまない形容を重ねた表現で紹介されるが、その早すぎた晩年、須賀が小説を書こうとしていたのは知られるところだ。全集に収められた松山巌による詳細な年譜によれば、死が三年後に来るとは知りえなかった一九九五年ごろ、その意思、構想を知人に相談し、創作メモも残している。翌一九九六年九月には小説の舞台となるアルザス地方を歩き回り、十月には序章を書き始めた(未定稿が、創作メモとともに全集に収められている)。しかし、すぐに体調悪化、年明け一九九七年一月に入院となって、体調すぐれず、一九九八年二月には見舞いに来た松山巌に「書くべき仕事が見つかった。いままでの仕事はゴミみたいなもんだから」と語ったけれども、三月二十日に帰天。享年六十九歳、ついに小説『アルザスの曲がりくねった道』を書き終えること、叶わなかった。
『ヴェネツィアの宿』は、文芸誌『文學界』に一九九二年から一年間にわたって連載発表された『古い地図帳』に加筆訂正、単行本として一九九三年に刊行された。
十二篇からなり、『ヴェネツィアの宿』『夏のおわり』『寄宿学校』『カラが咲く庭』『夜半のうた声』『大聖堂まで』(初出時は『待っている人』)『レーニ街の家』『白い方丈』『カティアが歩いた道』『旅のむこう』『アスフォデロの野をわたって』『オリエント・エクスプレス』である。エッセイとして読むと、どうにもまとまりなくばらばらにみえるが、旅の宿、父のこと、母のこと、親戚のこと、少女時代のこと、留学時代のこと(ローマ、パリ)、キリスト者としての体験、修道女のこと、自分を探すこと、京都での不思議な話、知人との出会い、音楽、歌声、などのテーマが、夫・家族・親しい知人の死とともにあらわれては消え、父の逸話が円環構造になっていたりと、決して一本調子ではなく、建築に興味があった人らしく構造的なのがわかる。読み進めれば、物理的時間の流れのとおりではなく、場所もあちこちに飛ぶ。作品それぞれの中でもまた追憶に向かいがちだ。過去時制を多用した文体で時間、空間が自在に往き来する回想小説と思って読めば、その構成の美意識がわかろうともいうものだ。
どういう文体で、どういうふうに書けばよいのかをつねに考え、口にしてきた須賀の文章は、あらすじを書いても抜け落ちるものが多すぎるので、なるべく文章そのものを引用しつつ、文体の考察を主に魅力の秘密を解く鍵を探しながら、読解を試みたい。
冒頭の『ヴェネツィアの宿』は本の全体と結末をよく構想したうえで、細部のエピソードにいたるまで意図をもって書きこまれ、のちのいくつかテーマを予兆している。人物の登場のさせ方がさりげないうえ、ときにドラマチックさも計算されているのは、連載時の題名が、本の最後の最後に登場する父の「古い地図帳」からとってきていることからも、あきらかだ。
書きだしは、《シンポジウムが開催されるヴェネツィアの空港に着いたのは、正午ちょっとまえだった。》 現在に近い過去であるにも関わらず、遠い昔のように過去時制の末尾を持つ、柔らかなひらがなを織り込んだ息の長い回想の文体が紡ぎだされてゆく。フェニーチェ劇場の広場に面した宿に向かうが、その夜は歌劇場の創立二〇〇周年を祝うガラ・コンサートで、入れなかった人たちのために、スピーカーから舞台の音が中継されている。《デイバッグを背負ったままで、男の子の胸に頭をもたせて聞きほれている少女》、《頭をあげたままうずくまる金色の髪の青年》、《用意よく小さな金属製の折りたたみ椅子にこしかけている夫婦らしい白髪の男女》、《四、五人つらなっている女子学生ふうの一群》のいきいきした描写に続いて、早くも光と音による追想がはじまる。
《そのうえを光と音がゆっくりと流れていて、まるで、どこか遠いところの川底で夢を見ているようだった。
魔法のように目前にあらわれたその光景と、それを包んでいる音楽が、忘れかけていた古い記憶にかさなった。ある夏の夕方、南フランスの古都アヴィニョンの噴水のある広場を友人と通りかかると、ロマランの茂みがひそやかに薫る暮れたばかりのおぼつかない光のなかで、若い男女が輪になって、古風なマドリガルを楽器にあわせて歌っていた。》
しかし、客観と自己省察の人は、ただ甘いだけの思い出に流れこんではゆかない。身なりはヒッピー風だったが、歌声はしっかりした音程だった。《あ、中世とつながっている。そう思ったとたん、自分を、いきなり大波に舵を攫われた小舟のように感じたのだった。ここにある西洋の過去にもつながらず、故国の現在にも受け入れられていない自分は、いったい、どこを目指して歩けばよいのか。ふたつの国、ふたつの言葉の谷間にはさまってもがいていたあのころは、どこを向いても厚い壁ばかりのようで、ただ、からだをちぢこませて、時の過ぎるのを待つことしかできないでいた。とうとうここまで歩いてきた。ふと、そんな言葉が自分のなかに生まれ、私は、あのアヴィニョンの噴水のほとりから、ヴェネツィアの広場までのはてしなく長い道を、ほこりにまみれて歩きつづけたジプシーのような自分のすがたが見えたように思った。》
中世とつながった時間の糸。アヴィニョンの噴水からヴェネツィアの広場までの長い時間、そして、ヴェネツィアの広場からこれを書くまでの長い時間。須賀作品は、ぶつりぶつりと断片化された時間の物語ではなく、それらがすべて一本の時間の糸でつながっていて、自在にたぐりよせられる。空間もあちこちに、「歩きつづける」場面が、時空をかえては、この本のテーマのひとつとしてあらわれるだろう。
音楽に身をまかせたい気がしたが、いつにない疲れを覚え、五階の船室ふうの屋根裏部屋まで登る。暑気で部屋はなまぬるく、せまいベッドの、つめたい麻のシーツに身をよこたえたが、からだがほてって、だるい。アスピリンを一錠のんでから、正方形の小窓をあけると、音楽が、待っていたようにどっと流れこんできた。《ずっと、自分は音楽には入りこめない、音楽がこちらを向いてくれない、と思いこんできた。いや、音楽のもってくる感動があまり純粋で、言葉にも色にも形にもすることができないのを、ひたすら恐れていたのかもしれない。》 この先も音楽と歌のテーマはしばしば顔をのぞかせるだろう。
すこしとろとろとすると、教会の鐘の音で目がさめる。あらしのような拍手が追いかけた。私はもうひとつの音楽会のように、白いシーツのなかで目をとじて聴いていた。やがて、劇場の横の路地を通る人々の人声と靴音が窓を通して部屋にはいってきた。《私も音楽会帰りの群衆のひとりになって窓の下を歩いている、そう思えてしまうほどに、興奮した声のピッチが、キャビン・ベッドの周囲を跳ねまわった。》
そうして、プルーストの小説冒頭のコンブレーのように記憶が「ピッチの声」とともによみがえり、反抗心もともなって父が記憶の門をあけて入ってくるのだった。
《パリで学生だった四十年ちかくもまえに、生活費をきりつめて、つぎつぎに出かけたピアノ演奏会の記憶が、満月の光だけの小部屋にひとつひとつ戻ってきた。若いサンソン・フランソワのショパンを聞いて、楽屋まで会いに行ってしまった夜。(中略)帰り道には、私もこんなピッチの声で友人と印象を語りあったのだろうか。都心からカルチエ・ラタンの学生寮まで、凍りつく冬の夜を頬をほてらせて歩いて帰ったこともあった。父に手紙でその興奮を伝えると、二枚きりの、いつもの大きな字で書いた返事がきた。音楽もよいけれど、勉強はしているのだろうか。すこしはしゃぎすぎてるように思う。それを読んで、かなしかった。寒い毎日の図書館通いや、聞きとるだけでも大変な大学の講義のことは、心配かけまいと思ってわざと書かなかったのに。自分こそ、ヨーロッパ旅行をしたときは、それこそぜいたく三昧で遊びほうけていたくせに。》
そこから、一九三五年の父のヨーロッパからアメリカにかけての一年近い大旅行の説明となって、ヴェネツィアに来たときは、どんな豪華なホテルに泊まったのだろうかとか、ベネチア、と彼はこの海の都の名を発音していて、ムラーノとか、ブラーノとかのガラス工場をたずねた話を聞いたことなどを思いだした。《レース編みをする女たちを見て、日本で待っている母を億っただろうか。家では子供がうるさくていつもいらいらしていたくせに、旅に出ると、私たちのことがなつかしかったのだろうか。三十歳になったばかりの父は、一時的にせよ大家族の家長の座から解放されて、ただ有頂天だったのではなかったか。》
四角い小窓からは音が伝わらなくなって、枕がひんやりと頬にふれてほっとする感覚があった。大旅行中に、母を億っただろうか、とか、うるさい子供のことから解放されたのではないか、といった微笑ましいひとつの家族、幸福に結びついた家庭の話題を卓袱台返しするかのような思い出が、たった一行の空白で、戻ってくる。
《父がふたつの家庭をもっているのを知ったのは、私がはたちのときだった。いろいろ話したいことがあるから、帰ってきてください。戦後はずっと病身だった母から東京の大学の寮に手紙が来て、私は十一月のはじめの短い休暇に帰省した。》
母も登場してくる。「私」が東京の大学の寮にいること、実家は夙川(しゅくがわ)であることもさりげなく語られてゆく。
《夕食のあと、ふたりだけになるのを待って、母がぽつりと言った。パパが家を出ちゃったの。会社にも出てないらしい。いやだなあ、と思った。(中略)病気だったの? 私は訊ねた。京大病院のお医者にかかってたみたい。(中略)こんどばかりは、はっきり、うらぎられちゃったみたい。そう言って母は小さな笑い声を立てた。》
うまくひらがなを織りこんでの会話(とりわけ母の会話には、ひらがなと「……みたい」を甘いオブラートのように響かせて)を地の文にとけこませる文体は、須賀がギンズブルグを翻訳することや、『源氏物語』、谷崎から学んだことだが、文体については、のちほど詳しく論じたい。
数日後、「私」は父が入院しているかもしれない京大病院を訪ねてみる。京都までひとりで行くのは、はじめてだった(年譜に拠れば、現実にはひとつ下の妹と一緒だったが、一人で行ったことにするほうがドラマチックな効果がでるのを狙っての表現にちがいない)。名を言うと、勘があたったが、病室に行くとベッドはからっぽで、看護婦さんが、いまお散歩に出られました、と言った。庭に降りると、広々としたポプラの並木道に出た。むこうから父が来た。ここからの文章は、いくらでも「私小説」の愁嘆場として告白調で書けるのに、じめじめせず、トスカーナの空のように澄んで乾いている。いつも自分の内面をあからさまには語らず、他の人の描写でそれを代弁するが、ここでは冷静な観察眼と洞察力をもった「私」が前面に出ての矜持さえあって、自分と他者との距離感が心地よい。
《すきとおるような秋のひかりのなかを、さっさっときもののすそをひるがすようにして、父が女の人とこっちにやってくる。休日に私たちと出かけるときとおなじように白足袋をはいた父の足もとがまぶしかった。(中略)
こんなところで、なにをしているんだ。父がこわい声で言った。遠くからは元気そうにみえたのに、向いあってみると、ひげがのびて、目がくぼんでいた。パパこそ、そう言うのがやっとだった。泣いてはだめだ、と思いながら、つけくわえた。パパを探しに来たんです。(中略)
病気だったらうちで寝てればいいのに。それに大阪にだって病院はあるでしょう。父にむかってそう言いながら、私は彼の肩に半分かくれて、ちょっと膝を曲げたような姿勢で立っている女をにらんだ。背のたかい父とほとんど肩をならべるくらい彼女は上背があって、面長な色白の顔も、骨太な体格も、小柄で肌が小麦色の母とはすべてが対照的といってよかった。くすんだ色合いの彼女のきものは、すこしくたびれていて、うぐいす色の地に竹のもようのある羽織をはおっていた。》
彼女はからだつきも着るものも、ほとんどすべての面で母とは違っているのに、どこか共通するものがあって、母とおなじように父のほうを向いて生きているうちに、父の好みに染まってしまったからではないか、と気づく。その人は、言葉づかいも、ものごしも、まっとうで、そのことがまた意表をついていた。《彼女が、そのときまで漠然とあたまに描いていた「いやらしい女」でなかったことに私は救われる思いだったけれど、自分がそう考えたことを、母には言えないとも思った。》
須賀は、いつも結末がうまいが、ここでも最後の、「見送った」でも「見送らなかった」でもない、記憶をたぐり寄せながらの「見せ消ち」のような否定形が、深い余韻を残す。
《父は苦々しげに言った。よくも京都まで。子供なんかの来るところじゃない。
ママのところに、はやく帰ってください。そう言って、私は父と別れた。ふりかえって、愛人といっしょに病棟の方に歩いていった父のうしろ姿を見送ったかどうかは、憶えていない。》
他ならぬヴェネツィアからはじめたのには理由があるのではないか。しかもヴェネツィアの宿のベッドでのうつらうつらした回想からはじめたのは、須賀自身が十分に意識的だったかどうかはともかく、時の水門を開くべく構想された「小説」としての妙があるからではないのか。
紅茶に浸したマドレーヌと同じように、ヴェネツィアのサン・マルコ寺院の敷石を無意志的回想の舞台としたプルーストのそれがすぐに思い浮かぶ。須賀自身はプルーストの読書体験についてはわずかしか語っていない。たとえば、森まゆみとの対談『夏だから過激に古典を』(『須賀敦子全集 別巻』所収)で、「日本の学校教育のせいだと思うけど、学生に『源氏物語』のことを聞くと、「読みました」って言う。でも、部分だけ。全部読むと、おもしろいと思うんだけど。学校の先生とかに、ここはこう読むんですと言われて読むのではね……。本というのは個人的な体験でしょう。間違えてもいいから、自分で読むことが大事なんです。そして、楽しみながらおもしろく読まなきゃ。プルーストもそう、本当に自由にここは好き、あそこは嫌、という感じで巻き込まれて読むのこそ、若い人の特権だと思うんですけどね」と語り、あるいは、丸谷才一・三浦雅士との鼎談『読書歓談・私が選ぶベスト3』(『須賀敦子全集 別巻』所収)で「いや、私はプルーストはすごく好きだし、あの人の文体というものにはある意味で影響されたと思うんですよ。それだけに、あまりベスト3に入れたくないというのかな」と語ったていどだ。
しかし須賀の書くことの出発点、文体の発見となったナタリア・ギンズブルグ体験というものがある。ギンズブルグはプルーストのイタリア語翻訳者であるだけでなく、ギンズブルグにおけるプルースト体験が、須賀におけるギンズブルグ体験であった。《彼女が訳したプルーストの『スワンの道』までも、つぎつぎと読んだが、いきいきとした彼女の文体に私はいつも魅了されるのだった》と『私のなかのナタリア・ギンズブルグ』に書いているが、『トリエステの坂道』の『ふるえる手』では、もう少し詳しく説明している。
《ナタリア・ギンズブルグの自伝的な小説『ある家族の会話』をはじめて読んだのはもう二十年もまえのことで、そのころ私はミラノで暮していた。日本の文学作品をイタリア語に訳す仕事をはじめてまもないころだったが、まだ自分が母国の言葉でものを書くことを夢みていた。ただ、周囲がイタリア語ばかりのなかでは、自分の中の日本語が生気を失って萎れるのではないか、そればかりが気がかりだった。こんなことでは、とても自分の文体をつくることなど考えられない。かといって、イタリア語でものを書くというのも、とても越えられない大きな壁のように見えた。ちょうどそのころ、書店につとめていた夫がナタリアの小説を持って帰ってくれた。表紙カヴァーにエゴン・シーレの絵がついた美しいエイナウディ社の本で、そのころ評判になっていた。第二次世界大戦に翻弄されながら、対ファシスト政府と対ドイツ軍へのレジスタンスをつらぬいたユダヤ人の家族と友人たちの物語が、はてしなく話し言葉に近い、一見、文体を無視したような、それでいて一分のすきもない見事な筆さばきだった。いったいこれはなんだろう。それまで読んだことのない本に思えた。
あるとき、私は、著者が幼かったころ、プルーストに夢中になった彼女の母親が、医学者だった父親の「軟弱な」お弟子さんたちといっしょに、気に入った箇所を声を出して読んでいたという話をあたまの中で反芻していた。それまでにもその話をなんどか読んでいながら、私はプルーストに夢中になるお母さんやきょうだいがいたなんて、ずいぶんすてきな家族だぐらいにしか考えなかったことに気づいた。もしかしたら、これはただ恣意的に挿入されたエピソードなんかではなくて、彼女の文体宣言に代わるものではないか、そう思いついたとき、ながいこと、こころにわだかまっていたもやもやが、すっとほどける感じだった。好きな作家の文体を、自分にもっとも近いところに引きよせておいてから、それに守られるようにして自分の文体を練りあげる。いまこう書いてみると、ずいぶん月並みで、あたりまえなことのようなのに、そのときの私にとってはこのうえない発見だった。》
ところで、ギンズブルグ『ある家族の会話』(原題『Lessico famigliare(レッシコ・ファミリアーレ)』須賀敦子訳、白水社)には、須賀が「自伝的小説」と名づけた内実に相当する作者の「まえがき」がある。
《この本に出てくる場所、出来事、人物はすべて現実に存在したものである。架空のものはまったくない。そして、たまたま小説家としての昔からの習慣で私自身の空想を加えてしまうことがあっても、その箇所はたちまちけずりとらずにはいられなかった。
人名もそのまま用いた。この本を書くにあたり、私は架空の介入をまったく許容できなかった。本名を変えなかったのはそのためであり、また本人たちと彼らの名を切りはなして考えることが私にとって不可能だったからでもある。これを読んで自分の名が出てくることに反撥を感じる人はあるかもしれない。その人たちには申しわけない、としか私には言えない。
また私は自分が憶えていたことだけしか書かなかった、したがってこの本をひとつの年代記として読む人は、多くの脱落を非難するだろう。だから題材は現実に即してはいても、やはり小説として読んでいただきたい。すなわち、小説が読者に提供することのできるもの以上、あるいは以下のいずれをも要求することなく読んでいただければさいわいである。
それから、自分で憶えてはいてもわざと書かなかったこともたくさんある。とくに私自身にかかわることについては、省略した。
自分についてはあまり書きたくなかったからである。というのも、いろいろな欠落、省略はあっても、この本は私についてのものがたりではなく、私の家族の歴史として書かれたものだからだ。最後にもうひとつ。私は幼いころ、さらに少女時代を通じて、当時私の周囲で共に暮していた人たちについて本を書きたいと思い続けてきた。部分的にはこの本がそれである。ただしそれは部分的でしかない。というのも記憶は時の経過についにあらがい得ず、しかも現実を土台にした本は、しばしば作者が見聞きしたすべてのことの、ほのかな光り、小さな破片でしかないからである。》
須賀は、『ナタリア・ギンズブルグ 人と作品についての試論』(「イタリア学会誌」一九七〇年十月 イタリア学会)で「自伝的小説」という彼女の命名について語っている。
《なお、最初にこの作品を、小説ふうの自伝と書いたが、この「小説ふう」という少々曖昧でもある形容詞を、もう少し掘り下げて検討する必要があるように思われる。ギンズブルグのこの作品は、単に「自伝」と片付けてしまうには、文学的、創作的意図があまりにも明白であって、しかもそれが成功しているため、私は、なにか適当な形容詞をこれに付け加える必要にかられた。そして、作者は、自分自身のことより、自分の家族のこと、自分の周囲に生きた人びとのことを主として書いているのであるから(いろいろな事件がおきた時の、作者自身の感想、あるいは、その時、彼女がとった行動などについては、殆んどふれられていない)、この作品が自伝というジャンルに厳密にあてはまるかどうかも疑問なのである。「登場人物は、みな、実在の人たちで、私は何一つ、つくり事はこの作品に入れなかった」と序文の中で作者自身いっているが、またすぐその後で、「実際にあったことしか書かなかったのであるけれど、小説として読んでいただいてよいと思う」ともことわっている。私小説という日本文学固有の、トリヴィアルな告白体といったイメージを与える用語を、この地中海的な大らかな作品にあてはめることを私は意識的に避けながら、やはりこの『レッシコ・ファミリアーレ』は、小説ふうの自伝と定義されるのがふさわしいと思う。》
これは須賀の作品、とりわけ『ヴェネツィアの宿』と同じではないのか。いっけん自分のことについて書いているような場面でも、作者自身のこと、作者自身の感想よりも、家族のこと、周囲に生きた人びとのことを主に書いていることに注意するべきである。
《夏になると、鬼藤の伯母を思い出す。(中略)どうして夏にばかり鬼藤の伯母を思い出すのか考えてみると、なんのことはない。子供のとき東京にいた私たちにとって、神戸に近い岡本という住宅地に住んでいたこの伯母に会うのが、夙川(しゅくがわ)の祖母のところに一家そろって「帰省」する夏休みと決まっていたからにすぎない。》
時系列的に、京大病院に入院している父を訪れたことを母に報告する様子をつづいて語ることはせず、時間は「私が十六」という昭和二十年にまで遡るのだが、そこには父と母の馴れ初めや、トーマス・マン『ブッデンブローク家の人々』を読んで感激したという「家族」のテーマがある(丸谷才一・三浦雅士との鼎談『読書歓談・私が選ぶベスト3』で、須賀「『魔の山』を皆さんはおっしゃるけれども、私はブッデンブロークのあの家族というもののすごいのと、それから彼の文体、私はイタリア語で読んだんですけれども、構成というか、そういうものにとても感激したのがやっぱり『ブッデンブローク家の人々』だったんです。」)。
「風がちがうのよ」と編集者に語ったという阪神間の雰囲気が幸せな気分で書かれている。
《電車から見ていても、おなじ沿線の芦屋や夙川では、春を告げるのがミモザの黄色い花枝だったり、五月の垣根をいちめんにおおうのが白やピンクの蔓薔薇だったりして、とかく西洋ふうが目立ったのに比べると、岡本あたりでは、秋の日にすずなりの柿が夕陽に照っていたり、冬の終りに見事な梅の大木が咲き誇っていたりするのが、他の住宅地にはないちょっと古風な気品をそえていて、そのことがなんとなく、鬼藤の伯母たちの、どこかで時間のとまったような、それでいて、ふんわりした懐かしさを誘う暮しぶりによく合っていた。》
この鬼藤の伯母という人は、九人きょうだいの末から二番目だった母の長姉で、十五歳ほどのひらきがあった。父と母がはじめて会ったのが、この伯母の家でだった。父方の祖父が設立した建築設備の会社の東京支店をまかされた鬼藤の伯父の結婚相手が母の姉で、長男が生まれたばかりの伯母を手伝いに鬼藤家に行っていた母を、父が見初めた。
鬼藤家の長男の欣一兄さんは学徒動員で兵隊にとられ、私たち親子も空襲の激しくなった東京をあとにして夙川に移ったのだが、その後まもなく、会社の定年をむかえた伯父夫婦が播州平野のはずれにある小野という小さな町にあった鬼藤家代々の屋敷に引っこんでしまった。戦争が激化して、西宮の旧市街が爆撃され、夙川もあまり安全とはいえなくなった昭和二十年の三月の声をきくと、母は妹と弟を連れ、小野の伯父の屋敷に身を寄せた。私が十六、妹は十五歳で、弟が十一歳の小学校五年生だった。私は、父と、父の妹にあたる若い叔母といっしょに夙川に残り、療品廠という海軍の医薬品を扱う部門で働くことになっていて、月一回の休日には、神戸から電車やバスを乗りついで小野の母たちを訪ねる。小野の田舎ぐらしの描写がある。伯父を知るようになって驚いたのは、鬼藤の伯母らしいと思っていた彼女の動作や仕草の多くが、ほとんど伯父の敷き写しだったことだ
(男の敷き写しの女は、母、父の愛人についで三人目となる)。座敷に姿勢を正して正座し、けっして声を荒げることがない伯父の人となりが、鴎外の『ぢいさんばあさん』も引きあいにだされてほのぼのと語られる。
しかし、そこから悲しい話に一転する。《いとこの子のかずちゃんが、もうすこしで二歳の誕生日をむかえるというときに小野で死んだのも、あの昭和二十年の夏だった。》
鬼藤家の欣一兄さんの年子の妹で、名古屋にお嫁にいっていた奈緒姉さんは、夫を戦地に見送ったあと、小野の両親のところに一粒だねのかずちゃんを連れて帰ってきていた。妹はかずちゃんを溺愛した。そのかずちゃんが、消化不良とか疫痢とかいわれていた病気で死んだ。
戦争が終った。もうすぐ九月というとき、母が原因不明の熱病にかかって何日も熱がさがらなかった。重態だとお医者に告げられても、私も妹もどうしてよいのかわからなかった。母の熱がさがりはじめて、伯父が、よかった、ほんとうに心配した、と言ったとき、何日も伯父の声を聞いていなかったような気がした。
九月も半ばをすぎたころ、母のいちばんのお気にいりの甥だった鬼藤の欣一兄さんがフィリピンで戦病死したという公報がとどいた。九月の終りには奈緒姉さんも戦争から帰った夫に連れられて名古屋にひきあげたが、あんたの大事な跡取りを、とんでもないことしてしもうて、と伯父は両手をついて奈緒姉さんのつれあいにあやまったという。その冬、伯父は病気という病気もないままひっそりと亡くなった。
《伯父が死んで、鬼藤の伯母は、戦争中に夫をなくした末の妹を小野に呼びよせて、ふたり仲よく暮していたが、その叔母が五十そこそこで他界すると、伯母もあとを追うように死んでしまった。昭和二十八年のことで、留学中の私はフランスで伯母の訃報をきいた。二年後、日本に帰ってきたとき、母は私に伯母の最期について話をしてくれた。伯母さんは、あの広い家にひとり残されて、どうしていいか、わからなくなったのよね。そう話をむすんだ母は、戦争の末期、アメリカ軍が本土にも上陸するかも知れないという噂がひろまったとき手に入れた青酸カリを、伯母が大切にしまっていたのを憶えていた。》
他の須賀作品もみなそうなのだけれども、『ヴェネツィアの宿』は追想の書であるとともに追悼の書でもある。その最初の、しかしあまりにもいくつもの死のはじまりがこの『夏のおわり』だった。
はっきりとは書かずに省略するのが、都会人の控え目な流儀でもある(この「省略の文体」については、あらためて後述する)し、谷崎潤一郎『細雪』の「ものがたり」としての終り方に学んだものでもあったろう。それは須賀作品の、とりわけ『ヴェネツィアの宿』の秘密を解く鍵になる。
須賀の数ある書評のうちで、もっとも優れたものといっていいのが、『作品のなかの「ものがたり」と「小説」』(『国語通信』1991年4月 春号、筑摩書房)という谷崎潤一郎の『細雪』論だ。この書評は『ヴェネツィアの宿』と同じように、書きだし(母と戦争で婚期のおくれていた叔母が帯がキュウキュウ音を立てるという箇所を読みあって、男の谷崎の気づきに感嘆していた)と末尾(いよいよ結婚のきまった叔母の文机のうえに、谷崎の『盲目物語』を見つけて、こんなにうつくしい本があるのかと息をのんだ)を私的な思い出で額縁のように封じるという構造的美意識をもつ。
《『細雪』をつらぬく主題は、これまでも指摘されてきたように、いろいろな意味での「逝く春を惜しむこころ」であり、雪子を惜しむこころであろう。しかし、私が、とくに興味をおぼえるのは、この主題を展開するにあたって作者がもちいた、語りの様式についての工夫である。
谷崎が『文章読本』(一九七三)において「和文のやさしさを伝え」る文章と「漢文のカッチリした味を伝え」る文章(「源氏物語派と非源氏物語派」)、さらに西洋と日本の文章の性格の区分をおこなっていることに野口武彦」は注目し、このような「物語風」とナレーションが用いられた「古典回帰」時代の語り口について言及されるわけだが、『文章読本』の執筆から十余年を経て完成される『細雪』には、「文章」を超えた、ジャンル様式の面での、画期的な工夫がこらされているように、私には思える。というのは、この作品のなかで作者は、雪子と妙子のふたりの対照的な人物のストーリーを並行あるいは交差させるにあたって、「文章」の域をこえて、ストーリーの物語的な展開と、小説的なそれを、並行、交差させているからである。
このような二重構造、すなわち、西欧の伝統的な「小説」のプロット的展開の構造と、『源氏物語』などを基点とする「ものがたり」風の展開は、いうまでもないが、「ものがたり」的、「日本人」「特有」の性格をもつ雪子と、その「反対」である「西洋人」のような妙子というふたりの人物のうえに築かれている。(中略)
雪子についての叙述が、ドラマ性のうすい、日常のこまごました出来事や人物をとりかこむ事象の、どちらかというと平凡な浮沈(「繰り返し」の手法と秦恒平氏が谷崎の『芸談』、『陰翳礼讃』を引いて指摘した)を主とする平坦ともいうべき「ものがたり」的作法にしたがって話がはこばれる反面、妙子については、男から男への遍歴につれて変容し、水害、板倉の死、赤痢、出産につづく赤ん坊の死という、不可避的な時間のうえに設定される、高低の多い、ドラマ性を核とした構成がみられる。この二つの作法をないまぜにして物語を進行させている点に、私は谷崎の非凡な構築の才能を見るのである。》
須賀は、以上のことをこころにとめて『細雪』の上、中、下の三巻を詳細に分析してゆく。
《妙子のプロットの結末が、彼女の出産、赤ん坊の死、という劇的な話題でしめくくられるのに対して、雪子の「ものがたり」は、彼女と貞之助夫妻の出発の、あっけないほどの幕切れで終る。このあっけなさを私は「小説」的な結びを周到に回避した作者の意図によるものと解したい。(中略)人生に挑んだ西洋的な妙子と、生の流れに身をゆだねる日本的な雪子という昭和初期に生きた対照的な姉妹の姿を、ストーリーの展開を単に異質な二つの性格描写といった安易な手法にゆだねることなく、西洋的な小説作法にのっとった「小説」的なプロットと、日本古来の「ものがたり」的な話の運びをないまぜにして織りあげるといった、構築力とふところの深さに、私はつよい感動をおぼえる。》
『ヴェネツィアの宿』は、あえて分類すれば、冒頭と最後の父のことの二篇(『ヴェネツィアの宿』『オリエント・エクスプレス』、そのあいだにはさまれた、母のことの二篇(『夜半のうた声』『旅のむこう』)、少女時代の一篇(『夏のおわり』)、修道会と留学に関わることの四篇(『寄宿学校』『カラが咲く庭』『大聖堂まで』『カティアが歩いた道』)、イタリア時代の二篇(『レーニ街の家』『アスフォデロの野をわたって』)、京都での一篇(『白い方丈』)からなり、それらが時系列的にはあらわれないから、とりとめないような、曲がりくねった道のどこを歩いているのかわからないような気がしてくるものだが、母のことの二篇、少女時代の小野での一篇、京都での不思議な一篇が「日本人」の性格をもつ日本的な「ものがたり」で、父のことの二篇、留学と修道会に関わることの四篇、イタリア時代の二篇が「西洋人」との西欧的な「小説」ともいえ、それらを並行あるいは交差させている。けれども、『細雪』が最後に、妙子の「小説」的なものが雪子の「ものがたり」的なものに吸収されて終ったのに対して、『ヴェネツィアの宿』は、生の流れに身をゆだねる母や鬼藤の伯母の「ものがたり」的なものが、人生に挑んだ父や修道女たちや「私」が「小説」的なものへと収斂するのであって、逆であることの現代的な強さ、構築力と深さにこそ人は感動をおぼえるのに違いない。
<『寄宿学校』/会話の文体>
『寄宿学校』は修道会と留学に関わることの四篇(『寄宿学校』『カラが咲く庭』『大聖堂まで』『カティアが歩いた道』)のうちのひとつである。作品の時間は『夏のおわり』の戦争終結をひきついだ少女時代であるが、舞台は東京のカトリック学校の寄宿学校に移り、外国人修道女が登場してくることによって、西洋小説のような雰囲気にかわる。そして最後は、半世紀後の雑司ケ谷墓地となる。
《Lord,lord,L-o-r-d,LORD.
もう一時間もこれだけだ。何十回、繰り返したことだろう。四時、午後のお茶の時間のあと、上演の日が近づいた英語劇のリハーサルで、出演予定者が講堂にあつめられたのだが、そのあと私だけがシスター・フォイにつかまって、発音の練習をさせられている。(中略)ああ、できた。かんぺきです。ふいにシスター・フォイが歓声をあげ、あっという間に私は外国の匂いのする彼女の胸もとに抱きしめられている。できたじゃありませんか。もう大丈夫。さあ、もう一回、Lord,lord,lord.》
「私」が学校とどう関わってきたか、学校の母体はどういうものかがかっちりと説明される。寄宿学校の様子がどんなふうかは数人の修道女や寄宿生とのやりとりを、これまでは間接話法一辺倒だったのを直接話法も交えた会話で活写することで、このさきの何篇かのカトリックのテーマの背景が自然に理解されることとなる。
《六歳で入学し、やがて関西から東京へと移り、また、戦争で東京から関西にもどっても、ずっと同じ修道会が経営するカトリック学校に通いつづけた私は、戦争の終始とともに親元をはなれ、東京のキャンパスにある専門学校の英文科に入学した。両親は疎開をつづけるかたちで関西に残ったから、十六歳の私は、焼け残った校舎での寄宿舎生活をおくることになった。》
《学校の母体である修道会は、十九世紀のはじめにフランスで創立されたあと、時代の要請と修道女たちの献身にささえられて、まもなく世界各国にひろまり、日本には明治のおわりごろ、オーストラリアから派遣されたシスターたちが学校をはじめたのが起りである。》
シスターたちとのエピソードをひとつひとつとりあげる紙数はないから、名前だけでもあげれば、英語劇の監督をする中年のオーストラリア人のシスター・フォイ、小柄だけど歩き方のきれいな生徒係のシスター・ヘレナ、「古典をお読みなさい。ホーマーとか、ダンテとか、シェクスピアとか。『風と共に去りぬ』はそれからでじゅうぶん」とつよいドイツなまりの英語で話すドイツ人のマイヤー院長、生粋のアイルランド人で聖歌隊の指揮をするがっしりと骨っぽい短気なシスター・フレンチ、レクリエイションにベースボールを導入して物議をかもしたアメリカ人のシスター・ダナム、修道院の事務や会計をとりしきっている金縁眼鏡の副院長シスター・シッケル、聖堂係のシスター・グテレス。
神父さんだったお兄さんが、戦争中にユダヤ人をかばってヒトラーの強制収容所にいれられ、そこで亡くなったという話をシスター・ヘレナから聞いたマイヤー院長と寄宿生との会話のたくみな表現だけ紹介しておこう。たとえば、この音楽の話。
《ある日、彼女は開口一番、ちょっときびしい声でたずねた。
「今日、十六番の教室で四時から五時までピアノを弾いていたのはだれですか?」
私たちは顔をみあわせた。中学生がおそるおそる手をあげた。「はい、わたくしです」
ふぉっふぉっふぉっと笑ってから、マイヤー院長は言った。
「ショパン、すきですか?」
「はい」その子は、ピアノを弾いていたことを叱られるのではないと知って、ほっとした声でこたえた。しかし、油断は禁物、あっという間にマイヤーさんの顔から笑いが消えた。
「ショパンばっかり弾いてると、音楽はわからない」きびしい声だった。「バッハを勉強なさい。バッハに音楽をならいなさい」
どうして、ショパンではだめで、バッハでなければならないのか。ドイツ人どうしだからかな、と思ってみたりしたが、マイヤーさんはそういうことは超越しているように思えた。》
副院長シスター・シッケルと聖堂係のシスター・グテレスに聖堂の準備室の鍵を紛失したのではないかと疑われて、修道院の焼け跡で、あるはずのない鍵を一時間も探させられ、《あれから半世紀近い時が過ぎたいまも、あの鍵がどうしてなくなったのか、あのあと見つかったのか、それならいったいどこにあったのか、とうとう私は知らずじまいだ》のあと一行あいて、その半世紀後の三月も終りに近いある日の午後、東京にながく住んでいるイタリアの友人と雑司ケ谷の墓地を荷風のお墓をたずねる場面となる。めざす荷風の墓碑はなかなか見つからなくて、迷いつづけたあげく、ふと、小さな鉄門のついた墓所と門についた紋章を見て、はっとした。それは、六歳のときから十六年間、なんだかんだと不平を言いながら勉強した学校の紋章だった。日本に来て、ふたたび故国に帰ることなく生涯を終えた修道女たちの墓所にちがいなかった。
《きいっと心をえぐるような音をたてる小さな鉄門をあけて私は中に入った。(中略)葬られた修道女の名と生年月日、そして亡くなった年と月日と、それぞれの故国の名がきざまれていた。親しかった人の名もあり、知らない名もあった。おもわず姿勢をただしたのは、畏敬の気持からというのとは、すこしちがっていた。しゃんと背をのばしなさい。修道女たちがそういって注意する声がきこえそうだったのだ。まっすぐに立って、私たちの顔を見てはっきり挨拶なさい。
「おーい、そんなところでなにしてるの。荷風はこっちだったよ」
友人の呼び声に、また、ここにはいつかひとりで来よう、と思いながら、私は暗い小径を声の方角に歩いていった。》
読者の情感の門も、きいっと心をえぐるような音をたててひらかれ、また、ここにはいつかひとりで来よう、と思う作者の孤独な追悼のありかたに共感をおぼえずにはいられない。
さて、フランス文学者の清水徹との対談『人生の時間 文学の時間』(一九九五年収録)(『須賀敦子全集 別巻』所収)で、清水は、どうして書き始めたのか、と会話文の使い方を話題とした。
清水は、須賀が七十年代の終りごろからギンズブルグ『ある家族の会話』の翻訳を雑誌に連載し、本が刊行されたと同時に、同じ雑誌に『ミラノ 霧の風景』の連載を始めたのが八五年末だから、作家がどうして書き始めたのかがいつも気になる自分にとって、外側のデータだけから類推すると、「ギンズブルグを翻訳したということが、須賀さんのエクリチュールの誕生を促したという結論になる」と指摘した。
須賀は「そうと思います」と答えてから、だいたい自分のなかにある書く材料を、どういう文体で、どういうふうに書けばよいのかをギンズブルグを訳すことで発見があったうえ、そのころから文体論に興味をもちはじめ、七〇年代に『源氏物語』を原文で読みとおして、この物語はこの文体でしか書かれ得なかったと思って、ずいぶんほっとしました、「あの会話をふくめたまま動いていく長いセンテンスの魅力に感動したと思います。それまでは、漠然と一葉の文章が好きだったり、谷崎潤一郎の小説も好きだったりしました。彼も文体を探して歩いた時代がありますね。そんなものが、いろいろ混ざったのかもしれません」と答えている。続いて、
《清水 僕は須賀さんの書かれたもの面白いと感じた一つは、会話の使い方なんです。つまりフランス語で言うと、直接話法、間接話法、自由間接話法、最近は自由直接話法まで出てきています。日本語では自由間接話法はうまく書けなくて、自由直接話法はみんなが書いている。しかし大衆小説などの自由直接話法はずいぶんルーズなものなんですが、須賀さんのはそうじゃない自由直接話法なんですね。読んだ上では一見とても均質な文章なんですけど、描写の文章と作者の感想と会話の部分というのが、実は織り糸がそれぞれ違っているにもかかわらず、それら全体を巧みに流しこんだ文章だなと思ったんです。これは面白いと感じたんですが、その後ギンズブルグを読みまして、ハハァーと思ったんです。
須賀 ギンズブルグと『源氏物語』とがうまく合ったのかもしれません。谷崎もいわゆる『春琴抄』などの古典時代の作品では、会話の使い方を工夫しています。それと関西弁に魅せられている。私ももとは関西ですから、自分のなかに何か惹かれるものがあったんだと思います。」》
この『寄宿学校』と、前出の『ヴェネツィアの宿』『夏のおわり』に会話の文体の具体的な例があるのは、すでに引用したとおりである。
<『カラが咲く庭』/言葉で通じあうこと>
《部屋で手紙を書いていると、だれかがそっとドアをノックした。こんなおそくに、いったいだれだろうと開けてみると、韓国人のキムさんが、暗い廊下にぽつんと立っている。どうぞ、はいってください、と言うと、ちょっとだけね、もうこんな時間だから、とことわりながら、それでもうれしそうににっこりした。》
こんな魅力的な文章ではじまる『カラが咲く庭』は、キムさんのノックの半年前、一九五八年の冬にローマからの奨学金の話に乗ることで、フランス留学から帰って三年間つづけた放送局の仕事をすっぱりやめ、日本をはなれることにしたからだった。
ちょっと自嘲的な調子で自分のことや、寮の待遇の不満を強い口調で言うが、ほんとうは淋しがりやで、人に話しかけられるのを待っているような三十代の半ばをすこしすぎた、高校の歴史の先生をしていたというキムさんは、このごろイタリア語を聞こうとすると、頭が痛くなるのよ、とせつなそうにしながら、午前一時をまわるまで、二時間話しこんでいった。翌朝、四年前に二ヶ月半、ペルージャの外国人大学で勉強したとき下宿させてもらったカンバーナ家の人たちに誘われてフレジェーネ(ローマ北西部の海岸線の別荘地)の海の家に行き一週間、遊びほうけて帰ってみると、キムさんが神経科の病院にはいったという。さっそく、シスターたちにかけあって、ヴィラ・フィオリータ(「花ざかりの家」)という神経科の病院に、キムさんと同室だったチョイさんと見舞いに行ったが、薬で眠らされ、もうろうとして、あんまりかわいそうだった。学生寮に帰って、修道女たちと彼女を故国に送り返す交渉をはじめたが、そうですね、ばかりでまったくらちがあかない。以前、留学していたときに会ったことのあるアノージュさんというフランス人の神父が日本大使館で顧問をしているので相談すると、大使館の人たちが韓国の出先機関に連絡をとって、キムさんは無事にローマを発っていった。
なにをするにも修道女の監視の目がひかっている学生寮を出ようと、アノージュさんに相談すると、大学の近くで女子学生の寮を経営しているフランス人の修道女を紹介してくれた。院長のマリ・ノエルさんがすぐに会ってくれ、来週からいらっしゃいね、となった。朝、起きてすぐ、早く逃げ出すに限ると奨学金の寮をとび出してきたものの、新しい学生寮の受付でいわれた午後の時間まで、モダンなローマ終着駅、スタツィオーネ・テルミニの切符売り場のまえの白いベンチに腰かけた私は、ハンドバッグを抱えこみ、膝のまえに大きなスーツケースを置いて、ひたすら時間の経つのを待っている。
『カラが咲く庭』は、意志を通じあうことの不可能と可能がテーマに違いなく、また他の作品よりも、「私」の意見や感想が周囲の人物を通してではなく「私」を通して語られる。これまでの「私」のイメージを壊すように、自分の話をすると、激しい口調になったり、言葉が迸りもするが、「私=須賀敦子」と限定してしまう自伝にも回想にもエッセイにもとどまっていないことは、五つに分たれ、巧みに計算された構成、とりわけ最初と最後の情景によってあきらかだ。普遍的な問題である、言葉、会話、声によって意志を通じあうこと、他者を受容すること、西洋の個人主義を見きわめ折りあいをつけること、などの、よりよく生きることの核心におずおずと触れはじめている「私」がそこにいる。
《となりにすわっていた、先のとがった茶の靴をはいた痩せぎすの男が話しかけてきたが、なまりが強くて、これからシチリアのパレルモに帰るところだ、というくらいしかわからない。いいかげんにあいづちをうっていると、コーヒーをおごるから、どこかに行こうと言いだした。じろじろとこちらのからだを見られると、それだけで、なにかを盗られたような気分になる。そんな、大きな荷物をもって、かわいそうに、と同情してみせる。ぼくが持ってあげよう。》 けっこうです、と邪険に答えたことさえ、まずかったと気づいて、返事をしないことにすると、あきらめて立って行った。
かわりに、大きな籠をさげた、体格のいいおばさんがどしんと腰をおろす。「あんた、なに待ってるの?」すわった途端に話しかけてくる。こんどの相手は田舎っぽいおばさんだから、ひどい悪党ということでもないだろうと質問に答え、イタリア人じゃないわねえ、と言われて、日本人です、と応じて、「おばさんは、何を待ってるんですか?」と攻めに出ると、「アプリリアまで帰るところよ」と彼女はつづけた。
《「近いわよ。一時間とかからない。あんた、私といっしょに、うちに来ない? 駅のすぐ近くだから、私といっしょに十時半の電車に乗れば、うちでお昼を食べて、すぐにローマに帰っても、約束に間にあう」
え、と私は驚いて彼女の顔を見た。駅で出会った見ず知らずの、しかも「生まれてはじめて」実物に接した日本人だというのに、いきなり自分の家の食事にさそうって、いったいどういう神経なのだろう。》 庭には花がいっぱいだし、いい家よ、あんたに見せたいの。「娘の部屋が空いてるから、あんたよかったら、うちに下宿しない?」 出会って十分も経たないうちに、途方もないところまでエスカレートしてしまう。たよりない顔をして、行きたいけれど、ここで待つことにすると返事をすると、そそくさと席を立ってしまった。
あたらしい学生寮の生活は快適だった。中世神学の研究所に週二回の講義を聞きに行くほかは、個室で本を読んだり、手紙を書いたりした。薬学部の学生のルチャーナ、文学部のアレッサンドラやクラウディアと、夜おそくまで暗いテラスでしゃべることもあった。寮生は主流が南部または中部イタリアから来ている大学生で、外国人は、アメリカ人のジェーン、ポーランド人のタデウシュカ、フランス人のシャンタルと、ヴァチカン勤務のマリ・アンジュ、東洋人はジャワ生まれの中国人のサンサンと私のふたりだった。
入寮前、すくない寮費のうめあわせに、ちょっとした仕事をしてもらうことになるかもしれないと、マリ・ノエル院長がほのめかしていたのに、いっこうはっきりしないので、私に仕事をください、と申し出ると、でもあなたはもう仕事をしています、といってつづけた、「アジアとかアフリカの、高い教育をうけた女の人がこういった寮にいてくれるだけで、イタリアの女子学生にとって、新しい世界がひらけることになります」
納得のいかない顔をしているのを見て、「一週間に二度、一時間ずつ、私のところにきて、日本のことや、あなたがヨーロッパについて考えていることをしゃべってくれませんか。レッスンのようにして。あなた自身のことだっていい。それがあなたの寮費の一部になる」という、ちょっと変った提案をした。こうしてローマにいた二年足らず、週に二回ずつ会っては、じつにいろいろなことを話しあった。とくに熱を入れて話したのは、これからの西欧と非西洋世界がどういうふうに関わっていくかについてで、マリ・ノエルは西洋はあまりにも自分たちの文明に酔いしれていると言って、かなしそうな顔をした。
《私が自分の話をすることもあったが、そんなとき、思わず激しい口調になった。自分のなかに凍らせてあったものが、マリ・ノエルのまえにいると、あっという間に溶けていった。どうして、仕事をやめてまでローマに来たか、何が東京で不満だったのか。本を読んだりものを書いたりすることが人間にとってなにを意味するのか。
「そんなことが知りたくてまたヨーロッパに来たんです」「それはわかるけれど」とマリ・ノエルがいった。「あなたがいつまでもヨーロッパにいたのでは、ほんとうの問題は解決しないのではないかしら。いつかは帰るんでしょう?」
「もちろんです。もう、どこにいても大丈夫って自分のことを思えるようになれば」》
フランス人の個人主義を、彼女はきびしく批難することがあった。生まれつきのジャンセニストなので自分にきびしいあまり、他人までも孤立させてしまう、と。
《「でも」反論せずにはいられなかった。「あなたはフランス人だから、そんなふうに個人主義を平然と批判できるのだと思います」
私の意志を超えて言葉が走った。
「あなたには無駄なことに見えるかも知れないけれど、私たちは、まず個人主義を見きわめるところから歩きださないと、なにも始めたことにならないんです」
こちらのけんまくにのまれて、マリ・ノエルはすこし茫然としている。開けはなした窓から、庭で遊んでいる幼稚園児の子供たちの声がとびこんできた。》
「開けはなした窓から、庭で遊んでいる幼稚園児の子供たちの声がとびこんできた」の内から外へ、外から内へ、と場面と情緒の転換が同期するうまさ。それは、この作品のラストで如何なく発揮される。
二年目の冬に、テレーズという名の、木彫り人形を思わせる小柄なヴェトナム人の修道女が、からだが丈夫でないために、パリの修道院からあたたかいローマの寮に配属されてきた。イタリア語ができないので、いつもだまって、胸当てのついた、白くてすその長い、ごわごわした木綿のエプロンをつけてかいがいしく働くすがたが可憐だった。フランス語も、できるというほどではなくて、私と目があうと、溶けるような笑顔で笑ってみせたが、それが私にはつらくて、ヴェトナム語をぺらぺらしゃべる夢を見たりした。春になって、テレーズが病気になった、結核かもしれないという噂が広まったが、マリ・ノエルは暗い表情で首を横にふった。「神経の病気なの。ぜんぜん、口がきけなくなってしまったのよ」
キムさんは、彼女の故郷の町には、いい神経科の病院がなくて、自宅の一室にとじこめられていると、チョイさんは話してくれた。西洋になんかやるんじゃなかった、とキムのおかあさんは、髪をかきむしって悲しんだとも聞いた。
《ある日の夕方、食事に行こうとして、修道院の庭に出ると、カラの花が濃いみどりの葉のかげに蒼白く咲いている噴水のそばに、小柄なヴェトナム人修道女のテレーズが、こっちを向いて立っていた。思わずフランス語で、よくなったの、と言いかけて、やめた。口がきけなくなった、とマリ・ノエルが話していたのを思い出したからだ。はたして、答えも、あの溶けるような笑顔も返ってこないで、テレーズは、私の視線を避けるように、つと横を向くと、そのままじっと、暗い木蔭に立ちつくしていた。修道衣の喉をおおう白い布だけが、夕方の光のなかでぼんやりと明るかった。》
<『夜半のうた声』/川端康成「そこから小説がはじまるんです」>
《やっぱりそうだったのねえ。その日、私が京都から帰って、父の愛人に会ってしまったことを話すと、病床の母はそう言って、淋しそうに笑った。どうもあの人はうそをついてると感じてはいたんだけれど、信じたくなかったのよね。》
書きだしの一節でわかるように、一作目の『ヴェネツィアの宿』の後半部分、京大病院で父とその愛人に出会ったところの続きに他ならず、家に帰って母に報告するところからはじまる。『夏のおわり』『寄宿学校』『カラの咲く庭』の三篇をはさんで、ふたたび戻って来たことになる。
母に、女の人のこともぜんぶ話してしまった夜から、母のとなりの座敷で寝ることにした。しゃべっていれば、せめてそのあいだだけでも母の気がまぎれると、妹と私は、せっせとばか話にせいをだした。廊下ですべってころんだ飼犬のベンのこと、戦後のヤミ市の時代に神戸から食料品を売りにきた台湾人のリンさんが山手に家を買って悠々自適なこと、それを知らせてくれた神戸で小さな洋装店をかまえている田口さんのところで、春になったら、またなにかいい洋服をつくってもらうといいわ、と母は言ってから、また父のことを思い出したのか、顔をかげらせて、だまってしまった。
妹や弟が寝にいってしまうと、「背はどれくらいだった?」ふいに母がたずねた。「高い。パパと歩いていても、小さくみえなかった。どうして?」「うん、ちょっと……。骨太っていう感じ?」「わからない。まあ、そうかな。背の高い骨太の人なら、ママ、心あたりあるの?」「そういうこともないけれど」
《話がとぎれると、もう夜中なのに、母はときどき小さな声で歌をうたった。どの歌というのでもない、細い声のメロディーだけだったが、聞いていて私はこわくなった。こうしてうたっているときに、ひょいとわけがわからなくなったらどうしよう。
「ママ」と呼んでみた。「なにうたってるの」
返事はなくて、母はうたいつづけた。まくらに顔をぴったりとつけて、私は声がやむのを待った。手が汗ばんでいるのがわかった。
むすめのころ、わたしは歌が上手だったのよ、母はよくそう言って自慢した。》
こうして、母の歌の話になる(ヴェネツィアの宿で聞いた音楽、アヴィニョンの歌声と通底しているだろう)のだけれども、麻布の家での幸福な歌の回想はたびたび父のことに戻って、母と父のいきさつを説明的ではなく語っていく。すこしは落着くかも知れないと祖母や大叔父が考えついた父の世界一周旅行から帰って二年、仕事はますますうわの空、責任の重い仕事をさせたらやる気を出すかもしれないというので、東京支店に勤務が決まった。関西の家から麻布に越してきたのは、私が九歳のときだった。
《三人の子供がそろってはしかだというのに、母はうれしそうに歌をうたいながら、ステップを踏んで畳のうえをくるくるまわっている。母の腕のなかの弟は、熱があるにもかかわらず、カンガルーの息子みたいにぬくぬくと幸福そうだった。(中略)
イッツァロングウェイ、トゥティッペラリィ
イッツァロングウェイ、トゥゴォ
発疹が風にあたるといけないというので、すっぽり毛布にくるまれた三歳の弟はごきげんで、リィとかゴォという語尾のところだけ、口をとがらせて母にあわせる。そのたびに母は、いやあね、この子はパパに似て音痴だわ、といって笑う。(中略)
それ、いったいなんの歌なの? とたずねても、返事はいつも、パパに教えてもらったの、イギリスの古い歌ですって、欧州大戦のときの、と言うだけだった。》
《シューベルトの子守歌は日本語だったので、意味がわかった。
ネームレー、ネームレー
ハーハーノームーネェーニィー
ではじまったが、ハーハーノームーネーというところの、まるくのびる節まわしそのものが、ちっちゃな森の動物が母親の胸に抱かれているようで居心地がよかった。》
母は天井に顔をむけたまま、話しつづけた。どうしても結婚しようって、あんまり熱心に頼むから、結婚してしまったのがまちがいだったのよ。わたしは三つも年うえだし、家のしきたりも違いすぎるから結婚はいやだっていったのに。あの人は、がんらいわがままなのよ。エゴイストなのよ。おばあちゃんに気ばかりつかって、いいことなにもなかったわ。毎晩のようにダンス・ホールに行こう行こうって、うるさくて困った時期があったのよ。自分たち親子だけで暮らしたい、と言いつづけた母の希望が麻布の家に移ることでやっと叶えられたのは、結婚して十年目だった。とうとう自分たちだけの生活を手に入れたのに、母は病気ばかりしていた。そのころの私にとって、父は気むずかしい暴君だったが、それでも、うっとうしい雲がすっと晴れたような瞬間が、ときにあった。父が朝の食卓で母をからかっている。おまえに値段がついているなんて、知らなかったなあ。子供たちのまえで「ママの醜態」をぶちまけてしまうと、母はまんざらでもなさそうに、いやあね、と笑って聞いている。父の帰りを待つあいだ、こたつで家計簿をつけていて、そのノートに顔をのせていねむりをしたものだから、数字がひたいに写ってしまったのだった。父がお酒を飲んでいる。母に長火鉢で燗をさせて。あら、あなた、よっぱらってるのね、と母が明るい声をあげる。自分のお酌で夫が酔ったことにうっとりしている。
父が家を出て二年目になると、母も私たちも、そろそろがまんの限界に達していた。いちど、あの二人を会わせてしまおう、と決心して、まず、母を説得することからはじめた。「わたしの見たところでは、パパはほんとうにいやがってるんじゃない。帰るきっかけほしいんだと思う」 父がいなくなってから、親は甘える対象ではなくて、甘えられるものになってしまって、そのことが重かった。妹にも加勢をたのんだ。ちょっと無理をしないと、あの夫婦は相手が折れてくるのを永遠に待ってるだけなんだから。
東京から母を迎えに行って、目黒にいた母の姉のところに一泊し、その夜は京都から出てくる父が麻布に泊まるはずなので、翌朝、父がでかけないうちに、母を麻布に連れてゆこう、という計画だった。子供のころ、妹といっしょに毎朝歩いて学校に通った道が秋の陽にかがやいていているのをタクシーの窓から眺め、横に座った母の着物の絹地が手にふれると、ひんやりした、という感覚の冴え。ここからの文章は、視覚と聴覚、行動と会話が、地に流しこんだ文体のなかでフーガを奏でている。リアリズムで、四畳半的湿っぽさがなく簡潔、突き放すようにそっけなく、私小説的告白から遠く離れているが、情緒は饒舌でもある。
《右手でドアのノブをまわして、三十センチほど開けると、いつものように、パジャマの上に和服を着て新聞を読んでいた父が、私の顔を見て、おう、と声をかけた。母はまだ私のうしろにいた。その母の肩を私は左手で抱くようにして、部屋に押しこんだ。父が小さな声をあげて、立ち上がった。なんだ、これはいったい。どういうことだ。
パパ、おこらないでね。ドアのノブに手をかけたまま、私が言った。ママとふたりでお話なさってください。これはパパとママの問題ですから。
なにかを投げつけてくるかと身構えた私を、父は一瞬、口惜しそうに睨んだが、あきらめたようにソファにくずれこんだ。外からドアをしめると、そのまま、中はひっそりしていた。》
すぐこれにつづいて、夜半の母のうた声と響きあうような母の手紙からの数行でこの作品は閉じられる。
《とうとうパパが帰ってきました、と母から手紙がきたのは翌年の一月だった。十一月に麻布の家で母と話してから二ヶ月目だった。
七日の昼に会社から電話をかけさせて、夕方、なんでもなかったように、ふつうの顔して、家にかえってきました。あきれたものです。でも、かたちだけだって、ぜんぜんないよりはましなのでしょう。》
母への愛情に満ちている表現なのはもちろんのこと、父のことは悪く書いているようでも、心の底はそうではない、ということが、あからさまに言葉に書かず、書かないことでむしろ伝わってくる文章である。
須賀が、なぜこのような文体で、およそ四十年前のことを書くことができたのかを考えるうえで、次の文章が糸口になるのではないか。それは、『小説のはじまるところ 川端康成『山の音』』(「ちくま日本文学全集」『川端康成』解説、筑摩書房)からである。
一九六八年の冬の日に、ノーベル賞の授賞式をおえてイタリアに寄せられた川端夫婦と夕食のテーブルをかこんでいた。ミラノの出版社から依頼されて『山の音』をイタリア語に翻訳させていただけないかとお願いに行ったのを、大使館の方が夕食にさそってくださったのだった。食後、スウェーデンの気候、イタリアでの日本文学の読まれ方などを話しているうちに、話題が一年前に死んだ私の夫のことにおよんだ。
《あまり急なことだったものですから、と私はいった。あのことも聞いておいてほしかった、このこともいっておきたかったと、そんなふうにばかりいまも思って。
すると川端さんは、あの大きな目で一瞬、私をにらむように見つめたかと思うと、ふいと視線をそらせ、まるで周囲の森にむかっていいきかせるように、こういわれた。それが小説なんだ。そこから小説がはじまるんです。
そのあとほぼ一年かけて『山の音』を翻訳するあいだも、数年後に帰国して、こんどは日本語への翻訳の仕事をするようになっても、私はあのときの川端さんの言葉が気になって、おりにふれて考えた。「そこから小説がはじまるんです」。なんていう小説の虫みたいなことをいう人だろう、こちらの気持も知らないで、とそのときはびっくりしたが、やがてすこしずつ自分でものを書くようになって、あの言葉のなかには川端文学の秘密が隠されていたことに気づいた。ふたつの世界をつなげる『雪国』のトンネルが、現実からの離反(あるいは「死」)の象徴であると同時に、小説の始まる時点であることに、あのとき、私は思い到らなかった。(中略)
川端が長編を仕上げるのにながい時間をかけたのは、論理的な構想に欠陥があるためではなくて、抒情の連想がじゅうぶんなふくらみをもつのに必要な、内的な時の流れを作者が必要としたからなのだ、と。まず最初に、ひとつの章が書かれ、そのあとは、つぎつぎと連想をバネにして書きつがれていく。そして、川端の作品に時として見られる書きだしと結末の可能なずれは、連歌や俳諧の運び方を見ればわかるだろう。日本古来の座の文学においては、これに参加した詩人たち自身も、最後の句がどのようになるかは、発句が詠まれた時点ではわからない。連想が詩のながれをどのように変えていくかを、ただ待つ以外に知る手だてはない。川端の場合も、これに似たことがいえる。作品にとりかかった時点では、その結末がみえていないことが多いのが、論理の必然性ではなく、「連想」のふくらみぐあいを待たなければならない作家にとって、これはほとんど当然といえよう。》
須賀の『ヴェネツィアの宿』は長い年月をかけて書きあげたものではなく、一年間の連載だったし、発句にあたる『ヴェネツィアの宿』を書いた時点で、確実に最後の『オリエンタル・エクスプレス』を意識している西洋的な論理的構想による作品だが、しかし、書きはじめるまでの長い年月が同じような役を果たしたとは言えまいか。『夜半のうた声』の出来事からの、およそ四十年という時間が、待たなければならなかった年月に相当する。あるいは、須賀が『ミラノ霧の風景』を書きはじめるのが一九八五年で、これが書かれるのが一九九三年であるから、作家として書いてゆくことを意識した八年間という年月がある。控えめにみれば、須賀が家族のことを、とりわけ父と母のことを、自分とは何者かを探求する限りは書かないわけにはゆくまいと意識した時点から、さらにはずっとずっと、あり得ないほどに控えめにみて、第一作の『ヴェネツィアの宿』を書いてから、その続編ともいえる『夜半のうた声』までの連載三回分、逡巡のまわり道のような三か月が、「抒情の連想がじゅうぶんなふくらみをもつのに必要な、内的な時の流れ」だったのではないか。その「ふくらみ」こそが芳醇な文体の秘密であり、「内的な時の流れ」こそが客観性と距離感をもつ作品の「深さ」に到ったのに違いない。
<『大聖堂まで』/教会建築>
パリ留学時代の二篇(『大聖堂まで』『カティアが歩いた道』)のうちのひとつで、これらはキリスト者としての「私」の経験に深く関わっている。雑誌連載時の原題は『待っている人』、題名の意味はラスト・シーンでわかるのだけれど、これだけが本にされるとき題名を変えられているのは、考えがあってのことだろう。たしかに、ここでも回想が、小さな波と大きな波で押しよせてきて、過ぎた時間がある種の主役ではあるけれども、「待っている」という受け身は、気持から少しずれていたか、真意にそぐわないと思ったのだろう。
一九七一年と一九五四年というふたつの時間があらわれ、それとなく対比されているともいえよう。ひとつはミラノからパリへの八〇〇キロの車での移動とノートル・ダム大聖堂、もうひとつはパリからシャルトルまでの八十キロの徒歩での巡礼とシャルトル大聖堂。
アルプスとジュラというふたつの山脈を越えるけれど、距離的にはミラノ―パリ間は八〇〇キロあまり、地図を見ながら走れば、なんということはないはずだった。モンブランの長いトンネルをすぎて、シャモニからジュネーブを抜け、フランスに入ったころには疲れが出て、ドールで一泊した。ディジョンで昼食をとると三時をまわっていて、はじめて車で行くパリには暗くならないうちに入りたいので、あわてて高速道路に乗って、パリ市内にさしかかると、ほどなく、リュクサンブール公園の横を走っているのに気づいた。学生のころ、この辺りに住んでいたリュ・デゼコルで車をとめて見まわすと、道をわたったところにオテル・ド・ラ・カリフォルニーがあった。《毎日その前を歩いて大学にかよった、なんの変哲もない学生街の安宿だが、貧乏学生のつめたいパリの日々に、カリフォルニアという名が、陽光にあふれる土地への郷愁をさそって、毎日その前を歩いて大学に通い、なんどか泊まってみたいなあと思ったことがある。》 そうだ、今夜の宿はここにしよう。行きあたりばったりに決めてはいっていくと、《カウンターにいた白髪のおばさんはちょっと帳簿をしらべただけで、にこりともしないで言った。運のいいひとねえ、あなたは。これが最後の空き部屋ですよ、マダム。屋根裏だけど、なにしろ観光シーズンですからね。聞きながして、荷物をひきずりながらとにかく無事に最上階にたどりついた。》
このあたりの文章は、聞きながすまでに変化した今の「私」と、学生時代のパリでの感情の澱を、さりげなく細やかな形容で表現、対比している。
《旅行者の多いこの季節にすんなりと寝るところが決まったのは、受付のおばさんの言ったとおり、ひどくありがたいことだったから、私はすっかり気をよくして、靴をはいたままベッドの上うえに体を投げだすと、そのまま目をつぶった。
一九七一年の七月で、秋にはいよいよ日本に帰ることが決まっていた。いったん引きあげてしまったら、いつまたヨーロッパに来られるかわからないから、出発までにフランスだけはもういちど見ておきたい。そう思っていたときに、ちょうどパリに住んでいる友人が来ないかとさそってくれたので、決心してミラノを出てきたのだった。(中略)
とろとろとねむったのかも知れない。どこかの部屋で水を流す音に気がついて時計をみると、八時をすぎていた。》
サン・ミシェル大通りに行き、簡単な夕食を手ばやにすませると、夏の観光客がごったがえす賑やかな大通りに出た。《つい、きのうまでミラノにいたのが、うそのように思えるいっぽう、パリにいるという実感がそれほど湧かないのは、どうしたことだろう。むかし、ソルボンヌの学生でこの道を急ぎ足に歩いていた自分と、十三年にわたったイタリア暮しをきりあげて、とうとう日本に帰ろうとしているいまの自分をへだてる時間のなかで、パリがかすかに変質したのではないだろうか。あす十六年ぶりで会うことになっている友人は、どんな顔をして迎えてくれるだろう。》
ホテルに戻ると、部屋の空気が澱んで、変に重かった。ベッドのうえに立ち上がると、両手でいきおいよく窓をあけた。ここから、ノートル・ダムについての美しい文章になる。
《すぐそこ、といっていい距離に、白くかがやくパリの大聖堂ノートル・ダムが、まだ昼間の青が残った夜空を背に、溢れるような照明の光をあびて、ぽっかり宙に浮かんでいた。それも、セーヌ河沿いの花やかな南面を惜しげもなくこちらに向けて。後陣にちかいトランプセプト(袖廊)の突出部の中央に位置した薔薇窓の円のなかには、白い石の繊細な枠ぐみにふちどられた幾何もようの花びらが、凍てついた花火のように、暗黒のガラスの部分を抱いたまま、しずかにきらめいている。宇宙にむかって咲きほこる、神秘の白い薔薇。トランセプトとネフ(身廊)の屋根の稜線が十字に交差する点にしっかりと植え込まれたように、天を突いて屹立する、細身の、鋭い尖塔。精神の均衡と都会的な洗練の粋をきわめるパリの大聖堂が目の前にあった。
なんでもないふつうの窓と思いこんで、力まかせにあけたものだから、その分だけ驚きは大きかった。ついさっきまで暮れなずんでいた背景の空には、もう暗い夜がいっぱいにひろがって、光のなかの薔薇窓は神秘に酔いしれて、いちだんとまばゆくきらめいた。十六年目のノートル・ダムは、もったいないほど美しかった。》
東京で大学生だったころ、ヒルデブラント神父の「教会建築史」がいちばんの愉しい講義で、いつか自分もヨーロッパに行って、ゴシックのカテドラルをたずねて歩こう、と思ったとあかされる。
パリ留学の望みが思いがけなく叶って、セーヌ河畔の大聖堂のまえに立ったのは。一九五三年の八月も半ばすぎたころだった。初めてパリで迎えた朝、早い時間に寮を出て、大聖堂をめざした。
《それまで自分のなかではぐくみそだててきた夢幻のカテドラルと、目のまえに大きくそびえわだかまる現実のカテドラルとが、きらきらとふるえる朝の光のなかで、たがいに呼びあい、求めあって、私の内部でひとつに重なった。腕に鳥肌がたったのは、あきらかに冷たい空気のせいだけではなかった。
その日から、それはたいてい、よろこびではなくて、悲しいこと、がまんできないことのほうがだんぜん多かったのだが、自分ひとりで持ちきれない荷が肩にのしかかるのを感じると、私はその重さを測りに橋をわたってノートル・ダムに出かけた。》
大聖堂がようやく自分にとって日常の風景になろうとしていた一年後(一九五四年)の六月の半ば、高校生と大学生をまじえた三万人のパリの学生のシャルトル大聖堂への巡礼に、父がフランス人、母が中国人で、ヴェトナム育ちのモニックにさそわれて、参加した時のことだ。二十世紀の教会史に大きな足跡をのこした詩人、シャルル・ペギイが呼びかけたシャルトルへの巡礼にならったもので、ペギイに流れを発したフランスのカトリック左派のデマゴジックな表現のひとつでもあった。《日本での学生時代にその運動の輪郭を手さぐりしていた私は、この巡礼に参加することで、いよいよ本物の「象」の表情ぐらいは摑めるかも知れないと期待は大きかった》とあるように、日本での学生時代からキリスト教左派の運動に関心を寄せていた「私」の姿が大きく前面にでてくる。つらく、重い希求とともに。
《はじめてのヨーロッパは、日本で予想していたよりずっときびしかった。言葉の壁はもちろん私を苦しめたが、それよりも根本的なのは、この国の人たちのものの考え方の文法のようなものへの手がかりがつかめないことだった。自分とおなじくらいの年齢で、自分に似た知的な問題をかかえているフランス人との対話が、いや、対話だけでなく、出会いさえが、パリの自分にはまったく拒まれているように思えて、私はいらだっていた。大学での比較文学の講義の愉しみとはべつに、こればかりは自分の手でさぐりあてなければ、どうしようもない。シャルトルへの巡礼は、そんな気持のなかで、ひとつの抜け道になるかも知れなかった。》
パリ大司教のミサと、ドミニコ会の司祭の説教のあと、五十キロ先のランブイエまで列車で行き、翌朝、シャルトルまでの三十キロの道を歩きだす。歩きながら、そのときどきにあたえられたテーマ、どういう選択をしてここにいるのか、キリスト者は自分たちにとって、どんな意味をもっているか、を討論するが、自分のフランス語ではとても討論にはついていけないことに気づいた。いつのまにかみんなの議論からは遠いことを考えて歩いていた。
東京で大学院にいたころ、ふたりのカトリックの女ともだちと毎日のように話しあった。話題はいつも、女が女らしさや人格を犠牲にしないで学問をつづけていくには、あるいは結婚だけを目標にしないで社会で生きていくには、いったいどうすればいいのかということに行きついた。はやく嫁に行け、いやなら修道院にはいればいい、と先輩に言われても、そんなんじゃないという気がした。《自分で道をつくっていくのでなかったら、なんにもならない。そのころ読んだ、サン=テグジュペリの文章が私を揺りうごかした。「自分がカテドラルを建てる人間にならなければ、意味がない。できあがったカテドラルのなかに、ぬくぬくと自分の席を得ようとする人間になってはだめだ」シャルトルへの道で、私は自分のカテドラルのことを考え、そして東京にいるふたりの友人はどうしているだろうと思った。》
含羞の人、須賀敦子にしては、生で直接的な言葉が飛び跳ねているのは、パリ留学時代の経験がそれだけ、つらく、重かったことの反動だったのだろう。
ピクニックとお祭り騒ぎが一緒になったような巡礼の夜は、農家の納屋の乾草の山にもぐりこんで寝た。二日目には、南仏や、ノルマンディからのグループも合流してくる。三時を過ぎたころ、なだらかな地平線に、針のような尖塔のてっぺんが、見えてきて、一歩、一歩、シャルトルに近づいて行った。驚いたことに、私たちのグループがシャルトルに着いたときには、ミサはもうはじまっていて、カテドラルはすでに超満員で、扉の外にいるしかなかった。やっとシャルトルまで来たというのに、大聖堂に入れてもらえないとは、いったいどういうことなのだろう。天井の音楽のように美しいといわれるステンド・グラスも見られない。帰りの列車に乗りはぐれてしまうので駅に行こうと決めたとき、聖者たちの像を熱心に見ていたモニックが、長いひげを波のようになびかせ、口をすこしあけて、ほとほと弱ったという表情で、壁のくぼみに立っている洗礼者ヨハネ像を見つけ、気落ちして口をきく気もしない私を元気づけるように、「あの顔が、いまの私たちには、なによりもぴったりよねえ」と明るい声で言った。ヨハネは苦行しながらキリストが世に出るのを待ちわびたという。
《考えようによってヨハネは、生きることの成果ではなくて、そのプロセスだけに熱を燃やした人間という気がしないでもない。
二日間、歩きつづけて大聖堂に入れなかった仲間たちといっしょに、駅への暗い坂道をおりていきながら、私は、待ちあぐねただけの聖者というのもわるくない、と思っていた。》
さきに、ヒルデブラント神父の「教会建築史」がいちばんの愉しい講義で、いつか自分もヨーロッパに行って、ゴシックのカテドラルをたずねて歩こう、と思ったというところがあった。なるほど、そこに書かれたカテドラルの詩学をもって須賀の作品は、いわば建築されるように書かれたと気づくのはそう難しいことではない。須賀の精神、および職人気質的な作品の構造と文体と装飾の堅固な土台になっているので、長くなるが引用したい。
《スライド写真で見たフランスやドイツのゴシックの教会建築が、激しい力で私を捉え、ヨーロッパをつくりあげた精神や思考の構造の整然とした複雑さに私は魅せられ、すっぽりのめりこんだ。日本人の自分にとってなじみのうすい石という素材を。まるで重量をもたない物体のように、縦横に使って組み立てていく。いくつもの層を重ねていきながら、底によこたわる思索の流れをすこしずつずらしていくことの愉楽。あるいは、繰り返しの遊びへの誘惑。威厳にみちた王たち、ながい髪を足までたらした聖女たち、悲しげな表情でキリストの降誕を待ちわびる旧約の聖者たちがいならぶ彫像のギャラリー。華麗であるだけの、繊細な柱廊のミニアチュア。ひとつひとつの秘密をさぐりたくて、私は図書室にこもり、大聖堂のファサードの写真を何日もかかって鉛筆で模写した。かたちを手でたどることによって、これを造った人たちの感覚が身につたわるかも知れない。なにがこんなに自分を駆りたてているのか、自分にもさっぱり摑めないまま、私はカテドラルの詩学を自分なりの方法で理解しようとした。線をヴォリュームに、平面を重みに変えるとは、いったいどういうことなのか。石で模様をつくるとは。このようなカテドラルをもった中世とはどんな時代だったのか。ひとびとはどんなことを考えていたのか。なにを信じてこんなものを造ったのか。そして、自分の目で見たとき、これらの建造物は、いったい、どんな力で迫ってくるものなのか。手で触ったら、どんな質感を伝えてくるのか。いつかきっと、自分もヨーロッパに行って、ゴシックのカテドラルをたずねて歩こう。ファサードを、内部空間の緊張を外から支えるというアルク。ブゥタン(飛び梁)を、人の手で切り出され、運ばれ、積み重ねられた石を、製法が職人といっしょに絶えてしまったというステンド・グラスの青を、どうしても自分の手でふれ、自分の目でたしかめなければ、その先のことがなにも見えないと思いこむほど、カテドラルが私を捉えた。》
<『レーニ街の家』/『白い方丈』>
これら二作は小説として差しだされれば何の不思議も抱かないだろう。どちらも、登場する「私」は補助線にすぎない。しかし、二作の性格はだいぶ異なる。『レーニ街の家』はフィレンツェとミラノを舞台にしている。『白い方丈』は京都が舞台である。舞台の違いによる以上に、『レーニ街の家』では、イタリアの小説家アルベルト・モラヴィアのような西洋小説を書いてみせ、『白い方丈』では谷崎か川端のような日本の小説(ものがたり)を書いてみせている。
『レーニ街の家』のあら筋を紹介しよう。
《その夏、私は、期日までに済ませなければならない仕事もなく、いつもよりはゆとりのある休暇をすごしたくて、フィレンツェに行くことを思いついた。》 東京に帰って十五年、ずっと働きづめだった私は、知人の紹介でフィレンツェのアパートメントを八月いっぱいの約束で借りることができ、時計の存在を忘れたような気ままいっぱいの毎日をおくっていた。そんなある日、十年来親しくしていた女ともだちのラウレッタと大聖堂のまえで待合せ、かねて探していた、手で刺繍したリネンの手拭きを求めてふたりで専門店をまわったが見つからない。あと一軒だけまわってみようと中央駅に通じる人通りの多い道を歩いていると、声をかけられた。十五年以上もまえ、ミラノにいたころ親しくつきあっていた友人のカロラ・ディ・フィディオだった。彼女とひんぱんに往き来していたのは、私が夫を亡くして、暗闇しか見えないような時期だった。都心をはずれたレーニ街の、神経質な夫のグイード、小さなふたりの娘たち。ミラノの音楽院で勉強しているルイーザのヴァイオリンのレッスンに通ってきたところだという。カロラのうしろには、黒いちぢれ髪を肩のあたりまでのばした。色白で華奢なからだつきの美しい少女が、まるでおこっているように、とがった目つきでこちらを見ていた。会えてよかったわ、ミラノにもう来ないの、そうたずねるカロラに、あんなによくしてくれたのにミラノを離れてから手紙一本書いていない私は、ことばをにごした。あのころのことを思い出すのがいやだから、とまでは説明しなかった。「それで、キアラは元気なの。」「キアラはね、死んだの。」 カロラはもういちどにっこりしようとしたが、くちもとがゆがんだ。目だけが必死に笑おうとしていた。「事故だったの?」「病気。それからね、わたし、グイードとも別れちゃったのよ」 こんどはほんとうに彼女の顔がゆがんだ。「ごめん。おそくなるから、もう行くね。さよなら」 それだけだった。そそくさと抱擁をかわすと、彼女のおくれ毛の感触が頬にのこった。手拭きはけっきょく見つからず、ラウレッタとも別れて、アルノの河沿いの道をゆっくりと歩いた。キアラがいなくなったことで、カロラとグイードの結婚がだめになったのは、ごく自然な成行きのような気がしないではなかった。
カロラは画家、グイードは彫刻家で、美術学校時代の同級生だった。夫とふたりで、はじめてカロラたちの一戸建てに招かれたのは寒い冬の夜で、キアラが七歳ぐらい、ルイーザが二、三歳だった。グイードは南のプリア地方出身で、政治的なことばをふんだんに織りこんでしゃべるグイードが食卓ではいばっていて、ルイーザが金きり声をあげると、グイードがカロラをにらんで、どうにかならないのか、と低い声でなじった。若い芸術家にしては、オリーブ農夫が題材のネオ・レアリズム的な作風だった。たずねると、おやじさんだとつぶやいた。きみたち北の人間にはわかりっこないよ、という言葉の苦々しさが、アトリエの裸電球の下で、黒い目と黒い髪の暗さをいっそう濃くしていた。今でも部屋に飾って大切にしているのは、イデオロギーの露出過多といった彫刻作品にくらべて、骨太な、彫刻家らしい立体性のある、子供がふたり描かれたデッサンだった。ふたりの女の子のうち、ヴェネツィアの名家に生まれ、ブロンドで背が高い、のんびり屋のカロラに似ているのは、おっとりしたブロンドのキアラのほうで、黒い髪のルイーザは、癇がつよくて気むずかしく、やきもちやきのところまでグイードに似ていた。
夫が死んだあとも、散歩の感覚で行ける距離にあったこともあって、よく出かけた。彼らの家の居心地よさは、ものごとを理詰めにしない、口数のすくないカロラのゆったりした性格ゆえだった。
ある日、夕食にいらっしゃい、と電話があって、その時間に行ってみると、カロラの姿がみえない。ピアノを弾いているとキアラが胸をはっていった。ピアノ上手なの、ママは。いまでも気分がくしゃくしゃすると、ママはピアノを弾くの。その夜、夕食にありついたのは、ニワトリがなかなか煮えなかったために二時間はすぎてからで、でも彼女がお米をぶちこんでつくったリゾットはおいしくて、パン切れをしゃぶっているうちに眠りこんでしまったルイーザも、ほっぺたに涙のあとをつけたまま、大きすぎるスプーンを口に運びはじめた。もうそのころから政治運動に巻き込まれてうわの空だったグイードは食事に帰らないことが多くて、カロラは、いいのよ、あのひとは、アトリエで寝るんだから、とあきらめる表情をした。
八月の午後の街を二時間以上も歩きつづけ、サンタ・クローチェ教会まえの広場のベンチで休むことにすると、鳩の群れを、すそいっぱいにフリルのついた、目のさめるようなピンクのよそゆきを着た、髪の黒い、二歳ぐらいの女の子が、まるで雪かきでもするような格好で追いかけてくる。おどろいた鳩がいっせいにとびたつと、広場のすみのベンチにいる、母親らしい、黒いもめんのスカートに洗いざらしのTシャツを着た、くたびれた表情の女の顔をみてべそをかく、というのをくりかえしている。ぎっしり中味のつまった紙の袋を三つほど乗せた買物用カートをベンチに立てかけた女はときどき広場に通じる細い道に目をやっている。あわてていたせいで、カロラにキアラの死についてくわしくたずねなかったことを悔やんでいた。持病だった糖尿病が悪化したのだろうか。あたし、自分で注射できるの。あっけらかんと自慢するキアラの声が聞こえてきそうだった。グイードは、この娘のなかに知り合ったころのカロラを想い描いているのではないかと考えてしまうほど大切にしていた。そのキアラが死んだいま、グイードがカロラと別れるのは、当然の結末なのだろうとも思えたし、もうすこしカロラが辛抱できなかったのかという気もした。グイードは、いったいどこでなにをしているのだろう。太陽がかたむいて、広場に直接光が射さなくなったころ、肌のあさぐろい、痩せた、上背のある男が、十二、三ぐらいに見える半ズボンをはいた男の子を連れて広場にやってきた。男の子は両手に、いっぱいにつまった紙袋を持ち、父親らしい男は、ファイバー製の大きなスーツケースと、ロープでしばった重そうなボール箱を提げている。ベンチのまわりは、そのまま、まずしげな家の内部といってよかった。日焼けした男の顔や黒い髪から考えると、南イタリアから仕事をもとめて出て来た人たちなのだろうか。《光が徐々にうすらいでいくサンタ・クローチェの広場で、女の子のピンクの晴れ着だけが、ひらひらと舞っていた。》
ラスト・シーンの「女の子のピンクの晴れ着だけが、ひらひらと舞っていた」の文章だけからでもわかるように叙情性にすぐれた文章である。だが、それだけにとどまることなく、イタリアの南北問題、貧困、階級、夫婦とふたりの娘という家族の愛情関係の線と密度と距離感、喪失、苦さが、薄明かりの下、明快なプロットをもって、醒めたリアリズムといきいきした会話で描かれている。
次の『白い方丈』は、いかにも、よくできた「ものがたり」で、語りくちのうまさが魅力となっている。ひらがなこそ多用していないけれど、谷崎潤一郎『蘆刈』を想わす息の長いやわらかな文体は幻想的で、禅寺の方丈の老師の時の流れを忘れ去った全宇宙を内在しているような存在そのものや、禅問答のような会話の受け応え、夢なのか現なのか、理解しようとする不条理な想像力を感じとるには原文を読むしかないので、ところどころ、そっくり引用する。
京都の竹野よし子という聞いたことのない名の人から手紙をもらったのは、そろそろミラノの生活にも慣れてきた一九六〇年代の半ばごろだった。手紙の主は、私が数年まえにローマで知りあった商社員の名のKをあげ、戦前、伏見ではちょっと知られた造り酒屋だった実家に大学生のKさんが下宿していたので、と前置きしてから、手紙はこう結ばれていた。「じつは私、近々、そちらに行くことになるかもしれなくて心細く思っていましたところ、あなた様というお方がミラノにお住いとうかがい、いろいろとおたずねしたり、おねがいしたいことがございます。もしや、近々、日本にお帰りになるようなことがおありではございませんか。その節はどうぞどうぞおしらせいだきとうございます」 まるで谷崎の小説のなかから届いたような風情もあって、書き手である竹野夫人という人について、好奇心があおられた。谷崎の小説、と思ったのは、まったくの的外れではなかった。追うように、Kさんから手紙がとどいた。勝手に住所を教えたことをあやまったあと、夫人についての簡単な紹介をそえていた。伏見では名のとおった造り酒屋の跡とり娘で、親が選んだ滋賀の在の旧家の三男坊と、はたちになったばかりで結婚させられたが、平凡な夫とのあいだには子供はなく、戦後しばらくして、ちやほやしてくれた両親が亡くなると、自分の生活が空虚にみえて、心のやり場がない、適当に相手になってあげてください、未知の都会にいるあなたを想像して、子供みたいに愉しんでいるのです。
ちょうどその年の秋に、日本に帰る予定を竹野夫人に知らせると、その節は京都をご案内したいと返事があった。帰国して、父に話すと、自分の車を運転手ともども貸してやるから、と勝手に決めてしまった。
伏見の竹野家は、近所でひときわ目立つ黒く塗った門をもち、入ると農家の庭先のような、白砂を敷きつめた空間で、そのむこうの左半分が高いところに窓のある酒蔵で、右手の板塀で仕切られた中がこれといって特徴のない木造の和風建築だった。男衆だろうか老人が出てきて、名を告げると、へえ、お待ちでございますとだけいって、ひっこんでしまったが、ひっそりとして、この家にはだれも住んでいないのではないかと思えるほどだった。かなり経ってから、竹野夫人があらわれた。年格好は私より十ほど多い四十台の半ばぐらい、お召とはいってもかなりくたびれた着物すがたで、足もとの白足袋もきれいにつくろってあったけれど、洗いざらしだった。髪はひっつめて結っていて、女学校出のインテリふうだったが、ととのった面長の顔立ちだが、片方の目がかなり強度の斜視なのが表情を暗くしていて、戦争中に結核をわずらって死んだ父の妹を思い出した。
夫人は大座敷に招じいれ、手早く薄茶を立てながら、自分がミラノに行くことになったいきさつを話しはじめた。ミラノの若いおじょうさんが、だれか禅の話をしに、イタリアに来てくれるような人を知らないか、と探していて、Kさんが、私にたのんで来られたのだと言う。うちのお寺の老師さんにと申されて、有名な禅宗の寺の名を口にした。それにしても、このいっぷう変った計画の仕掛人になりたがっている、ミラノの若いおじょうさんというのは、いったいだれのことだろう、格式のある禅寺の老師を竹野夫人といっしょに招待するというからには、かなりな財力がある人にちがいない、という私の疑問を察したのか、夫人がするりと答えてくれた。「ティルデさん、そのおじょうさんは、ティルデ・ドネリさんというお方どす。」 名を聞いて、私はおどろいて夫人の顔を見つめた。ティルデはローマにいたころ、大使館のレセプションなどでなんども会ったことのある女性だった。年齢は夫人とほとんどおなじくらいで、物事をいったん思いこむとゆずらない頑固なところがあって、人に好かれるというたちではなかった。日本の男性、とくに外交官となると、人をえらばずに好きになり、ひどく癇のつよい性格で、気に入らないことがあると、人前だろうとかまわずに泣きわめくというような噂があって、大使館員たちは慇懃に敬遠していた。のめりこまないほうがいい、と私は言いたかった。他人のことを考えて行動するような人柄とはとても思えなかった。全額負担の招待など、話がうますぎて、うさんくさかったし、長年イタリア人とつきあった経験が、実現する種類の話ではないとささやいていた。それをいま説明したところで、夫人は耳をかたむけないだろう。この人にとって大切なのは、この話が信頼できるものかどうかではなくて、自分が決めたことを、強引に実現にもっていくことなのだ。お点前がすんでほっとしたところで、竹野夫人が、当尾(とうのお)の浄瑠璃寺まで足をのばしてはどうだろうと、提案した、せっかく、お父さまのお車でおいでやしたんどす、すこし遠出をしてみてはいかがどすやろ。辺鄙なところ、と聞くと、その寺をみたくなったので、夫人にすべてをまかせることにした。夫人は、ちょっと用意がありますので、しばらくお待ちくださいますか、と座敷から出ていった。いまさらのように、まるで池の底にいるようなしずかさが気になった。お待たせして、とふたたび姿をあらわした夫人は、さっきと同じ着物、足袋もふだんのままだった。来週には、丹波から杜氏が到着する、仕込みのあいだは気苦労が多くて心配ばっかりといって胸もとに手をあてて軽く叩いた。車に乗り込むとき、運転手が彼女に、おっしゃったように、お荷物はトランクに入れました、と言うのをなにげなく聞きながしたが、その「荷物」があの風がわりな昼食につながろうとは思ってもみなかった。
竹野夫人は、鄙びた浄瑠璃寺のこれも時の流れに忘れられたような池の端に立つと、しばらくあちこち見まわしていたが、やがて岬のようにまるく水際につきだした場所をえらぶと、手ばやく雛まつりのような緋もうせんを敷いてその上に私をすわらせ、自分も腰をおろした。紅葉のさかりをすぎた楓のまばらな枝のあいだから見上げると、淡い水色の空に白い雲がとぎれとぎれに走っていた。木の根が張っていて地面がでこぼこなうえに、池にむかってゆるく傾斜していたから、すわり心地はよくなかったが、せめてその感触が私を現実につなぎとめていたのかも知れない。山あいの空気は、もう冬の棘をふくんでいて、私は、軽いウール地のジャケットの下で肩をすぼめていた。奈良や京都市内の名所ならともかく、山ふかいここ当尾のあたりまで足をのばす人はめったになかったのか、あたりはしんとしずまりかえっていて、色とりどりの落葉が浮かぶ緑青(ろくしょう)色に濁った水面に、ときどき浮かび上がってはぷつんとはじける泡の音が聞えそうだった、緋もうせんの上には、ふたり分のおべんとうにちょうどよい大きさの、みごとな蒔絵の三段がさねのお重がひろげられ、その段のひとつひとつには、ていねいに面取りをした目のさめるような赤さの京人参や小芋や椎茸や湯葉、高野豆腐などのお煮しめ、みりんで照りつけ、梅酢漬けのはじかみ生姜をそえた甘鯛の西京漬け、ふんわりとレモン色に焼きあげた出し巻などが配色よくつめられ、三の重には、あの関西ふうの、黒ごまをふった指先ほどの小さい俵形のおにぎりの白が、正午をすぎたばかりの秋の陽をうけて、つやつやと光っていた。
「つめとおすけど、こんなん召しあがりますかしら。うちの蔵のをすこしだけ持ってまいりました」
そう言って竹野夫人が、赤い縮緬の袱紗につつんだ、ぱちんと閉まる小さなふたのついた錫の銚子を取り出して冷酒をすすめるのを、私は夢のなかの出来事のように、ぼんやりと眺めていた。》
有名な九体仏を見て、浄瑠璃寺をあとにし、老師のいる今日の禅寺にむかった。勝手を知りつくしたという感じの竹野夫人のあとから、黒光りのするつめたい廊下を何回も曲り、渡り廊下をこえ、部屋のひとつの、ふすまのそとで立ち止まった。夫人が声をかけると、中から、おう、というような返事がきこえた。
《夫人がゆっくりふすまをあけると、六畳ほどだろうか、日本間にしては変則的に横長な部屋のなかには、障子ごしに射しこむ白い陽光が洪水のようにあふれていて、その奥に、黒い、ちろちろと燃える燠のようによく動く老人の目が、白い羽二重のふとんをかけた炬燵のむこうから、さぐるようにこっちを見ていた。小柄な体を包んだ着物も白の羽二重で、まるで、ときならぬ雪景色のなかに迷いこんだようである。袖口からにゅっと突き出した、手首の骨がまるく盛り上った白い手が、炬燵の上に行儀よくそろえておかれている。
初対面の挨拶をする私を見て、老師さんはあはは、というように、歯のない口をあけて笑ったかと思うと、まるで古くからの友人に対しているような、気易い声で言った。
「あんたか」
「はい」
つられて笑いながら答えると、老師さんは、愉快そうに私をにらんでから、炬燵の上に頭をさげて見せた。
「なんやら、ご厄介になるようだな」》
八十をすぎた老師の小さなからだから出る、精力にあふれた笑い声に圧倒されて、私は、竹野夫人といっしょに、白い陽光にあふれた方丈を辞去した。
ミラノに帰って一年が経ったが、なんの音沙汰もなかった。周囲の知人に、日本から老師が禅につて講演する話を聞いたことがあるかと訊ねてみたが、だれもがきょとんとしていた。夢を見ていたのかと思うほどに遠いことに思えはじめたある日、竹野夫人から手紙が来て、ティルデさんからなかなかはっきりした返事が来ないと思っていたら、先週、ふいに手紙が来て、いったん白紙にもどしてほしいといってきたのだけれど、どうしてとつぜん中止になるのか、手紙に書いてきた理由が納得できないので、私の意見をうかがいたく、筆をとった、ということだった。それによると、ティルデは日本の若い留学生と恋をして、家族の大反対にあい、老いた両親は、娘をドイツの女子修道院に二、三年のあいだ、閉じこめることに決めてしまった、というのである。ティルデの話はとてもほんとうとは考えられません、と私はすぐに返事を書いた。ティルデの精神状態が正常でないからとまで書いて、ぜんぶのイタリア人が彼女みたいではない、例外です、とイタリアを擁護したがっている自分が滑稽でもあった。
夫が死んで二か月後に、こんどは母が大病をして一時、日本に帰っていた。何週間も母の危篤状態はつづいて、疲労の極にあった。ある晩のこと、電話が鳴って、私が出た。もしもし、もしもし、と聞きなれない声が呼びつづけ、もしもしというばかりでいやになって、受話器を置こうとしたとたん、相手の声がとびこんできた。「こちらは伏見の竹野と申しますが」「今朝の新聞で、あつこさんが日本文学の翻訳について書かれたエッセイを読ませていただいて、ご主人をなくされたことを知りましたが、ほんとうでございますか」「はい」 そう返事をしておいてから、私はいそいでつけくわえた。「ほんとうです、私、本人でございますが」「あっ」と小さな叫び声が受話器のむこうで聞こえたかと思うと、電話はぷっつり切れた。その後も、電話はかかってこなかった。どうして、なにも言わないで電話を切ってしまったのか、ずっとあとになっても、理解できなくて、気がめいることがあった。
《もしかしたら、電話に出た私が、本人ですと答えたあの瞬間まで、私は夫人の空想のなかでだけ生きつづけた、うつつを離れた存在にすぎなかったのではないか。遠い外国の都会に住む私という人間のイメージから芽が出て葉をしげらせ、枝がつぼみをむすんで、いくつかの物語が彼女のなかでつぎつぎと花をひらかせた。たとえば、あの夢のような浄瑠璃寺への遠出。彼女にとっておあつらえむきなことに、私までが父からの贈物やらぴかぴかのメルセデス・ベンツやらお抱え運転手という時代ばなれした小道具にかこまれて登場したものだから、夫人は完全に現実から遊離してしまう。彼女がおさないころ両親に連れられて観た南座の芝居の一場面を、あるいはかつて両親と遊んだ幸福にみちた紅葉狩りの場面を、私をなかに入れて再現してみたかったのではなかったか。青い池の水を顔に反射させて、黙々とお煮しめを口にはこぶ夫人の顔が目に浮かんだ。》
そして、ミラノの美女、スフォルツェ城の近辺に住むティルデの物語が、夫人の夢をいやがうえにもかきたてたのだろう。夫人からのサインを彼女は敏感に受けとめて、禅の講義やミラノへの招待やらを発信し、ゲームをもりあがらせる。ディルデのドイツ修道院にとじこめられるという中世めいた物語は、京都製といった感じが濃厚な気もした。空想やら嘘や虚構が入りまじった果てに、私の夫が亡くなったと知り、お悔やみの電話をかけることにした。ところが、家族のだれかれではなく、ミラノにいるはずの私が電話口に出て、いきなり本人だと名のった。
《竹野夫人のゲームの軽やかな進行にとって、死の事実はどうみても重すぎる現実にちがいない。それまで快適にふくらんでいた夫人の想像の風船が、ナマの私の声を聞いた瞬間、パチン、と小さな音をたてて破れた。
「あはは」
老師さんの笑い声が白い方丈にひびくのが、遠い廊下のむこうから聞えてきそうだった。》
<『カティアが歩いた道』/キリスト者>
この本のなかで、もっともエッセイらしい作品かもしれない。回想形式ではないが、パリ留学時代から、書かれた現在に近い時点までの、三十年以上の時をへだてての静かな再会の物語となっているとはいえ、須賀の内面の関心にもっとも近かった問題、「よりよく生きること」と「深さ」のテーマが扱われている。キリスト教に関係して、エディット・シュタインについて多くのページがさかれ、シモーヌ・ヴェイユやトマス・アクイナス(「アクイナスのトマ」)の名も見える。キリスト者としての自分の立ち位置と、生き方という課題が、カティアを鏡にして、「歩くこと」を象徴に語らせつつも、街角の心象風景と労働司祭による講義の場面とともに、思想の言葉がストレートに文字となっている。
前の年の夏にパリ、ベルナルダン街の寮に来て、七ヶ月のあいだに、せせこましく混みあった部屋のルームメイトは日本人のユキ、フランス人のカトリーヌ、ギリシア人のエレーヌとめまぐるしく替った。こんどはドイツのアーヘンから来た、子供みたいに赤く上気した、丸い、しもぶくれの顔の、学生というよりは、元気なパン屋のおばさんという感じだったから、ひとまずはほっとした。「カティア・ミュラーです。たぶん、秋までパリにいるつもり」 ブロンドの長い髪のカティアの登場の仕方と、ささいな挙動で垣間見せる性格描写はたくみだ。
ゆっくり本を読んだり、人生について真剣に考える時間がほしかったので、アーヘンの公立中学校の先生をやめてしまってフランスに来た、と言う。しばらくパリに滞在して、宗教とか、哲学とか、自分がそんなことにどうかかわるべきかを知りたい。いまここでゆっくり考えておかないと、うっかり人生がすぎてしまうようでこわくなったのよ。いきなり本題に突入したようだった。あの戦争をした私の国の人たちのものの考え方には、ついていけない事柄が多すぎるから、国をはなれたほうがいいと思った、と言う。十二、三歳うえ、そろそろ四十に手のとどく年頃らしかった。《戦争のなかで育って、「お上」がつくった「当局の方針」という人生のプログラムに知らず知らずのうちに組み込まれていた私の世代にくらべて、彼女たちには、戦争についてのなんらかの意見や選択の余地があったはずで、それだけに、苦しみも大きかったかも知れないのだが、戦争の年月をこの人はいったいどこですごしたのだろうか。ドイツを覆ったあの狂気とはどのように対決したのだろうか。それとも、私たちの大半がそうであったように、無力な沈黙を強いられていたのか。》 作者には珍しく、あの戦争についての意見が口にされている、自分の国への批判精神と、ドイツの人びとへの精神的な探求をもって。
同じ部屋に暮らしてみると、カティアは手ごたえのある同居人だった。《なによりも、自分だけの人生をもとめて故国をはなれ、一歩一歩手さぐりしながら歩いている彼女に、深い共感をおぼえた。おなじような感慨がカティアの側にあることも、おおよそ知れた。》
カティアは「歩き靴」を持っていた。重たそうな革の、底の厚い編み上げ靴は、見とれるほどに、堂々としたりっぱなものだった。《あるまぶしさのようなものを覚えたのは、それが、歩くことを通して子供たちに土地のつながりの感覚をおぼえさせるという、ヨーロッパの人間が何世紀にもわたって大事にしてきた、文化の伝統の一端をまざまざと象徴しているように思えたからだった。》 「歩くこと」のテーマが、須賀らしく具体的な「物」を手がかりに語られてゆく。そのころ、私は自分にとって異質なこの街の思想や歴史を、歩くことによって、じわじわとからだのなかに浸みこませようとするみたいに、勉強のひまをみては、地図を片手に、よくパリの街を歩いた。詩人ネルヴァルが首をつって自殺したのは、このあたりだという、サン・ジャックの塔のそばを、つめたい雨の夜に通りすぎることもあった。
カティアはほとんどいつも、夏までにエディット・シュタインの著作五巻を読破するのだといって、ぶあつい哲学書を読みふけっていた。一八九一年に、東部ドイツのユダヤ人の家庭に生まれたシュタインは、ゲッティンゲンやフライブルク大学で哲学をおさめ、現象学のフッサールの助手をつとめるなどしたが、三十歳のとき、カトリックの洗礼をうけて高校の教諭になった。ナチスによるユダヤ人迫害がはじまると、同胞の救済を祈るために、カルメル会の修道女として生涯を捧げようと決心するが、迫害が波及しそうなのを知って、オランダの修道院に身をかくすも、ドイツ軍のオランダ侵攻とともに秘密警察に捕らえられ、一九四二年にアウシュヴィッツのガス室で死をむかえた。五〇年代初頭に、シュタインの著作集がミュンヘンで刊行されると、高い学識と深い思索に裏づけられた劇的な生涯は、感動をもって内外のキリスト教徒に迎えられた。《彼女の名声が、カトリックの神学を現象学の立場から解釈しようとした哲学者としてよりも、ユダヤ人でありながらキリスト教をえらび、それでもなお、ユダヤの血をうけているために死ななければならなかったという悲劇性によって増幅された事実は、否定できない。やはりユダヤ人でキリスト教を求め、戦争中に病死したフランスの思想家シモーヌ・ヴェイユのデマゴーグ性には欠けるかも知れないけれど、非キリスト教世界にむかって教会の門が開かれることを切実に望んでいた一部のキリスト教徒にとっては、シュタインも、時の流れを象徴するひとつの重い存在だった。》
カティアがシュタインについて興味をもつようになったのは、靴なおしをしている女性の影響で、その人はもとシュタインとおなじ修道院にいたのだけれども、彼女があんなふうにして死んだあと、修道院の生活が無力におもえて、ふつうの人間の暮しをしながら、深い精神生活を生きられないかと、修道院を出たのだという。その人がカティアに、シュタインの本をおしえ、南フランスでおなじような生き方をしているグループの人びとを紹介してくれた。でも、私はまず、まっすぐに南仏には行かないで、ここでしばらく本を読みながら、自分の人生についてゆっくり考えてみたいと思ったの。須賀にとって、カティアを語ることは、シュタインを語ることでもあり、そしてまた自分を語ることへ螺旋のように戻ってくることでもあった。
《きょうは、何巻目を読み終る予定だといって、にこにこしているカティアの顔を見ると、私はなにかしなければとあせった。ヨーロッパに来たのは、文学の勉強をするためだけではないはずだった。戦後の混乱のなかで両親の反対をおして選びとったキリスト教を、自分のこれからの人生のなかでどのように位置づけるのか、また、ヨーロッパの女性が社会とどのようにかかわって生きるのか、学問以外にも知りたいことは山のようにあった。》
けっきょく、カトリック信者、ミッションの人、須賀敦子は「戦後の混乱のなかで両親の反対をおして選びとったキリスト教」のいきさつと内実をどこにも書き残さなかったのだが、そこには須賀の矜持、強い意志があるだろう。語らなかったが、その後、母も父も生前洗礼するのだから、須賀の説得力と生き方がどのようであったかは想像しうる。
毎週金曜日の夜、フォーブル・サン・ジャック街のドミニコ会修道院で、労働司祭がミサをおこなっていて、そのあと旧約聖書の勉強会があると、寮で学生の世話をしているシュザンヌが教えてくれた。行ってみたら、なにか、あなたの探しているものが見つかるかも知れないし、だれか話のできる人に会えるかも知れない。
ここからはシンパシーと落胆、あせりと寂寥にみちている。昼間は工場などで働き、余暇の時間に司祭の責務をはたすという、戦時の対独レジスタンスから生まれ、戦後、欧米各国にひろまった労働司祭の運動が、ローマの教会当局の批判を浴びて全面的に禁止されたのは、ちょうどそのころだったが、ドミニコ会のおもだった神学者たちは、くじけることなく反抗的ともいえる立場をとっていた。そんな状況の中だったから、宗教的な意味をこえて、教会の方針に対する批判の行為でもあり、非合法的な政治集会に参加するのにも似た、ある精神の昂揚を感じて緊張した、とあるように立場を明示している。寮から目的地までの道のりを歩いていくことにしたが、迷ってはいないかと、なんども道の名を街燈の明りでたしかめ、足音が硬い石畳にはねかえるのを聞きながら、歩いたが、八時に出て、着いたのは九時を過ぎていた。よごれたシャツを着た労働司祭が、駅の待合室のように殺風景な部屋でひっそりとミサをあげていて、四、五人の参会者たちが石の床にひざまずいて祈っている。司祭が、今日の工場労働者をガリラヤのイエスのもとにあつまった群衆にたとえ、彼らの側に立つことの意味を説いた。《そして、なんの脈絡もなく、薔薇窓やステンド・グラスの華麗なカテドラルを造って、彼らの時代の歓喜にみちた信仰を美しいかたちで表現しようとした中世の職人たちのことが、こころに浮かんだ。》 ミサがすむと、聖書の講義があった。悲しみのなかで、神を信じつづけたヨブの歎きがその日のテーマだったが、科学的、歴史的方法を用いた講義は、従来の教会ばんざい式の感傷に流れない客観性に裏づけられていて、こころづよかった。寮から歩いてきた長い道の寒々とした暗さが、そのまま、人生のよろこびに見棄てられたヨブの悲しみに思えて、熱心にノートをとっている人たちをぼんやりと眺めていた。《帰りは地下鉄に乗ることにしたが、サン・ジャックという駅の名を見て、さっきミサのあった場所が、十三世紀の天才的神学者のアクイナスのトマが、ナポリからパリに来てソルボンヌで教えていたときに泊まっていた修道院に違いないことに気づいた。アリストテレス的な神学理論を展開して危険人物視されたトマは、これもイタリア人で、プラトン派の神学者だったボナヴェントゥラと、サン・ジャック街を夜っぴて行ったり来たりしながら論争したという話をどこかで読んだことがあった。彼らは、今夜会った労働司祭たちとはちがって、おそらく生気に溢れていたのだ。夜のミサには、その後、二、三度、通っただけでやめてしまった。》 須賀はトマス・アクイナスについても理解は深かった。
《一年近い時間をパリですごして、大学の硬直したアカデミズムに私は行きづまりを感じていた。教会のほうも、もっと新しい風潮にじかに触れられるかと期待していたのに、せいぜいがサン・ジャック街のミサぐらいだった。岩に爪を立てて登ろうとするのだが、爪が傷つくだけで、私はいつも同じところにいた。》
「歩き靴」といっしょにドイツから持ってきた、見るからに固そうな黒パンを朝食に食べていたカティアが、夏休みには、イタリアに行ってみようという考えにたどりついた私に、私もペルージャの外国人大学でイタリア語をならったことがあるからと、イタリア語の手ほどきをしてくれた。カティアにならった動詞活用のおかげで、ペルージャで初級をとばして、中級に編入されたが、夏休みが終ってパリに帰ると、カティアは旅に出たあとだった。だいぶ経ってから、絵はがきが南仏からとどいた。いつかあなたに話した、アーヘンの靴なおしをしている女性に紹介されたグループに自分は入ろうと考えている、と書いてあった。それきりカティアの音信はとだえた。
「まさかとは思いましたが、もしかすると先生のことかもしれないと思って」大学の廊下ですれちがった、フィリピンから帰ったばかりの若い同僚が言った、「そのドイツ人のおばさん、カティア・ミュラーっていうんです。ぼくのいた山の町の学校の校長先生です」 近辺の住民に尊敬されているそのドイツ人の先生は、南仏のミッションのグループからフィリピンに派遣されていて、パリでルームメイトだった日本人の「アツコ」にイタリア語を教えたことがあると聞いて、先生じゃないかと思ったんです。来週、ある国際機関に招かれてカティアが日本を訪問するという。予定がつまっている彼女の日本での最後の日の夕方、市ヶ谷の土手を、レセプションのあるホテルまで、東京の春を満喫してほしくて、歩いて送ることにした。
《透明な蜜を流したような四月の夕方だった。》 カティアの髪は銀髪になって、もう、七十をいくつかすぎている勘定だった。フィリピンで事故にあった後遺症だといって、杖をついているのが痛々しかったが、彼女の白いスニーカーを見て、「歩き靴」が記憶の底にちらついた。「桜なんて、ほんとうはどっちでもいいのよ」カティアがひくい声でいった。「あなたに会えただけで、私は満足しているの」 カティアは、杖をついていないほうの手を私の肩にまわした。むかしとおなじ、産毛におおわれた、まるい、肉のやわらかい、ずっしりと重い手だった。
《四谷に近い女子高の塀がつづくあたりまで来ると、塀のむこうに、赤い大きな太陽がゆっくりと、沈みはじめた。
「ずっとフィリピンにいるつもり?」
私がたずねると、カティアはふふっというように笑ってから、しずかな声でいった。
「神様のおぼしめしのまま、よ」
粗末なワイン・カラーのじゅうたんを敷いたせまい部屋の小さな机にむかって、むさぼるように哲学書に読みふけっていたカティアの姿が目に浮かんだ。会うまでは、あれも話そう、これもたずねようと思っていたのに、会ってみると、ベルナルダン街の部屋で向いあって朝食を食べていたときとおなじぐらい、なにも話すことがなかった。カティアはカティアなりの道を選んで、いまはやすらいでいる。》
足音が硬い石畳にはねかえるパリの対極のような、湿って、音のない、川端の小説のような美しくもせつない情景となるが、そこには会ってみると「なにも話すことがなかった」ふたりの、互いの歩いてきた道を認めあう何ものかがあって、幻影かもしれないが幸福のさくら色に染める。
《道がカーブになったあたりで土手に上ると、そこだけ樹木が密生していて、深い森に来たようだった。地面が湿っているのを敬遠してか、その辺りだけは花見客の姿が途だえ、紅白の幕もなかった。人影のない薄闇をとおして見ると、空気がさくら色に染まって、音のない音楽のなかを手さぐりで迷い歩いている気がした。地面に散り敷いた花が、あたりをぼんやり照らしている。
「もう時間がないわ」
かすれたようなカティアの声にわれにかえると、花に呆けた私がおかしいのか、目じりにしわをよせて、笑っている。ちっとも変っていないね。すっかりやさしい老女になった彼女は、そう言うと、さもおかしそうにくつくつと笑いつづけた。》
伝記批評をするつもりはないが、松山巌による年表(『須賀敦子全集、第八巻』)をみると、一九五三年の夏に須賀はパリに到着し、十一月、妹良子、結婚の記事のまえに、こんな記載がある。《この時期から、シャルル・ペギー、エマニュエル・ムニエなどの新しい神学をさらに学ぶ。シモーヌ・ヴェイユや、エディット・シュタイン、サン=テグジュベリの著作に親しむ。》 翌一九五四年四月には、聖週間に学生の団体旅行に参加し、ローマ、アッシジ、フィレンツェを訪れている。《四月末、冷たい雨の日の午後、アッシジへ行く。サクロ・コンヴェントの広場、サンタ・マリア・ミネルヴァ、サン・ルッフィーノなどを巡る。小さな聖キアラの庭に心を奪われる。夕刻にフィレンツェに向かう。》 三年後、パリから帰国後の一九五七年に、『アッシジでのこと』という一文を『聖心(みこころ)の使徒』に発表している。また、六月には、《シャルル・ペギーの呼びかけではじめられた、シャルトル大聖堂への学生巡礼に参加》とある。そして、七月には、ペルージャの外国人大学中級に入学し、九月末にはパリにもどったのは、この一篇のとおりであるが、同時期に並行して行われていた、エディット・シュタインを読むことと、イタリアのアッシジ訪問の件と、シャルトル巡礼の件は、見事なまでに、この一篇からは消えている。小説において、何を書くかはもちろん大切だが、何を書かないかも重要だという創作術を須賀はよく知っていた。それらを、このカティアをめぐる一連の文章に混ぜあわせれば、ドラマチックさは激減し、それ以上に、論理と感情の道筋は混乱するだろうから。シュタインはカティアだけに、イタリアはカティアにイタリア語を習って行くペルージャだけに集中させ、サン・ジャック街の労働司祭によるミサと講義は扱うがシャルトル巡礼には触れない、のが文学的効果を生む、それは嘘をつくことではなく、読者に深くとどくためである、と須賀はわかっていた。こうして考えてゆくと、カティアという存在自体が、須賀の思いを語らせるために、カティアという名前で造形された小説の人物ではないのか、すべてはフィクションではないか、あの『白い方丈』のような、とさえ思われてくる。そして、それが事実か勝手な妄想か、カティアは実在したのか、ロマネスクな人物なのか、約三十年後の春に彼女は日本を訪問し、桜咲く四谷の土手を須賀といっしょに散策したのか、といった伝記的事実を詮索することは、小説であろうがエッセイであろうが、思いを伝えることを第一義に考えるならば、必要ないのはもちろんのことである。
上記の『アッシジでのこと』から、ごく一部分だけ引用してみたい。若い須賀に決定的ともいえる影響を与え、次のイタリア留学の熾火になったに違いないアッシジ訪問が、硬く、息の短い、体言止めまである文体、回想の過去時制ではなく現在時制で断定されがちな、成熟していない文体ではあるけれども、カティアが見まもっていたパリの時間と比較して、熱く素直に語られているからだ。
《雨が降っていた。聖週間にパリをたち、御復活祭をローマにむかえてまもないころだった。ポルティウンコラに近い、アッシジの駅から、四キロへだてた丘のうえに、サクロ・コンヴェルトの印象的な、白い廻廊が、灰色の空を背に長くつらなってみえた。それが、私の、はじめてのアッシジだった。(中略)
サン・ルフィーノを出て、小さな坂道を降ると、サンタ・キアラに出る。この街にはめずらしい感じの、堂々としたゴチック建築。(略)旅行者の「私」は、いつの間にか、ややほんとうに近い「私」に席をゆずっていた。どうしてか私にはわからない。けれども私は、たしかに、サン・ダミアノには、今でも聖(サン)フランチェスカと聖(サン)キアラが、まだそっくりあの時のままの生活をふたりしてつづけているとしか思えない。(中略)
ふたりのよろこびは自らを包みきれなくなって、いわゆる、「聖キアラの庭」で昇華する。案内の若い修道士(フラテ)はうれしそうに云われた。ここで聖フランチェスカが太陽の讃歌をつくられたのだということです、と。
庭とは名ばかり、三方を高い石の壁にかこまれた一坪ほどの細長い空間である。(中略)
この小ささ、そしてこの豊けさ。一週間まえあとにしてきた勉強が、パリの美しさ全部が、私の頭の中で廻転しはじめ、淡い音をたてて消えてしまった。力づよい朝の陽光にたえられず、橙々色にしぼんでしまう月見草の花のように。講義、図書館、音楽会、展らん会、議論。私にとってあれはみな、幻影にしかすぎぬものなのではなかったのだろうか。私の現実は、ひょっとすると、このウムブリアの一隅の、小さな庭で、八百年もまえに、あのやさしい歌をうたった人につよくつながっているのではないだろうか。私も、うたわなければならぬのではないだろうか。
しばらくやんでいた雨が、またぱらつきはじめた。案内の修道士(フラテ)が、金魚の水溜りに浮んでいた二三枚の葉をとりのけてやりながらつぶやいた。雨だよ、たくさんあたっておたのしみ。(後略)》
<『旅のむこう』/ロラン・バルト>
母の両親の地、豊後竹田を汽車で通過する娘の新婚旅行のひとこまではじまり、その新婚旅行からミラノへ翌日に帰ってしまう母の歎きの声で閉じるこの一篇については、趣を変えて、あら筋ではなく、母の声を野暮な人情解説ぬきで紹介することとしたい。母についての娘の思い出は、母が思い出を娘に語って聞かせることで、遡って娘が母を生きなおしているような様相さえ帯びてくるのは、《だれにも守ってもらえない婚家での苦労を一時でも忘れようとして、母は、つらい分だけ、まるで編み棒の先からついとすべり落ちた編目を拾うように、あるいはやがて自分自身をとじこめることになる繭のために糸を吐きつづける蚕のように、いまは透明になった時間の思い出を子供たちに話して、自分もそれに浸った。思い出をたどるときだけ、母は元気だったので、私たちは、母の思い出にそだてられた》からだろう。
《微禄だったけど、竹田の殿さんのおさむらいだったのよ。ママのうちは。
それは、商家に嫁いで、なにもかも見当ちがいでとまどいつづけ、しゅうとめや、自分をかまってくれない夫への不満を、面とむかっては一言もいえない気弱な母が、二階の六畳間に来て私たち姉妹にだけ打ち明けるとき、まるで魔法のことばを口にのぼせて窮地を逃れる女の子みたいに繰り返すフレーズだった。これだけは奪うことができない、というように。》
《がむしゃらに母と母の兄たちを説きふせて結婚した父が、天にも登る心地で選んだ新婚旅行の目的地が、やはり別府だったからだ。黒っぽいコートを長めに着て、手袋をはめようとしている。耳かくしに結った母のスナップ・ショットがある。背景は山で、あ、私の写真なんて、というような羞じらいとほのかな媚びのまざった笑いを口もとに浮かべた表情がういういしい。ママ、きれい。すると、母は、ちょっとなつかしそうに目をつぶって笑う。
「いやあね、新婚旅行のときの写真よ。パパが撮ったのよ、別府で」》
《ほんの幼いころ、母は三度、悲しい思いをした。まず、四十になったばかりの父親をなくした。母は小学校の一年生で、先生に呼ばれて家に帰ると、お父さんはもう死んで、ふとんに寝かされていた。悲しかったわ。母はそう言った。(中略)
明治天皇の死は三番目の悲しみで、そのまえに、もうひとつ、胸がはりさけそうだった、と彼女がくりかえした大きな悲しみがあった。それまで住んでいた川っぷち(大阪の、どの川だったのだろう)の官舎を出て、父がいつか母と口論したときに子供たちのまえで「場末」と呼んだ、遠い町の狭い家に越したからである。そのまえに、ながいこと家にいたスエという名の女中が、いとまをとって、ぽんぽん蒸気に乗って行ってしまった。
「ママの家はお父さんが死んで、貧乏になったから、スエはいられなくなったのよ」
母は言った。
「ちぎれるように手をふって、スエは泣いてた。悲しくて、わたしも、姉さんたちも、おいおい泣いたわ」
まるで、自分が泣いているのを、どこかで見ていたように、そのときの話をした。おそらくは、あとになって、姉たちや母親に聞いたことをとりまぜて、脚色を加えたのだろう。》
《どうして、ここの家の人たちは冗談をいわないのかしら。結婚したころ、わたしは、毎日がつまらなくて、どうしていいかわからなかったわ。そう母は言って嘆いた。母にとって、冗談は、おいしいものを食べるのとおなじぐらい、大切なのだった。そういえば、母の兄弟たちは、ひとりのこらず食いしんぼうで、季節ごとに祖母が漬けこむ野菜の話や、九州の人たちならだれでも好きだというメンタイコの話や、家がケガレルからと祖母がいやがるので、兄たちが庭で煮たというイノシシ料理の話などをすると、母の声は高くはずんだ。話してしまってから、母は、しまったというように首をすくめて、おばあちゃんには、こんな話をしてはだめよ、と、食べ物の話をきらう姑に私たちがしゃべるのを警戒して、注意した。》
《母は、もっとびっくりするようなことを言った。シナ語、とくに北京語は日本語よりもうつくしい、というのである。フランス語も日本語よりきれいなの? と私がたずねると、もちろん、と自信ありげだった。「どこの言葉がいちばんうつくしいか」など、私はそれまで考えてみたこともなかったのだが、「なんでも世界一」というふうにそのころ教えこまれていた日本の私たちが話している言葉より、もっとうつくしいものが世界にあると聞いて、いったいこれはどうしたことかと、衝撃をうけたが、まず、言葉がうつくしい、というのがどんなことなのか、私には意味がわからなかった。
「大きくなったら、フランス語をならおうかな」
私がそう言うと、すぐになんでも熱中してしまう私を、母は心もとなさそうに見すえて言った。
「なにも、フランス語でなくたっていいのよ。北京語もすてきなんだから、どっちか勉強するといいわ」》
《私がだれかに写真をとってもらうとき、そばにいると、かならずといってよいほど、こう注意した。
「笑わないで、ちゃんとお口をしめて」
それは、にこにこして相手に迎合したり、「女らしさ」によりかかろうとする私より、まじめな表情をした私のほうが、私らしいという考えに通じていたようで、私はながいこと、あの気弱でひっこみ思案の母が、そんなふうに世間いっぱんとは違ったものの考え方を大事にしているのを、理解できないでいた。》
《「洗礼をうけたら、悩みがなくなるなんて、私にはとてもしんじられない」(中略)
母は、およそ母らしくないフランスの聖女の洗礼名にもらって、日曜日には、教会に行くようになったが、その後もときどき、ねえ、おまえたち、ほんとうに神さまのことを信じているの、などとたずねて、私たちをあわてさせた。
「なにも信じないよりはましだって、そう思って、わたしは洗礼をうけることにしたんだから」(中略)
「終点にだれもいないより、神さまがいたほうがいいような気もするわ」》
《二階の六畳間に行くと、たんすのまえにすわった母は私にもすわりなさいと言ってから、低い声でたずねた。
「フランスまで行ったのは、おまえ、どういうことだったの?」
いつになく鋭い母の矛先を私はありきたりの冗談でかわそうとしたが、母は笑わないでつづけた。
「このところ、自分の生き方をサボってるみたいなおまえを見ていると、わたしはなさけなくなるわ」母は言った。「そんなために、おまえをフランスまで行かせたのではない気がするのよ」
そして母はとどめを刺すように、こうつけくわえた。
「一日も早く、東京に行くなりなんなりして、自分の考えていたような仕事を見つけてちょうだい」》
《どうなだめても、母はメルセデス・ベンツで旅行するぐらいなら、家でお留守番する、と言いはった。いたたまれない気持で、私が妥協案を出した。ママと私は高山まで汽車で行く。高山から上高地までだけ、車にすればいい。母はやっと折れた。(中略)
わっと思っていると、またトンネルを出る。小さな白いハンカチを口にあてた母のおかしそうに笑っている顔が、煙のなかから、出てくる。そして、また、消える。
「煙のなかから出てくるたびに、おまえの顔がすこしずつ、まえよりすすけているの。おかしかったわ」
母はずっとあとまで、この旅行を思い出しては声をたてて笑った。
「おまえがふたつのときに、東京へ連れていったときから、ふたりだけで旅行したのは、あれがはじめてだったわね」》
《三週間の滞在はあっという間に終って、あしたは出発という日の夜に、横文字の苦手な母のためにいつもしたように、ミラノの家の住所を書いた封筒を一束、居間に持っていくと、母はその宛名をじっと見つめながら、言った。
「ミラノなんて、おまえは、遠いところにばかり、ひとりで行ってしまう。」》
須賀敦子と同じように、晩年に小説を書こうとしたが、不慮の交通事故死で世を去り(一九八〇年、六十五歳)、書き終えられなかった人として、ロラン・バルトがいる。
ロラン・バルトに、『長いあいだ、私は早くから寝た』(吉田一義訳(『現代詩手帳 臨時増刊 ロラン・バルト』一九八五年十二月、現代思潮社))という一九七八年十月の講演記録がある。ここには、小説を書くとはどういうことか、書こうとした小説とは何か、という問題がある。
《この講演の題として私が掲げた文章がお分かりになった方もおられることでしょう。「長いあいだ、私は早くから寝た。ときには、蝋燭が消えると、すぐに目が閉じて、<眠るんだな>と思う間もないことがあった。そして、三十分後、そろそろぐっすり眠らなければならない頃だと考えては、目が覚める……」これは『失われた時を求めて』の冒頭です。ということは、私はプルースト<について>の講演をしようというのでしょうか? そうでもあり、そうでもない。こう言ってよければ、むしろ「プルーストと私」ということになりましょう。何という自惚れ!》といった諧謔からはじまって、書物を書きたいと思い、それに成功したプルーストについて語ってゆく。長くなるが、できるだけかいつまんで引用する。
《『失われた時を求めて』に先立って、一冊の書[『楽しみと日々』]、翻訳、論考など、数多くのものが書かれています。あの大作が本当に書き始められたのはようやく一九〇九年の夏のあいだのことですが、その時点からは周知のごとく、書物を未完の危険にさらしかねない死と闘いながらの脇目もふらぬ疾走となるのです。どうやらこの一九〇九年に(ある作品の開始時期を正確に特定しようとするのは無駄だとしても)、決定的な躊躇の時期があったようだ。実際プルーストは、二つの道、二つのジャンルの十字路にあって、二つの<方向>に引裂かれていたのであって、ちょうど話者(・・)が、ジルベルトとサン=ルーが結婚するまでの非常に長いあいだ、スワン家の方がゲルマント家の方に到達することを知らないのと同じで、両方向が一緒になるかもしれぬことなど知る由もなかった――その二つの方向とは、(批評の)評論(・・)の方向と小説(・・)の方向だったのです。(中略)
彼が迷っている二つの<方向>は、ヤコブソンによって明らかにされた対立の二項、暗喩(メタフォール)と換喩(メトニミー)との対立にあたる。暗喩は、「それは何なのか? それは何を意味しているのか?」という問を提示するあらゆる言述を支えており、これはあらゆる評論(・・)が問うところのものである。換喩の方は反対に、また別の、「私が述べているこれの後には何が続きうるのか? 私が物語っている挿話は何を産み出しうるのか?」という問を出すのであって、こちらは小説(・・)が問うところなのです。ヤコブソンは、子供たちが「ヒュッテ」という語にどんな反応を示すかを調べた、ある教室での実験のことに注意を喚起していました。ある子供たちは、ヒュッテとは小さな小屋だ(暗喩)と答え、他の子供たちは、それは焼けてしまった(換喩)と答えたという。プルーストは、ヤコブソンの述べる教室の子供たちがそうであったように、分裂した主体だったとも言えましょう。人生のひとつひとつの出来事は、それに注釈(解釈)を加えるか、それとも、物語る際のその前(・)と後(・)を示したり想像させるような筋立をつくるか、そのどちらかの機会になるとは、彼も承知しているところです。》
そして、プルーストがこの迷いからどのような決意で抜け出したのか、またなぜ彼が根本的に『失われた時』へと没入していったのかは知る由もないが、
《彼が選びとった形式は分っている――『失われた時』の形式それ自体がそうだと。小説か? 評論か? そのどちらでもないし、その両方だとも言えよう。私はこれを、第三の形式(・・・・・)と呼びたい。》として、この三番目のジャンルについて考えみる。
《私がこの考察の冒頭に『失われた時』の最初の文章を据えたのは、それが五十ページばかりの挿話を開くもので、この挿話こそが、チベットのマンダラさながら、プルーストの作品全体を一望のもとに収めているからです。この挿話は何を物語っているのか? 眠りです。(中略)
それは、時(・)の水門を開くことにある。時の論理(クロノロジー)が揺さぶられると、理知的なものであれ物語的なものであれ、さまざまな断章が、物語(・・)や論理(・・)がもつ父祖伝来の法則を免れたある脈絡を形づくることとなり、そしてこの脈絡が評論(・・)でも小説(・・)でもない第三の形式を無理なく産み出していく。その作品の構造は、文字通り、ラプソディ風(・・・・・・)、つまり(その語源からして)断章を織り継いだものとなるのです。》
ここからはプルーストの作品の伝記的解体を考察した後、ダンテ『神曲』の「ワレラガ人生ノ道ノ半バニシテ(・・・・・・・・・・・・・・)……」を引用してから、バルト自身の「新生(ヴィタ・ノーヴァ)」への望み、読書体験とそれによる教訓から、小説が持つ能力を発展させ、三つの任務を果たしてもらいたいと思う。
《一つは、私が自分の愛する人達のことを語ることができるようにしてもらいたいということで(サドは――そう、あのサドが、小説の本領は自分が愛する人達を描くところにあると述べていた)、私がその人達に愛していると言うことができることではない(それなら文字通り抒情詩の企てになってしまう)。私は小説にいわば自己中心主義の超克を期待しているのであって、それは、自分の愛する人達のことを語ることが彼らが<無駄>に生きた(そして大ていの場合、苦しんだ)のではないことを証言することになるからです。(中略)
第二の任務は、私に情愛の提示を十全に、だが間接的に、可能にしてくれることにある。(中略)
最後に、そして特に、小説は(不確かでまるで規準に当てはまらない形式を指して私がそう言うのも、私がこの形式を着想しておらず、それを思い出すか、望んでいるだけだからだが)、その書き方が媒介的である以上(小説はさまざまな介在者を通じてのみ思想や感情を提示する)、他者(読者)に圧力をかけることがない。その審理は、感情の真実を問うのであって、思想の真実を裁くものではない。》
翌年の一九七九年にバルトが書いた、いっけん写真論にみえるが母の思い出を語っている『明るい部屋』と日記風の『パリの夜』には、あきらかにロマネスクな物語が織りあげられている。母子家庭で、ずっと一緒に過ごしたバルトにとっての母と、捩じれがあったとはいえ父と母がいて、早くに家を出、海外にも行ってしまった須賀にとっての母は、その母性の密着度があまりにも違いはするが、『明るい部屋』の写真をとおしての母の思い出は、『旅のむこう』の声をとおしての母の思い出と通じあうものがあるだろう。バルト『明るい部屋』(花輪光訳、みすず書房)の第二部から、小説的なエクリチュールをごく一部となるが書きだしておく。
《ところが、母の死後まもない、十一月のある晩、私は母の写真を整理した。母を《ふたたび見出そう》と思ったのではない。《写真を見てある人のことを思い出すよりも、その人のことを考えるだけにしておくほうが、もっとよく思い出せる、そうしたたぐいの写真》(プルースト)に、私は何も期待していなかった。思い出すことができないという宿命こそ、喪のもっとも耐えがたい特徴の一つなのであるから、映像に頼ってみたところで、母の顔立ちを思い出すこと(そのすべてを私の心に呼びもどすこと)はもはや決してできないだろう、ということはよくわかっていた。(中略)
かくして私は、母を失ったばかりのアパルトマンで、ただ一人、灯火のもとで、母の写真を一枚一枚眺めながら、母とともに少しずつ時間を溯り、私が愛してきた母の顔の真実を探し求め続けた。そしてついに発見した。
その写真は、ずいぶん昔のものだった。厚紙で表装されていたが、角がすり切れ、うすいセピア色に変色していて、幼い子供が二人ぼんやりと写っていた。ガラス張りの天井をした「温室」のなかの小さな木の橋のたもとに、二人は並んで立っていた。このとき(一八九八年)、母は五歳、母の兄は七歳だった。少年は橋の欄干に背をもたせ、そこに腕を乗せていた。少女は、その奥のほうにいて、もっと小さく、正面を向いて写っていた。写真屋が少女に向かって、《もっとよく見えるように、もうちょっと前に出て》、と言ったらしかった。少女は、子供がよくやるように、片手でもう一方の手の指を無器用につかみ、両手を前で組み合わせていた。(中略)
私は少女を観察して、ついに母を見出した。少女の顔の明るさ、その手の無邪気なポーズ、出しゃばるわけでもなく隠れるわけでもなく、ただ素直に身を置いたその位置、そして「善」が「悪」から区別されるように、彼女をヒステリックな小娘や大人のまねをしてしなをつくるかわいいだけの女の子から区別する、その表情、それらすべてが至高の純真無垢(・・・・)の姿を表わしていた(ここでは、この純真無垢(イノサンス)という語を、語源に従って、《人を傷つけることを知らない》という意味にとっていただきたい)。それらすべてが、この写真の少女のポーズを、ある維持しがたい逆説的な姿勢、母が生涯維持してきた姿勢に変えていた。すなわち、やさしさを主張するということ。この少女の映像から私は善意を見てとった。(後略)》
<『アスフォデロの野をわたって』/「回想=省略の文体」>
須賀敦子のイタリア文学論のひとつ、『ナタリア・ギンズブルグの作品Lessico famigliareをめぐって』(「イタリア語 ことばの諸相」一九九二年、イタリア書房)は、須賀の作品に大きな影響を与えたギンズブルグのLessico famigliare、すなわち『ある家族の会話』を、文体という視点から具体的に論じたものだ。二つの語りの様式が、この作品には仕掛けられていて、一つは「家族用語」によって話が運ばれる「言葉の記憶=饒舌の文体」、もう一つは「回想」の叙述における「回想=省略の文体」であると論じられている。前者の、「家族用語」によって話が運ばれる「言葉の記憶=饒舌の文体」については、母の声による『夜半のうた声』に活かされている。ここでは後者の、「回想」の叙述における「回想=省略の文体」についてとりあげてみたい。
《ナタリアが「女のよく陥る自叙伝風の」エクリチュールを極力回避しようとしたのは、自己を中心とした、心理の吐露にかまけた作品としての回想記であり、自叙伝であったと考えられるが、このように言葉によって触発される記憶の詩法は、そのために、もっとも効果的な手法であった。作者がかつて退けた「女性」的要素が、ここで逆転して作品の大きな魅力となったのである。彼女の避けたのが、女性らしさそのものではなくて、くだくだしい心理描写をともなうような文体であったことが、これで理解される。要するに、感傷的で、自己顕示欲のあらわな表現が彼女には耐えられなかったのだ。
しかし、それだけではない。彼女の文体には、もうひとつの強力な工夫がかくされている。それを、仮りに省略の詩学と呼んでみよう。すなわち、饒舌の対極に、彼女は省略/忌避による沈黙を置く。その例として、回想のなかでもっとも痛みに満ちていてよいはずの、夫レオーネの死を告げる箇所を読んでみよう。
最初、彼の死は、戦後ナタリアが働きはじめたエイナウディ出版社主のジュリオの託して語られる。
(引用されたイタリア語原文、略)
レオーネの肖像を壁にかけたのはジュリオ・エイナウディであって、彼女自身ではない。そんなところに、ナタリアの忌避が読みとれるだろう。そして、淡々と、彼の無惨な死が告げられるのだが、この文章が読者の心を打つのは、最後の”un gelido febbraio”という換喩的な表現によってである。作者は、そのこと自体ではなくて、彼が死んだ朝の冷たさをつけくわえることによって、彼女自身の恐ろしさを告げ、この文章を抒情的にむすぶのである。
もうひとつ例をあげよう。ふたたびレオーネの死に関するものである。
(引用されたイタリア語原文、略)
アブルッツォの流刑地から、たいへんな苦労をして子供たちといっしょに、「私」は、レオーネの待っているローマに着く。その「ほっとした」(tirai il fiato)から”felice”という形容詞を経て、ローマの緊迫した生活を語ったあと、作者は「彼には二度と会わなかった」(e non lo rividi mai piu)という、これ以上みじかくなり得ない表現で、夫との永劫の別れを読者に告げている。わずかに、しかし、決定的に感情を伝えるのは、feliceに対しておかれた、最後の”mai piu”という絶望的な副詞句で、あとはすべて、「行動で構築」され、感情のはげしさは、「省略」で表現されている。夫との再会のよろこびは、わずかに”tirai il fiato”にとどまり、彼が収容されたレジナ・チェリ刑務所への言及も、拷問のすえの酷たらしい死についても、まったく触れられていない。そして、直後におかれた段落は、大きく息を吸って、泣き声にならないのを確認したうえでのように、つぎの言葉ではじまる。
“Mi ritrovai con mia madre a Firenze.”
省略が、他のどのような抒情的形容よりも、深い悲しみと強い衝撃を表明しうることを、ギンズブルグは知っていた。(中略)
省略が用いられるのは、しかし、かならずしも喪失をあらわすためだけではない。つぎのような例はどうであろうか。
兄たちは、彼ら自身の言動によることもあるが、通常、母親あるいは父親の言葉をとおして「私」の記憶にとどまる。しかし、それだけではない。たとえば、作者がレオーネと結婚することになった過程は、彼女あるいはレオーネの心理に関するかぎり、すべて省略されている。いや、読者にはほとんどなにも知らされないで、その代りに、父母による彼についてのコメントが置かれるのである。(中略)
「自分のことをくだくだと他人にしゃべらない」というナタリアの北イタリア人らしい控え目な(羞恥心に根ざした)表現を基底にもつ省略ということができる。》
ギンズブルグを考察した「回想=省略の文体」を頭に入れたうえで、阪神間に生まれ育った人らしい控え目な(羞恥心に根ざした)表現を基底にもつ人だった須賀の『アスフォデロの野をわたって』を読みすすめる。『旅のむこう』は母についてだった。これは夫のことである。そして、先回りして言えば、最後となる次の『オリエント・エクスプレス』は父のことだ。
《昼さがりの風がレモンの葉裏をゆっくり吹きぬけると、濃い緑のところどころが季節はずれの淡い黄色で染め抜かれた木立にかすかなざわめきが走る。見上げると、光が乱反射して暗さを感じさせるほど青い七月の空の切れはしが、ちらちらと葉のあいだに揺れている。庭に面した隣家の窓からポンとぶどう酒の栓を抜く音が小さくひびいて、昼食のテーブルをかこんだ家族の会話がぱらぱらと聞こえてくる。》 南イタリア、地中海の光がきらめく、幸福な詩情で『アスフォデロの野をわたって』ははじまる。しかし、すぐ二、三行さきで、そこはかとした、とりとめない不安の影が、前作『旅のむこう』で、日本への新婚旅行で登場してきた、「窓側の席にすわった夫にそうささやくと、彼はだまってうなずいた」、「握手しないで、ただ笑って会釈しただけだった」夫ペッピーノに対して宿る。
《いいよ、ぼくはここのほうが落着く。そう言って三階の部屋で午睡に溺れているペッピーノのほうが正解だったかもしれない。二日まえの午後おそく、ソレントに近いこのペンションに着いて以来、彼はひまさえあれば額にうっすらと汗をかいて眠っている。
こんなに眠ってばかりいるのは、ただ疲れているだけなのだろうか。私の知らないところで、からだのどこかが蝕まれているのではないか。四年前の秋にペッピーノと結婚したときから、日々を共有するよろこびが大きければ大きいほど、なにかそれが現実ではないように思え、自分は早晩彼を失うことになるのではないかという一見理由のない不安がずっと私のなかにわだかまりつづけていて、それが思ってもいないときにひょいとあたまをもたげることがあった。》
この不吉な予感は、まるきり根も葉もないわけではなく、彼のひとつ違いの兄は二十一歳のとき結核で死に、妹も、兄の死んだ翌年、おなじ病気で逝った。さらに二年も経たないうちに父親が死んだ。ペッピーノ自身、決して丈夫なほうではなかった。彼はこれらを隠そうとしなかったし、彼の結婚をおくらせていた原因のひとつであることもうすうす感じていたが、過去の悲しみをいっしょに担うことになれば、人生を変えられるはずだと私たちは信じようとして、結婚に向って走った。友人たちは口をそろえて結婚して彼が明るくなったといった。はじめて知りあったころは、ぼくはあんまり食べ物には興味がないんだ、とつまらなそうな顔をした彼が、いろいろ台所に註文をつけるようになって私をよろこばせ、しばらく会わなかった友人が、結婚してずいぶん元気そうになったじゃないか、などと言ってよろこんでくれたりすると、私はやはりあの不安は杞憂なのかもしれないとほっとするのだった。ソレントで十日間も夏休みをすごすことに決めたとき、仲間たちは彼が「変った」ことを祝福してくれた。ナポリ大学で政治学科の無給助手をしながら、アルバイトのほかに南北問題などの記事を新聞や雑誌に寄稿して生計をたてているロサリオは、ペッピーノが共同経営しているコルシア書店の地方にちらばったカトリック左派の協賛者のひとりで、北にやってくるとかならず書店に立ち寄ってあたらしい情報を仕入れ、また自分たちの近況を伝えて、帰って行った。
そのロサリオに、「夏ぐらいは、人間らしく休みなさいよ」と真剣な顔でさそいかけられると、平穏な生活から遠ざかるのが苦手な夫が、どういう風の吹きまわしだったか、すなおにうんと言った。ロサリオの見つけてくれたペンションは小ウィーンという、ソレントらしくない名だったが、清潔で静か、居心地はよかった。
ロサリオの友人のモーターボートで遠出をしたとき、エレナというながい金髪の娘がいっしょに来て、婚約者なの、とロサリオにたずねると、うれしそうに白い歯をみせて笑った。彼女はコルシア書店に来たことがあるそうで、ロサリオとおなじナポリ大学の政治学科の学生だった。若い仲間のひとりが銛で仕とめたサン・ピエトロという聖者の名がついた魚に舌つづみをうちながら、教会論がとびだし、キリスト教民主党の批判に飛火して、ひとしきりの政治談議になった。陽にあたると疲れると言って、帰り道、ペッピーノはほとんど口をきかなかった。目だけはいつものように終始笑っていたけれど。ある日、ソレントの浜辺で、ずっと沖に見える島ともいえない岩山まで泳いで行こうということになって、私も泳げるので参加することにした。水がきらいだから、とまったく興味を示さないペッピーノは浜辺に残ったが、戻ってきて波打ち際にいる彼の姿が目にはいったとき、私は一瞬、胸をつかれて立ちつくした。わずか二、三日のうちに真っ赤に日焼けした、このところすこし肉のついた上体を波の動きにつれてゆらゆらと揺らせながら、ながながと水のなかに横たわっている。両手をひじのところで折って胸にあてて、上をむいた頭だけをこころもち上げて、しかもめがねをかけたままで。そばに行くと彼は私を見上げて笑った。赤ん坊じゃあるまいし、を追いかけるように、もうひとつのフレーズがあたまを駆けぬけた、死人じゃあるまいし。
今日は、すこし遠いけれどペストゥムの遺跡を見に行こうとロサリオたちに言われて、なんとなく重い気持で車に乗った。ポンペイのようなヴェスビオ火山の噴火で埋まったローマ時代の遺跡のひとつだろうと思いこんでいたからだ。火山灰に埋まって命を落した人々の無惨な石膏の人形(ひとがた)はぜったいに見たくなかった。子供のときも、病院の裏口では死者が運び出されると聞いて目をあけないようにして通ったし、キリストの磔刑のさし絵のあるページが目にとびこんでこないように糊で貼りつけてしまって学校で物議をかもしたし、戦争のときも、米軍機の機銃掃射をうけて逃げまわった空襲のあとでさえ、私は死者の姿が目に入らないよう細心の注意を払うのを忘れなかった。《死は、なにがあっても目をそむけるべきもので、一生、死に手を触れないで済ませられるのなら、私はそのほうがよかった。》 車のなかでそんな話をすると、みんなが笑って、教えてくれた。ペストゥムは紀元前にはポセイドニアと呼ばれる、海神にささげられたギリシアの植民地で、いくつかの神殿をふくむ建築物がすばらしく、古代ギリシアの建物としてはどこよりもよく保存されていて、アテネのパルテノンに比べても、勝るとも劣らない、という。古い町の名が、ホメロスの詩への郷愁をさそった。
ここからの二段落は、『ヴェネツィアの宿』のライト・モティーフのひとつ、「時」についての、詩的であることが哲学的でもある、情景と精神の融合した文章で、この描写がラストの省略の文体の、無言の背景になっている。
《ペストゥムの遺跡の夏枯れの野に、私はひとりで立っていた。着いて車を降りると、なんとなくみながそれぞれの方向に散ってしまったのだった。ゆっくりと傾きはじめた太陽がふいに速度をはやめて森のむこうの海に沈む時間で、オレンジをしぼったような光が、ふたつの神殿のうち他を圧して一段と高くみえるポセイドンの神殿をすっぽりと包み、言葉を失って立ちつくす私も同じ柑橘類の色に染まっていた。ギリシアの神殿に接するのはこれが最初だったが、完全なものがいつもそうであるように、しばらくのあいだはその偉大な調和がかもしだす静謐が、ほとんど人間の手を経ることなくそこに存在していると思わせるほど巧妙な錯覚の網で私をすっぽりと包みこんだ。
私が見上げているのは、まぼろしの屋根を支える巨大なドリア様式の円柱列に抱かれた、たぐいまれな神々の空間で、明晰という言葉から人間が想像しうる最高の表現と思われるものが夕陽をいっぱいに受けてかがやいていた。柱の一本一本に並行して刻まれた垂直の縦溝が、時間と気候と人の手が刻んだ大小の傷に被われながらも、今日も海に落ちようとしている太陽の光線を、最後の微片にいたるまで逃すことなく荒廃した石の肌に吸いとろうと、根づよい生命のエネルギーのすべてを傾けていて、石に封じこめられた息づまるような精神の集中のとくとくと脈うつ鼓動が聞こえるようだった。》
ロサリオの声がずっと遠くで聞こえて、廃墟のどこかにはペッピーノも、おなじ光のなかに佇立しているはずだった。みんなのところに行こう。それにしてもペッピーノはどこに行ってしまったのだろう。大きな大理石のかたまりの上によじのぼって、ロサリオはエレナと海を見ていた。ペッピーノは? と訊くと、なんだ、いっしょじゃなかったのか、という。ぼんやりとあたりを見まわした。なんの関連もなく、好きな「オデュッセイア」の一節があたまに浮かんだ。《アキレスは、アスフォデロの野を どんどん横切って行ってしまった》 「アスフォデロ」という言葉の意味が知りたくて、いくつか辞書を引いたが、いろいろな説があって、忘却を象徴する草ということだけわかった。ペッピーノの友人が訳したエイナウディ社の対訳版では、「忘却の野」と形容名詞になっていた。「アキレウスは、忘却の野をすたすた去って行った」
ほんの短い時間、ペッピーノの姿がみえなくなったことで、ロサリオがあわてたぐらい、私はとりみだし、《いわれのない不安に追われるようにして、廃墟に散らばる大小の石に足をとられながら、失くしものを探す子供のように、私は彼を探し歩いた。十日間の休暇は避暑客でごったがえすソレントについてほとんど縁のないままに終って、私たちは愉しかった日々のざわめきを陽焼けした皮膚にとどめただけで、また「人間らしくない」ミラノの日常にもどった。》 ペッピーノを探し歩いた結果を省略している。
学生運動のニュースが伝わってくるようになって、コルシア書店の将来をめぐって仲間たちの意見が対立しはじめた。ペッピーノは慣れているはずの書店のなかで転んで怪我をしたり、大切な用件を忘れたりすることがあって、自分でもふしぎがった。もうすぐクリスマスというある夜、ロサリオがエレナと連れだってメキシコに行ってしまったという報せをもってきた。メキシコの大学で仕事がみつかったんだよ、と言ったが、腑に落ちないのでさらに訊ねると、エレナはほかの男と結婚してたんだ、とぽつんと言った。これからの南イタリアについていっしょうけんめい論議していたロサリオが、大学でのキャリアと南部問題に明るい光を求めようとする情熱をなげうって、エレナといっしょになるだけのためにメキシコに行ってしまったのは、どう考えても彼らしくなかった。そして、翌年の三月の霧のたちこめた夜、ペッピーノがこんどはもっと思いがけない報せをもってかえってきた。ロサリオの訃報だった。心臓の発作で急死したという。それを聞いて、三十をすぎたばかりのロサリオの、なにか生きいそいでいたようなやり方がすこし理解できたように思った。
ここまでもそうだったが、いっそうの「回想=省略の文体」が、抒情的なむすびとともに、痛々しいほどに生かされている。
《それからまた三か月経つか経たないうちにペッピーノが死んだ。ひと月まえから肋膜炎で床についていたのだったが、その病名を知ったときから。私は夜も昼も、坂道をブレーキのきかない自転車で転げ降りていくような彼をどうやってせきとめるか、そのことしか考えなかった。
死に抗って、死の手から彼をひきはなそうとして疲れはてている私を残して、あの初夏の夜、もっと疲れはてた彼は、声もかけないでひとりで行ってしまった。
がらんとしてしまったムジェロ街の部屋で朝、目がさめて、白さばかりが目立つ壁をぼんやりと眺めていると、暮れはてたペストゥムの野でどこかに行ってしまったペッピーノを、石につまずきながら探し歩いている自分が見えるような気のすることがあった。
アスフォデロが花の名だったのか、ただ単に忘却を意味する普通名詞なのかは、いまだにはっきりしない。》
<『オリエント・エクスプレス』/愛するものについて語る>
場所は、ロンドン、エディンバラ、ミラノ中央駅、そして最後はオリエント・エクスプレスと東京。それぞれ、一行あけて四つに分たれている。時は、一九五九年のこと、書かれた時点から三十四年溯るとはいえ、ロンドンから東京まで、ところどころで父(「彼」とか「あの人」とか、客観的に名づけられもする)の回想が混じりつつも、直線的に流れる。これまでとはちょっと違った、前へ前へと、せっつかれるように時計が進む構成となっているのは、『ヴェネツィアの宿』の円環構造を閉じる大団円だからだろう。
これ一篇を独立して読むことは、父のヨーロッパからアメリカにかけての一年近い大旅行のいきさつや、父のふたつの家、母の父への思い、父にまつわるあれこれを順に読んできた者にとってはすでに難しく、これまでのさまざまな父に関する言述が堆積した頭と心で、この『オリエント・エクスプレス』を読むことになる。
《「朝、九時にキングズ・クロス駅から『フライング・スコッツマン』という特急列車が出ているはずです。それに乗ってエディンバラまで行ってください。パパもおなじ列車でスコットランドへ行きました。エディンバラでは、ステイション・ホテルに泊まること」
行ってください、という一見、おだやかでていねいな口調とはうらはらな「泊まること」という命令のほうが父の本音だということぐらいは、すぐにわかった》という文章で、父の人となりはおおよそわかるが、これにつづく次の文章で、来し方の娘の父への感情が明言される。それを書いておいて、実は、というところが、この一篇の勘所である。
《フライイング・スコッツマン、空飛ぶスコットランド男、たぶん、父はなによりもその列車の名が気にいっていたのだろう、自分に似て旅の好きな娘をそれに乗せて古い北方の首都まで行かせる。一見、唐突にもとれる手紙だったが、いかにも彼らしいロマンがそこには読みとれて、父への反抗を自分の存在理由みたいにしてきた私も、こんどばかりはめずらしくすんなりと彼の命令を受け入れる気持になった。》 「父への反抗を自分の存在理由みたいにしてきた私」なのである。
留学先のローマから友人をたずねて、ほんの二週間ほどの予定でイギリスに渡ったところ、ヴィクトリア駅の近くに快適なフラットをきた。それはよかった、金のことなら心配ないから、できるだけ長くロンドン生活を愉しみなさい、という、考えていたよりもはるかに機嫌のいい手紙だった。父からの航空便はどれも、《自分もかつてひと月あまり滞在したことのあるロンドンに娘がいること、しかもその旅行の費用は自分がすべて支えていることへの深いよろこびに文章が踊っていた。》 父の便りは、リージェント・ストリートかなにかの、足がすくむような専門店でワイシャツを買って送れだったり、ロンドン塔に行くまえに漱石を読んでおけと何冊かの岩波文庫が届いたり、《私自身も徐々に父の昂奮に巻き込まれたかたちで、父の手紙とローマから持って来た旅行案内とをハンドバッグに入れて、せっせと父のロンドンを歩きまわった。》 「父の昂奮に巻き込まれた」、「父のロンドン」という表現がせつない。《エディンバラに行ってください、という手紙が届いたときは、以前から自分でも行ってみたいと思っていた場所だったこともあって、私はたちまち素直なロボットみたいに家をとび出した。そしてキングズ・クロス駅で、おどろいたことに父の言ったとおりの列車が言ったとおりの時間に出るのを知ってほとんど無力感におそわれながらも、さっそく三等車の切符を求めると、八月十八日の出発を心細さと期待のまざった気持で待ちわびた。》 「三等車」、「八月十八日」を記憶の片隅にとどめておこう。
東京―大阪とほぼおなじくらいの距離と思えたエディンバラの駅に到着したのは、午後のおそい時間だった。父に勧められた「ステイション・ホテル」の場面となる。前方にStation Hotelという赤いネオンのしるしがあるのが見え、ネオンの下まで行ってみると、薄暗い、トンネルのような通路が口を開いていて、ちょっと不安になった。《ほんとうにだいじょうぶなのかしら、という気持は、でも、すぐに、いや、そんなはずはない、あの人が泊まったホテルなんだから、という確信に払いのけられて、私は荷物を片手にその細い通路を歩きはじめた。》
いきおいよくドアをあけると、豪奢なルネッサンスの宮廷のような、美しいシャンデリアが燦いていた。いまさら後戻りするわけにもいかず、赤い絨毯の海を渡り、フロントのカウンターのまえに立つと、でっぷりふとった、盛装した白髪の老バトラーがにこやかに近づいてきた。《キングズ・クロスの駅を離れてからずっと、往年の父の優雅な旅をあたまのなかで追ってきた私が、そのとたん、貧乏旅行しかしたことのない戦後の留学生に変身した。》 「三十年まえ、このホテルに泊まった父にいわれて、駅からまっすぐこちらに来たのですが」そういうと、はてな、という表情が一瞬、老バトラーの顔をよこぎったが、身をのりだすようにして耳をかたむけてくれた。「どうも、私の予算にくらべて、こちらはりっぱすぎるようです」「それで?」「こちらでいちばん高くない部屋はいくらぐらいかしら?」 当然とはいえ、どれも私の予算をはるかに超えたものだった。「ほんとうにもうしわけないけれど……」もういちどくりかえした。「あまり遠くないところで、こちらほど上等でなくて、でもしっかりしたホテルを教えていただけないかしら。父に言われていたので、ここに泊まることだけを考えて来たものだから」 老バトラーの糸のように細くなり、贅沢な用箋に別のホテルの名を書きつけ、ウィンクしながら背のびしている私に差し出した。「正面のドアを出て、通りを渡ったところです。ちゃんとしたホテルだから、安心なさってだいじょうぶです。では、おじょうさん、よいご旅行を」
《それにしても、ステイション・ホテルがどういった格の宿なのか、説明もしてくれないなんて。薄暗い朝のあたたかいベッドのなかで、私は、父がうらめしかったが、同時に、三十そこそこで、そんな贅沢旅行をやってのけた若い父親の姿には、どこかいとおしささえ覚えた。高すぎるカウンターのまえで、あの立派な体格のバトラーに言い分をうまく伝えたいと、大汗をかいていた自分を思い出すとちょっとみじめな気もしたが、それでも、この話をしたら、きっとあの人はよろこぶだろう。そうも思った。女のくせに、そんなはずかしい真似をして、と口では叱りながら。》 「口では叱りながら」のあとは、あえて言葉にしない。
バトラーにいわれたホテルに荷物をおき、街に出た。北国の八月はロンドンよりもっと日が長く、雨もよいのせいだろうか、いつまでも夜になりきれないでいるようにみえた。肩のはった骨太で背の高い男女が、幅のある歩調で、薄暮のなかをゆっくりと歩いて行く。八月というのに重たげな、でも質のいい毛織のジャケットをはおり、がんじょうな靴をはいて闊歩する人々の流れにまじって歩きながら、まるで声のない街にとじこめられたような気がしていた。《父はいったい、どんな顔をしてこの道を歩いたのだろう。私は、少し猫背な彼のうしろ姿が、人びとの群れにまじっているような気がした。》
エディンバラ城の容姿を、遠くからでもいいから、日が暮れてしまわないうちに視覚におさめておきたかった。《エディンバラのお城のそばで、と父はなんども私たちに話してくれた。ちょうどおまえたちぐらいの年齢の、学校の制服を着た女の子が、十人ほど、若い、きれいなシスターに連れられて遊びに来ていた。犬ころみたいに、芝生のうえをころがりまわっていて、なんだ、スコットランドまで来ても子供はおまえたちとおんなじだと思った。
パパたちがお城の見物をして出てくると、ちょうどシスターも子供をあつめて帰るところだった。どうもひとり、人数が足りないらしい。その子の名をたてつづけに呼んでいた。透きとおった、きれいな声で。
メアリーという名だったぞ。父は、これだけは忘れてない、といわんばかりに、力をこめて、言った。目をとじて、すこし音痴な声をはりあげ、メアリー、メアリーと若い修道女の声色をまねて、私たちを苦笑させることもあった。》 六ケ月にわたる父の外遊の思い出話のなかには、子供の出てくることがあった。ふと日本でミッション・スクールに通っている娘たちを思い出したのだったろうか。《どんなお天気だったの、その日は。そう訊いておけばよかった。プリンセス・ストリートを西に向って歩きながら、私は思った。》
突然あらわれた岩山はただ奇異としかいいようがなかった。地図によると、たしかにエディンバラ城の方角だったが、城砦なのか、ただの岩山なのか、判断がつかない。あれはほんとうにエディンバラ城だったのだろうか。山も岩もすべてが魔性のものに思えて、そのまま散歩を打ち切ってホテルに帰ったのだった。《それにしても、のどかな一幅の絵のような父のエディンバラ城と、私の見た霧のなかの岩山の、なんという隔たりだろう。》
翌朝は、ガイド・ブックどおりに、いくつかの城をたずね、教会を見学し、美術館をおとずれたが、着いた日の夕方の奇怪な岩山の印象があまりに圧倒的だったので、なにもかもが色褪せてみえた。
場面は変わり、十一年の時が流れている。
一九七〇年の三月のある日、ミラノ中央駅にいそいだ。パリ発―イスタンブール行きの国際列車が、入るはずだった。「父上からのおことづけですが」そういって、父の会社の人と名のる会ったことのない人物からの電話が、ローマからミラノの家にあった。二年前に手術をうけた父の癌が、昨年の秋に再発して、もう手のほどこしようのないところまで来ていると、弟がつぎつぎと書いてくる手紙で知っていた。「近々お見舞いに日本に帰られるとのことで、お父様はたいへんおよろこびです」知らない人の声はいった。「それで、おみやげを持って帰ってほしいとおっしゃって、お電話するようお頼まれしたのですが」 十年に二、三度にすぎなかったが、日本に帰るたびに、みやげなんか持って帰るな、と叱り、すなおにありがとうといってくれない父が、こんどはおみやげを持って帰れとことづけする。しかも、父がほしいというのが、かつてそれに乗って旅をした、ワゴン・リ社の客車の模型と、オリエント・エクスプレスのコーヒー・カップが欲しいのだという。模型は玩具店ですぐに見つかったが、コーヒー・カップを手に入れる方法がわからないでいると、あちこち探すよりも、じかに列車まで行ったほうが、手っとりばやくないかな、と友人が提案してくれたので、取るものも取りあえず中央駅に出てきたのだった。乗客でもない者に、頒けてくれるのだろうか、と思うと、構内アナウンスが到着を告げたとき、喉がからからになって、息ぐるしいような気がした。《私がこうしているあいだにもひとり死に向っている父に、いましてあげられることは、これだけしかないのだ。夫が死んでふた月後の夏に、母の危篤で帰国したとき、父はすでに一回目の胃の手術を受けたあとだった。母の病状が一応、落着いたあと、父の看護をするために日本にとどまるべきか迷う私に、父はきっぱりいった。おれのために、いまさら、おまえの選んだ生き方を曲げるな。ミラノへ帰れ。》
「ヨーロッパに行ったら、オリエント・エクスプレスに乗れよ」と、はじめてフランスに留学することがきまったとき、父は上気した声でくりかえしたけれど、夢のような列車の名は、あたまのなかを素通りしただけだった。生涯でたった一度になった父の外遊のみやげに、まだ幼かった息子のために買ってきたのは、ドイツのメルクリン社の電気機関車一式で、弟は座敷いっぱいに敷いたレールに、客車と機関車を走らせるのに夢中になって、父をよろこばせた。そのなかには、ワゴン・リ社の、青と金色の車体の寝台車もまじっていて、父は、なつかしそうに国際列車の話を、私たちに話して聞かせた。オリエント・エクスプレスには、若いときに旅をつづけた時間と空間への深い思いがこめられていて、その記憶が、大波のいくつかを乗り越えるうちにようやく仕事に自信をもつようになった父の晩年を、どこかで支えていたに違いない。《会社がひまになったら、とイタリアから私が帰るたびに、父はくりかえした。もう一回、ヨーロッパに行くぞ。》
列車が停止した。凝縮されたヨーロッパそのものを見るようなうつくしい人々が降り立つ。客車の入口の黒い蝶ネクタイをつけた車掌長に出会った。「少々、おかしなお願いがあるんですけど」「なんなりと、マダム、おっしゃるとおりにいたしましょう」 威厳たっぷりだが人の好さがにじみでている、恰幅のいいその車掌長に、日本にいる父が重病で、若いとき、一九三六年に、パリからシンプロン峠を越えてイスタンブールまで旅したこと、そのオリエント・エクスプレスの車内で使っていたコーヒー・カップを持って帰ってほしいと、たのんで来たことなどを手みじかに話した。ひとつだけ、カップだけでいいから、頒けていただけるかしら、とたずねると、はじめは笑っていた顔をだんだんとかげらせたかと思うと、「わかりました。ちょっとお待ちいただけますか」と低い声でいって、車内に消えた。まもなく大切そうに白いリネンのナプキンにくるんだ包みをもってあらわれた。《ありがとう。そう言った私の声はかすれていた。お代は、とたずねる私に、彼は包みを開いて、白地にブルーの模様がはいったデミ・タスのコーヒー茶碗と敷皿を見せてくれながら、まったくなんでもないように、言った。
「こんなで、よろしいのですか。私からもご病気のお父様によろしくとお伝えください」
羽田から都心の病院に直行して、父の病室にはいると、父は待っていたようにかすかに首をこちらに向け、パパ、帰ってきました、と耳もとで囁きかけた私に、彼はお帰りとも言わないで、まるでずっと私がそこにいていっしょにその話をしていたかのように、もう焦点の定まらなくなった目をむけると、ためいきのような声でたずねた。それで。オリエント・エクスプレス……は?
死にのぞんで、父はまだあの旅のことを考えている。パリからシンプロン峠を越え、ミラノ、ヴェネツィア、トリエステと、奔放な時間のなかを駆けぬけ、都市のさざめきからさざめきへ、若い彼を運んでくれた青い列車が、父には忘れられない。私は飛行機の中からずっと手にかけてきたワゴン・リ社の青い寝台車の模型と白いコーヒー・カップを、病人をおどろかせないように気づかいながら、そっと、ベッドのわきのテーブルに置いた。それを横目で見るようにして、父の意識は遠のいていった。
翌日の早朝に父は死んだ。あなたを待っておいでになって、と父を最後まで看とってくれたひとがいって、戦後すぐにイギリスで出版された、古ぼけた表紙の地図帳を手わたしてくれた。これを最後まで、見ておいででしたのよ。あいつが帰ってきたら、ヨーロッパの話をするんだとおっしゃって。》
雑誌連載時の題名、『古い地図帳』は、最後のこの場面からきた。
うつくしくも、抑制された文章による感動的なクライマックスに水を差すつもりはないが、エディンバラのホテルから父に宛てた手紙を『須賀敦子全集 第8巻』で読むことができる。旅行に相当する部分を、抜き書きしておく。ユーモアに富んだ人柄が偲ばれる。
《十月十日 エジンバラ Royal British Hotel,Princes St.,Edinburgh,Scotland(父宛航空書簡)
ロンドンでは家の近くのトマス・クックで汽車の切符を買って、(もうヨーロッパには三等がないので二等です。それでも、往復七ポンドでした)昨日、一号車ですゝだらけになって旅行しました。(中略)エヂンバラについたのは、ちょうど六時半、クックできいてゐた、ノース・ブリティッシュ・ホテル(ステーションホテル)に行ってみると、いやなんだか立派なので、まづいな、と思って、とにかく値段をきくと47シリングが最低、とても贅沢すぎるので困るといふと、それではお向ひにいゝホテルがございますといふので、ほんたうにいゝホテルですかと念をおして、なるほどこれもなかなか立派なホテル(ロイヤル・ブリティッシュ)の三十七シリングの部屋におちついたわけです。
エヂンバラはなるほど美しい町です。といっても何か、マクベスとか、あのまほうつかいの婆さん共が祖先といふだけあって、今でも、なんとなく妖怪的な要素あり。今朝、お城の丘にのぼって、霧が吹きよせてくる中で、全く全くふしぎな町だとおもひました。とても廿世紀後半とは思へません。女の人は、ロンドンでびっくりしていたら、いやもう、こゝでは、男の一間で消えてなくなったやうなもので、店の陳列棚も、タータンチェック以外の着るものは、あげるといって追っかけられてこられても必死になって逃げだしたいやうなものばかり。お城の半分は兵営になっていて、チェックのズボン(キルトではなく)をはいた兵隊がたくさん番してましたが、安物のゴム人形のやうな表情ではなはだ興ざめ。(後略) 敦子》
父への手紙に書いてあることが事実だとするならば、『オリエント・エクスプレス』に書かれた旅行記には、いくつかの言い換え、誇張、修飾、逆にあえて書かなかったことなどがありそうだ。八月、三等車、老バトラーとの会話、人びとの服装、着いた夕方にエディンバラ城に向ったのか、などである。おそらくは、オリエント・エクスプレスのコーヒー・カップの入手、死に際の父の様子にも、多少とも嘘や脚色があるだろう。『ヴェネツィアの宿』十二篇のそこかしこに、それらはあるに違いない。しかし、それがどうしたというのか。
ふたたびロラン・バルトだが、彼は遺筆となった『人はつねに愛するものについて語りそこなう』(『テクストの出口』、沢崎浩平訳(みすず書房))で、その秘密を説いている。奇しくもそれはミラノ中央駅から書きはじめられる。《数週間前、私はイタリアにごく短期間の旅行をしました。夜、ミラノの駅は寒く、霧がかかり、薄汚れていました。列車が出ようとしていました。それぞれの車輛には黄色いプレートが掛けられ、《ミラノ―レッチェ》と記されておりました》からはじまって、スタンダールのイタリアは、彼にとって、一つの幻想(ファンタスム)だったが、そのイタリア旅日記は失敗に終っていると述べている。《イタリアへの愛を語ってはいるが、それを伝えてくれないこれらの「日記」(これは少なくとも私自身の読後感ですが)だけを読んでいると、悲しげに(あるいは、深刻そうに)、人はつねに愛するものについて語りそこなうと繰り返すのももっともだと思うでしょう。しかし、二十年後、これも愛のねじれた論理の一部である一種の事後作用により、スタンダールはイタリアについてすばらしい文章を書きます。それは、私的日記が語っていたが、伝えてはくれなかったこの喜び、あの輝きでもって、読者である私(私だけではないと思いますが)を熱狂させます。この感嘆すべき文章とは『パルムの僧院』の冒頭の数ページのことです。(中略)スタンダールは、若かった頃、『ローマ、ナポリ、フィレンツェ』を書いた頃、《……嘘をつくと、私はド・グーリ氏のようだ。私は退屈する》と書くことができました(RNF六四)。彼はまだ知らなかったのです。真実からの迂回であると同時に――何という奇跡でしょう――彼のイタリア熱の、ようやくにして得られた表現であるような嘘が、小説的な嘘があるということを。》
須賀敦子は、愛する父や母のことを「小説的な嘘」をまじえて書くことによって「愛するもの」について語りきったのに違いない。
(了)
*****参考または引用文献*****
*ナタリア・ギンズブルグ『ある家族の会話』、須賀敦子訳(白水社)
*ロラン・バルト『長いあいだ、私は早くから寝た』、吉田一義訳(『現代詩手帖 一九八五年十二月臨時増刊 ロラン・バルト』(思潮社))
*ロラン・バルト『明るい部屋 写真についての覚書』、花輪光訳(みすず書房)