
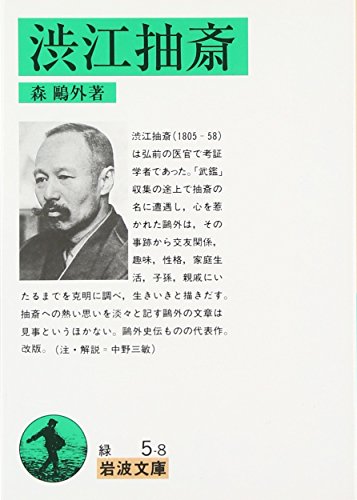
森鷗外『渋江抽斎』は世に「史伝」と称されて、《鷗外の教養なくしては不可能と思われるほど詳細にして厳密なんです。そのうえで十分に面白い》《人間関係の詳細が探索されているほど、探偵的方法がみごとに発揮されてるんです》(丸谷才一『文学のレッスン』)であり、また《未知のものに肉薄しようとする努力は、心がうごき、眼がうごき、手足がはたらいて行くに応じて、もはやペンに於てしか発現できない態(てい)である》《なにか身にしみることがあってたちまち心あたたまり、からだがわれを忘れて乗り出して行き、用と無用とを問わず、横町をめぐり溝板をわたるように、はたへの気兼で汚されることのない清潔なペンがせっせとうごきはじめると、末はどんな大事件をおこすに至るか。仕合せにも「抽斎」一篇がここにある》(石川淳『森鷗外』)。
《鷗外は、抽斎の嗣子(渋江保)を知って、その父のことを訊いた。その母は抽斎の四人目の妻、山内氏五百(いほ)である。保が二歳のとき、抽斎は亡くなり、五百はその後二六年生きのびたから、保の父抽斎についての回想は、母五百を通してのものである。保の証言に拠るところが多い『渋江抽斎』に五百についての記述が多いのは、保の直接に知っていたのが、母だったからにちがいない。しかしその記述が五百を語って、格別の生彩を帯びるのは、単に情報の量の問題ではなくて、作者が抽斎のみならず五百にも敬意と親愛の情を感じていたからであろう》(加藤周一『『渋江抽斎』について』)。
《五百という女性の骨太な描き方につよい感銘をうけたのは、二度目に読んだときだったように思う。こういう知的な女性は、それまでの日本の文学には出てこなかった。漱石のいわゆるインテリ女たちは、うわついていて私は好きになれなかったが、五百にはかなわない、と思った。そういう人物を、遊女ばかり出てくる江戸文学の時代にくみこんでくれた鷗外に、私は感謝する気持ちだった。それからしばらくのあいだ、私にとっての『澀江抽斎』は、五百が宝石のように光っている作品としてだけ、あたまに残った》(須賀敦子『父の鷗外』)。
全篇「その一」から「その百九」のうち、実に渋江五百の名は「その九」で登場すると、「その三十」で詳しく出自が紹介されるや、「その百六」で絶息したあとまでも、数々のエピソードで『渋江抽斎』を飾った。抽斎が「その六十二」で歿してからも、《抽斎歿後の第四年は文久二年である》《抽斎歿後の第十三年は明治四年である》といった調子で、戊辰戦下の弘前へのロード・ムーヴィーも交えて、五百は巻を閉じるまで纏綿、闊達として生き続けるのだった。さながら『渋江抽斎』のタイトル・ロールこそ抽斎だが、ワキの五百で舞台が展開する「澁澤五百」が本来の題名であるかのように。
五百のほかに魅惑的な人物をあえてあげるとすれば、終生鴎外を尊敬してやまなかった荷風(その死の床には『渋江抽斎』が開かれていた)が随筆『梅雨晴』で、《森先生の渋江抽斎(しぶえちゅうさい)の伝を読んで、抽斎の一子優善(やすよし)なるものがその友と相謀(あいはか)って父の蔵書を持ち出し、酒色の資となす記事に及んだ時、わたしは自らわが過去を顧みて慚悔(ざんかい)の念に堪(た)えなかった。天保の世に抽斎の子のなした所は、明治の末にわたしの為したところとよく似ていた。抽斎の子は飛蝶(ひちょう)と名乗り寄席(よせ)の高座に上って身振声色(こわいろ)をつかい、また大川に舟を浮べて影絵芝居を演じた。わたしは朝寝坊夢楽という落語家の弟子となり夢之助と名乗って前座(ぜんざ)をつとめ、毎月師匠の持席(もちせき)の変るごとに、引幕を萌黄(もえぎ)の大風呂敷(おおぶろしき)に包んで背負って歩いた。明治三十一、二年のころのことなので、まだ電車はなかった》と情をよせた抽斎の次男優善であろうが、ここでは筆を伸ばさない。
加藤周一も須賀敦子も、五百を中心として『渋江抽斎』を読み代えたアメリカの書物について言及しているのだが、本邦でも、『渋江抽斎』というリゾーム(根茎)の錯綜から「渋江五百」の一本の太い根幹を抽出したい。
*
その九
気候は寒くても、まだ炉を焚(た)く季節に入らぬので、火の気のない官衙の一室で、卓を隔てて保さんとわたくしとは対坐した。そして抽斎のことを語って倦(う)むことを知らなかった。
今残っている勝久さんと保さんとの姉弟、それから終吉さんの父脩(おさむ)、この三人の子は一つ腹で、抽斎の四人目の妻、山内氏五百(いお)の生んだのである。勝久さんは名を陸(くが)という。抽斎が四十三、五百が三十二になった弘化四年に生まれて、大正五年に七十歳になる。抽斎は嘉永四年に本所へ移ったのだから、勝久さんはまだ神田で生まれたのである。
終吉さんの父脩は安改元年に本所で生まれた。中三年置いて四年に、保さんは生まれた。抽斎が五十三、五百が四十二の時のことで、勝久さんはもう十一、脩も四歳になっていたのである。
抽斎は安政五年に五十四歳で亡くなったから、保さんはそのときまだ二歳であった。幸いに母五百は明治十七年までながらえていて、保さんは二十八歳で恃(じ)(筆者註:母のこと)を喪ったのだから、二十六年の久しい間、慈母の口から先考の平生を聞くことを得たのである。
抽斎は保さんを学医にしようと思っていたと見える。亡くなる前にした遺言によれば、経を海保漁村に、医を多紀安琢(あんたく)に、書を小島成斎に学ばせるように言ってある。それから洋学については、折を見て蘭語を教えるが好いいと言ってある。抽斎は友人多紀茝庭(さいてい)などと同じように、すこぶるオランダ嫌いであった。学殖の深かった抽斎が、新奇を趁(お)う世俗と趨舎(すうしゃ)を同じくしなかったのは無理もない。劇を好んで俳優を品評した中に市川小団次の芸を「西洋」だと言ってある。これは褒めたのではない。しかるにその抽斎が晩年に至って、洋学の必要を感じて、子に蘭語を教えることを遺言したのは、安積艮斎(あさかごんさい)にその著述の写本を借りて読んだとき、翻然として悟ったからだそうである。想うにその著述というのは『洋外紀略』などであっただろう。保さんは後に蘭語を学ばずに英語を学ぶことになったが、それは時代の変遷のためである。
わたくしは保さんに、抽斎のことを探り始めた因縁を話した。そして意外にも、わずかに二歳であった保さんが、父に「武鑑」をもらってもてあそんだということを聞いた。それは出雲寺板(いずもじばん)の「大名武鑑」で、鹵簿(ろぼ)の道具類に彩色を施したものであったそうである。それのみではない。保さんは父が大きい本箱に「江戸鑑」と貼札をして、その中に一ぱい古い「武鑑」を収めていたことを記憶している。このコルレクションは保さんの五、六歳のときまで散佚(さんいつ)せずにいたそうである。「江戸鑑」の箱があったなら、江戸図の箱もあっただろう。わたくしはここに『江戸鑑図目録』の作られた縁起を知ることを得たのである。
わたくしは保さんに、父のことに関する記憶を、箇条書にしてもらうことを頼んだ。保さんは快諾して、同時にこれまで『独立評論』に追憶談を載せているから、それを見せようと約した。
保さんと会見してから間もなく、わたくしは大礼に参列するために京都へ立った。勤勉家の保さんは、まだわたくしが京都にいるうちに、書きものの出来たことを報じた。わたくしは京都から帰って、すぐに保さんを牛込に訪ねて、書きものを受け取り、また『独立評論』をも借りた。ここにわたくしの説くところは主として保さんから獲(え)た材料に拠るのである。
その三十
克己を忘れたことのない抽斎は、徳(筆者註:三人目の妻岡西氏徳)を叱り懲らすことはなかった。それのみではない。あらわに不快の色を見せもしなかった。しかし結婚してから一年半ばかりの間、これに親近せずにいた。そして弘前へ立った。初度の旅行のときのことである。
さて抽斎が弘前にいる間、江戸の便りがあるごとに、必ず長文の手紙が徳から来た。留守中の出来事を、ほとんど日記のようにくわしく書いたのである。抽斎は初め数行を読んで、ただちにこの書信が徳の自力によって成ったものでないことを知った。文章の背面に父允成の気質が歴々として見えていたからである。
允成は抽斎の徳に親しまぬのを見て、前途のために危ぶんでいたので、抽斎が旅に立つと、すぐに徳に日課を授けはじめた。手本を与えて手習いをさせる。日記をつけさせる。そしてそれにもとづいて文案を作って、徳に筆を把(と)らせ、家内のことは細大となく夫に報ぜさせることにしたのである。
抽斎は江戸の手紙を得るごとに泣いた。妻のために泣いたのではない。父のために泣いたのである。
二年近い旅から帰って、抽斎は勉(つと)めて徳に親んで、父の心を安んぜようとした。それから二年立って優善(やすよし)が生まれた。
ついで抽斎は再び弘前へ往って、足掛三年淹留(えんりゅう)した。留守に父の亡くなった旅である。それから江戸に帰って、中一年置いて好が生まれ、その翌年また八三郎が生まれた。徳は八三郎を生んで一年半立って亡くなった。
そして徳の亡くなったあとへ山内氏五百が来ることになった。抽斎の身分は徳が往き、五百が来る間に変って、幕府の直参になった。交際は広くなる。費用は多くなる。五百はにわかにそのうちに身を投じて、難局に当らなくてはならなかった。五百があたかもよしその適材であったのは、抽斎の幸いである。
五百の父山内忠兵衛は名を豊覚といった。神田紺屋町に鉄物問屋を出して、屋号を日野屋といい、商標には井桁(いげた)の中に喜の字を用いた。忠兵衛は詩文書画を善くして、多く文人墨客に交わり、財をすててこれが保護者となった。
忠兵衛に三人の子があった。長男栄次郎、長女安、二女五百である。忠兵衛は允成の友で、嫡子栄次郎の教育をば、久しく抽斎に託していた。文政七八年のころ、允成が日野屋をおとずれて、芝居の話をすると、九つか十であった五百と、一つ年上の安とが面白がって傍聴していたそうである。安はすなわちのちに阿部家に仕えた金吾である。
五百は文化十三年に生まれた。兄栄次郎が五歳、姉安が二歳になっていたときである。忠兵衛は三人の子の次第に長ずるに至って、嫡子には士人たるに足る教育を施し、二人の女(むすめ)にも尋常女子の学ぶことになっている読み書き諸芸の外、武芸をしこんで、まだ小さいときから武家奉公に出した。中にも五百には、経学などをさえ、ほとんど男子に授けると同じように授けたのである。
忠兵衛がかくのごとくに子を育てたには来歴がある。忠兵衛の祖先は山内但馬守盛豊の子、対馬守一豊の弟から出たのだそうで、江戸の商人になってからも、三葉柏の紋をつけ、名のりに豊(とよ)の字を用いることになっている。
その三十一
五百は十一二歳のとき、本丸に奉公したそうである。年代を推せば、文政九年か十年かでなくてはならない。徳川家斉が五十四五歳になったときである。御台所(みだいどころ)は近衛経煕(けいき)の養女茂姫である。
五百は姉小路という奥女中の部屋子(へやこ)であったという。姉小路というからには、上臈(じょうろう)であっただろう。しからば長局(ながつぼね)の南一の側に、五百はいたはずである。五百らが夕方になると、長い廊下を通って締めに往かなくてはならぬ窓があった。その廊下には鬼が出るという噂(うわさ)があった。鬼とはどんな物で、それが出て何をするかというに、誰もよくは見ぬが、男の衣(きもの)を着ていて、額(ひたい)に角が生えている。それが礫(つぶて)を投げかけたり、灰を蒔(ま)きかけたりするというのである。そこでどの部屋子も窓を締めに往くことを嫌って、互いに譲り合った。五百はおさなくても胆力があり、武芸の稽古をもしたことがあるので、自ら望んで窓を締めに往った。
暗い廊下を進んで行くと、はたしてちょろちょろと走り出たものがある。おやと思うまもなく、五百は片頬(かたほお)に灰をかぶった。五百には咄嗟(とっさ)の間に、その物の姿がよくは見えなかったが、どうも少年の悪作劇(いたずら)らしく感ぜられたので、五百は飛びついてつかまえた。
「許せ許せ」と鬼は叫んで身をもがいた。五百はすこしも手をゆるめなかった。そのうちにほかの女子たちが馳(は)せつけた。
鬼は降伏してかぶっていた鬼面を脱いだ。銀之助様と称えていた若者で、おさなくて美作国(みまさかのくに)西北条郡津山の城主松平家へ壻入りした人であったそうである。
津山の城主松平越後守斉孝(なりたか)の次女徒(かち)の方(かた)のもとへ壻入したのは、家斉の三十四人目の子で、十四男参河守斉民(なりたみ)である。
斉民は小字(おさなな)を銀之助という。文化十一年七月二十九日に生まれた。母はお八重の方である。十四年七月二十二日に、御台所の養子にせられ、九月十八日に津山の松平家に壻入し、十二月三日に松平邸に往った。四歳の壻君である。文政二年正月二十八日には新居落成してそれに移った。七年三月二十八日には十一歳で元服して、従四位上侍従参河守斉民となった。九年十二月には十三歳で少将にせられた。人と成って後確堂公と呼ばれたのはこの人で、成島柳北の碑の篆額(てんがく)はその筆である。そうして見ると、この人が鬼になって五百に捉えられたのは、従四位上侍従になってからのちで、ただ少将であったか、なかったかが疑問である。津山邸に館はあっても、本丸に寝泊りして、小字の銀之助を呼ばれていたものと見える。年は五百より二つ上である。
五百の本丸を下がったのはいつだかわからぬが、十五歳のときにはもう藤堂家に奉公していた。五百が十五歳になったのは、天保元年である。もし十四歳で本丸を下ったとすると、文政十二年に下ったことになる。
五百は藤堂家に奉公するまでには、二十幾家という大名の屋敷を目見えをして廻ったそうである。そのころも女中の目見えは、君(きみ)臣を択(えら)ばず、臣君を択ぶというようになっていたと見えて、五百がかくのごとくに諸家の奥へのぞきに往ったのは、到(いた)るところで斥(しりぞ)けられたのではなく、自分が仕うることを肯(がえん)ぜなかったのだそうである。
しかし二十余家を経(へ)めぐるうちに、ただ一カ所だけ、五百が仕えようと思った家があった。それが偶然にも土佐国高知の城主松平土佐守豊資(とよすけ)の家であった。即ち五百と祖先を同じうする山内家である。
五百が鍛冶橋内の上屋敷へ連れられて行くと、外の家と同じような考試に逢った。それは手跡、和歌、音曲の嗜(たしな)みを験(ため)されるのである。試官は老女である。先ず硯箱(すずりばこ)こと色紙とを持ち出して、老女が「これに一つお染めを」という。五百は自作の歌を書いたので、同時に和歌の吟味も済んだ。それから常磐津(ときわず)を一曲語らせられた。これらのことは他家と何のことなることもなかったが、女中がことごとく綿服であったのが、五百の目に留まった。二十四万二千石の大名の奥の質素なのを、五百は喜んだ。そしてすぐにこの家に奉公したいと決心した。奥方は松平上総介斉政(かずさのすけなりまさ)の女(むすめ)である。
このとき老女がふと五百の衣類に三葉柏の紋のついているのを見つけた。
その三十二
山内家の老女は五百に、どうして御当家の紋と同じ紋を、衣類につけているかと問うた。
五百は自分の家が山内氏で、昔から三葉柏の紋をつけていると答えた。
老女はしばらく案じてから言った。ご用に立ちそうな人と思われるから、お召抱えになるように申し立てようと思う。しかしその紋は当分御遠慮申すがよかろう。由緒(ゆいしょ)のあることであろうから、追ってお許しを願うことも出来ようと言った。
五百は家に帰って、父に当分紋を隠して奉公することの可否を相談した。しかし父忠兵衛は即座に反対した。姓名だの紋章だのは、先祖から承(う)けて子孫に伝える大切なものである。みだりに匿(かく)したり更(あらた)めたりすべきものではない。そんなことをしなくては出来ぬ奉公なら、せぬがよいと言ったのである。
五百が山内家をことわって、次に目見えに往ったのが、向柳原の藤堂家の上屋敷であった。例の考試は首尾よく済んだ。別格をもって重く用いてもよいと言って、懇望せられたので、諸家を廻りくたびれた五百は、この家に仕えることにきめた。
五百はすぐに中臈(ちゅうろう)にせられて、殿様附きと定まり、同時に奥方祐筆(ゆうひつ)を兼ねた。殿様は伊勢国安濃郡(あのごおり)津(つ)の城主、三十二万三千九百五十石の藤堂和泉守高猷(たかゆき)である。官位は従四位侍従になっていた。奥方は藤堂主殿頭(とのものかみ)高崧(たかたけ)の女(むすめ)である。
このとき五百はまだ十五歳であったから、尋常ならば女小姓に取らるべきであった。それが一躍して中臈を贏(か)ち得たのは破格である。女小姓は茶、煙草(たばこ)、手水(ちょうず)などの用を弁ずるもので、今いう小間使である。中臈は奥方附きであると、奥方の身辺に奉仕して、種々の用事を弁ずるものである。幕府の慣例ではそれが転じて将軍附きとなると、妾(しょう)になったと見てもよい。しかし大名の家では奥方に仕えずに殿様に仕えるというに過ぎない。祐筆は日記をつけたり、手紙を書いたりする役である。
五百は呼名は挿頭(かざし)とつけられた。後に抽斎に嫁することにきまって、比良野氏の娘分にせられたとき、翳(かざし)の名をもって届けられたのは、これを襲用したのである。さてしばらく勤めているうちに、武芸の嗜(たしな)みのあることを人に知られて、男之助という綽名(あだな)がついた。
藤堂家でも他家と同じように、中臈は三室位に分(わか)たれた部屋に住んで、女二人を使った。食事は自弁であった。それに他家では年給三十両内外であるのに、藤堂家では九両であった。当時の武家奉公をする女は、多く俸銭を得ようと思っていたのではない。今の女が女学校に往くように、修行をしに往くのである。風儀のよさそうな家を択(えら)んで仕えようとした五百なぞには、給料の多寡(たか)は初めより問うところでなかった。
修行は金を使ってする業で、金を取る道は修行ではない。五百なぞも屋敷住いをして、役人に物を献じ、傍輩に饗応(きょうおう)し、衣服調度を調(ととの)え、下女を使って暮すには、父忠兵衛は年としに四百両を費したそうである。給料は三十両貰もらっても九両貰っても、格別の利害を感ぜなかったはずである。
五百は藤堂家で信任せられた。勤仕いまだ一年に満たぬのに、天保二年の元日には中臈頭(ちゅうろうがしら)に進められた。中臈頭はただ一人しかおかれぬ役で、通例二十四五歳の女が勤める。それを五百は十六歳で勤めることになった。
その三十三
五百は藤堂家に十年間奉公した。そして天保十年に二十四歳で、父忠兵衛の病気のために暇(いとま)を取った。後に夫となるべき抽斎は五百が本丸にいた間、尾島氏定を妻とし、藤堂家にいた間、比良野氏威能、岡西氏徳を相踵(あいつ)いで妻としていたのである。
五百の藤堂家を辞した年は、父忠兵衛の歿した年である。しかし奉公をやめたころは、忠兵衛はまだ女(むすめ)を呼び寄せるほどの病気をしてはいなかった。暇を取ったのは、忠兵衛が女を旅に出すことを好まなかったためである。この年に藤堂高猷(たかゆき)夫妻は伊勢参宮をすることになっていて、五百は供のうちに加えられていた。忠兵衛は高猷の江戸を立つに先だって、五百を家に還らしめたのである。
五百の帰った紺屋町の家には、父忠兵衛の外、当時五十歳の忠兵衛妾(しょう)牧、二十八歳の兄栄次郎がいた。二十五歳の姉安は四年前に阿部家を辞して、横山町の塗り物問屋長尾宗右衛門に嫁していた。宗右衛門は安がためには、ただ一つ年上の夫であった。
忠兵衛の子がまだ皆いとけなく、栄次郎六歳、安三歳、五百(いお)二歳のとき、麹町の紙問屋山一の女で松平摂津守義建の屋敷に奉公したことのある忠兵衛の妻は亡くなったので、あとには享和三年に十四歳で日野屋へ奉公に来た牧が、妾になっていたのである。
忠兵衛は晩年に、気が弱くなっていた。牧は人の上に立って指図をするような女ではなかった。しかるに五百が藤堂家から帰ったとき、日野屋では困難な問題が生じて全家が頭(こうべ)を悩ませていた。それは五百の兄栄次郎の身の上である。
栄次郎は初め抽斎に学んでいたが、ついで昌平黌(しょうへいこう)に通うことになった。安の夫になった宗右衛門は、同じ学校の諸生仲間で、しかもこの二人だけがあまたの士人の間に介(はさ)まっていた商家の子であった。たとえて言って見れば、今の人が華族でなくて学習院に入っているようなものである。
五百が藤堂家に仕えていた間に、栄次郎は学校生活に平らかならずして、吉原通いをしはじめ、相方は山口巴の司(つかさ)という女であった。五百が屋敷から下がる二年前に、栄次郎は深入りをして、とうとう司の身受けをするということになったことがある。忠兵衛はこれを聞き知って、勘当しようとした。しかし救解のために五百が屋敷から来たので、沙汰やみになった。
しかるに五百が藤堂家を辞して帰ったとき、この問題が再燃していた。
栄次郎は妹の力によって勘当を免れ、しばらく謹慎して大門をくぐらずにいた。その隙(ひま)に司を田舎大尽が受け出した。栄次郎は鬱症になった。忠兵衛は心弱くも、人に栄次郎を吉原へ連れて往かせた。このとき司の禿(かぶろ)であった娘が、浜照という名で、来月突出(つきだし)になることになっていた。栄次郎は浜照の客になって、前よりも盛んな遊びをしはじめた。忠兵衛はまた勘当すると言い出したが、これと同時に病気になった。栄次郎もさすがに驚いて、暫く吉原へ往かずにいた。これが五百の帰ったときの現状である。
このときに当って、まさに覆(くつがえ)らんとする日野屋の世帯を支持して行こうというものが、新たに屋敷奉公を棄すてて帰った五百のほかになかったことは、想像するに難くはあるまい。姉安は柔和に過ぎて決断なく、その夫宗右衛門は早世した兄の家業を襲(つ)いでから、酒を飲んで遊んでいて、自分の産を治することをさえ忘れていたのである。
その三十四
五百は父忠兵衛をいたわり慰め、兄栄次郎を諌(いさ)め励まして、風浪にもてあそばれている日野屋という船の柁(かじ)を取った。そして忠兵衛の異母兄で十人衆を勤めた大孫某を証人に立てて、兄をして廃嫡を免れしめた。
忠兵衛は十二月七日に歿した。日野屋の財産は一旦忠兵衛の意志に依よって五百の名に書き更(か)えられたが、五百は直ちにこれを兄に返した。
五百は男子と同じような教育を受けていた。藤堂家で武芸のために男之助と呼ばれた反面には、世間で文学のために新少納言と呼ばれたという一面がある。同じころ狩谷棭斎の女俊(たか)に少納言の称があったので、五百はこれに対(むか)えてかく呼ばれたのである。
五百の師としてつかえた人には、経学に佐藤一斎、筆札に生方鼎斎(うぶかたていさい)、絵画に谷文晁、和歌に前田夏蔭(なつかげ)があるそうである。十一二歳のときはやく奉公に出たのであるから、教を受けるには、宿に下がるたびごとに講釈を聴くとか、手本をもらって習って清書を見せに往くとか、兼題の歌を詠んで直してもらうとかいう稽古のしかたであっただろう。
師匠のうちで最も老年であったのは文晁、次は一斎、次は夏蔭、最も少壮であったのが鼎斎である。年齢を推算するに、五百の生まれた文化十三年には、文晁が五十四、一斎が四十五、夏蔭が二十四、鼎斎が十八になっていた。
文晁は前に言ったとおり、天保十一年に七十八で歿した。五百が二十五のときである。一斎は安政六年九月二十四日に八十八で歿した。五百が四十四のときである。夏蔭は元治元年八月二十六日に七十二で歿した。五百が四十九のときである。鼎斎は安政三年正月七日に五十八で歿した。五百が四十一のときである。鼎斎は画家福田半香の村松町の家へ年始の礼に往って酒に酔い、水戸の剣客某と口論をし出して、其の門人に斬られたのである。
五百は鼎斎を師とした外に、近衛予楽院と橘千蔭(たちばなのちかげ)との筆跡を臨模(りんも)したことがあるそうである。予楽院家煕(いえひろ)は元文元年に薨(こう)じた。五百の生まれる前八十年である。芳宜園(はぎぞの)千蔭は身分が町奉行与力で、加藤又左衛門と称し、文化五年に歿した。五百の生まれる前八年である。
五百は藤堂家を下がってから五年目に渋江氏に嫁した。おさないときから親しい人を夫にするのではあるが、五百の身にとっては、自分が抽斎に嫁し得るというポッシビリテエの生じたのは、二月に岡西氏徳が亡くなってからのちのことである。常に往来していた渋江の家であるから、五百は徳の亡くなった二月から、自分の嫁して来る十一月までの間にも、抽斎を訪うたことがある。未婚男女の交際とか自由結婚とかいう問題は、当時の人は夢にだに知らなかった。立派な教育のある二人が、男は四十歳、女は二十九歳で、多く年を閲(けみ)した友人関係を棄てて、にわかに夫婦関係に入ったのである。当時においては、醒覚(せいかく)せる二人の間に、かくのごとく婚約が整ったということは、絶えてなくしてわずかにあるものといってよかろう。
わたくしは鰥夫(おとこやもめ)になった抽斎のもとへ、五百の訪(とぶr)い来たときの緊張したシチュアションを想像する。そして保さんの語った豊芥子(ほうかいし)の逸事を憶い起しておかしく思う。五百の渋江へ嫁入する前であった。ある日五百が来て抽斎と話をしていると、そこへ豊芥子が竹の皮包を持って来合わせた。そして包みを開いて抽斎に鮓(すし)を薦(すす)め、自分も食い、五百にぜひ食えと言った。のちに五百は、あのときほど困ったことはないと言ったそうである。
その三十五
五百は抽斎に嫁するに当って、比良野文蔵の養女になった。文蔵の子で目附役になっていた貞固(さだかた)は文化九年生まれで、五百の兄栄次郎と同年であったから、五百はその妹になったのである。しかるに貞固は姉威能のあとに直る五百だからというので、五百を姉と呼ぶことにした。貞固の通称は祖父と同じ助太郎である。
文蔵は仮親になるからは、まことの親とあまり違わぬ情誼(じょうぎ)がありたいと言って、渋江氏へ往く三箇月ばかり前に、五百を我が家に引き取った。そして自分の身辺におらせて、煙草を填(つ)めさせ、茶を立てさせ、酒の酌をさせなどした。
助太郎は武張った男で、髪を糸鬢(いとびん)に結い、黒紬(くろつむぎ)の紋附を着ていた。そしてもう藍原氏(あいばらうじ)かなという嫁があった。初め助太郎とかなとは、まだかなが藍原右衛門の女であったとき、穴隙(けつげき)を鑽(き)って相見(あいまみ)えたために、二人は親々の勘当を受けて、裏店(うらだな)の世帯を持った。しかしどちらもかわいい子であったので、間もなくわびがかなって助太郎は表立ってかなを妻に迎えたのである。
五百が抽斎に帰(とつ)いだときの支度は立派であった。日野屋の資産は兄栄次郎の遊蕩によって傾きかかってはいたが、先代忠兵衛が五百に武家奉公をさせるためにしむけておいた首飾(しゅしょく)、衣服、調度だけでも、人の目を驚かすに足るものがあった。今の世の人も奉公上がりには支度があるという。しかしそれは賜物(たまわりもの)をいうのである。当時の女子はこれに反して、おもに親のしむけた物を持っていたのである。五年の後に夫が将軍に謁したとき、五百はこの支度の一部を沽(う)って、夫の急を救うことを得た。またこれに先だつこと一年に、森枳園(きえん)(筆者註:福山藩の医師、のち医学館講師)が江戸に帰ったときも、五百はこの支度の他の一部を贈って、枳園の妻をして面目を保たしめた。枳園の妻はのちのちまでも、衣服を欲するごとに五百に請うので、お勝さんはわたしの支度を無尽蔵だと思っているらしいと言って、五百が歎息したことがある。
五百の来たり嫁したとき、抽斎の家族は主人夫婦、長男恒善、長女純、次男優善の五人であったが、間もなく純は出でて馬場氏の婦となった。
弘化二年から嘉水元年までの間、抽斎が四十一歳から四十四歳までの間には、渋江氏の家庭に特筆すべきことが少かった。五百の生んだ子には、弘化二年十一月二十六日生まれの三女棠(とう)、同三年十月十九日生まれの四男幻香、同四年十月八日生まれの四女陸(くが)がある。四男は死んで生まれたので、幻香水子はその法諡(ほうし)である。陸は今の杵屋勝久さんである。嘉永元年十二月二十八日には、長男恒善が二十三歳で月並み出仕を命ぜられた。
五百の里方では、先代忠兵衛が歿してから三年ほど、栄次郎の忠兵衛は謹慎していたが、天保十三年に三十一歳になったころから、また吉原へ通いはじめた。相方は前の浜照であった。そして忠兵衛はついに浜照を落籍させて妻にした。ついで弘化三年十一月二十二日に至って、忠兵衛は隠居して、日野屋の家督をわずかに二歳になった抽斎の三女棠に相続させ、自分は金座の役人の株を買って、広瀬栄次郎と名のった。
五百の姉安を娶った長尾宗右衛門は、兄の歿した跡を襲(つ)いでから、終日手杯をおかず、塗り物問屋の帳場は番頭に任せて顧みなかった。それを温和に過ぐる性質の安は諌めようともしないので、五百は姉を訪うてこの様子を見るたびにもどかしく思ったがしかたがなかった。そういうとき宗右衛門は五百を相手にして、『資治通鑑(しちつがん)』の中の人物を評しなどして、容易に帰ることを許さない。五百が強(し)いて帰ろうとすると、宗右衛門は安の生んだお敬お銓(せん)の二人の女に、おばさんを留めいという。二人の女は泣いて留める。これはおばの帰った跡で家が寂しくなるのと、父が不機嫌になるのとを憂えて泣くのである。そこで五百はとうとう帰る機会を失うのである。五百がこの有様を夫に話すと、抽斎は栄次郎の同窓で、妻の姉壻たる宗右衛門の身の上を気づかって、わざわざ横山町へ諭(さと)しに往った。宗右衛門は大いに慙(は)じて、やや産業に意を用いるようになった。
その三十六
森枳園は大磯で医業が流行するようになって、生活に余裕も出来たので、ときどき江戸へ出た。そしてそのたびごとに一週間位は渋江の家に舎(やど)ることになっていた。枳園の形装は決してかつて夜逃げをした土地へ、忍びやかに立ち入る人とは見えなかった。保さんの記憶している五百の話によるに、枳園はお召(めし)縮緬(ちりめん)の衣(きもの)を着て、海老鞘(えびざや)の脇指を差し、歩くに褄(つま)を取って、剥身絞(むきみしぼり)の褌(ふんどし)を見せていた。もし人がその七代目団十郎を贔屓(ひいき)にするのを知っていて、成田屋と声をかけると、枳園は立ち止まって見えをしたそうである。そして当時の枳園はもう四十男であった。もっともお召縮緬を着たのは、あながち奢侈(しゃし)と見るべきではあるまい。一反二分一朱か二分二朱であったというから、着ようと思えば着られたのであろうと、保さんが言う。
枳園の来て舎るころに、抽斎のもとにろくという女中がいた。ろくは五百が藤堂家にいたときから使ったもので、抽斎に嫁するに及んで、それを連れて来たのである。枳園は来り舎るごとに、この女を追い廻していたが、とうとうある日逃げる女を捉(とら)えようとして大行燈(おおあんどう)を覆(くつがえ)し、畳を油だらけにした。五百は戯れに絶交の詩を作って枳園に贈った。当時ろくをからかうものは枳園のみでなく、豊芥子も訪ねて来るごとにこれに戯れた。しかしろくは間もなく渋江氏の世話で人に嫁した。
枳園はまた当時わずかに二十歳を踰(こ)えた抽斎の長男恒善の、いわゆるおとなし過ぎるのを見て、たびたび吉原へ連れて往こうとした。しかし恒善は聴かなかった。枳園は意を五百に明かし、母の黙許というをもって恒善を動かそうとした。しかし五百は夫が吉原に往くことを罪悪としているのを知っていて、恒善を放ちやることが出来ない。そこで五百はいくたびか枳園と論争したそうである。
その三十七
阿部家への帰参がかなって、枳園が家族をまとめて江戸へ来ることになったので、抽斎はお玉が池の住宅の近所に貸家のあったのを借りて、敷金を出し家賃を払い、応急の器什(きじゅう)を買い集めてこれを迎えた。枳園だけは病家へ往かなくてはならぬ職業なので、衣類も一通り持っていたが、家族は身に着けたものしか持っていなかった。枳園の妻勝のことを、五百があれでは素裸といってもいいと言ったくらいである。五百は髪飾りから足袋下駄まで、一切揃(そろ)えて贈った。それでも当分のうちは、何かないものがあると、蔵から物を出すように、勝は五百のところへもらいに来た。ある日これで白縮緬(しろちりめん)の湯具(ゆぐ)を六本やることになると、五百が言ったことがある。五百がどのくらい親切に世話をしたか、勝がどのくらい恬然(てんぜん)として世話をさせたかということが、これによって想像することが出来る。また枳園に幾多の悪性癖があるにかかわらず、抽斎がどのくらい、その才学を尊重していたかということも、これによって想像することが出来る。
その三十八
抽斎の将軍家慶(いえよし)に謁見したのは、世の異数となすところであった。(中略)
目見えをしたものは、先ず盛宴を開くのが例になっていた。そしてこれに招くべき賓客の数もほぼ定まっていた。然るに抽斎の居宅には多く客を延(ひ)くべき広間がないので、新築しなくてはならなかった。五百の兄忠兵衛が来て、三十両の見積りをもって建築に着手した。抽斎は銭穀(せんこく)のことに疎(うと)いことを自知していたので、商人たる忠兵衛の言うがままに、これに経営を一任した。しかし忠兵衛は大家の若(わか)檀那(だんな)上がりで、金をなげうつことにこそ長じていたが、靳(おし)んでこれを使うことを解せなかった。工事いまだ半ばならざるに、費すところはすでに百数十両におよんだ。
平生金銭に無頓着であった抽斎も、これにはすこぶる当惑して、鋸の音槌の響のする中で、顔色は次第に蒼(あお)くなるばかりであった。五百は初めから兄の指図を危ぶみつつ見ていたが、このとき夫に向かって言った。
「わたくしがこう申すと、ひどく出過ぎた口をきくようではございますが、ご一代に幾たびというおめでたいことのある中で、金銭のことくらいで御心配なさるのを、黙って見ていることは出来ませぬ。どうぞ費用のことはわたくしにお任せなすって下さいまし」
抽斎は目をみはった。「お前そんなことを言うが、何百両という金は容易に調達せられるものではない。お前は何か当てがあってそう言うのか」
五百はにっこり笑った。「はい。いくらわたくしが癡(おろか)でも、当てなしには申しませぬ」
その三十九
五百は女中に書状を持たせて、ほど近い質屋へやった。すなわち市野迷庵のあとの家である。かの今に至るまで石に彫(え)られずにある松崎慊堂(こうどう)の文にいうごとく、迷庵は柳原の店で亡くなった。そのあとを襲(つ)いだのは松太郎光寿で、それが三右衛門の称をも継承した。迷庵の弟光忠は別に外神田に店を出した。これよりのち内神田の市野屋と、外神田の市野屋とが対立していて、彼は世々(よよ)三右衛門を称し、これは世々市三郎を称した。五百が書状をやった市野屋は当時弁慶橋にあって、早くも光寿の子光徳の代になっていた。光寿は迷庵の歿後わずかに五年にして、天保三年に光徳を家督させた。光徳は小字(おさなな)を徳治郎といったが、このときあらためて三右衛門を名のった。外神田の店はこのころまだ迷庵の姪(てつ)光長の代であった。
ほどなく光徳の店の手代が来た。五百は箪笥(たんす)長持から二百数十枚の衣類寝具を出して見せて、金を借らんことを求めた。手代は一枚一両の平均をもって貸そうと言った。しかし五百は抗争した末に、遂に三百両を借ることが出来た。
三百両は建築の費(つい)えを弁ずるには余りある金であった。しかし目見えに伴う飲醼贈遺(いんえんぞうい)一切の費えは莫大であったので、五百はついに豊芥子(ほうかいし)に託して、主おもなる首飾類を売ってこれに充てた。その状まさに行うべきところを行うごとくであったので、抽斎はとかくの意見をその間に挟(さしはさ)むことを得なかった。しかし中心には深くこれを徳とした。
抽斎の目見えをした年の閏(うるう)四月十五日に、長男恒善は二十四歳ではじめて勤仕した。八月二十八日に五女癸巳(きし)が生まれた。当時の家族は主人四十五歳、妻五百(いお)三十四歳、長男恒善二十四歳、次男優善十五歳、四女陸三歳、五女癸巳一歳の六人であった。長女純は馬場氏に嫁し、三女棠は山内氏を襲ぎ、次女よし、三男八三郎、四男幻香は亡くなっていたのである。
嘉永三年には、抽斎が三月十一日に幕府から十五人扶持を受くることとなった。藩禄等はすべて旧に依よるのである。八月晦(かい)に、馬場氏に嫁していた純が二十歳で歿した。この年抽斎は四十六歳になった。
その四十八
抽斎が本所二つ目の津軽家上屋敷から、台所町に引き返して見ると、住宅はことごとく傾き倒れていた。二階の座敷牢は粉韲(ふんせい)せられて迹(あと)だに留(とど)めなかった。対門の小姓組番頭土屋佐渡守邦直の屋敷は火を失していた。
地震はその夜歇(や)んでは起り、起っては歇んだ。町筋ごとに損害の程度は相ことなっていたが、江戸の全市に家屋土蔵の無瑕(むきず)なものは少かった。上野の大仏は首が砕け、谷中天王寺の塔は九輪が落ち、浅草寺の塔は九輪が傾いた。数十カ所から起った火は、三日の朝辰(たつ)の刻に至ってはじめて消された。公に届けられた変死者が四千三百人であった。
三日以後にも昼夜数度の震動があるので、第宅(ていたく)のあるものは庭に小屋掛けをして住み、市民にも露宿するものが多かった。将軍家定は二日の夜吹上の庭にある滝見茶屋に避難したが、本丸の破損が少かったので翌朝帰った。
幕府の設けた救い小屋は、幸橋(さいわいばし)外に一箇所、上野に二箇所、浅草に一箇所、深川に二箇所であった。
この年抽斎は五十一歳、五百は四十歳になって、子供には陸(くが)、水木(みき)、専六、翠暫(すいざん)の四人がいた。矢嶋優善のことは前に言った。五百の兄広瀬栄次郎がこの年四月十八日に病死して、その父の妾(しょう)牧は抽斎のもとに寄寓した。
牧は寛政二年生まれで、初め五百の祖母が小間使に雇った女である。それが享和三年に十四歳で五百の父忠兵衛の妾になった。忠兵衛が文化七年に紙問屋山一の女くみを娶とったとき、牧は二十一歳になっていた。そこへ十八歳ばかりのくみは来たのである。くみは富家の懐子(ふところご)で、性質が温和であった。後に五百と安とを生んでから、気象の勝った五百よりは、内気な安の方が、母の性質を承け継いでいると人に言われたのに徴しても、くみがどんな女であったかと言うことは想いやられる。牧は特に悍(かん)と称すべき女でもなかったらしいが、とにかく三つの年上であって、世故(せいこ)にさえ通じていたから、くみがただにこれを制することが難(かた)かったばかりでなく、ややもすればこれに制せられようとしたのも、もとより怪しむに足らない。
すでにしてくみは栄次郎を生み、安を生み、五百を生んだが、ついで文化十四年に次男某を生むに当って病に罹(かか)り、生まれた子とともに世を去った。この最後の産の前後のことである。くみは血行の変動のためであったか、重聴になった。そのとき牧がくみのことをたびたび聾者(つんぼ)と呼んだのを、六歳になった栄次郎が聞き咎(とが)めて、のちまでも忘れずにいた。
五百は六七歳になってから、兄栄次郎にこのことを聞いて、ひどく憤った。そして兄に言った。「そうして見ると、わたしたちには親の敵(かたき)がありますね。いつか兄いさんと一しょに敵を討とうではありませんか」と言った。そののち五百は折り折り箒(ほうき)に塵(ちり)払(はら)いを結びつけて、双手のごとくにし、これに衣服をまとって壁に立てかけ、さてこれを斫(き)る勢をなして、「おのれ、母の敵、思い知ったか」などと叫ぶことがあった。父忠兵衛も牧も、少女の意の斥(さ)すところを暁(さと)っていたが、父ははばかってあえて制せず、牧は懾(おそ)れて咎めることが出来なかった。
牧はいかにもして五百の感情を和らげようと思って、甘言をもってこれを誘おうとしたが、五百は応ぜなかった。牧はまた忠兵衛に請うて、五百に己(おのれ)を母と呼ばせようとしたが、これは忠兵衛が禁じた。忠兵衛は五百の気象を知っていて、かくのごとき手段のかえってその反抗心を激成するに至らんことを恐れたのである。
五百が早く本丸に入いり、また藤堂家に投じて、始終家に遠ざかっているようになったのは、父の希望があり母の遺志があって出来たことではあるが、一面には五百自身が牧とともに起き臥しすることを快からず思って、よそへ出て行くことを喜んだためもある。
こういう関係のある牧が、今寄辺(よるべ)を失って、五百の前に首(こうべ)を屈し、渋江氏の世話を受けることになったのである。五百は怨みに報ゆるに恩をもってして、牧の老(お)いを養うことを許した。
その五十三
八月二十二日に抽斎は常のごとく晩餐の饌(ぜん)に向かった。しかし五百が酒をすすめたとき、抽斎は下物(げぶつ)の魚膾(さしみ)に箸を下さなかった。「なぜ上がらないのです」と問うと、「少し腹工合が悪いからよそう」と言った。翌二十三日は浜町中屋敷の当直の日であったのを、所労をもって辞した。この日にはじめて嘔吐(おうど)があった。それから二十七日に至るまで、諸証は次第に険悪になるばかりであった。
多紀安琢、同じく元佶、伊沢柏軒、山田椿庭(ちんてい)らが病牀に侍して治療の手段を尽くしたが、功を奏せなかった。椿庭、名は業広、通称は昌栄である。抽斎の父允成の門人で、允成の歿後抽斎に従学した。上野国高崎の城主松平右京亮(うきょうのすけ)輝聡(てるとし)の家来で、本郷弓町に住んでいた。
抽斎は時々譫語(せんご)した。これを聞くに、夢寐(むび)の間に『医心方』を校合(きょうごう)しているもののごとくであった。
抽斎の病況は二十八日に小康を得た。遺言の中に、かねて嗣子と定めてあった成善を教育する方法があった。経書を海保漁村に、筆札を小島成斎に、素問を多紀安琢に受けしめ、機を看て蘭語を学ばしめるようにというのである。
二十八日の夜丑(うし)の刻に、抽斎は遂に絶息した。すなわち二十九日午前二時である。年は五十四歳であった。遺骸は谷中感応寺に葬られた。
抽斎の歿した跡には、四十三歳の未亡人五百を始として、岡西氏の出(しゅつ)次男矢嶋優善(やすよし)二十四歳、四女陸(くが)十二歳、六女水木(みき)六歳、五男専六五歳、六男翠暫(すいざん)四歳、七男成善(しげよし)二歳の四子二女が残った。優善を除くほかは皆山内氏五百の出である。
抽斎の子にして父に先だって死んだものは、尾島氏の出長男恒善(つねよし)、比良野氏の出馬場玄玖(げんきゅう)妻長女純(いと)、岡西氏の出二女好(よし)、三男八三郎、山内氏の出三女山内棠(とう)、四男幻香、五女癸巳(きし)、七女幸(さち)の三子五女である。
矢嶋優善はこの年二月二十八日に津軽家の表医者にせられた。初めの地位に復したのである。
五百の姉壻(あねむこ)長尾宗右衛門は、抽斎に先だつこと一月、七月二十日に同じ病を得て歿した。次で十一月十五日の火災に、横山町の店も本町の宅も皆焼けたので、塗り物問屋の業はここに廃絶した。あとに遣(のこ)ったのは未亡人安四十四歳、長女敬二十一歳、次女銓(せん)十九歳の三人である。五百は台所町の邸の空地に小さい家を建ててこれを迎え入れた。五百は敬に壻を取って長尾氏の祀(まつり)を奉ぜしめようとして、安に説き勧めたが、安は猶予して決することが出来なかった。
比良野貞固は抽斎の歿した直後から、しきりに五百に説いて、渋江氏の家を挙げて比良野邸に寄寓せしめようとした。貞固はこう言った。自分は一年前に抽斎と藩政上の意見を異にして、一時絶交の姿になっていた。しかし抽斎との情誼を忘るることなく、早晩疇昔(ちゅうせき)の親しみを回復しようと思っているうちに、はからずも抽斎に死なれた。自分はどうにかして旧恩に報いなくてはならない。自分の邸宅には空室が多い。どうぞそこへ移って来て、我が家に住むごとくに住んでもらいたい。自分は貧しいが、日々にちにちの生計には余裕がある。決して衣食の価は申し受けない。そうすれば渋江一家は寡婦(かふ)孤児として受くべき侮(あなど)りを防ぎ、無用の費(つい)えを節し、安んじて子女の成長するのを待つことが出来ようと言ったのである。
その五十四
比良野貞固は抽斎の遺族を自邸に迎えようとして、五百に説いた。しかしそれは五百を識(し)らぬのであった。五百は人の廡下(ぶか)に倚(よ)ることを甘んずる女ではなかった。渋江一家の生計は縮小しなくてはならぬこともちろんである。夫の存命していたときのように、多くの奴婢(ぬひ)を使い、食客をおくことは出来ない。しかし譜代(ふだい)の若党や老婦にして放ちやるに忍びざるものもある。寄食者のうちには去らしめようにも往いて投ずべき家のないものもある。長尾氏の遺族のごときも、もし独立せしめようとしたら、定めて心細く思うことであろう。五百は己(おのれ)が人に倚らんよりは、人をして己に倚らしめなくてはならなかった。そして内に恃むところがあって、あえて自らこの衝に当ろうとした。貞固の勧誘の功を奏せなかったゆえんである。
その六十
渋江氏の勤王はその源委を詳(つまび)らかにしない。しかし抽斎の父允成(ただしげ)に至って、師柴野栗山(りつざん)に啓発せられたことは疑を容れない。(中略)
抽斎の王室における、常に耿々(こうこう)の心を懐いていた。そしてかつて一たびこれがために身命を危うくしたことがある。保さんはこれを母五百に聞いたが、憾(うら)むらくはその月日を詳らかにしない。しかし本所においての出来事で、多分安政三年のころであったらしいということである。
ある日手嶋良助というものが抽斎に一の秘事を語った。それは江戸にある某貴の窮迫のことであった。貴人は八百両の金がないために、まさに苦境に陥らんとしておられる。手嶋はこれを調達せんと欲して奔走しているが、これを獲(う)る道がないというのであった。抽斎はこれを聞いて慨然として献金を思い立った。抽斎は自家の窮乏を口実として、八百両を先取することの出来る無尽講を催した。そして親戚故旧を会して金を醵出せしめた。
無尽講の夜、客がすでに散じたのち、五百は沐浴していた。明朝金を貴人のもとにもたらさんがためである。この金をたてまつる日はあらかじめ手嶋をして貴人に稟(もう)さしめておいたのである。
抽斎はたちまち剥啄(はくたく)の声を聞いた。仲間(ちゅうげん)が誰何(すいか)すると、某貴人の使いだと言った。抽斎は引見した。来たのは三人の侍である。内密に旨を伝えたいから、人払いをしてもらいたいと言う。抽斎は三人を奥の四畳半に延(ひ)いた。三人の言うところによれば、貴人は明朝を待たずして金を獲(え)ようとして、この使いを発したということである。
抽斎は応ぜなかった。この秘事にあずかっている手嶋は、貴人のもとにあって職を奉じている。金は手嶋を介してたてまつることを約してある。面(おもて)を識らざる三人に交付することは出来ぬというのである。三人は手嶋の来ぬ事故を語った。抽斎は信ぜないと言った。
三人は互いに目語して身を起し、刀の欛(つか)に手をかけて抽斎を囲んだ。そして言った。我らの言(こと)を信ぜぬというは無礼である。かつ重要の御使いを承わってこれを果さずに還っては面目が立たない。主人はどうしても金をわたさぬか。すぐに返事をせよと言った。
抽斎は坐したままでしばらく口をつぐんでいた。三人が偽(いつわり)の使いだということは既に明らかである。しかしこれと格闘することは、自分の欲せざるところで、また能わざるところである。家には若党がおり諸生がおる。抽斎はこれを呼ぼうか、呼ぶまいかと思って、三人の気色けしきを覗(うかが)っていた。
このとき廊下に足音がせずに、障子がすうっと開いた。主客はひとしく愕き眙(み)た。
その六十一
刀の欛(つか)に手を掛けて立ち上った三人の客を前に控えて、四畳半の端近く坐していた抽斎は、客から目を放さずに、障子の開いた口を斜めに見やった。そして妻五百の異様な姿に驚いた。
五百はわずかに腰巻一つ身に着けたばかりの裸体であった。口には懐剣をくわえていた。そして閾(しきい)ぎわに身を屈(かが)めて、縁側に置いた小桶二つを両手に取り上げるところであった。小桶からは湯気が立ちのぼっている。縁側を戸口まで忍び寄って障子を開くとき、持って来た小桶を下に置いたのであろう。
五百は小桶を持ったまま、つと一間に進み入って、夫を背にして立った。そして沸き返るあがり湯を盛った小桶を、右左の二人の客に投げつけ、くわえていた懐剣をとって鞘(さや)を払った。そして床の間を背にして立った一人の客を睨んで、「どろぼう」と一声叫んだ。
熱湯を浴びた二人が先に、欛(つか)に手をかけた刀をも抜かずに、座敷から縁側へ、縁側から庭へ逃げた。あとの一人も続いて逃げた。
五百は仲間や諸生の名を呼んで、「どろぼうどろぼう」という声をその間に挟んだ。しかし家に居合せた男らの馳せ集まるまでには、三人の客は皆逃げてしまった。このときのことはのちのちまで渋江の家の一つ話になっていたが、五百は人のその功を称するごとに、慙(は)じて席を遁(のが)れたそうである。五百は幼くて武家奉公をしはじめたときから、匕首(ひしゅ)一口だけは身を放さずに持っていたので、湯殿に脱ぎ棄てた衣類のそばから、それを取り上げることは出来たが、衣類を身にまとう遑(いとま)はなかったのである。
翌朝五百は金を貴人のもとに持って往った。手嶋の言(こと)によれば、これは献金としては受けられぬ、ただ借上げになるのであるから、十箇年賦で返済するということであった。しかし手嶋が渋江氏を訪うて、お手元不如意のために、今年は返金せられぬということが数度あって、維新の年に至るまでに、還された金はすこしばかりであった。保さんが金を受け取りに往ったこともあるそうである。
この一条は保さんもこれを語ることを躊躇し、わたくしもこれを書くことを躊躇した。しかし抽斎の誠心(まごころ)をも、五百の勇気をも、かくまで明らかに見ることの出来る事実を湮滅(いんめつ)せしむるには忍びない。ましてや貴人は今は世に亡き御方である。あからさまにその人を斥(さ)さずに、ほぼそのことを記すのは、あるいは妨げがなかろうか。わたくしはこう思惟(しゆい)して、抽斎の勤王を説くに当って、ついにこのことに言いおよんだ。
抽斎は勤王家ではあったが、攘夷家ではなかった。初め抽斎は西洋嫌いで、攘夷に耳を傾けかねぬ人であったが、前に言ったとおりに、安積艮斎の書を読んで悟るところがあった。そしてひそかに漢訳の博物窮理の書を閲(けみ)し、ますます洋学の廃すべからざることを知った。当時の洋学は主に蘭学であった。嗣子の保さんに蘭語を学ばせることを遺言したのはこれがためである。
抽斎は漢法医で、丁度蘭法医の幕府に公認せられると同時に世を去ったのである。この公認を贏(か)ち得るまでには、蘭法医は社会において奮闘した。そして彼らの攻撃の衝に当ったものは漢法医である。その応戦の跡は漢蘭酒話、一夕医話等のごとき書に徴して知ることが出来る。抽斎はあえて言をその間に挟(さしはさ)まなかったが、心中これがために憂え悶(もだ)えたことは、想像するに難(かた)からぬのである。
その六十三
鰻(うなぎ)を嗜(たしな)んだ抽斎は、酒を飲むようになってから、しばしば鰻酒ということをした。茶碗に鰻の蒲焼(かばやき)を入れ、すこしのたれを注ぎ、熱酒をたたえて蓋を覆(おお)っておき、しばらくしてから飲むのである。抽斎は五百を娶ってから、五百が少しの酒に堪えるので、勧めてこれを飲ませた。五百はこれを旨(うま)がって、兄栄次郎と妹壻長尾宗右衛門とにすすめ、また比良野貞固に飲ませた。これらの人々は後に皆鰻酒を飲むことになった。
その六十五
抽斎はかつて自ら法諡(ほうし)を撰んだ。容安院不求甚解居士というのである。この字面は妙ならずとはいいがたいが、余りに抽象的である。これに反して抽斎が妻五百のために撰んだ法諡は妙極まっている。半千院出藍終葛大姉(しゅつらんしゅうかつだいし)というのである。半千は五百、出藍は紺屋町に生まれたこと、終葛は葛飾郡で死ぬることである。しかし世事の転変は逆覩(げきと)すべからざるもので、五百は本所で死ぬることを得なかった。
この二つの法諡はいずれも石に彫られなかった。抽斎の墓には海保漁村の文を刻した碑が立てられ、また五百の遺骸は抽斎の墓穴に合葬せられたからである。
大抵伝記はその人の死をもって終るを例とする。しかし古人を景仰(けいこう)するものは、その苗裔(びょうえい)がどうなったかということを問わずにはいられない。そこでわたくしは既に抽斎の生涯を記しおわったが、なお筆を投ずるに忍びない。わたくしは抽斎の子孫、親戚、師友等のなりゆきを、これより下(しも)に書きつけておこうと思う。
わたくしはこの記事を作るにあまたの障礙(しょうがい)のあることを自覚する。それは現存の人に言いおよぼすことがようやく多くなるに従って、忌諱(きき)すべきことに撞着(とうちゃく)することもまた漸く頻(しき)りなることを免れぬからである。この障礙は上に抽斎の経歴を叙して、その安政中の末路に近づいたとき、早くすでに頭(こうべ)をもたげて来た。これからのちは、これがいよいよ筆端に纏繞(てんじょう)して、厭うべき拘束を加えようとするであろう。しかしわたくしはよしや多少の困難があるにしても、書かんと欲することだけは書いて、この稿を完うするつもりである。
渋江の家には抽斎の歿後に、すでにいうように、未亡人五百、陸(くが)、水木(みき)、専六、翠暫(すいざん)、嗣子成善(しげよし)と矢嶋氏を冒(おか)した優善(やすよし)とが遺(のこ)っていた。十月朔にわずかに二歳で家督相続をした成善と、他の五人の子との世話をして、一家の生計を立てて行かなくてはならぬのは、四十三歳の五百であった。
遺子六人の中でさしあたり問題になっていたのは、矢嶋優善の身の上である。優善は不行跡のために、二年前に表医者から小普請(こぶしん)医者に貶(へん)せられ、一年前に表医者介に復し、父を喪う年の二月にわずかにもとの表医者に復することが出来たのである。
しかし当時の優善の態度には、まだ真に改悛(かいしゅん)したものとは看なしにくいところがあった。そこで五百は旦暮(たんぼ)周密にその挙動を監視しなくてはならなかった。
残る五人の子の中うちで、十二歳の陸、六歳の水木、五歳の専六はもう読書、習字を始めていた。陸や水木には、五百がみずから句読を授け、手跡は手をとって書かせた。専六は近隣の杉四郎という学究のもとへ通っていたが、これも五百が復習させることに骨を折った。また専六の手本は平井東堂が書いたが、これも五百が臨書だけは手を把って書かせた。午餐後日の暮れかかるまでは、五百は子供の背後(うしろ)に立って手習いの世話をしたのである。
その六十六
邸内に棲まわせてある長尾の一家にも折り折り多少の風波が起る。そうすると必ず五百が調停に往かなくてはならなかった。その争いは五百が商業を再興させようとして勧めるのに、安が躊躇して決せないために起るのである。宗右衛門の長女敬はもう二十一歳になっていて、生得やや勝気なので、母をして五百の言(こと)に従わしめようとする。母はこれを拒みはせぬが、さればとて実行の方へは、一歩も踏み出そうとはしない。ここに争いは生ずるのであった。
さてこれが鎮撫に当るものが五百でなくてはならぬのは、長尾の家でまだ宗右衛門が生きていたときからの習慣である。五百の言には宗右衛門が服していたので、その妻や子もこれに抗することをばあえてせぬのである。
宗右衛門が妻の妹の五百を、ただ抽斎の配偶として尊敬するのみでなく、かくまでに信任したには、別に来歴がある。それはあるとき宗右衛門が家庭のティランとして大いに安を虐待して、五百のきびしい忠告を受け、涙を流して罪を謝したことがあって、それからのちは五百の前に項(うなじ)を屈したのである。
宗右衛門は性質亮直(りょうちょく)に過ぐるともいうべき人であったが、癇癪(かんしゃく)持(も)ちであった。今から十二年前のことである。宗右衛門はまだ七歳の銓(せん)に読書を授け、この子が大きくなったなら士(さむらい)の女房にすると言っていた。銓は記性があって、書を善く読んだ。こういうときに、宗右衛門が酒気を帯びていると、銓をそばに引きつけておいて、忍耐を教えると言って、戯れのように煙管(きせる)で頭を打つことがある。銓は初め忍んで黙っているが、のちには「お父っさん、いやだ」と言って、手を挙げて打つ真似をする。宗右衛門は怒って「親に手向いをするか」と言いつつ、銓を拳(こぶし)で乱打する。ある日こういう場合に、安が停めようとすると、宗右衛門はこれをも髪をつかんで拉(ひ)き倒して乱打し、「出て往け」と叫んだ。
安はもと宗右衛門の恋女房である。天保五年三月に、当時阿部家に仕えて金吾と呼ばれていた、まだ二十歳の安が、宿に下がって堺町の中村座へ芝居を看に往った。このとき宗右衛門は安を見初そめて、芝居がはねてから追尾して行って、紺屋町の日野屋に入るのを見きわめた。同窓の山内栄次郎の家である。さては栄次郎の妹であったかというので、ただちに人をやって縁談を申し込んだのである。
こうしたわけでもらわれた安も、拳のもとに崩れた丸髷(まるまげ)を整える遑(いとま)もなく、山内へ逃げ帰る。栄次郎の忠兵衛は広瀬を名のる前のころで、会津屋へ調停に往くことを面倒がる。妻はおいらん浜照がなれの果てで何の用にも立たない。そこでたまたま渋江の家から来合わせていた五百に、「どうかしてやってくれ」と言う。五百は姉を宥(なだ)めすかして、横山町へ連れて往った。
会津屋に往ってみれば、敬はうろうろ立ち廻っている。銓はまだ泣いている。妻の出たあとで、更に酒を呼んだ宗右衛門は、気味の悪い笑顔をして五百を迎える。五百はしずかに詫言を言う。主人はなかなか聴かない。しばらく語を交えている間に、主人は次第に饒舌になって、光燄(こうえん)万丈当るべからざるに至った。宗右衛門は好んで故事を引く。偽書孔叢子(こうそうし)の孔氏三世妻を出だしたという説が出る。祭仲の女雍姫(ようき)が出る。斎藤太郎左衛門の女が出る。五百はこれを聞きつつ思案した。これは負けていては際限がない。例(ため)しを引いて論ずることなら、こっちにも言い分がないことはない。そこで五百も論陣を張って、旗鼓(きこ)相当った。公父文伯の母季敬姜(きけいきょう)を引く。顔之推(がんしすい)の母を引く。ついに大雅思斉の章の「寡妻を刑(ただ)し、兄弟(けいてい)に至り、以て家邦を御(ぎょ)す」を引いて、宗右衛門が雝々(ようよう)の和を破るのを責め、声色ともに厲(はげ)しかった。宗右衛門は屈服して、「なぜあなたは男に生まれなかったのです」と言った。
長尾の家に争いが起るごとに、五百が来なくてはならぬということになるには、こういう来歴があったのである。
その六十七
抽斎歿後の第二年は万延元年である。成善はまだ四歳であったが、はやくも浜町中屋敷の津軽信順に近習として仕えることになった。もちろんときどき機嫌を伺いに出るに止(とど)まっていたであろう。このとき新たに中小姓になって中屋敷に勤める矢川文一郎というものがあって、おさない成善の世話をしてくれた。(中略)
文一郎はこの宗兵衛の長子である。その母の姉妹には林有的の妻、佐竹永海の妻などがある。佐竹は初め山内氏五百を娶らんとして成らず、遂に矢川氏を納(い)れた。某(それ)の年の元日に佐竹は山内へ廻礼に来て、庭に立っていた五百の手を摻(と)ろうとすると、五百はその手を強く引いて放した。佐竹は庭の池に墜(お)ちた。山内では佐竹に栄次郎の衣服を着せて帰した。五百はのちに抽斎に嫁してから、両国中村楼の書画会に往って、佐竹と邂逅(かいこう)した。そして佐竹の数人の芸妓に囲まれているのを見て、「佐竹さん、相変らず英雄色を好むとやらですね」と言った。佐竹は頭を掻(か)いて苦笑したそうである。
その六十九
矢島優善をして別に一家をなして自立せしめようということは、前年即ち安政六年の末から、中丸昌庵(しょうあん)が主として勧説したところである。昌庵は抽斎の門人で、多才能弁を以て儕輩(せいはい)に推されていた。文政元年生まれであるから、当時四十三歳になって、食禄二百石八人扶持、近習医者の首位におった。昌庵はこう言った。「優善さんは一時の心得違いから貶黜(へんちつ)を受けた。しかし幸いに過ちを改めたので、一昨年もとの地位に複(かえ)り、昨年は奥通りをさえ許された。今は抽斎先生が亡くなられてから、もう二年立って、優善さんは二十六歳になっている。わたくしは去年からそう思っているが、優善さんの奮(ふる)ってみずから新たにすべき時は今である。それには一家を構えて、責めを負ってことに当らなくてはならない」と言った。すでにして二三のこれに同意を表するものも出来たので、五百は危ぶみつつこの議を納れたのである。比良野貞固は初め昌庵に反対していたが、五百が意を決したので、また争わなくなった。
優善の移った緑町の家は、渾名(あだな)を鳩医者と呼ばれた町医佐久間某の故宅である。優善は妻鉄を家に迎え取り、下女一人を雇って三人暮しになった。
鉄は優善の養父矢嶋玄碩(げんせき)の二女である。玄碩、名を優繇(やすしげ)といった。もと抽斎の優善に命じた名は允善(ただよし)であったのを、矢嶋氏を冒すにおよんで、養父の優字を襲用したのである。玄碩の初めの妻某氏には子がなかった。後妻寿美は亀高村喜左衛門というものの妹で、仮親は上総国一宮の城主加納遠江守久徴(ひさあきら)らの医官原芸庵(うんあん)である。寿美が二女を生んだ。長を環といい、次を鉄という。嘉永四年正月二十三日に寿美が死し、五月二十四日に九歳の環が死し、六月十六日に玄碩が死し、跡にはわずかに六歳の鉄が遺った。
優善はこのとき矢嶋氏に入って末期養子となったのである。そしてその媒介者は中丸昌庵であった。
中丸は当時その師抽斎に説くに、すこぶる多言を費やし、矢嶋氏の祀(まつり)を絶つに忍びぬというをもって、抽斎の情誼に愬(うった)えた。なぜと言うに、抽斎が次男優善をして矢嶋氏の女壻たらしむるのは大いなる犠牲であったからである。玄碩の遺した女(むすめ)鉄は重い痘瘡を患(うれ)えて、瘢痕(はんこん)満面、人の見るを厭(いと)う醜貌であった。
抽斎は中丸の言に動かされて、美貌の子優善を鉄に与えた。五百は情として忍びがたくはあったが、ことが夫の義気に出でているので、強(し)いて争うことも出来なかった。
このことのあった年、五百は二月四日に七歳の棠(とう)を失い、十五日に三歳の癸巳(きし)を失っていた。当時五歳の陸(くが)は、小柳町の大工の棟梁(とうりょう)新八がもとに里にやられていたので、それを喚び帰そうと思っていると、そこへ鉄が来て抱かれて寝ることになり、陸は翌年まで里親のもとにおかれた。
棠は美しい子で、抽斎の女(むすめ)の中では純(いと)と棠との容姿が最も人に褒められていた。五百の兄栄次郎は棠の踊りを看るたびに、「食いつきたいような子だ」と言った。五百もあまり棠の美しさを云々するので、陸は「お母あさまの姉えさんを褒めるのを聞いていると、わたしなんぞはお化けのような顔をしているとしか思われない」と言い、また棠の死んだとき、「大方お母あさまはわたしを代かわりに死なせたかったのだろう」とさえ言った。
その七十
女(むすめ)棠が死んでから半年の間、五百は少しく精神の均衡を失して、夕暮れになると、窓を開けて庭の闇を凝視していることがしばしばあった。これは何故ともなしに、闇のうちに棠の姿が見えはせぬかと待たれたのだそうである。抽斎は気づかって、「五百、お前にも似ないじゃないか、少ししっかりしないか」と飭(いまし)めた。
そこへ矢嶋玄碩の二女、優善の未来の妻たる鉄が来て、五百に抱かれて寝ることになった、蜾臝(から)の母は情を矯(た)めて、暱(なじ)みのない人の子を賺(すか)しはぐくまなくてはならなかったのである。さて眠っているうちに、五百はいつか懐にいる子が棠だと思って、夢現(ゆめうつつ)の境にその体を撫でていた。たちまち一種の恐怖に襲われて目をあくと、痘痕のまだ新しい、赤く引き吊った鉄の顔が、触れ合うほど近い所にある。五百は覚えず咽(むせ)び泣いた。そして意識の明らかになるとともに、「ほんに優善は可哀そうだ」とつぶやくのであった。
緑町の家へ、優善がこの鉄を連れてはいったときは、鉄はもう十五歳になっていた。しかし世馴れた優善は鉄を子供扱いにして、詞(ことば)をやさしくして宥(なだ)めていたので、二人の間には何の衝突も起らずにいた。
これに反して五百の監視のもとを離れた優善は、門を出でては昔の放恣(ほうし)なる生活に立ち帰った。
その七十三
抽斎歿後の第四年は文久二年である。抽斎は世にある日、藩主に活版薄葉刷(うすようずり)の医方(いほう)類聚(るいじゅ)を献ずることにしていた。書は喜多村栲窓の校刻する所で、月ごとに発行せられるのを、抽斎は生を終るまでつぎを逐(お)ってたてまつった。成善は父の歿後相継いで納本していたが、この年に至って全部を献じおわった。八月十五日順承は重臣をもって成善に「御召御紋御羽織並御酒御吸物」を賞賜した。
成善は二年前から海保竹逕に学んで、この年十二月二十八日に、六歳にして藩主順承から奨学金二百匹を受けた。おもなる経史の素読をおわったためである。母五百は子女に読書習字を授けて半日を費やすを常としていたが、毫(ごう)も成善の学業に干渉しなかった。そして「あれは書物がご飯より好きだから、構わなくてもいい」と言った。成善はまた善く母に事(つこ)うるというをもって、賞を受くること両度におよんだ。(中略)
成善がこのころ母五百と倶ともに浅草永住町の覚音寺に詣でたことがある。覚音寺は五百の里方山内氏の菩提所である。帰途二人は蔵前通りを歩いて桃太郎団子の店の前に来ると、五百の相識の女に邂逅した。これは五百と同じく藤堂家に仕えて、中老になっていた人である。五百は久しく消息の絶えていたこの女と話がした
いと言って、ほど近い横町にある料理屋誰袖(たがそで)に案内した。成善もあとについて往った。誰袖は当時川長、青柳、大七などと並称せられた家である。
三人の通った座敷の隣に大一座の客があるらしかった。しかし声高く語り合うこともなく、ましてや絃歌の響などは起らなかった。しばらくあってその座敷がにわかに騒がしく、多人数の足音がして、あとはまたひっそりとした。
給仕に来た女中に五百が問うと、女中は言った。「あれは札差の檀那衆(だんなしゅ)が悪作劇(いたずら)をしておいでなすったところへ、お辰さんが飛び込んでおいでなすったのでございます。蒔(ま)き散らしてあったお金をそのままにしておいて、檀那衆がお逃げなさると、お辰さんはそれを持ってお帰りなさいました」と言った。お辰というのは、のち盗みをして捕えられた旗本青木弥太郎の妾である。
女中の語りおわるとき、両刀を帯びた異様の男が五百らの座敷に闖入(ちんにゅう)して「手前たちも博奕の仲間だろう、金を持っているなら、そこへ出してしまえ」と言いつつ、刀を抜いて威嚇した。
「なに、この騙(かた)り奴(め)が」と五百は叫んで、懐剣を抜いて起った。男は初めの勢いにも似ず、身をひるがえして逃げ去った。この年五百はもう四十七歳になっていた。
その七十四
矢嶋優善(やすよし)は山田の塾に入って、塾頭に推されてから、やや自重するもののごとく、病家にも信頼せられて、旗下(はたもと)の家庭にして、特に矢嶋の名を斥(さ)して招請するものさえあった。五百も比良野貞固もこれがためにすこぶる心を安んじた。
すでにしてこの年二月の初午(はつうま)の日となった。渋江氏では亀沢稲荷の祭を行うと言って、親戚故旧を集(つど)えた。優善も来て宴に列し、清元を語ったり茶番を演じたりした。五百はこれを見て苦々しくは思ったが、酒を飲まぬ優善であるから、よしや少しく興に乗じたからといって、のちに累(わずらい)を胎(のこ)すようなことはあるまいと気にかけずにいた。
優善が渋江の家に来て、その夕方に帰ってから、二三日立ったころの事である。師山田椿庭(ちんてい)が本郷弓町から尋ねて来て、「矢嶋さんはこちらですか、あまり久しく御滞留になりますから、どうなされたかと存じて伺いました」と言った。
「優善は初午の日にまいりましたきりで、あの日には晩の四つころに帰りましたが」と、五百は訝(いぶ)かしげに答えた。
「はてな。あれから塾へは帰られませんが」椿庭はこう言って眉を蹙(しか)めた。
五百は即時に人を諸方に馳せて捜索せしめた。優善の所在はすぐに知れた。初午の夜に無銭で吉原に往き、翌日から田町の引手茶屋に潜伏していたのである。
五百は金を償って優善を帰らせた。さて比良野貞固、小野富穀の二人を呼んで、いかにこれに処すべきかを議した。幼い成善も、戸主だというので、その席に列(つら)なった。
貞固はしばらく黙していたが、容(かたち)を改めてこう言った。「このたびの処分はただ一つしかないとわたくしは思う。玄碩さんはわたくしの宅で詰腹を切らせます。小野さんも、お姉(あね)えさんも、三坊も御苦労ながらお立会い下さい」言いおわって貞固は緊(きび)しく口を結んで一座を見廻した。優善は矢嶋氏を冒してから、養父の称を襲(つ)いで玄碩と言っていた。三坊は成善の小字(おさなな)三吉である。
富穀は面色土のごとくになって、一語を発することも得なかった。
五百は貞固の詞(ことば)を予期していたように、しずかに答えた。「比良野様のご意見はご尤もと存じます。たびたびの不始末で、もうこの上何と申し聞けようもございません。いずれ篤(とく)と考えました上で、改めてこちらから申し上げましょう」と言った。
これで相談は果てた。貞固は何事もないような顔をして、席を起って帰った。富穀はあとに残って、どうか比良野を勘弁させるように話をしてくれと、繰り返して五百に頼んでおいて、すごすご帰った。五百は優善を呼んで厳(おごそ)かに会議の始末を言い渡した。成善はどうなることかと胸を痛めていた。
翌朝五百は貞固を訪うて懇談した。大要はこうである。昨日の仰せは尤も至極である。自分は同意せずにはいられない。これまでの行きがかりを思えば、優善にこの上どうして罪を贖(あがな)わせようという道はない。自分も一死がその分であるとは信じている。しかし晴れがましく死なせることは、家門のためにも、君侯のためにも望ましくない。それゆえ切腹に代えて、金毘羅に起請文(きしょうもん)を納めさせたい。悔い改める望みのない男であるから、必ず冥々(めいめい)のうちに神罰をこうむるであろうというのである。
貞固はつくづく聞いて答えた。それはよいお思いつきである。このたびのことについては、命乞いの仲裁なら決して聴くまいと決心していたが、晴がましい死にざまをさせるにはおよばぬというお考は道理至極である。しからばその起請文を書いて金毘羅に納めることは、姉上にお任せすると言った。
その七十五
五百は矢嶋優善に起請文を書かせた。そしてそれを持って虎の門の金毘羅へ納めに往った。しかし起請文は納めずに、優善が行く末のことを祈念して帰った。
その七十六
この年六月中旬から八月下旬まで麻疹が流行して、渋江氏の亀沢町の家へ、御柳の葉と貝多羅葉(ばいたらよう)とをもらいに来る人が踵(くびす)を接した。二樹の葉が当時民間薬として用いられていたからである。五百は終日応接して、諸人の望みにそむかざらんことを努めた。
その七十七
多年渋江氏に寄食していた山内豊覚の妾牧は、この年七十七歳をもって、五百の介抱を受けて死んだ。
その八十一
鮓屋久次郎はもとぼて振りの肴屋(さかなや)であったのを、五百の兄栄次郎が贔屓(ひいき)にして資本を与えて料理店を出させた。幸に鮓久の庖丁は評判がよかったので、十ばかり年の少(わか)い妻を迎えて、天保六年に倅(せがれ)豊吉をもうけた。享和三年生まれの久次郎は当時三十三歳であった。のち九年にして五百が抽斎に嫁したので、久次郎は渋江氏にも出入りすることになって、次第に親しくなっていた。
渋江氏が弘前に徙(うつ)るとき、久次郎は切に供をして往くことを願った。三十四歳になった豊吉に、母の世話をさせることにしておいて、自分は単身渋江氏の供に立とうとしたのである。この望みを起すには、弘前で料理店を出そうという企業心も少し手伝っていたらしいが、六十六歳の翁(おきな)が二百里足らずの遠路を供に立って行こうとしたのは、おもに五百を尊崇する念から出たのである。渋江氏ではゆえなく久次郎の願いを卻(しりぞ)けることが出来ぬので、藩の当事者に伺ったが、当事者はこれを許すことを好まなかった。五百は用人河野六郎の内意を承けて、久次郎の随行を謝絶した。久次郎はひどく落胆したが、翌年病に罹(かか)って死んだ。
渋江氏の一行は本所二つ目橋の畔から高瀬舟に乗って、竪川(たてかわ)を漕がせ、中川より利根川に出で、流山、柴又等を経て小山に着いた。江戸を距(さ)ることわずかに二十一里の路に五日を費やした。近衛家に縁故のある津軽家は、西館孤清の斡旋あっせんによって、すでに官軍に加わっていたので、路の行く手の東北地方は、秋田の一藩を除くほか、ことごとく敵地である。一行の渋江、矢川、浅越の三氏の中では、渋江氏は人数も多く、老人があり少年少女がある。そこで最も身軽な矢川文一郎と、乳飲み子を抱いた妻という累(わずらい)を有するに過ぎぬ浅越玄隆とをば先に立たせて、渋江一家があとに残った。
五百らの乗った五挺の駕籠(かご)を矢嶋優善が宰領して、若党二人を連れて、石橋駅にかかると、仙台藩の哨兵線に出合った。銃を擬した兵卒が左右二十人ずつ轎(かご)を挟(さしはさ)んで、一つ一つ戸を開けさせて誰何(すいか)する。女の轎は仔細なく通過させたが、成善の轎に至って、審問に時を費した。この晩に宿に着いて、五百は成善に女装させた。
出羽の山形は江戸から九十里で、弘前に至る行程の半ばである。常の旅にはここに来ると祝う習いであったが、五百らはわざと旅店を避けて鰻屋(うなぎや)に宿を求めた。
その八十二
山形から弘前に往く順路は、小坂峠を踰(こ)えて仙台に入るのである。五百らの一行は仙台を避けて、板谷峠を踰えて米沢に入ることになった。しかしこの道筋も安全ではなかった。上山(かみのやま)まで往くと、形勢が甚だ不穏なので、数日間淹留(えんりゅう)した。
五百らは路用の金が竭(つ)きた。江戸を発するとき、多く金を携えて行くのは危険だと言って、金銭を長持五十荷(か)余りの底に布(し)かせて舟廻しにしたからである。五百らは上山で、ようよう陸を運んで来た些(ちと)の荷物の過半を売った。これは金を得ようとしたばかりではない。間道を進むことに決したので、嵩高(かさだか)になる荷は持っていられぬからである。荷を売った銭はもとより路用の不足を補う額には上らなかった。幸いに弘前藩の会計方に落ち合って、五百らは少しの金を借ることが出来た。
上山を発してからは人烟まれなる山谷の間を過ぎた。縄梯子(なわばしご)にすがって断崖を上下したこともある。夜の宿は旅人に餅を売って茶を供する休息所の類(たぐい)が多かった。宿で物を盗まれることも数度におよんだ。
院内峠を踰えて秋田領に入ったとき、五百らは少しく心を安んずることを得た。領主佐竹右京大夫義堯(よしたか)は、弘前の津軽承昭(つぐてる)とともに官軍方になっていたからである。秋田領は無事に過ぎた。
さて矢立峠を踰え、四十八川を渡って、弘前へは往くのである。矢立峠の分水線が佐竹、津軽両家の領地界(ざかい)である。そこを少し下ると、碇関(いかりがせき)という関があって番人がおいてある。番人は鑑札を検してから、はじめて慇懃(いんぎん)な詞(ことば)を使うのである。人が雲表に聳(そび)ゆる岩木山を指ざして、あれが津軽富士で、あの麓が弘前の城下だと教えたとき、五百らは覚えず涙を翻(こぼ)して喜んだそうである。
弘前に入ってから、五百らは土手町の古着商伊勢屋の家に、藩から一人一日金一分の為向(しむ)けを受けて、下宿することになり、そこに半年余りいた。船廻しにした荷物は、ほど経てのちに着いた。下宿屋から街(ちまた)に出づれば、土地の人が江戸子江戸子と呼びつつあとについて来る。当時髻(もとどり)を麻糸で結い、地織木綿の衣服を着た弘前の人々の中へ、江戸育ちの五百らが交じったのだから、物珍らしく思われたのも怪しむに足りない。ことに成善が江戸でもまだ少かった蝙蝠傘(かわほりがさ)を差して出ると、看るものが堵(と)のごとくであった。成善は蝙蝠傘と、懐中時計とを持っていた。時計は識らぬ人さえ紹介を求めて見に来るので、数日のうちに弄(いじ)り毀(こわ)されてしまった。
成善は近習小姓の職があるので、毎日登城することになった。宿直は二カ月に三度くらいであった。
その八十三
このころ五百は専六が就学問題のために思いを労した。専六の性質は成善とは違う。成善は書を読むに人の催促を須(ま)たない。そしてその読むところの書は自ら択(えら)ぶに任せることが出来る。それゆえ五百は彼が兼松石居に従って経史を攻(おさ)めるのを見て、毫も容喙(ようかい)せずにいた。成善が儒となるもまた可、医となるもまた不可なるなしとおもったのである。これに反して専六は多く書を読むことを好まない。書に対すれば、先ず有用無用の詮議をする。五百はこの子には儒となるべき素質がないと信じた。そこで意を決して剃髪せしめた。
五百は弘前の城下について、専六が師となすべき医家を物色した。そして親方町に住んでいる近習医者小野元秀を獲(え)た。
その九十
抽斎歿後の第十三年は明治四年である。成善は母を弘前に遺(のこ)して、単身東京に往くことに決心した。その東京に往こうとするのは、一には降等に遭って不平に堪えなかったからである。二には減禄ののちは旧によって生計を立てて行くことが出来ぬからである。その母を弘前に遺すのは、脱藩の疑いを避けんがためである。
弘前藩は必ずしも官費を以て少壮者を東京に遣ることを嫌わなかった。これに反して私費をもって東京に往こうとするものがあると、藩はすでにその人の脱藩を疑った。いわんや家族をさえ伴おうとすると、この疑はますます深くなるのであった。
その九十一
成善は藩学の職を辞して、この年三月二十一日に、母五百と水杯を酌(く)み交して別れ、駕籠に乗って家を出た。水杯を酌んだのは、当時の状況より推して、再会の期しがたきを思ったからである。成善は十五歳、五百は五十六歳になっていた。抽斎の歿したときは、成善はまだ少年であったので、このときはじめて親子の別れの悲しさを知って、轎中(きょうちゅう)で声を発して泣きたくなるのを、ようよう堪え忍んだそうである。
その九十三
この年六月七日に成善は名を保(たもつ)と改めた。これは母を懐(おも)うがゆえに改めたので、母は五百の字面の雅ならざるがために、常に伊保と署していたのだそうである。矢嶋優善の名を優(ゆたか)と改めたのもこの年である。山田専六の名を脩(おさむ)と改めたのは、別に記載の徴すべきものはないが、ややのちのことであったらしい。
この年十二月三日に保と脩とが同時に斬髪(ざんぱつ)した。(中略)
これよりさき保は弘前にある母を呼び迎えようとして、藩の当路者に諮(はか)ること数次であった。しかし津軽承昭の知事たる間は、西館らが前説を固守して許さなかった。前年廃藩の詔(みことのり)が出て、承昭は東京におることになり、県政もまたすこぶる革(あらた)まったので、保はまた当路者に諮った。当路者はまた五百の東京に入ることを阻止しようとはしなかった。ただ保が一諸生(しょせい)をもって母を養わんとするのが怪しむべきだと言った。それゆえ保は矢嶋優に願書を作らせて呈した。県庁はこれを可とした。五百はようよう弘前から東京に来ることになった。
保が東京に遊学したのちの五百が寂しい生活には、特に記すべきことはない。ただ前年廃藩前に、弘前俎(まないた)林(ばやし)の山林地が渋江氏に割与せられたのみである。これは士分のものに授産の目的をもって割与した土地に剰余があったので、当路者が士分として扱われざる医者にも恩恵を施したのだそうである。この地面の授受は浅越玄隆が五百の委託によって処理した。
五百が弘前を去るとき、村田広太郎のもとから帰った水木を伴わなくてはならぬことは勿論もちろんであった。そのほか陸(くが)もまた夫矢川文一郎とともに五百について東京へ往くことになった。
その九十四
五百は五月二十日に東京に着いた。そして矢川文一郎、陸の夫妻並びに村田氏から帰った水木の三人とともに、本所横網町の鈴木方に行李を卸した。弘前からの同行者は武田代次郎というものであった。代次郎は勘定奉行武田準左衛門の孫である。準左衛門は天保四年十二月二十日に斬罪に処せられた。津軽信順のもとで笠原近江が政(まつりごと)をほしいままにしたときのことである。
五百と保とは十六箇月を隔てて再会した。母は五十七歳、子は十六歳である。脩は割下水から、優は浦和から母に逢いに来た。
三人の子の中で、最も生計に余裕があったのは優である。優はこの年四月十二日に権少属(ごんしょうさかん)になって、月給僅わずかに二十五円である。これに当時の潤沢なる巡回旅費を加えても、なお七十円ばかりに過ぎない。しかしその意気は今の勅任官に匹敵していた。(中略)
保は下宿屋住いの諸生、脩は廃藩と同時に横川邸の番人をやめられて、これも一戸を構えているというだけでやはり諸生であるのに、独り優が官吏であって、しかもかくのごとく応分の権勢をさえ有している。そこで優は母に勧めて、浦和の家に迎えようとした。
「保が卒業して渋江の家を立てるまで、せめて四五年の間、わたくしのところに来ていて下さい」と言ったのである。
しかし五百は応ぜなかった。「わたしも年は寄ったが、幸いに無病だから、浦和に往って楽をしなくてもいい。それよりは学校に通う保の留守居でもしましょう」と言ったのである。
優はなお勧めてやまなかった。そこへ一粒金丹のやや大きい注文が来た。福山、久留米の二箇所から来たのである。金丹を調製することは、始終五百が自らこれに任じていたので、この度もまたすぐに調合に着手した。優は一旦浦和へ帰った。
その九十八
陸はこの年矢川文一郎と分離して、砂糖店を閉じた。生計意のごとくならざるがためであっただろう。文一郎が三十三歳、陸が二十七歳のときである。
ついで陸は本所亀沢町に看板を懸けて杵屋勝久と称し、長唄の師匠をすることになった。(中略)
抽斎歿後の第十七年は明治八年である。一月二十九日に保は十九歳で師範学校の業を卒(お)え、二月六日に文部省の命を受けて浜松県に赴くこととなり、母を奉じて東京を発した。
その九十九
保は母五百を奉じて浜松に着いて、初めしばらくのほどは旅店にいた。次で母子の下宿料月額六円を払って、下垂町(しもたれちょう)の郷宿(ごうやど)山田屋和三郎方にいることになった。郷宿とは藩政時代に訴訟などのために村民が城下に出たとき舎(やど)る家をいうのである。また諸国を遊歴する書画家等の滞留するものも、大抵この郷宿にいた。山田屋は大きい家で、庭に肉桂(にくけい)の大木がある。今もなお儼存(げんそん)しているそうである。
山田屋の向いに山喜(やまき)という居酒屋がある。保は山田屋に移った初めに、山喜の店に大皿に蒲焼(かばやき)の盛ってあるのを見て五百に「あれを買って見ましょうか」と言った。
「贅沢(ぜいたく)をお言いでない。鰻(うなぎ)はこの土地でも高かろう」と言って、五百は止(と)めようとした。
「まあ、聞いて見ましょう」と言って、保は出て行った。価あたいを問えば、一銭に五串(くし)であった。当時浜松辺で暮しの立ちやすかったことは、これによって想見することが出来る。
その百四
抽斎歿後の第二十五年は明治十六年である。保は前年の暮に東京に入って、仮に芝田町一丁目十二番地に住んだ。そして一面愛知県庁に辞表を呈し、一面府下に職業を求めた。保は先ず職業を得て、次で免罷(めんひ)の報に接した。一月十一日には攻玉社の教師となり、二十五日には慶応義塾の教師となって、午前に慶応義塾に往き、午後に攻玉社に往くことにした。(中略)
勝久は相生町の家で長唄を教えていて、山田脩はその家から府庁電信局に通勤していた。そこへ優が開拓使の職を辞して札幌から帰ったのが八月十日である。優は無妻になっているので、勝久に説いて師匠をやめさせ、もっぱら家政をつかさどらせた。
八月中のことであった。保は客を避けて京浜毎日新聞に寄する文を草せんがために、一週日ほどの間柳嶋の帆足謙三というものの家に起臥していた。烏森町の家には水木を遺して母に侍せしめ、かつ優、脩、勝久の三人をしてかわるがわるその安否を問わしめた。しかるにある夜水木が帆足の家に来て、母が病気と見えて何も食わなくなったと告げた。
保が家に帰って見ると、五百は床を敷かせて寝ていた。「只今帰りました」と、保は言った。
「お帰りかえ」と言って、五百は微笑した。
「おっ母(か)さま、あなたは何も上がらないそうですね。わたくしは暑くてたまりませんから、氷を食べます」
「そんならついでにわたしのも取っておくれ」五百は氷を食べた。
翌朝保が「わたくしは今朝は生卵にします」と言った。
「そうかい、そんならわたしも食べてみよう」五百は生卵を食べた。
午になって保は言った。「きょうは久しぶりで、洗いに水貝を取って、少し酒を飲んで、それから飯にします」
「そんならわたしも少し飲もう」五百は洗いで酒を飲んだ。そのときはもう平日のごとく起きて坐っていた。
晩になって保は言った。「どうも夕方になってこんなに風がちっともなくては凌(しの)ぎ切れません。これから汐(しお)湯(ゆ)にはいって、湖月に寄って涼んで来ます」
「そんならわたしも往くよ」五百は遂に汐湯に入って、湖月で飲み食いした。
五百は保が久しく帰らぬがために物を食わなくなったのである。五百は女子中では棠を愛し、男子中では保を愛した。さきに弘前に留守をしていて、保を東京にやったのは、意を決した上のことである。それゆえよく年余の久しきに堪えた。これに反して帰るべくして帰らざる保を日ごとに待つことは、五百の難(かた)んずるところであった。このとき五百は六十八歳、保は二十七歳であった。
その百五
この年十二月二日に優(ゆたか)が本所相生町の家に歿した。優は職をやめるときから心臓に故障があって、東京に還って清川玄道の治療を受けていたが、屋内に静坐していれば別に苦悩もなかった。歿する日には朝から物を書いていて、午(ひる)ごろ「ああくたびれた」と言って仰臥(ぎょうが)したが、それきり起たなかった。岡西氏徳の生んだ、抽斎の次男はかくのごとくにして世を去ったのである。優は四十九歳になっていた。子はない。遺骸は感応寺に葬られた。
優は蕩子であった。しかしのちに身を吏籍に置いてからは、微官におったにもかかわらず、すこぶる材能(さいのう)を見(あら)わした。優は情誼に厚かった。親戚朋友のその恩恵を被ったことは甚だ多い。優は筆札を善くした。その書には小嶋成斎の風があった。その他演劇のことはこの人の最も精通するところであった。新聞紙の劇評のごときは、森枳園と優とを開拓者のうちに算すべきであろう。大正五年に珍書刊行会で公にした劇界珍話は飛蝶(ひちょう)の名が署してあるが、優の未定稿である。
抽斎歿後の第二十六年は明治十七年である。二月十四日に五百が烏森の家に歿した。年六十九であった。
五百は平生病むことが少かった。抽斎歿後に一たび眼病に罹(かか)り、ときどき疝痛(せんつう)を患(うれ)えたくらいのものである。特に明治九年還暦ののちは、ほとんど無病の人となっていた。しかるに前年の八月中、保が家に帰らぬを患(うれ)えて絶食したころから、やや心身違和の徴があった。保らはこれがために憂慮した。さて新年に入って見ると、五百の健康状態はよくなった。保は二月九日の夜母が天麩羅(てんぷら)蕎麦(そば)を食べて炬燵(こたつ)に当り、史を談じて更のたけなわなるに至ったことを記憶している。また翌十日にも午食に蕎麦を食べたことを記憶している。午後三時ごろ五百は煙草を買いに出た。二三年前からは子らの諌(いさ)めを納れて、単身戸外に出ぬことにしていたが、当時の家から煙草店へ往く道は、烏森神社の境内であって車も通らぬゆえ、煙草を買いにだけは単身で往った。保は自分の部屋で書を読んで、これを知らずにいた。しばらくして五百は烟草を買って帰って、保の背後(うしろ)に立って話をし出した。保はかつ読みかつ答えた。初めてドイツ語を学ぶころで、読んでいる書はシェッフェルの文典であった。保は母の気息の促迫しているのに気がついて、「おっ母(か)さま、大そうせかせかしますね」と言った。
「ああ年のせいだろう、少し歩くと息が切れるのだよ」五百はこう言ったが、やはり話をやめずにいた。
少し立って五百は突然黙った。
「おっ母さま、どうかなすったのですか」保はこう言って背後を顧みた。
五百は火鉢の前に坐って、やや首を傾けていたが、保はその姿勢の常に異なるのに気がついて、急に起ってかたわらに往き顔をのぞいた。
五百の目は直視し、口角からは涎(よだれ)が流れていた。
保は「おっ母さま、おっ母さま」と呼んだ。
五百は「ああ」と一声答えたが、人事を省(せい)せざるもののごとくであった。
保は床を敷いて母を寝させ、自ら医師のもとへ走った。
その百六
渋江氏の住んでいた烏森の家からは、存生堂という松山棟庵(とうあん)の出張所が最も近かった。出張所には片倉某という医師が住んでいた。保は存生堂に駆けつけて、片倉を連れて家に帰った。存生堂からは松山の出張をも請いに遣った。
片倉が一応の手当をしたところへ、松山が来た。松山は一診して言った。「これは脳卒中で右半身不随になっています。出血の部位が重要部で、その血量も多いから、回復の望みはありません」と言った。
しかし保はその言(こと)を信じたくなかった。一時空を視(み)ていた母が今は人の面(おもて)に注目する。人が去れば目送する。枕辺(ちんぺん)に置いてあるハンカチイフを左手にとって畳む。保がそばに寄るごとに、左手で保の胸を撫(な)でさえした。
保は更に印東玄得をも呼んで見せた。しかし所見は松山と同じで、この上手当のしようはないと言った。
五百はついに十四日の午前七時に絶息した。
五百の晩年の生活は日々印刷したように同じであった。祁寒(きかん)のときを除く外は、朝五時に起きて掃除をし、手水(ちょうず)を使い、仏壇を拝し、六時に朝食をする。ついで新聞を読み、しばらく読書する。それから午餐の支度をして、正午に午餐する。午後には裁縫し、四時に至って女中を連れて家を出る。散歩がてら買物をするのである。魚菜をも大抵このとき買う。夕餉(ゆうげ)は七時である。これを終れば、日記をつける。ついでまた読書する。倦(う)めば保を呼んで棋(ご)を囲みなどすることもある。寝につくのは十時である。
隔日に入浴し、毎月曜日に髪を洗った。寺には毎月一度詣で、親と夫との忌日には別に詣でた。会計は抽斎の世にあったときからみずからこれに当っていて、死にいたるまで廃せなかった。そしてその節倹の用意には驚くべきものがあった。
五百の晩年に読んだ書には、新刊の歴史地理の類が多かった。兵要日本地理小志はその文が簡潔でいいと言って、そばに置いていた。
奇とすべきは、五百が六十歳を踰(こ)えてから英文を読みはじめたことである。五百はすこぶる早く西洋の学術に注意した。その時期を考うるに、抽斎が安積艮斎の書を読んで西洋のことを知ったよりも早かった。五百はまだ里方にいたとき、ある日兄栄次郎が鮓久(すしきゅう)に奇なことを言うのを聞いた。「人間は夜逆さになっている」云々と言ったのである。五百は怪しんで、鮓久が去ったのちに兄に問うて、はじめて地動説の講釈を聞いた。そののち兄の机の上に気海観瀾(きかいかんらん)と地理全志とのあるのを見て、取って読んだ。
抽斎に嫁したのち、ある日抽斎が「どうも天井に蝿(はえ)が糞をして困る」と言った。五百はこれを聞いて言った。「でも人間も夜は蝿が天井に止まったようになっているのだと申しますね」と言った。抽斎は妻が地動説を知っているのに驚いたそうである。
五百は漢訳和訳の洋説を読んであきたらぬので、とうとう保にスペルリングを教えてもらい、ほどなくウィルソンの読本に移り、一年ばかり立つうちに、パアレエの万国史、カッケンボスの米国史、ホオセット夫人の経済論等をぽつぽつ読むようになった。
五百の抽斎に嫁したとき、婚を求めたのは抽斎であるが、この間にある秘密が包蔵せられていたそうである。それは抽斎をして婚を求むるに至らしめたのは、阿部家の医師石川貞白が勧めたので、石川貞白をして勧めしめたのは、五百自己であったというのである。
その百七
石川貞白は初めの名を磯野勝五郎といった。いつのことであったか、阿部家の武具係を勤めていた勝五郎の父は、同僚が主家の具足を質に入れたために、永の暇になった。そのとき勝五郎はかねて医術を伊沢榛軒に学んでいたので、すぐに氏名を改めて剃髪し、医業をもって身を立てた。
貞白は渋江氏にも山内氏にも往来して、抽斎を識り五百を識っていた。弘化元年には五百の兄栄次郎が吉原の娼妓浜照のもとに通って、ついにこれを娶るに至った。そのとき貞白は浜照が身受けの相談相手となり、その仮親となることをさえ諾したのである。当時兄の措置を喜ばなかった五百が、平生青眼をもって貞白を見なかったことは、想像するに余りがある。
ある日五百は使をやって貞白を招いた。貞白はおそるおそる日野屋の閾(しきい)をまたいだ。兄の非行を幇(たす)けているので、妹に譴(せ)められはせぬかと懼(おそ)れたのである。
しかるに貞白を迎えた五百にはいつもの元気がなかった。「貞白さん、きょうはお頼み申したいことがあって、あなたをお招きいたしました」と言う、態度が例になく慇懃(いんぎん)であった。
何事かと問えば、渋江さんの奥さんの亡くなったあとへ、自分を世話をしてはくれまいかと言う。貞白はことの意表に出でたのに驚いた。
これよりさき日野屋では五百に壻を取ろうという議があって、貞白はこれをあずかり知っていた。壻に擬せられていたのは、上野広小路の呉服店伊藤松坂屋の通(かよ)い番頭で、年は三十二三であった。栄次郎は妹が自分たち夫婦にあきたらぬのを見て、妹に壻を取って日野屋の店を譲り、自分は浜照を連れて隠居しようとしたのである。
壻に擬せられている番頭某と五百となら、はたから見ても好配偶である。五百は二十九歳であるが、打ち見には二十四五にしか見えなかった。それに抽斎はもう四十歳に満ちている。貞白は五百の意のあるところを解するに苦しんだ。
そこで五百に問い質(ただ)すと、五百はただ学問のある夫が持ちたいと答えた。その詞(ことば)には道理がある。しかし貞白はまだ五百の意中を読み尽くすことが出来なかった。
五百は貞白の気色を見て、こう言い足した。「わたくしは壻を取ってこの世帯を譲ってもらいたくはありません。それよりか渋江さんのところへ往って、あの方に日野屋の後見(うしろみ)をしていただきたいと思います」
貞白は膝を拍(う)った。「なるほどなるほど。そういうお考えですか。よろしい。一切わたくしが引き受けましょう」
貞白は実に五百の深慮遠謀に驚いた。五百の兄栄次郎も、姉安の夫宗右衛門も、聖堂に学んだ男である。もし五百が尋常の商人を夫としたら、五百の意志は山内氏にも長尾氏にも軽んぜられるであろう。これに反して五百が抽斎の妻となると栄次郎も宗右衛門も五百の前に項(うなじ)を屈せなくてはならない。五百は里方のために謀って、労少くして功多きことを得るであろう。かつ兄の当然持っておるべき身代を、妹として譲り受けるということは望ましいことではない。そうしておいては、兄の隠居が何事をしようと、これに喙(くちばし)を容(い)れることが出来ぬであろう。永久に兄を徳として、そのなすがままに任せていなくてはなるまい。五百はかくのごとき地位に身を置くことを欲せぬのである。五百は潔(いさぎよ)くこの家を去って渋江氏に適(ゆ)き、しかもその渋江氏の力を藉(か)りて、この家の上に監督を加えようとするのである。
貞白はすぐに抽斎を訪うて五百の願いを告げ、自分も詞(ことば)を添えて抽斎を説き動かした。五百の婚嫁はかくのごとくにして成就したのである。
その百十二
陸がはじめて長唄の手ほどきをしてもらった師匠は日本橋馬喰町の二世杵屋勝三郎で、馬場の鬼勝と称せられた名人である。これは嘉永三年陸がわずかに四歳になったときだというから、まだ小柳町の大工の棟梁新八の家へ里子に遣られていて、そこから稽古に通ったことであろう。
母五百も声がよかったが、陸はそれに似た美声だと言って、勝三郎が褒めた。節もよく記(おぼ)えた。三味線は「宵は待ち」を弾くとき、早くすでにみずから調子を合わせることが出来、めりやす黒髪くらいに至ると、師匠に連れられて、所々大浚(おおざら)えに往った。
その百十三
渋江氏が一旦いったん弘前に徙(うつ)って、そののち東京と改まった江戸に再び還ったとき、陸は本所緑町に砂糖店を開いた。これは初め商売を始めようと思って土着したのではなく、ただ稲葉という家の門の片隅に空地があったので、そこへ小家を建てて住んだのであった。さてこの家に住んでから、稲葉氏と親しく交わることになり、その勧奨によって砂糖店をば開いたのである。また砂糖店を閉じたのちに、長唄の師匠として自立するに至ったのも、同じ稲葉氏が援助したのである。(中略)
ある日また五百と保とが寄席に往った。心打(しんうち)は円朝であったが、話の本題に入る前に、こういうことを言った。「このごろ緑町では、ご大家のお嬢様がお砂糖屋をお始めになって、ことのほかご繁昌だと申すことでございます。時節柄結構なお思い立ちで、誰もそうありたいことと存じます」と言った。話のうちにいわゆる心学を説いた円朝の面目が窺われる。五百は聴いて感慨に堪えなかったそうである。
この砂糖店は幸か不幸か、繁昌の最中(もなか)に閉じられて、陸は世間の同情に酬(むく)いることを得なかった。家族関係の上に除きがたい障礙(しょうがい)が生じたためである。
商業を廃して間暇(かんか)を得た陸のもとへ、稲葉の未亡人は遊びに来て、談はたまたま長唄のことにおよんだ。長唄は未亡人がかつて稽古したことがある。陸には飯よりも好きな道である。一しょに浚(さら)って見ようではないかということになった。いまだ一段を終らぬに、世話好の未亡人は驚歎しつつこう言った。「あなたは素人(しろうと)じゃないではありませんか。ぜひ師匠におなりなさい。わたしが一番に弟子入りをします」
その百十四
稲葉の未亡人の詞(ことば)を聞いて、陸の意はやや動いた。芸人になるということをはばかってはいるが、どうにかして生計を営むものとすると、自分の好む芸をもってしたいのであった。陸は母五百のもとに往って相談した。五百は思いのほかたやすく許した。
陸は師匠杵屋勝三郎の勝の字を請い受けて勝久と称し、公に稟(もう)して鑑札を下付せられた。そのとき本所亀沢町左官庄兵衛の店(たな)に、似合わしい一戸が明(あ)いていたので、勝久はそれを借りて看板をかけた。二十七歳になった明治六年のことである。
その百十九
陸は遠州流の活花(いけばな)をも学んだ。碁象棋(ごしょうぎ)をも母五百に学んだ。五百の碁は二段であった。五百はかつて薙刀(なぎなた)をさえ陸に教えたことがある。
陸の読書筆札のことはすでに記したが、やや長ずるにおよんでは、五百が近衛予楽院の手本を授けて臨書せしめたそうである。
陸の裁縫は五百が教えた。陸が人と成ってからのちは、渋江の家では重ねものか普段着までほとんど外へ出して裁縫させたことがない。五百は常に、「為立(した)ては陸に限る、為立屋の為事(しごと)は悪い」と言っていた。張物も五百が尺(ものさし)を手にして指図し、布目(ぬのめ)の毫(ごう)も歪(ゆが)まぬように陸に張らせた。「よく張った切れは新しい反物(たんもの)を裁(た)ったようでなくてはならない」とは、五百のつねの詞(ことば)であった。
*
この最後の五百の詞(ことば)「よく張った切れは新しい反物(たんもの)を裁(た)ったようでなくてはならない」と、須賀敦子『父の鷗外』の、《五百は、あの煩雑な澀江家のしがらみのなかに組み入れられたとき、いっそうの光彩を放つのだ》こそ、「五百」の魅力、ひいては『渋江抽斎』の本質的な魅力であろう。
丸谷才一が『文学のレッスン』で《森鷗外が漱石にくらべて人気がないのは、鷗外は学識がうんと高くて普通の読者には読めないからというようなことがいわれるけれど、そうではなくて、鷗外の登場人物には魅力のある人があまりいないということがありはしないか。最後に史伝を三つ書きましたが、あのときになってはじめて魅力のある人物が出てくる》というのも、石川淳が『鷗外』で《抽斎への「親愛」が氾濫したけしきで、鷗外は抽斎の周囲をことごとく、凡庸な学者も、市井の通人も、俗物も、蕩児も、婦女子も、愛撫してきわまらなかった》というのもまた念頭に凛とした「五百」をおいていたに違いあるまい。
(了)
*****引用または参考文献*****
*加藤周一『加藤周一著作集18』(『『渋江抽斎』について』所収)(平凡社)